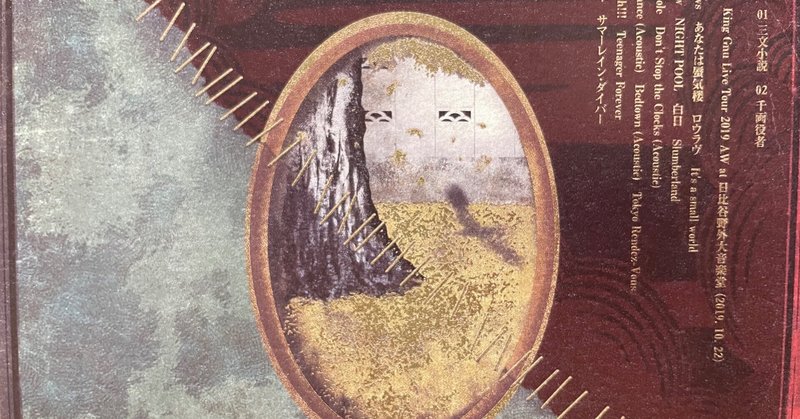
『三文小説』 vol.4【小説】
これは、三文小説。
枕詞は「あなたは知らないだろうけど、」 で始まる物語。
―――川本十和子、の場合―――
「あなたは、知らないでしょうけれど、」
今日も玄関に、大輪の百合が、美しく活けられている。深い藍色の花びんに挿した、その花を、ちょっと手で直しながら、川本十和子は、美夏を出迎えた。
「わたしが、所帯を持っていた頃にも、大地震
が、毎年のようにあったのよ」
高円寺駅から、環七をまたいで、東高円寺駅に向かうと、蚕糸公園に出る。
流れる滝の音、樹々のざわめき、近くの小学校の子どもたちの歓声、青梅街道沿いとは思えない、ゆったりとした時間が、十和子のマンションにも、流れている。
銀座のママだった人で、言葉遣いと、掃除にはウルさいから気をつけてと、鶴崎から聞いていた。
初めて、ケアに入った日には、玄関の奥に掲げられた、菊のご紋の入った、大きな額に驚いた。時の、内閣総理大臣の名前で、感謝状、とある。
そばには、胸元に勲章のついた、燕尾服を着て立つ「先生」の遺影が飾ってあった。百合の花は、その遺影から見える位置に、決まって活けられている。
「わたしは、まあ、のち添えと言うのかしら
ね。そんな身分の者だから、先生が亡くなっ
たときには、お葬式に行けなくて当然だった
のにね、娘さんがどうしてもと、呼んでくだ
さってね」
「先生」は、中国の満鉄というところを作った、エンジニアだったようだが、美夏には、何をした偉い人なのか、さっぱり分からない。
亡くなる直前まで、戦争の爪痕が残る、アジアの国々を訪れ、帰国すると、自宅には帰らず、まっすぐに銀座の十和子の店か、この東高円寺のマンションに、顔を出したそうだ。
「まずは、熱いお茶だ。それから、お茶漬け一
杯、食わせてくれ、ってね」
懐かしそうに、十和子が、微笑む。
先生の妻は、最期まで、十和子を「二号さん」と呼び、その名を口にすることはなかった。
その妻が、先に亡くなり、先生は、男やもめになった。それで、十和子は、本人の言う「のち添え」というのになるわけだが、一緒に暮らすでもなく、先生は相変わらず、アジアを飛び回り、たまに帰れば十和子のところに寄って、くつろいだ。
どういうわけか、先生の娘さんは、十和子を慕ったようだ。
自分の父親が、心を寄せた女性を、憎むのではなく、憧れの対象とした、娘心が、なんとなく、美夏には分かる。
十和子には、銀座のクラブのママであること以上に、人を包み込むような、大きさを感じる。仕事には、もちろん厳しいが、同時に、背中を預けられるような安心感、そして、どこか突き抜けた、明るさがあった。
「川本さんは、男前で、素敵です」
いつだったか、美夏が、窓を磨きながら、思わず軽口を叩くと、
「こんな、皺クチャのおばあさんに、男前った
ぁ、あなたも面白い人ね」
と、笑いながら言った。
今は、コンプライアンス的に、言えないような言葉も、この年代と話していると、自由に使える。ていうか、日本語って、味のある表現、コンプラ的に、ヤバいのばっかりじゃん。
十和子は、まんざらでもない顔で、そうか、オトコマエかぁと、先生の、遺影の前で、繰り返す。
先生が、亡くなったときも、娘さんから、一報を受けながら、十和子は、いつもどおり銀座の店を開けた。
「わたしは、先生の、死に水を取ることも、し
なかった。ご家族に、顔向けできるわけがな
い」
長年、店のバーテンダーをしている中川が、一度だけ、酔いつぶれたママを見た、と言う日だ。
店が畳まれた今も、中川は、かつての雇い主を、物心両面でサポートし、美夏も、何度か、ここの玄関先で、話したことがある。
店の女の子たちが、中川を目当てに入って来て困った、と十和子から聞いていたとおり、たしかに、頭に白いものが混じる今も、かなりのイケメンだ。
独身で、女っ気が無いのが不思議なくらいだが、十和子のマンションに、何かの使いで来たときも、決して玄関から先に、入ることはなかった。
先生の娘さんや、中川が、どんなに十和子を大切に思い、慕っているかを、美夏は、そばにいて感じる。
「わたしは、もともと関西の人間でね。
大阪で、青物商の旦那と所帯を持っていたこ
ろ、空襲も大変だったけれど、その頃、大き
な地震が、毎年、起こったのよ。
でも、新聞もラジオも、なぁんにも、言わな
くてねえ。鳥取から、三河から、土佐の方ま
で、ぐらぐら揺れて、ずいぶん、人も亡くな
ったみたいだけれど、
今思えば、お上も、知らんぷりだった。
戦争中だったから、かしらねぇ」
三月初めにしては、暖かい日が続いている。
同じように、この一週間ぐらい、東京に小さな地震が頻発していて、今朝も、震度3くらいの揺れがあった。
美夏も、独り暮らしの利用者たちが心配で、今朝は少し早めに、出勤していた。
気丈な十和子は、地震が怖い、と言うより、持病の心臓が、ショックで発作を起こすのを気にしているのだ。
それでも、顔には出さず、割れるといけない物は、下に降ろして置いてちょうだいと、美夏に、テキパキと指示を出した。
テレビ台の横の棚に、先生が好きだったという、古いジャズのレコードが、今もきれいに並んでいる。
棚の上には、たくさん写真が、飾られているのだが、七〇年代あたりの、サイケなミニドレスを着た、十和子の写真は、香港の映画女優のように、モダンで、美しい。
先生が連れてきた、アジアの若者たちと、店で撮った写真も多い。当時は、東京でも外国人、とりわけ肌の浅黒い人々は、ヘタをしたら、敬遠されていただろうが、十和子は、彼らと、実に楽しそうに笑っている。
先生が、十和子を愛し、心から信頼していた理由を、垣間見るような気がした。
「伝えるばかりが、愛じゃないのよ」
十和子の、穏やかだが、凛とした声が響いた。
美夏は、勤務中には、ムダ口を開かぬよう、気をつけていた。とりわけ、十和子の前では。
だが、その日は、疲れ切った顔をしていたのだろう。
男は、いくつかの映画化も決まっている、流行作家で、美夏は、数年前まで、勤めていた出版社で、彼の担当だった。
男の妻は、精神を病み、入退院を繰り返している。男の、献身的な看病は、作家活動が軌道に乗り、多忙を極める中でも変わらなかった。
作家仲間をはじめ、内外の編集者も、その作品にも通底する、無骨ながら誠実な、彼自身に、多くの者が魅かれていた。
美夏も、そのうちの一人、のはずだった。
どちらからだとか、なにが理由だとか、ひとりの男と、ひとりの女に、なってしまえば、言葉にできるものは、なにもない・・・
美夏が、想いに沈んで、写真立てを、ぼんやりと、磨き続けているのを見て、十和子は、続けて、静かに言った。
「あなたね、世の中の女、全員を敵に回すくら
いじゃなきゃ、惚れた、って言わないのよ。
地獄に堕ちても愛してしまう、
それだけの、男なんだから」
十和子のマンションを出たのは、昼前だった。
近くの蚕糸公園で、朝作ってきたおむすびと、卵焼きの弁当を食べた。小学校からも、給食の良い匂いが、子どもたちの歓声とともに、漂ってくる。
三月にしては、本当に暑いくらいの、天気の良い日だ。
まだ、十代の若妻だった、十和子が、毎年のように経験した、という大地震が、その日の午後、半世紀以上をゆうに経て、最大級で、東京を揺らした。
https://open.spotify.com/track/7BMKWT0Vw0EKDELXLvuWCp?si=q3ZVWvt6TIGpVuEfYBZxpg
(続)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
