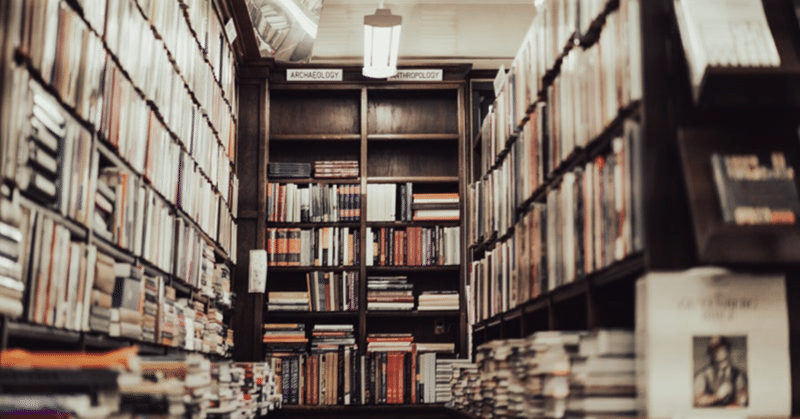
Photo by
kiyofico
参考文献の恐ろしさ
私(および『大阪歴史倶楽部』)は、多くのnoteの記事の文末に【参考資料(参考文献)】を掲載しています。
それは当然その記事を書くにあたって参考にした文献や資料の一覧なのですが、同時に読んでくださった皆さまに更に興味を持っていただき、より深く調べていただく時の参考としていただくための資料の一覧という意味でもあります。
さて、学術論文には必ず「註」をつけますね。また多くの学術書にも「註」や「参考文献」が付けられています。概説書にも親切なものでは「参考文献」などがついていますね。
じつは、専門家がこれらの「註」や「参考文献」をみると、その筆者が何を考え、何を言いたいのか、何を基準としてどのように論を進めようとしているのか、そしてその筆者の学問的なレベルや物事の読解能力、理解力・考察力などが一目瞭然で手に取るように分かるのです。
なので私は本や論文を読む時にはその「信憑性」をはかるためにまず「註」や「参考文献」を見ます。それでその本や論文はきちんとしたものなのか、筆者(やその論文)は信頼できるのかどうかを判断しています。
いわば「註」や「参考文献」はその筆者の身ぐるみをはがす、筆者のレベルや能力の限界をさらけ出しているアイテムだとも言えるのです。とても恐ろしいものだと思うのです。
※このエッセイは相互フォローをしてくださっている山根あきら様の募集企画「理解はしてほしいこと」に応募したものです。
