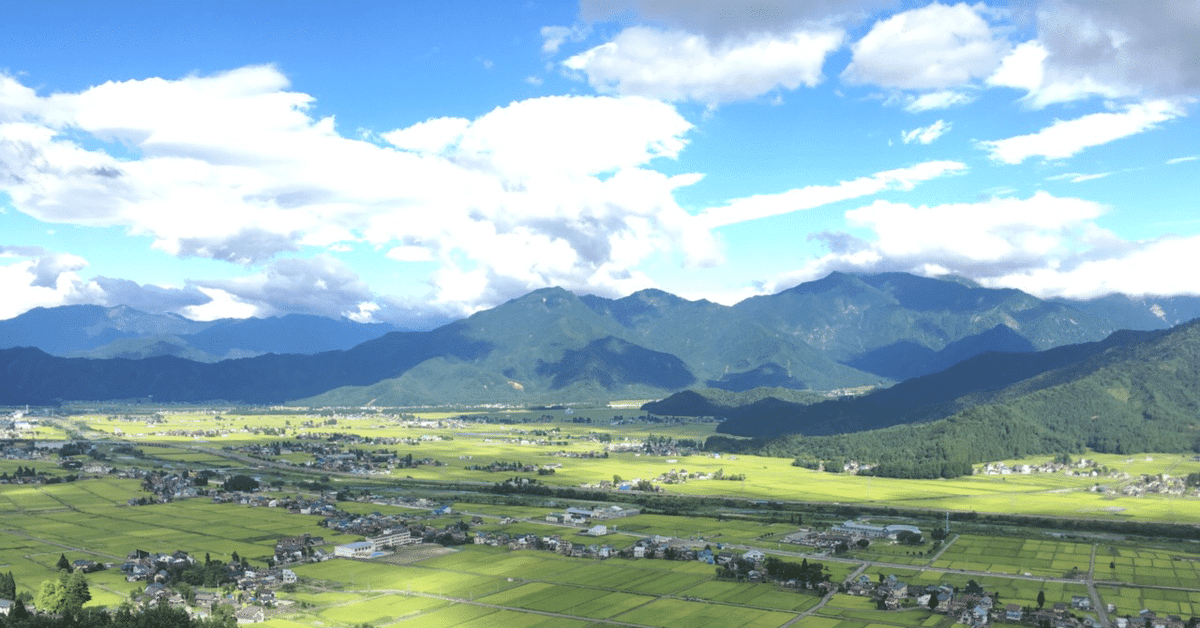
宿災備忘録-発:第2章1話
宿災の始まりは、ある娘の末裔だと言われています。天の荒ぶりは神の怒りとされていた頃、ある家の娘が人柱として災厄に捧げられました。
命を賭けて災厄を治めるはずが無傷で戻り、結果、その娘は奇跡の子と呼ばれ、度々人柱として災厄の前に置かれるようになりました。そうしているうちに、ただの人ではなくなってしまいました。
娘はやがて大人になり、子を産み、孫ができ、当然の如く寿命が尽きてこの世を去りました。しかし永き時を経て、その娘の直系に、生まれながらに災厄を宿した子が生まれました。その性質は受継がれ、いつしか宿災と呼ばれるように……私もこの見た目に生まれたおかげで、幼くして人柱となりました。
生まれつき色素が失われる病だとか。白い髪で、薄い茶色の目をした子どもなど、相当不気味だったのでしょうね。両親は迷わず私を差し出しました。ですが私は命を繋ぎ、奇跡の子となった……
崇めることは、恐れることと、そう違いはないのかもしれません。他者の視線が痛かった。頬に打ちつけた雹よりもずっと……
私は幾度も災厄の前に置かれ、いつしか災厄が宿った、偽宿(ぎしゅく)という存在です。生来の宿災ではありません。この身に宿った災厄が放たれてしまわぬよう、強い結界で留められています。この服にも結界が施されています。全身にも、勿論。
目の色も結界によって色を変えているんですよ。ほら、よく見れば、独特な文字が刻まれているんです。
――そんなこと、信じられる……?
美影は記憶の反芻をやめ、流れる景色にピントを合わせた。黒のワンボックスカーの窓の外。カーブの多い山道。濃淡様々な緑。緑、緑、緑。窓を開けたら、むせかえるような緑の香が流れ込むだろう。
車内には運転手を合わせ4人。しばらく誰も口を開いていない。美影は、隣の運転手を意識下。
小柄な女性。落ち着いたブラウンのセミロング。オフホワイトのシャツ、ジーンズは綺麗な青。運転用のシンプルなスニーカーが、ブレーキを静かに踏み込んだ。
三叉路。対向車はなし。青になった車線からも、車の進入はない。
「帰ってきたって感じするでしょ? この交通量の少なさ」
「懐かしいです」
「疲れてたら寝てもいいからね。長時間の移動って、座ってるだけなのに疲れるのよね」
新幹線で3時間移動。車に乗り換えてから、およそ1時間が経った。久遠が予告した通り、美影は湖野に向かっている。
新幹線の駅で、石橋香織と合流した。山間の湖野までは在来線を乗り継がなければならず、それでは大変だろうと香織が送迎を引き受けてくれた。
香織に連絡をしたのは石寄だった。石寄から連絡を受けた香織から電話がかかってきた時、美影は後戻りできないと感じた。久遠が描いた流れに乗っていると思うと、反発したくなる。まだ信じたわけではない、と心を固くしてしまう。しかし、久遠が石寄の信頼を得たのは事実。石寄という人間が繋ぎとなり、美影は久遠と行動をともにすることを決めた。
久遠は今、後部座席で目を閉じている。新幹線の中でも、ずっとそうしていた。普段から静かな気配の持ち主だから、眠っているのか否か、美影には判断がつかなかった。
美影は、ペットボトルに残っていた炭酸のジュースを飲み干した。新幹線に乗る前に買ったもので、とっくに常温になっていたが、液体の感覚が喉を通り過ぎると、一瞬ぞくりと肌寒さを感じた。半袖のパーカーから伸びた腕を軽くこする。
「エアコン、寒い?」
美影は首を横に振った。そういう種類の寒さではないと、判断できた。
――体の内側から、冷気が流れ出してくる……
灯馬から聞いた【宿災の始まり】を、すんなりとは受け入れられなかった。しかし、目にしてしまったものや、感じてしまったもの、それらと合わせれば、多少強引ではあるが、納得しようと努力することはできた。
否、努力とは少し、違うのかもしれない。灯馬は自身の過去を語った。その話のひとつでも否定すれば、それは灯馬という存在の否定に繋がる。美影はなぜか、灯馬を否定したくなかった。とんでもなく不可思議な存在であるというのに、人間の久遠よりも、なぜか近しく感じている。
宿災の始まり
灯馬の過去
偽宿
全身に施された結界
ぐるぐると頭を巡る謎を振り払うように、美影はいちど咳払いをし、運転席に顔を向けた。
「香織さん、もう少しでコンビニありますよね? 寄ってもらってもいいですか」
「いいわよぅ。ちょっと休憩にしましょうか」
はい、と返し、美影が助手席のシートに座り直すと、後部座席で中森が小さな声を上げた。
「ごめんなさい、眠っちゃった……なんかすごいね、マイナスイオン? 緑のおかげかな。ぐっすり眠った感じ」
「香織さん、運転上手なんです」
「そんなことないない!」
香織は大げさに言って、照れ笑い。美影もつられて笑った。久しぶりに、自然と笑顔になった。
「中森さん、こういう田舎って初めてですか?」
「そういえば、そうかも。あんまり東京から出たことないなぁ」
「慣れない環境って疲れますよね。もう少し行ったら休憩しましょうって言ってたところなんです」
「やったぁ! 僕、新幹線の中でガムしか食べてなくて、実は結構お腹空いてるんですよねー。食事がとれそうなところ、あります?」
「もう少し行くとドライブインがありますよ。コンビニより手前だから、そこに寄りましょうか?」
「地元のご飯とか食べられますかね」
「ありますよ。簡単なものですけど」
やった、と喜ぶ中森は、遊びにきたわけではないと理解した上で楽しんでいる。それは美影にとっての、僅かな救いとなっていた。
――普通に帰省したら、私も楽しめたのかな
美影は、香織と中森の談笑を耳に流し込みながら、空と樹々のコントラストを見つめ続けた。
ドライブインに到着。中森は、先にちょっと、と言ってトイレにダッシュ。久遠は目を閉じたまま。エンジンはかけたままで大丈夫、と言って、香織も車を降りた。
久遠を涼しい車内に残し、熱されたアスファルトの上を歩く。パーキングは、ほぼ満車。売店も食堂も、客入りが良い。
美影も用を済ませ、香織のもとへ。売店の前で、中森と土産物を見ている。
「先生、もうお土産買うんですか?」
美影は中森のことを、先生と呼び続けている。もう医者してないんだけどなあ、と言いつつも、違和感もないようで、中森は受け入れてくれた。
「今、食堂いっぱいみたいだから、なにか買って食べようかなって。ほら、このお饅頭とか美味しそうだし。味噌パンっていうのもあっちにあったよ。初めて見た」
「すぐにあくと思いますよ。そんなに長居するタイプのお店じゃないし」
じゃあ待とうかな、と気を変えた中森に、香織も賛同。食堂へ向かう途中で、美影は微かな冷気を感じた。
――この冷気は……
車に忘れ物をした、と言って、美影は駐車場へ。美影の足は自然と速くなり、香織のワンボックスに着いた時には、鼓動も速くなっていた。
静かにドアを開け、乗車。後部座席の久遠。その隣に、灯馬の姿。
「……まだ、眠ってる?」
「はい」
「疲れてるのかな」
「どうでしょう。湖野自体が大きな結界の中にありますから、安心しているのかもしれません。貴方の状態も落ち着いていますしね。私の気配を感じて、災厄は少し、高ぶっているようですが」
言葉終わりに笑顔。それに反応したのか、美影の深部で、なにものかがざわめく。ざわめきの主は、とある災厄。もとは、灯馬の中にいたのだという。
落ち着いて
今は
私と一緒
あなたは
私と一緒
元の宿り主を求めるものを静め、美影は長く息を吐いた。自分の中にあるのに、自分自身ではない。それを制御するなんて、とんでもなく奇妙なこと。この感覚を、言葉で表せる自信はない。
白装束
深い青色の目
微かに漂う冷気
美影はいつの間にか、灯馬の気配を感じ取れるようになっていた。災厄が感じとり、それが伝わってくるのだろう。灯馬が恋しくて、常に探しあぐねいているのかもしれない。そ
――災厄も幸福を感じる?
だから私も灯馬がそばにいると嬉しいの?
だから灯馬を否定できないの?
私が?
それとも
「美影」
ふいに名を呼ばれ、美影は肩をびくつかせた。この反応は、確かに自分のもの。
「災厄の感情に捕らわれないように。理解は必要ですが、貴方は、貴方自身の意思で動かなければなりません。共生というのは、互いに認め合うということです。どちらかが支配するのとは違います」
丁寧で、柔らかい口調。しかし芯のある音。美影は灯馬の言葉に聞き入った。自分自身の意思で。
「まだ始まったばかりですから、徐々に……ただ、大きな力であることは確かです。自分でどうにもならないと感じたら、すぐに私達を求めて下さいね」
言い終えて、しばしの空白。美影が次の言葉を見つけられずにいると、ポケットのスマートフォンが音を上げた。メッセージは香織から。食堂の席が確保できたとのこと。
読み終えて顔を上げると、灯馬の姿はなかった。ため息。それに反応したように、久遠が目を開ける。そして、寝起きとは思えないほど無駄のない身のこなしで、車を降りた。
美影に声もかけず、スタスタと進む久遠。美影は後を追った。というより、向かう方向が一緒だった。
パーキングを突っ切り、食堂の出入り口が見えた時、久遠は突然立ち止まった。そして、
「どこだ?」
「え、なにが?」
言った美影の横を、もれるもれる、と少年が駆け抜けて行った。久遠は少年の背中を追った。美影はしばしその場で立ち尽くし、堪え切れずに噴き出す。そして思った。
本当に、ただの帰省だったら良かったのに、と。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
