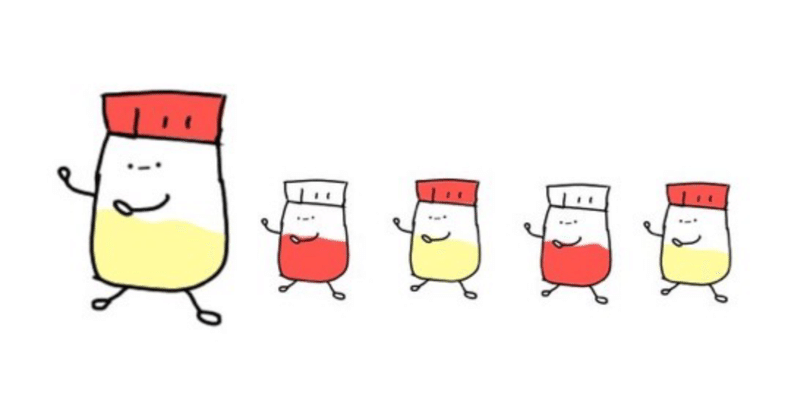
無権代理の意味
【 自己紹介 】
プロフィールページはこちら
このブログでは、2019年7月にうつ病を発症し、それをきっかけに同年12月からブログを始めて、それ以降、700日以上毎日ブログ更新してきた、しがないサラリーマン弁護士である僕が、日々考えていることを綴っています。
毎日ご覧くださってありがとうございます。本当に励みになっています。
【 今日のトピック:無権代理 】
さて、昨日は、「利益相反取引」について書きました。
世の中には、自分の借金の担保として、子どもの不動産に抵当権を設定する親がいて、そんな身勝手な親の所業を放置していいの?と思った最高裁判所は、「そんなときは特別代理人を選任してね。さもなくば抵当権設定契約は無効にします。無効になるとはいえ、銀行は親権者に対して損害賠償を請求できるよ」と認めました。
結局、自分の借金の担保として子どもの不動産に抵当権を設定するのは、「利益相反取引」に該当し、特別代理人の選任が義務付けられ、特別代理人を選任しない場合は無権代理となる、というのが結論です。
うーん、難しいワードがいくつも出てきましたが、「特別代理人」とは、昨日も説明したように、親権者の代わりに子どもの代理人になる人です。
利益相反取引の場面では、親権者が子どもの代理人になれないので、その代わりに、裁判所が選任した「特別代理人」(弁護士がなることもあります)が、子どもの代理人として、契約を結びます。
「無権代理」というワードが出てきましたが、これは、「代理権がない代理人」を意味します。
「代理権がない代理人」ってどういうこと?ですが、例えば、父親が亡くなったので母と子ども3人で話し合い、長男が父親の遺産を全部取得すると合意したので(遺産分割協議)、不動産の名義を亡くなった父から長男名義に変更するため、司法書士に依頼し、印鑑証明書と実印をその司法書士に預けたところ、その司法書士が、実印と印鑑証明書があるのをいいことに、名義変更するどころか、その不動産を売却してしまった、なんてのが「無権代理」の典型例です。
この「売却」、つまり、「不動産の売買契約」がどうなるか、というのが「無権代理」の話で、これは原則として無効となります。
名義変更を依頼しているので、司法書士には名義変更する権限(代理権)はあるのでしょうけど、売却する権限(代理権)はありません。
だから、表面上は、代理人として売買契約を結んだとしても、その契約が土地の持ち主本人も拘束することはありません。
この「契約が土地の持ち主本人は拘束しない」というのを、「効果帰属しない」と法律の世界では呼んでいます。
売買契約の効果が、土地の持ち主本人に帰属しない。これが、「無権代理」となった場合の法的な結論です。
ただ、無権代理の場合、悪いのは無権代理人です。自分に代理権がないのに、代理権があるかのように装って契約を結んでいるわけですからね。
契約が持ち主本人に効果帰属しないとなると、不動産を買った買主はたまったもんじゃありません。
代理人だというから、それを信じて契約を結び、お金も払ったのに、フタを開けてみたら、代理権もないのに勝手に売買契約を結んでいて、それが本人に効果帰属しない結果、せっかくお金を払ったのに不動産の名義が自分(=買主)に変わりません。
変わらないなら変わらないで、お金を返してもらう必要があります。それが「無権代理人の責任」というやつで、無権代理人である司法書士は、受け取った代金を全額返金しなきゃいけません。
昨日は、「無権代理だと契約は無効になる」と、サラッと書いてしまいましたが、正確には「無権代理になる」です。
この「無権代理になる」の意味がわかりにくいので、今日は少し丁寧に説明しました。
さて、昨日は最後に「親権の濫用について説明する」と言っておきながら、今日は無権代理について説明してしまいました汗
明日また、親権の濫用について説明しようと思います。
それではまた明日!・・・↓
*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*
TwitterとFacebookでも情報発信しています。フォローしてくださると嬉しいです。
昨日のブログはこちら↓
僕に興味を持っていただいた方はこちらからいろいろとご覧ください。
━━━━━━━━━━━━
※内容に共感いただけたら、記事のシェアをお願いします。
毎日記事を更新しています。フォローの上、毎日ご覧くださると嬉しいです。
サポートしてくださると,めちゃくちゃ嬉しいです!いただいたサポートは,書籍購入費などの活動資金に使わせていただきます!
