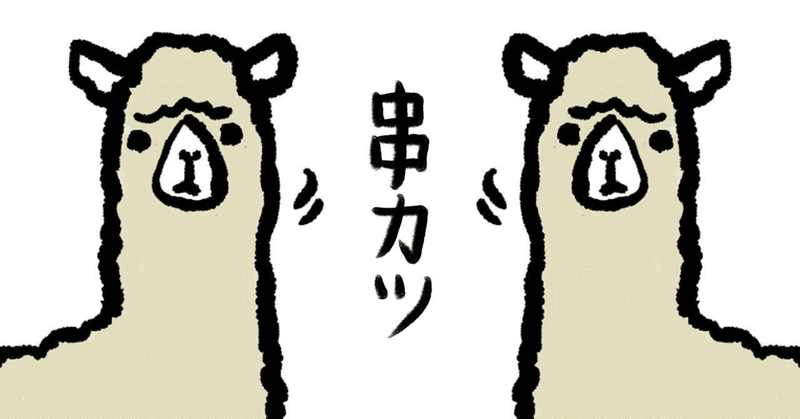
【短編小説】ぼんやりだけど通じてる
ある意味、名は体を表すのかもしれなかった。
39歳、独身。派遣社員で工場勤務の萩野流星は今日も薄暗い工場内でライン業務を黙々とこなしていた。
このところの冷えた朝の空気は気分が引き締まるだなんて、とてもじゃないが言えたものではない。だが萩野は毎朝、余りものを詰めた自作弁当と熱いお茶の入った水筒をリュックを背に出勤し、帰宅時には業務用スーパーなどに立ち寄り、生活用品や酒、食材を購入する日々を送っていた。
ちなみに今日の弁当はきのう多めのごま油と卵を3個も使い、弁当用に取り置いたにら玉の残りだ。大きめのタッパぎゅうぎゅうに詰めた白米に、にら玉を乗せ、その上に固めの甘酢餡を乗せたもの。コンビニ店員とやり取りをするよりも萩野にとっては自分で作る弁当のほうが断然楽だった。
買い出しの手間も省けて節約にもなり、なにより男飯はうまいので一石二鳥、三鳥なのである。工場の仕事の受け入れ幅は広いが、実際、誰にでもできる仕事内容ではない。工場内の夏はうだるように暑く、冬は凍えるほど冷たい。萩野の場合は夜勤もあった。
労働環境は厳しいと言われ、訳ありの人間も多いこの職場はひとの入れ替わりも激しい。その場所で萩野は今年勤務9年目になろうとしていた。
萩野の見た目を小柄な小太りと形容するには最近では無理も出てきた。
8年間の月日は萩野の横幅をかなりの速度で成長させ、作業服のサイズを3回も変えた。
それでも『流星』との名の通り、萩野の発する言葉は流れ星のようにスピードが早く、声も細く小さい。フッと現れ、すっと空中に吸い込まれてゆく。なのに流れ星である荻野に願い事を唱えようとする人間は未だかつて現れていなかった。
それどころか「あ? なんだって?」「ボソボソ喋りやがって! 何言ってんのかわかんねーよ!」勤務当初はそれだけでリーダー長に工場内の騒音を上回る大声でよく怒鳴られていた。
流星という名。昨今ではキラキラネームでもないが多少チャラついた奴にこそ、やはりよく似合うと萩野は感じてしまう。萩野は今日も工場の一部になりながらそう思った。
しかも、こういう少し目立つような名前は大人になっても親しくない人間にまで『流星』と呼ばれてしまいがちだ。
そもそも萩野に親しい人間自体が存在したのかという話だが。
今まで色々な職場を転々とした萩野だったが圧倒的に『流星』と下の名前で呼ばれることが多かった。
そして仕事上でのミスや深刻な話がある際に(要はクビ)上司が『萩野くん』とお決まりのように苗字を呼ぶことにも慣れてしまった。
どこかのお母さんが『めいちゃん』と普段呼んでいる我が子に、怒るときだけドスを効かせながら『めい、こっちにいらっしゃい』とやる、例のあれと根っこは同じだ。
学生の頃の『静香』はもれなくうるさい奴が多かったし『陽子』はいつもうつむき加減で暗い印象を漂わせていた川辺陽子のおかげで『陽子という名前の奴は暗い』と萩野のなかで偏見も生まれた。
だから川辺陽子のなかで『流星という名前のやつは小柄なでぶでボソボソ喋る何言ってるかわかんないやつ』という偏見があってもそれは甘受しなければと萩野は思っていた。
唐突だが萩野は幸せ者である。
ひとつは萩野が料理好きであり食べること、飲むことの喜びに身を委ねる才能があるからだった。
頑張った一週間のお楽しみは自分の食べたい物を作り、濃い目のレモンサワーを飲むことが萩野の至福の時間だ。
作業中に突如、頭に浮かんだ串カツ。晩酌は串カツでレモンサワーだ。
材料は大したものじゃなくて十分だった。
玉ねぎ、冷凍オクラを戻し、半額だった豚バラ肉を解凍しグローブのような手でぎゅっと握って一口サイズの肉の固まりにした。それらをバッター液につけ、パン粉をまぶしひとつひとつ丁寧に揚げた。
3人分はありそうな串カツが出来上がり、トンカツソースと辛子、それにしなびかけていたキャベツをザク切りにして横に置いた。
まずは豚バラ串だ。トンカツソースにたっぷりの辛子を混ぜたものをつけ、はふはふと言いながらがぶりと歯を立てた。口内に豚の甘味と脂と油がほとばしり、そこにレモンサワーで追い打ちをかける。キャベツのザク切りもソースにちょんとつけてぼりぼりと食べた。
玉ねぎも熱々カリカリで、なかはほわっと柔らかく甘い。冷凍オクラもシンプルながら油との相性はばっちりだ。手にしているレモンサワーの濃度がどんどん上がり、萩野は饒舌になりはじめた。
「アミちゃん僕はねアミちゃんがいるから毎日頑張れるんだ」
〈……相変わらず、何言ってんのかわからないんだけど……〉
アミは萩野をしげしげと眺めた。
「アミちゃんアミちゃんは僕の言ってることわかるんだよね」
〈うん? わたし目が悪いから景色さえぼやけてるのよねえ……〉
顔を上げたアミが萩野と数秒ほど見つめ合ったかのように見えた。
「アミちゃんかわいいねいつもありがとう」
〈でも、そんなことどうだっていいわ。なんだか心地がいいんだもの〉
8歳になるニシキヘビのアミはそっと目を閉じ、萩野の膝の上でゆっくりととぐろを巻いた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
