
30年ほど前からも、私の問いに丁寧に答えて下さり、耐久性関連の資料も下さった山本幸一先生が、最新の(木材保存-2024.VOL50.NO3)に寄稿されている。テーマは木材の素材耐久性ではあるが、裏に流れるテーマは、”持続可能資源”のようである。
こう書かれている。
持続可能な世界を築くためのSDGs(持続可能な開発目標:Sustainable Development Goals)の一つである気候変動(地球温暖化)対策の観点から、化石資源利用の抑制と天然資源、とりわけ再生可能な木質資源の活用が必須となっている。

以前にも、出している国産材の統計のグラフであるが、積極的に国産材を使える状況にあると思う。

どんどん、国産材の蓄積が増えていくという状況にあるのは今も変わらない。
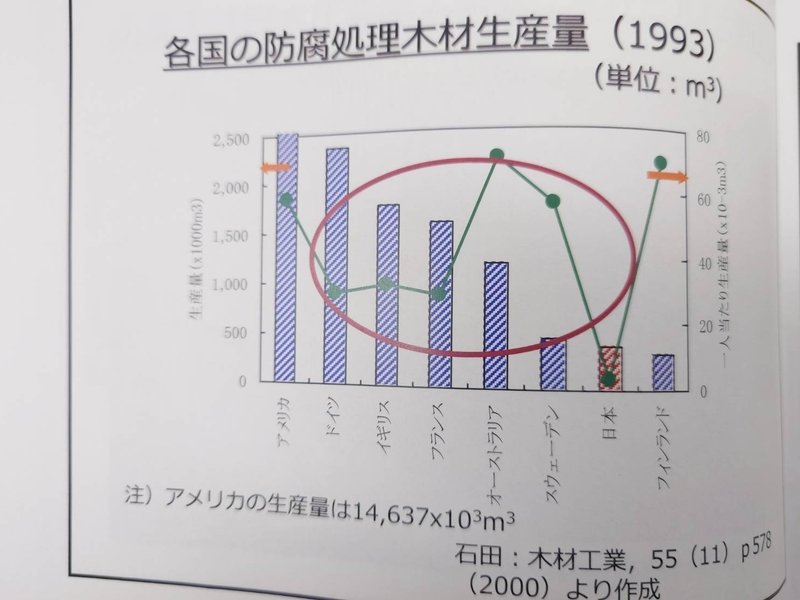
木材の改質で、耐久性を高めて、エクステリア利用を増やすことが国産材使用のBEST解ではないだろうか?
(再び山本幸一先生の考察に戻ろう)
木材保存の分野においては、建築物や土木構築物を中心として利用される木質材料の長命化のため
①耐久設計・構造
②環境配慮型の木材保存処理
③木材の素材耐久性
④維持管理
耐久設計・構造 といった多様な配慮を求められるであろう。
と書かれ、以下エクステリア用で①~④を心がけるため、もう一度、国産材・外材の耐久性について考察をされている。
①~④は、以前から自分自身、心がけていたあるいは、施工で留意している極めて大事な項目である。
②の木材の保存処理は環境順応のため、かつてのように、強力な保存剤を使わないので、それに対応するには、耐腐朽は、何重ものディフェンスをするべき(物理的・化学的両面で)
杉・ヒノキという樹種は、よく保存剤を吸収しつつ、樹種自体も心材の耐久性は高い。
環境省の耐久性比較にも、一回目の保存処理だけでも、イペ・ウリンにほぼ匹敵するとされている。
弊社はそれに、更に、二回目の保存処理で外周を腐朽菌に突破されても持ちこたえられるようにしている。
最後に、シリコン塗膜でコーティングし、物理的な耐久性・・水分吸収への準備、を行っている。
工学には絶対安全がないと思うが、それを限りなく安全な漸近線に持ってくのが、施工に期待しなければ実現しない、という①耐久設計・構造④維持管理だ。
今、これは実行している。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
