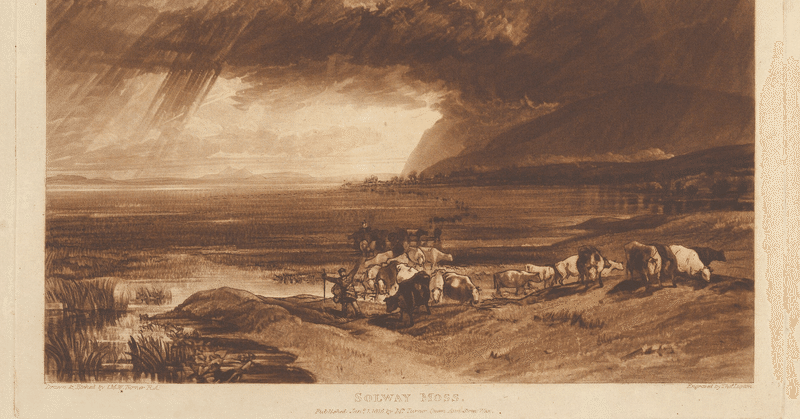
「何であれ構わない」性の超克
抽象的で、かつ役に立たないことを書く。そうエクスキューズしなければ、ここから何も語れないだろうと思う。自分の内面があるとするならば、それは中東の荒野にある町のように乾いている。触れないが、よく見える。
閉塞したとき、停滞した時にわたしは書く。と思っていたが、閉塞と停滞とは突き詰めるとつまり、飽きることである。飽食の時代。気付けばサブスク、YouTubeの動画、安価なコンテンツで腹を膨らしたことへの怒りが湧く。
この前先生が、他人と同じコンテンツの消費の仕方をしないために、比較文学が存在する、というようなことを言った。そうかもしれない、と思った。それと同時に、コンテンツの消費の仕方一つで差異化して、他人と別れて、自分の小径に入ってゆく孤独さを想った。
文学とは、読書とは、創作とは、孤独なものだ。
孤独を愛せる者のみが、ひとりしずかに機を織り、自分という内面を切り開くことができる。そしてそれは、承認欲求、その果てにある他者の承認から遠く隔たった、核シェルターのような静謐なところでなされる秘密の作業であったはずのものだ。しかしそれゆえに、その孤独を歩む者は、他の人間と強度が異なる。少し話せば、それは感知できる。こいつは孤独を知っている、いい人間だと。
書くこと。読むこと。孤独の散歩道を往来する夢遊病者のごとく、私はその作業を繰り返したいと思う。だがその一方で、自分の在り方を、社会的な大きな文脈にすり合わせたいとも思う。他者の承認のもと、文章を書き、それに読者がいればどんなにか幸せだろうと思うのだ。
「あなたでなくてはいけない」と言ってくれる他者は、どのように生まれてくるのかについて考える。それは恋愛の文脈でも、アイドルなどの推しに対してでも、友人でも家族でもあり得るだろう。だが、それが実現するための条件は何か。
それはおそらく、一定程度の偶然と、他者を惹きつけておく引力だ。それは他者を愉しませる娯楽性だ。
東浩紀は、娯楽性について暫定的にではあるが以下のように定義している。
娯楽性とはなんでしょうか。それはひとことで言えば、こちらにふまじめにしか接してこない人間を、掴み離さない能力のことです。
私たちは普段文章を読むにせよ、動画を見るにせよ、音楽を聴く、そして人と会うときさえ、ある程度は「何であれ構わない」と思っている。でなければ、毎日が失望の連続で、ままならぬ生の辛酸があまりにも重荷になるだろう。
その「何であれ」性をもって接されるコンテンツのはずだったものが、突然鋭く自分の内面を抉ってくるときがある。或いはこれは自分のためのものだ、と直感されたりする。(サリンジャーの『キャッチャー』の有名なファンの反応のように)
掴むこと、離さないこと。これらはいずれも簡単ではないだろう。それは長い板の先端に重りをつけて持ち続けるようなものだ。こちら側に相当の筋力と、そして持久力が要求されるだろう。批評言語を確立し、その強度を高めるだけでなく、なにか一つでもかまわないから、継続して見せようと思う。継続は苦手だ。友人にからかわれる度に、「おれは命と学校以外継続していることがない」というのももう食傷気味で、厭いてきたところだ。
風穴を開け、剔抉する。「何であれ構わない」ものから、一歩進む。それは切実な希求であり、自らの内側にもある「何であれ構わない」ものというひとつの概念を抹殺することでしか得られない。これを越えなければ、自分が始まらない。芽吹かない。
砂漠の真ん中で枯れた川のように、創作意欲も題材もなく、ただ口を開けて物を読み耽ったここ三か月を糧にするのだ。
とんでもない寒さになるらしい。雪が降って、白くなる街並みを想う。神戸は滅多に雪が降らない。が、もし雪が降ったなら、新しい言語で雪を綴ろうと思う。それがどのような形をとるかは分からない。それが文章という形をとったならば、ここに書くこともあるかもしれない。
