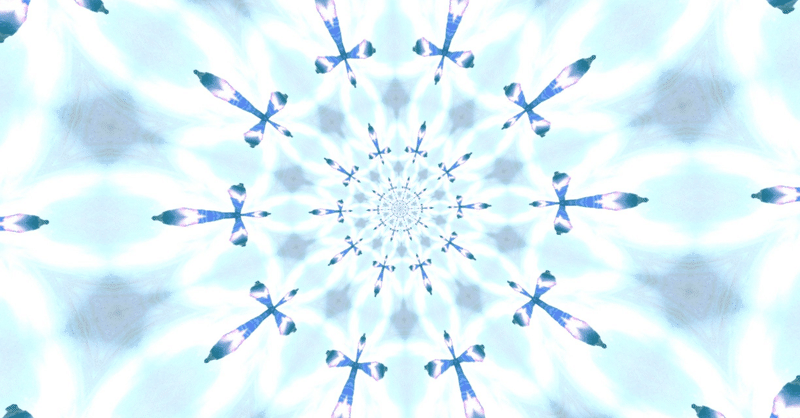
『奇談・怪談・夢語り その五』
~ダンスダンスダンス~
もう四十年も前の話し。
私が高校を卒業と同時に東京に職を得て上京した頃のこと。
職場は創業100年という老舗の茶葉の会社だった。
田舎暮らしに嫌気がさしていたから、初めはとにかく出てこれた嬉しさを噛みしめていた。職場に都会に早く慣れようとウキウキしながら私は必死に溶け込もうとしていた。
新入社員は研修期間、都内の商店街各所で実演販売が課せられた。
一日だけ本社でオリエンテーションとロールプレイングを行い、翌日から先輩のルート販売員の配達車で、商品、必要な道具一式と共に見知らぬ街において行かれる。夕方迎えに来てもらうまでその場でひたすら声を張り上げ茶葉を売るのだ。
二人体制だったがそのうち私はひとりで任されるようになった。それをひと月こなした後、百貨店や駅ビルの各店舗へ配置になるのだ。
私は要領よくこなしていた。周りの評判もよかった。自分では早くも憧れの街に馴染んだような気になっていた。
ところが次第に、林立するビルディングに息苦しさを感じ、祭りでもないのに人が溢れていることに辟易し、水道やお風呂の消毒液の臭いに嫌気がさしてきた。生活環境のあまりの違いに、夢見ていた都会生活をまったく楽しめていない自分に気付いた。
どこか丈の合わない衣装を身に着け、無理に踊っているようなものだったのだ。魂のうんと奥では、ちぐはぐな外側と内側が擦れて傷を作っていたに違いない。
そうして実演販売の途中、行き交う人の視線が妙に気になったり、商店街に流れてくる有線の歌に涙が溢れたりと神経が過敏になっていた。
それはまだ二十歳前の何の覚悟もない、背伸びしすぎた田舎娘のホームシックというものだったのだろう。
その日は身体が重くどうしようもなく眠かった。
疲れが溜まっているだけなのだと思い、休日、私は寮の同室の先輩の誘いを断り、ひとり、部屋で休むことにした。
「気晴らしになるから」と買物やイベントなど、どこかしらへよく連れ出してくれた先輩だった。でも今日はとにかく身体を休めようと思った。
先輩を送り出しベッドに寝ころんで階下で回っている洗濯機が止まるのを待っていた。
すぐにウトウト眠気が差してきた。
その時足元に近い部屋のドアが開いて廊下の明かりが細く入って来た。
先輩が忘れ物でも取りに帰ったのだろうと思った。私は眠気に逆らえず声もかけずそのまま横になっていた。
ところが、入って来た人影がこちらへやって来る。
重い瞼の隙間から見えたのは足元がジーンズの男性だった。
女子寮に男?
起き上がろうとした。声を上げようとしたのだが。
身体は動かないし声も出せない。瞼もこれ以上開けられない。明るい春の陽が部屋に満ちるその中で私は金縛りにあっていた。
人影は私の傍らに立った。
両手を背中と腿裏に差入れられ軽々と抱き上げられた。
その人影はどこからか流れてくる音楽にのって、私を抱き上げたまま踊っていた。ときに優しくスイングしている。
小さな子どもをあやすかのように踊っていた。
私は恐怖も感じずされるがままで、むしろ、いつまでもこのままでいたいような気分になっていた。ゆったりと腕に抱えられ、優しい曲に乗って光の中ダンスが続く。
溜まっていた疲れが隅々まで癒されていくようだった。
あまりの心地よさに、とうとうそのまま眠りに落ちていった。
眠りに落ちるとき微かに見えたのは、白いTシャツに胸の紅い模様。
花びらのようだ。と思う間もなく深く深く眠りに落ちていた。
誰かに膝をゆすられた。
「あなたずっとそんな恰好で寝てたの?いくらなんでも、風邪ひくよ」
帰って来た先輩だった。ゆり起こされて目を開けると、もう辺りは夕闇に包まれていた。
夢?夢を見ていたのか。
ああそれにしてもなんて気持ちのいい夢だったのだろう。
明日からまた一週間が始まる。どこへ配置になるのか決まる頃だった。
晩ごはんの食堂では、八重洲地下街だの小田急百貨店だの吉祥寺の駅ビルだの人気の店舗が、新入社員の間から聞こえていた。
そんなことより私はあの人影が気になっていた。
さっきの夢のあの男性はいったい誰だったのだろう。とんでもなくリアルな夢だったじゃないか。夢に出てくるほど恋焦がれる人なんていないというのに。それとも未来の恋人だったのだろうか。
それが誰だかわかったのは、お盆に里帰りしたときだった。
帰省の飛行機の中でふと思い出したことがあった。
近所のお兄ちゃん。
一人っ子の私を小さい頃可愛がってくれたお兄ちゃんだ。
お兄ちゃんにも弟妹はなく実の妹のように接してくれていた。
あれは小学校に入ってすぐくらいの頃だった。
テレビの社交ダンスを見てお兄ちゃんがふざけて私の手を取った。
何かの用事でお兄ちゃんは両親と一緒に私の家に来ていたのだ。
お兄ちゃんのお父さんとお母さんが「若い頃やってたんだ」と踊り始めたからだ。
ワルツだとかルンバだとか聞きなれない言葉が頭の上を飛び交っていた。
私の父や母はまるっきりそんなことには関心がなく苦虫を嚙み潰したような顔になっていた。きっとまた「あの都会もんが、」と陰で罵るのだと胸が痛んだ。
三人はご機嫌だった。
あのときの三人の笑顔が私はとても羨ましかった。
私の家にはないものだった。
だから、父よりも母よりも一番にあの人たちに会いたかった。
なのにもう会えないなんて。
たまたま空港で会った親戚に事の顛末を聞かされ私は立ちすくんだ。
春のある日、一家心中の末三人は亡くなっていた。
都会から田舎へやってきた一家は何年たってもこの土地に馴染めなかった。病身の両親をひとりで支えていたというお兄ちゃん。
疲れ果てて追いつめられふたりを手にかけた。
お兄ちゃんは最後に自分の胸をナイフで刺し絶命したという。
白いTシャツにはまるで紅い牡丹のような模様が広がっていたというのだ。
お兄ちゃんは私に会いに来てくれたのだ。
疲れ果てていた幼いままの私を癒しに来てくれたのだ。
私は何もしてあげられなかったというのに。
了
ご高覧たまわりありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
