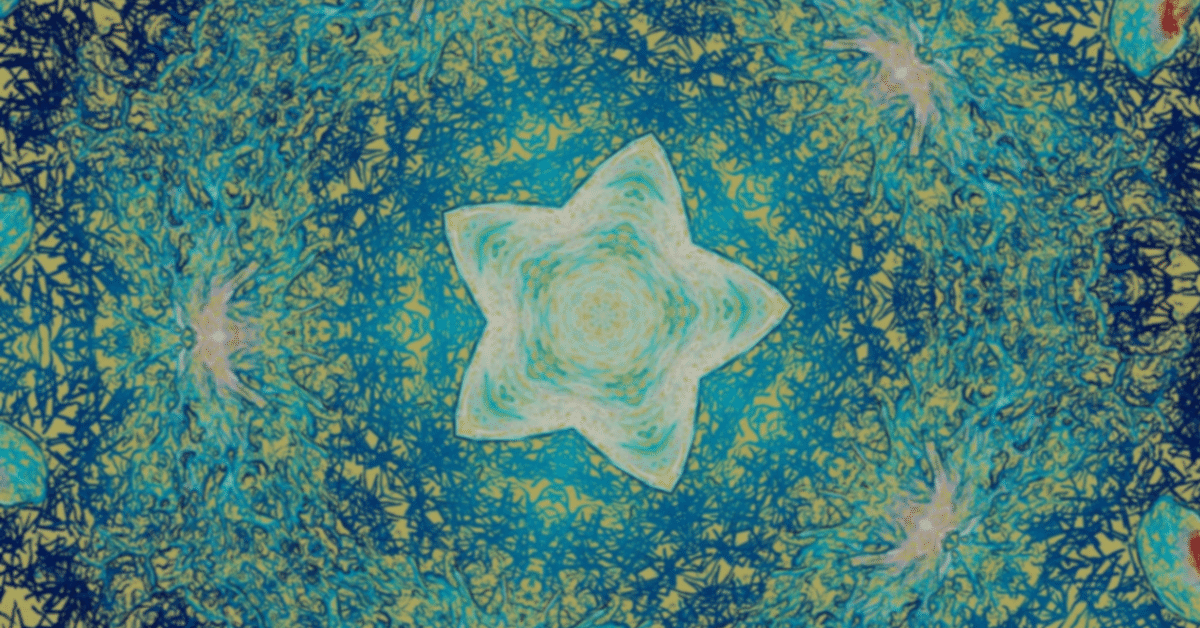
『奇談・怪談・夢語り その七』
~不老不死~
「あの、大丈夫、ですか」
横断歩道の真ん中で倒れ込んだ老人に私は手を貸した。
信号はもう赤に変わってしまったがまだ渡りきれない。
その間老人は今来た方を振り返り振り返りして、心ここにあらずといった様子だった。
ようやく歩道までたどり着きもう一度「大丈夫ですか」と声をかけたが、やはり返事はなく躰が小刻みに震えている。
「救急車、呼びましょうか?」
そこでようやく気付いたように老人は私に目を合わせた。
「い、いや、かまわんで、くれ。わしは、大丈、夫じゃ」
杖を頼りに歩き出そうとするがふらついている。危なっかしくて見ていられない。
「そこのカフェで少し休んでいかれたら、いかがです」
見ず知らずの老人に要らぬお節介かもしれないが、ほっとけなくてまた声をかけた。
目の前に「純喫茶 ボン」と看板があった。
くすんだドアや庇がカフェというよりもずい分と昭和の匂いをさせている店だった。
「おおっ、そうだ、そうしよう。
あんた、あんたもよかったらどうかね。ちょっとお礼もさせてほしいし」
断れない雰囲気だった。大して急ぐ用事もないし、私は老人が落ち着くまで付き合おうと思った。少し気になることもあったし。
ついさっき老人は、青信号で動き始めた人の流れの中、急に立ち止まり棒立ちになっていた。私は少し後ろを歩いていたのだが、休日の繁華街へ向かう道筋に突然立ち止まるから人の流れが滞る。
「ちっ」「おいおい」「邪魔」
怒気を含んだ呟きがいくつも聞こえた。
そしてイヤホンの音楽に気を取られた若者に勢いよくぶつかったのだ。
若者にはこれといってダメージはなかったのだが、驚ろかされたことに苛ついたのだろう、老人に迷惑そうな一瞥をくれ足早に立ち去っていった。
「いらっしゃいませ」ドアを押すと明るい声が響いた。
「あら、佐々木さん、今日は若い女の子とご一緒なのね」
老人はここの常連だったようだ。
一番奥のボックス席に落ち着いた途端、佐々木さんは私にこんなことをいった。「あんた、年も取らず、死にもしない。不老、そう、不老不死、という言葉をどう思うかね」
「年も取らず、死にもしない。不老不死、ですか?
ドラマか映画の話し、ですか?」
「いや、それが・・・」
これは是非とも誰かに聞いてもらいたいと焦ったのだろう、運ばれてきたコップの水にむせていた。
「ごほっごほっ、」「あの、本当に病院とか行かなくて大丈夫ですか」
佐々木さんは私に掌を向けた。まあ聞いてくれということらしい。
そうして佐々木さんの話は始まった。
今年九十三歳になるという佐々木さんは十五歳で終戦を迎えたが、あともう少しで特攻隊員として飛び立つところだったそうだ。
先輩に二十歳になったばかりの辻さんという隊員がいた。
辻さんは年下の佐々木さんを実の弟のように可愛がってくれた。
厳しい訓練に音を上げそうになることが度々あったがいつも励ましてくれたし、時に上官からかばってもくれた人だったという。尊敬する憧れの先輩、兄のような人だったと。
その辻さんがある夜、つかの間の休息時間に佐々木さんの部屋を訪れた。
その日は特に激しい訓練で、心身ともに疲れ果て立ち上がれないくらい疲弊していたからまた励ますつもりでやってきてくれたのだと思った。
辻さんは寝台に起き上がろうとする佐々木さんをそのままにさせ、故郷の話しをしてくれた。美しい景色やおいしい食べ物のことなど、他愛のない話しだったが最後にこんなことをいった。
「佐々木、俺はもう四、五日もすれば任務に向かうが、きっと俺は帰ってくる。お前も何とかしてこの戦いを生き延びろ。そしたらまた会うこともあるだろう」
辻さんは自分を励ますためにそういったのだろうが、任務に向かうというのはそのまま死を意味するのだ。帰ってくることはあり得ない。
それともまさか何か不都合なことでも計画しているのか。
佐々木さんの疑問は顔に出ていたのだろう。帰りかけた辻さんは戻ってきて、
「いいか、これはお前にだけ打ち明ける。誰にもいってはいけないぞ。
佐々木、俺は、これ以上年も取らず、何があっても死なない躰、なのさ」
秘密を打ち明ける小学生のように笑ってウインクまでした。
それだけいうと「じゃあな」と部屋を出ていった。
これが別れの夜だった。
四、五日といっていたが急きょ翌日、辻さんは飛び立ち帰還することはなかった。やはり戦禍に散ったのだと思った。
しばらくしてこの大戦は敗戦し終戦となった。
佐々木さんは天涯孤独の身だった。故郷に帰っても頼る者もない。ひとり都市部に出てこれまで遮二無二働き、裸一貫の人生を歩んできたという。
あれから78年にもなるが辻さんのことを忘れたことはなかった。
兄と慕った人だ。その人と撮った、すり切れた一枚の写真を肌身離さず持ち歩いていた。
その辻さんに今さっきすれ違ったというのだ。
横断歩道の反対側から歩いてきたのだと。
身なりは今どきの青年だが、あの基地から飛び立ったときそのままの顔かたちだった。見間違えるはずがない。間近ですれ違ったとき確信したのだ。
その特徴的な顔の傷。頬にくっきり刻まれた、こめかみまで走る傷は見間違えようがない。
そして、一瞬目が合ったとき見開いた瞳がこちらをはっきり認めた様子だったという。
「あんた、これ、どう思うかね。」
佐々木さんは運ばれてきたコーヒーに口もつけずにいた。
流れる汗を拭こうとおしぼりに手を伸ばした。
「いけませんね、佐々木さん」
冷たい私の呟きに佐々木さんは顔を上げた。
やっぱりそんなことだったのだ。嫌な予感がしたのだ。
「うっ、ううう、」
今度は私が、うめき声の漏れる佐々木さんに掌を向ける。
「いけませんね、佐々木さん。その話ししちゃあ。
辻さんはそれを、あなたにだけ打ち明けたのです」
一度腰を浮かした佐々木さんは目を大きく見開き、そのまま赤いビロードの椅子に沈んでいった。
頭を椅子の背にもたせかけゆっくり目を閉じていく。
息が静かに途切れていく。
「これ二人分の代金です。
佐々木さん、ちょっとお疲れみたいなの。
少し休ませてあげてくださいね」
私はそういうと店を後にした。
人には語ってはいけないことがある。
誰にも明かしてはいけない、匂わせてもいけないことが。
これはどちらも決して口外してはならなかったのだ。
ペナルティは辻さんにも課さなくてはならない。
それが監視者の私の仕事。
春の名残、交差点の端に植えられている桜はもう葉桜になっていた。
了
ご高覧たまわりありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
