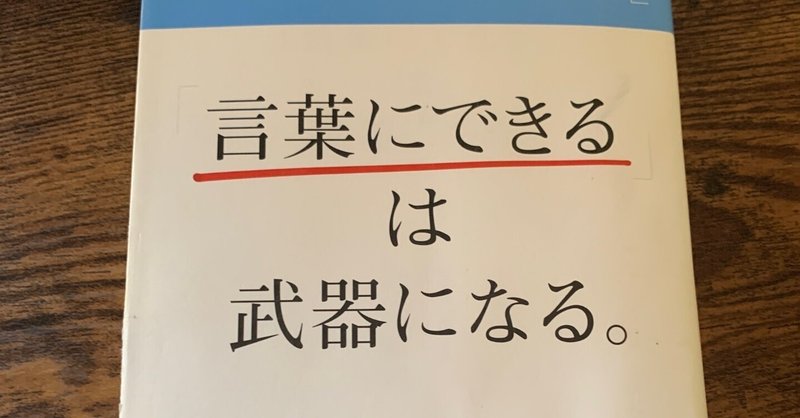
言葉とはなんなのか?
「言葉にできる」は武器になる。
著者 梅田悟司 日本経済新聞出版社
自分は話すのが苦手だ。もともとの性格なのか、いままでの経験の影響なのか、または他の影響なのか、、。周りには話すことが得意な人、苦手な人がいる。その差はなんだろうか。自分の思いや気持ちを「言葉」にして表現できるようになりたいと思ったのがキッカケで本を取った。
自分が思う、話が上手い人とは自分の考え、思考がしっかりと基本にあり、それを他人に自分の言葉に変換して伝えられている。そう考えると思考が大切なのか、、または、言葉の量、知識量が必要なのかと考えていた。
この本を読んで気づいたことは
・ コミュニケーションにはレベルがあること。
不理解、誤解→理解→納得→共感、共鳴。
並べた言葉だけで伝わるのは理解までとなってしまう。自分の思いが加わって初めて納得まで行けるのではないか?
・言葉が意見を伝える道具ならば、まず、意見を育てる必要があること。
・課題に対して、頭に浮かんだ言葉や考えを「なぜ?」、「それで?」、「本当に?」と繰り返すこと。
・自分の「思い」をどれだけ言葉にしてさらけ出せるか。
この3つがコミュニケーションをとる上で基本となることを知った。
本を読んで衝撃だった。会話とは情報交換のようなものだと思っていた。自分の言葉を伝えられる、コミュニケーションを良くするためには、見直すのは「外に出る言葉」ではなく、自分の思い、意志がある「内なる言葉」と向き合い、言葉にして深く掘り下げていくこと。その為には、自分の内から湧いてくるもの、「感情」が必要と。「感情」や「思い」を伝えるために言葉があるのだと。社会人となり、忙しい日々や仕事に追われて成果を出すために働いていると、情報や統計的、科学的数値からモノゴトを考えることが増えてしまっていた。
一度、立ち止まって自分と向き合い、「なぜ?」、「ほんとに?」、「それで?」と問いかける必要がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
