
「ソロキャンプを動画に撮る」シリーズ『厳選ギアで夏を軽やかに楽しむ』 〜 解説(2) 動画編集の裏話
さて、今回の動画解説は記事を2つに分けて、前編ではギアなどのキャンプそのものの話を、後編の当記事ではその撮影や撮ってきた素材の編集にまつわる裏話的な話をしています。前回の記事はこちらになります。
動画全般について
そもそも今回の動画はこれまでの動画とは多少趣向を変えている部分があります。まずイントロからしてそうなのですが、これまでの動画ではほとんど使っていない「アップテンポ(というほど速くはないのですが)の明るい楽曲」を採用しています。
わたしのキャンプ動画は基本的に「自分がソロキャンプに求めるものを抽出して保存したい」的な動機が大元にあって作っているものなので、BGMとして挿入する曲も、ずっと雰囲気を重視して選んでいます。具体的にはアコースティックギターのソロとか、ピアノのソロとか、シンプルでセンチメンタルな曲調のものが多いわけですが、夏はなかなかそういう画になりにくいんですよね。日差しが強くて、緑も濃くて。
そこで今回はちょっと「動画としてのメリハリ」ということを考えて、明るいシーンでは無理に暗い曲を使わず、むしろ明るさを強調する方向にしています。ついでに、動画として見ていて退屈しないようにシーンの切り替えの「トランジション」も、少し過剰なくらいの演出を入れてみました。
この点には実はちょっと逡巡というか、少し屈託があって、個人的には「本当に研ぎ澄まされたカットにはディゾルブもフェードアウトも要らない」みたいな思い込みがあるので、編集作業の中で、自然に繋げずにディゾルブを入れたりフェードアウト&フェードインにしたりする度に、かすかに何かに負けたような感覚があるんですね。でも、たとえば音楽のビートに合わせて刻んで行ったり、そのままだと無駄に長い尺になってしまう冗漫な場面を短縮するために同アングルでジャンプカット的に切る時、見ている側がむしろその引っ掛かりを楽しめるように細工を利かす、というのは、ある意味で映画的な「ただ切って、ただ繋ぐ」というストイックな編集とは少し違うジャンルの行為なのかな、ということを何となく考えながら作っていったのが今回の動画です。
以下、種明かしではないですが、その「細々した細工」の部分についてひとつずつ。
イントロのタイピング演出

今回のイントロでは明るい曲に合わせて少しコミカルな印象を醸し出したかったので、あたかも画面にタイピングしているように文字がひとつずつ現れて漢字変換されていくように「お題」を表示しています。(これにはいつもの動画と違って雰囲気オンリーの動画ではなく「テーマ」に基づいて作られた動画なのでそのつもりで見て欲しいですよ、ということを伝える意味もありました。)
なお、この演出はテキストをアニメーションさせているのではなく、エディタでその文字列を(大きなフォントで)実際に打ち込むところをスクリーンレコーディングで録画したものを背景画像に重ねています。
ただ、そのままでは水面の照り返し部分が明るすぎて白文字が見えなくなってしまったので、入力した文字列が確定されるタイミングで、同じ画像にガウスぼかしをかけたものを描画モード「除外」でさらに下に差し込んで擬似的に輪郭に見えるようにしています。テキストでアニメーションを真面目に作っていれば色々やりようのあるところかと思いますが、録画で処理という手抜きをやっているので追加の小細工が必要になったケースでした。
ちなみに背景で流れている設営の早回し映像は、設営前から設営終了まで同じポジションからトータルで2時間ほど撮影した映像を16倍速にし、タープ張り、グランドシート展開、テント設営など、キーになる部分だけをカットして繋げたものです。それぞれのポイントで手元での撮影などもやっているので結構時間がかかるのですが、カメラ2台体制で、ロングショット側のカメラは外部電源を繋いで、外部レコーダーでSSDに録画しているのでこういう力技が可能でした。
木漏れ日の映像

わたしが作るキャンプ動画は先述の通り、「どういう場所でどんな雰囲気でキャンプをしているのか」を残したいというのが根っこにあるので、基本的にオープニングとかその直後に、「その時、その場所の空気」を伝えるためのカットを入れるようにしています。
今回は「夏」の動画なので、日差しの強さを強調できる画が欲しい、ということで、一部のカットに、フレーム内に強い光源を入れると派手なフレアを引き起こす「アナモルフィックレンズ」を採用しました。以前にクラウドファンディングサイト Indiegogo で Sirui が 75mm T/2.9 のプロジェクトを立ち上げたときに一口乗っていたものなのですが、めちゃくちゃ重い上にやはり使いどころが難しく、なかなか使えずにいたものをようやく使えた形です。
同じレンズを後半の焚き火のカットでも使っていて、以下のショットではアナモルフィック特有の縦長のボケが確認できます。

本当ならこの特有のボケの形状についてももっと効果的に見せていきたいところなのですが、キャンプ動画だとそもそも「遠景の点光源」というのがあまり存在しないので、なかなかうまく使えるシチュエーションが思い付かず、今後の課題という感じになっています。
ムービングショット

上の木漏れ日と同様、その場の雰囲気を伝える目的で、今回逗留した場所を歩きながら全景を捉えたショットを入れていますが、このショットでは移動撮影ということでジンバルを使っています。
これだけ歩き回りながらさらにカメラを大きく振ると、まともに使える映像を手持ちで撮るというのは非常に難しくなるのですが、ジンバルを使えば、まぁとりあえず見苦しくはないくらいのレベルにはなります。
実際にはさらにその先にジンバルを活かした超絶技巧ショットみたいな世界があるわけですが、そういうのはやはりプロのカメラマンのセンスと経験が不可欠で、一朝一夕にいきません。ただ、アマチュアの撮影ということでも、ジンバルがあることでとりあえず手軽に可能になるショットがキャンプ動画にはもうひとつあります。それが以下のショットでやっているテント内360°撮影です。

今回のような小型テントだと中に入ってしまうともうほとんど身動きは取れないので内部の撮影は恐ろしく困難になるのですが、最近のモータライズドジンバルはスマートフォンでリモート操作ができるようになっているので、ジンバルに足をつけてテント内に自立させ、自分は外からリモートでカメラを回転させる、という方法を取ることで、テント内の隅々を自由に、無理のないアングルで撮影することができるわけです。
ジンバルに限らず、撮影用の機材にはやはりそれぞれ「それがないと撮れない画」というのがあるのですが、そういう飛び道具的な特有効果に引っ張られて、逆に道具に使われてしまう危険性もあったりするので、基本的にはワンポイント的な使い方に留めるようにしています。
動画の音声について

キャンプ動画を撮る時に意外と問題になるのが、音声です。自分が撮るタイプのキャンプ動画では特に大きな問題がふたつあって、ひとつは「薪割りなどの突発的に発生する大きな音で発生する音割れ」で、もうひとつが「動画に残したくない不要なノイズ」です。
以前の動画では為すすべもなくただ録れた音をそのまま使っていたのですが、最近はマイクをはじめとする録音用の機材も徐々に拡充されてきて、手を加えられる度合いも深くなってきました。
基本的に外部マイクを使って、カメラ本体側のプリアンプのレベルを極力下げて録音しているので通常の撮影で音割れすることはないのですが、「雰囲気を残す」ために周囲の環境音もある程度は拾えるように、というレベルで録音していると、やはり斧で薪を割る瞬間などは 0dB を振り切って完全に割れてしまった音しか録れていない、というケースが出てきます。
ということで、最近は 32ビット録音が可能な外部レコーダーを持ち込んで、音声は完全に別録りにし、後からタイムコードで同期させるようにしています。自然な音の収録ということではもう少し経験を積まないといけない感はありますし、別録りになると素材の取り回しも格段に煩雑になるのですが、少なくともソースとなる音源は、音割れのないものが残せるようになりました。
その上で、ということになるのですが、やはり音というのは「キャンプの雰囲気」という点で非常に重要な要素なので、動画制作においては、耳障りでなく、それなりに臨場感があり、時には耳に心地よい、自分なりの理想のサウンドデザインを目指して日々あれこれ調整しています。
そしてこの「あれこれ調整」というプロセスは、もうひとつの問題である「不要なノイズ」への対策としても必要で、最近の編集ではこれに結構な時間を取られるようになっています。
わたしが普段お邪魔しているキャンプ場はとても静かな場所が多く、周りに人がいないことも多いのですが、それでもやはり日のある内はどこからともなく車の音や、どこかで作業をしている重機の音といった「雰囲気の上では絶対に入れたくない音」が聞こえてきます。夜になると今度は手元のショットが増えてくるため、「自分の呼吸音」や、あと冬の間はありがちなんですが「軽く鼻を啜る音」というのがどうしても入ってきます。
自分が望むレベルで「雰囲気を伝えるための環境音」を録ろうと思うとどうしても撮影者自身が立てる音も拾ってしまうんですが、昔は「カメラを回している間は息を止める」とか「垂れてきても啜らない」とか非常に無理のある方法で対処していたのを、最近は Audition を使って音自体をいじって「修復」しています。おっさんの息遣いなどは排除しつつ、熾火の爆ぜる音や風にゆれる木々の音、薪が立てる乾いた音、遠いせせらぎの音などをなるべく残すように奮闘していますので、ご視聴いただく方々には、ぜひヘッドホンなどで音にも注目して楽しんでいただければという思いもあったりします。すでに一度ご覧いただいた方も、またお時間のある時にぜひこれまでの動画も合わせて見直して、音を聴いてみていただければと思います😉(宣伝)
タイムラプスについて
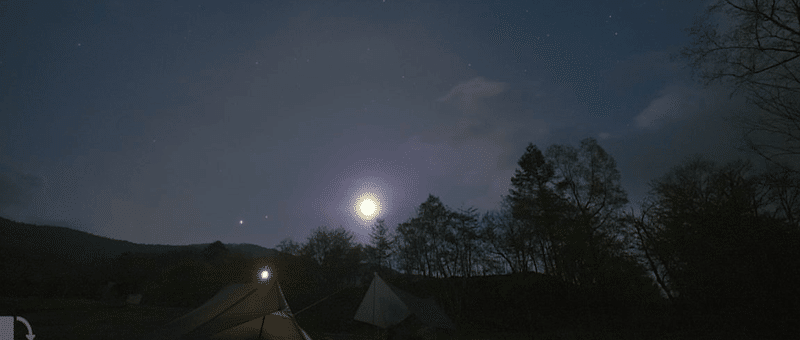

わたしが作る動画では、「夜のタイムラプス映像」から「朝の動画」に繋ぐというのがある意味、定番のようになっています。
夜寝る前に静止画のタイムラプス撮影をセットし、翌朝、カメラを動かさずにバッテリーを入れ替えて、そのまま動画モードに切り替えて露出等を調整し、同じ位置を保ったまま動画を撮って、それをディゾルブで繋ぐ、という手法なのですが、静止画と動画では撮影範囲が違っているので(タイムラプスに使っているカメラは静止画は8192x5464、動画は4096x2160)サイズと位置を合わせる必要があります。
基本的にはタイムラプスの方を縮小し、動画にピクセル単位で違和感なく合うように調整するのですが、今回はタイムラプスパートで画をフレーム内で徐々に上空に向け、あたかもゆっくりと空を見上げていくように動かしながら、最終的に動画が待ち受けている位置に合うようにしています。
さらに今回は動画パートでも、撮影開始後にカメラを三脚に据えたまま、三脚ごとゆっくり前に傾けることでアングルを動かしたりもしています。それによって何か特別な効果が生まれるというわけではないんですが、「ん? 今のはどうやった?」というかすかな引っかかりを埋め込んでおくのが、撮影側の小さな楽しみだったりします。
朝食からコーヒーのパートについて

わたしの動画は大体いつも6幕構成で、大体1・2幕が到着から設営、3・4幕が焚き火開始から深夜まで、5・6幕が翌朝、という形式なのですが、今回は夜が明けるまでが5幕になっていてしかもいつもより長かったので、最後を短くまとめる必要がありました。この辺も、今回「メリハリをつけるためにアップテンポの曲を採用した」という話の背景にあったりするのですが、とりあえずせっかくリズム感のある曲を使うならリズムを前に出した編集を、ということで、前回の動画の頭で採用したモーションブラー付きのスライドトランジションを(一部バリエーションを加えながら)全面的に使っています。
リズムに合わせたトランジションを強調するために、さらに画像のエフェクトに合わせて「シュッ」というサウンドエフェクトを入れていたりするのですが、実は今回、この「シュッ」という音を探すのがすごく大変でした。BGMも含めて動画で使っている音源は epidemicsound.com で用意しているのですが、たとえば今回の、何かが風を切るような「シュッ」という音だと、Whoosh というカテゴリで何千種類もの音があって、自分がイメージしている音をピンポイントで探す手段がなくて、とりあえず片っ端から聞いていくしかなかったりします。
最終的には Whip Whoosh Swoosh 1 という音源をベースに少し引き延ばしてピッチを下げたものを使ったんですが、この「望みの音を見つけ出す」というのも、まだまだ経験やスキルが足りない部分な気がしています。映像業界のプロの方たちはどうやってるんでしょうね。
ちなみにこの最後のシーンで使っている楽曲の方は、同じ epidemicsound.com で見つけた Victor Lundberg さんの「Tell me should I've known」という曲ですが、これも原曲が4分13秒あるのを、Premiere Pro のリミックス機能で3分10秒に縮めていたりします。曲を伸ばしたり縮めたりして大まかに動画の尺に合わせ、最後に動画をいじって微調整をする、というのがいつものルーチンです。
最後のカットについて

今回の動画の最後のショットではドローンを飛ばして引いていくショットで「事の終わり」感を醸し出しつつサイトの全体像を見せていますが、今回、このショットに合わせて、動画チャンネルのロゴを出しています。
このロゴは常日頃からダジャレや雑談でお世話になっている友人にしてプロのデザイナーであるニンパイさんにデザインしていただいたものですが、せっかく素晴らしいロゴを作っていただいたのにその使い方がぞんざいでは申し訳が立たない、という思いがあり、何か思いつく度に「新しい出し方」で出すようにしています。
今回はドローンの引いていく画面内にロゴを 3D 展開して、あたかもロゴがその場にとどまって緩やかに上昇しながら回転しているかのように、カメラの移動に応じて景色と同じように遠ざかっていく、というアニメーションを After Effects のコンポジションとして作っています。
さらにそのコンポジションを元に同じ空間上で反転させて位置を下げたものを作成し、「水面よりは明るいが芝の地面よりは暗い」レベルに彩度を落としておいてから描画モード「比較(明)」で合成することで、反転したロゴが水面部分にだけ表示され、あたかも水面への写り込みのように見える、という効果を狙っています(ついでに水面に馴染ませるために青みを持たせてブラーをかけています)。
こういうことをあれこれ工夫すること自体も含めた全体が、わたしにとっては「キャンプに行って動画を撮ってYouTubeにアップする」という趣味の一環なのですが、今回の写り込みについてはほんの数秒しか写っておらず、気づく人もほとんどいないようなレベルの話なので、動画編集にかかる時間が徐々に長くなっている、という厳然たる事実(問題)を考えると、もう少し考え直した方がいいのかもしれません。
終わりに
ということで今回初めて「種明かし」的なことをしてみたのですが、いかがでしょうか。個人的には、所詮アマチュアが独学であれこれやっているレベルなので、ノウハウの紹介、みたいな話はとても恐れ多くて手が出せないのですが、もう少し緩い、「話の種」としてはアリなのかなという気がします。もし興味のある方がいらっしゃるようでしたら、コメントなり何なり、反応いただければ、今後も少しこういう話をしてみようと思いますので、よろしくお願いいたします。
大オチ
で、今回の動画の本当のオチですが、ここまで書いてきた内容を総合すると、今回の動画の撮影には少なくとも、
カメラ2台
それぞれの三脚
外部レコーダーと外部電源
外部録音機材
アナモルフィック含めた複数のレンズ
モータライズドジンバル
ドローンとバッテリー
を使用していることが分かります。これらの機材は緩衝材入りのハードケースに納めているのですが、ケース自体も合わせると合計で20kgを遥かに超える重量になっていたりします。
「ギアを厳選して軽量化してバックパックひとつで13kg!」とかタイトルでも謳っていますが、いくらギアが13kgで薪・水・食料諸々を足しても20kg未満と言ってみたところで、20kgを超える撮影機材も持ち込んで、となると、実態は軽やかでも何でもなく、かなり過酷なキャンプだったりするわけです。
まぁそれだけのものを持ち込んで汗をかきながら奮闘するだけの楽しさがあるからこそやっていることですが、わたしが制作している動画はそういう意味では、「撮影で苦労せずに純粋にキャンプだけを楽しんだとしたらどんな感じか」という、ある意味で、「夢」を形に残しているような行為と言えるかもしれません。
バックパックひとつを謳いながら実際には25kgのハードケースも一緒に持ち込んでいる、というのは考えようによっては不誠実なことかもしれませんが、ご視聴いただく際にはとりあえず「幻想を共有」するような形で楽しんでいただければ幸いです。もしくは「こんな優雅にリラックスしたような画を撮ってはいても、泥臭い撮影で四苦八苦してるんだろう、知ってるぞ」と笑いながら見ていただくのもオッケーです。動画を制作して公開しているからには、見ていただけさえすればもう本望です。
それではまた、次のキャンプでお会いしましょう。何らかポジティブなフィードバックがあるようなら今後の動画でも、またこういう話をしてみたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
