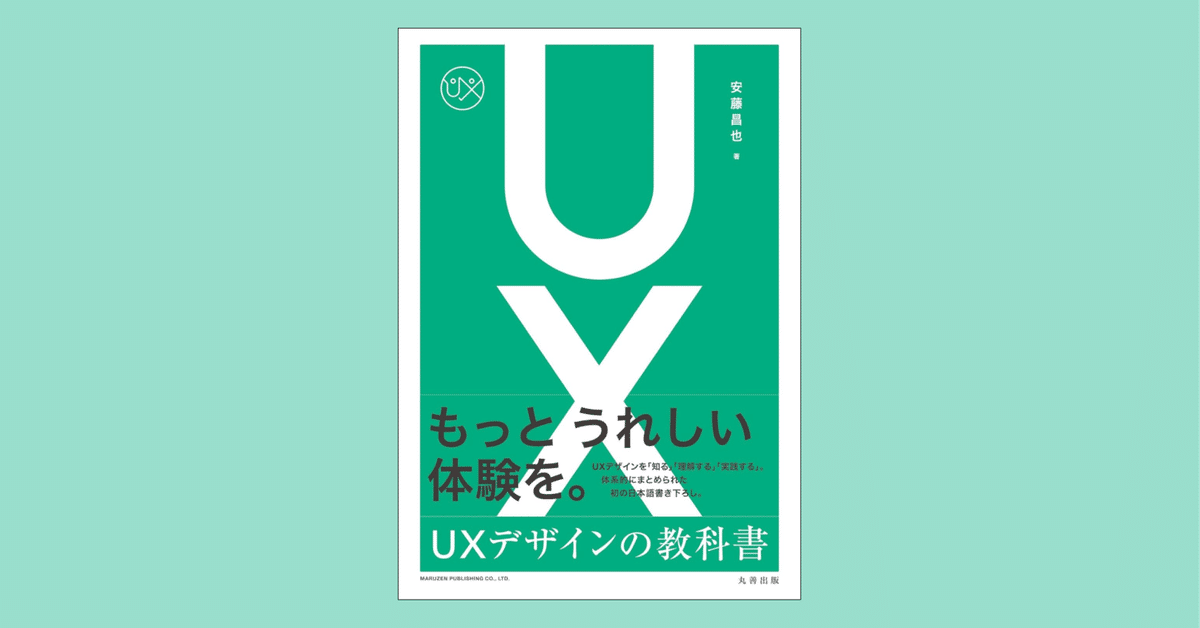
【読書録】UXデザインの教科書
UXについてはさまざまな手法や事例が出版されているが、学問領域として取り上げている書籍は少ない。
今回はアカデミックな内容も含めた、UXをデザインするための理論とプロセス、手法に関する知識を体系的に解説している本書を手に取った。
本書の構成は以下の通り。
1 概要
1.1 UX デザインが求められる背景
1.2 ユーザーを重視したデザインの歴史
1.3 UXデザインが目指すもの
2 基礎知識
2.1 UXデザインの要素と関係性
2.2 ユーザー体験
2.3 利用文脈
2.4 ユーザビリティ、利用品質
2.5 人間中心デザインプロセス
2.6 認知工学、人間工学、感性工学
2.7 ガイドライン、デザインパターン
2.8 UXデザイン
3 プロセス
3.1 利用文脈とユーザー体験の把握
3.2 ユーザー体験のモデル化と体験価値の探索
3.3 アイデアの発想とコンセプトの作成
3.4 実現するユーザー体験と利用文脈の視覚化
3.5 プロトタイプの反復による製品・サービスの詳細化
3.6 実装レベルの制作物によるユーザー体験の評価
3.7 体験価値の伝達と保持のための基盤の整備
3.8 プロセスの実践と簡易化
4 手法
4.1 本章で解説する手法
4.2 「①利用文脈とユーザー体験の把握」の中心的な手法
4.3 「①利用文脈とユーザー体験の把握」の諸手法
4.4 「②ユーザー体験のモデル化と価値体験の探索」の中心的な手法
4.5 「②ユーザー体験のモデル化と価値体験の探索」の諸手法
4.6 「③アイデアの発想とコンセプトの作成」の中心的な手法
4.7 「④実現するユーザー体験と利用文脈の視覚化」の中心的な手法
4.8 「④実現するユーザー体験と利用文脈の視覚化」の諸手法
4.9 「⑤プロトタイプの反復による製品・サービスの詳細化」の諸手法
4.10 「⑤プロトタイプの反復による製品・サービスの詳細化」の諸手法
4.11 「⑥実装レベルの制作物によるユーザー体験の評価」の諸手法
4.12 「⑦体験価値の伝達と保持のための指針の作成」の文献紹介
総評
1章ではUXデザインが重要視されるようになった歴史的背景やUXデザインが目指すもの、2章では基礎知識としてUXデザインの7つの要素を取り上げている。
3章ではUXデザインのプロセスを7段階に分け、それぞれの段階で行う実施概要や代表的な手法を確認する。
流れとしては大まかに、
調査・分析→コンセプトデザイン→プロトタイプ→評価→提供
であり、それぞれの段階で必要になる知識を確認できる。
4章では、前章で取り上げた手法の概要が説明されている。実施方法を詳細に取り上げているものもあるが、より実践的な実施方法については参考文献を読む必要がある。あくまで、どの段階でどんな手法を取ればいいのか確認するためのもの。
本書の使い方は、UXデザインの全体像を学術的な点も含めて知識として吸収し、実践の段階になったら3〜4章を中心に辞書的に使うのが良いだろう。まさに”教科書”として使うのに相応しい。
大学の授業(名付けるとしたら”UXデザイン概論”であろうか)の教科書として使えるような網羅的に確認できる一冊だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
