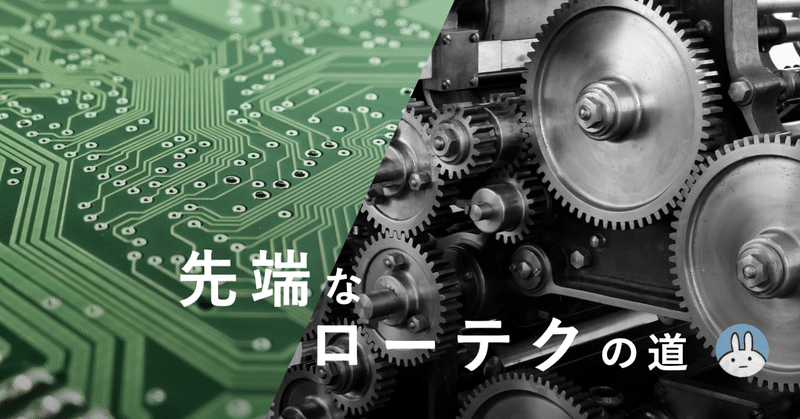
先端なローテクの道
このネタを書くには基礎知識がなさすぎて、ずっと記事にならないトピックですが、なんとなく伝わればよいと思ってつぶやいています。
みんな高度な先端テクノロジー、いわゆるハイテクに傾倒していますよね。
あらゆる困難な問題をテクノロジーによって乗り越えることが人間の英知のなせる技である、といったようなことです。表現は違うかもしれませんが、そのような感覚は少なからずわたしの中にもみなさんの中にもあるのではないでしょうか。実際に多くの恩恵を受けてもいます。
ただ一方で、高度なテクノロジーによって、わたしたちの生活がどこか規定された世界に閉じ込められたように感じられることがあります。例えば、ソーラーパネルなんかそうだと思うのですが、原理を知識としてわかっていても、そのテクノロジーを使ってわたしにできることはほとんどありません。ソーラーパネルを自作せよと言われたってできないし、それを実際の活用レベルで何かに応用することすらできない。パソコンだってそうです。目の前にあるパソコンの故障すら直せません。やれてマザーボードの部品交換まで。
人間はその高度なテクノロジーによって、生活のさまざまな問題を解消できるようになりました。けども、人間の個としてはどうだろう?製品がなければ何もできない。返ってわたしは生身の人間として何もできない生物に退化しているような気にすらなります。
もちろん、パソコンをなくせとか、そんなこと言うつもりはないですよw ただね、身の回りの生活品すべてがテクノロジーなんです。ジッポライターぐらいだったら、原理わかるじゃないですか?故障したら材料さえあればなんか直せそうな雰囲気ありますよw ところが、最近は身の回りのものですら電子ライターができたり、オール電化によってガスコンロがなくなって、壊れたら最後、もうわたしの力量では治すことすらできない。昔は近所のおじさんなんかはよく車のエンジンルームを開けて何やらやってましたけど、最近は車もすべてが電子制御、わたしたちは生活レベルにおいて、文字通り何もできない人と化している。これは、個としては進化といって良いものなのだろうか?
テクノロジーの進化と共に、個として人が扱える自然や、身体の限界といったものを広げる努力は一方で必要なのではないか?
ローテクってなんだろう!?
余談が長くなっちゃいましたけども、そんな折にふっと職場の先輩との雑談を思い出すんです。「これからはローテクを高度活用する時代だと思うんだよね。」IT業界という、むしろハイテク産業側に行きがちな目線をぐいっと引き戻された感覚がして、なんだか妙に印象に残った言葉でした。
この雑談ってもう10年以上前のことですけども、なんとなく頭に引っかかって、このローテクの高度活用というものが世の中的にどのように実用化されるのか気にしているのですが、まだ世の中的にこれ!といった概念は登場しきれていないように思います。
その中で、かなりふわっとですけれども、わたしがこれまでに気になった、「ローテク」について少し触れたいと思います。ローテクといっても色々に定義できるように思いますが、大きく2種類の方向性があるように思います。
レガシーテクノロジー
ひとつめの方向性としては、レガシーテクノロジーという言葉で表せるかもしれません。使い古された技術、と言った意味です。例えば、むかーしのトラクターのエンジンだったり、水車で使っていた簡単な発電タービンだとか。
こういった特許権の消滅した技術設計書はいまとなってはネット上で無料で一般公開されていたりするんです。サイトとかもうすっかり忘れてしまったのですが、まとめサイトみたいなものも存在していたはずです。最近は3Dプリンターなどを使って、一般人であっても簡単に部品などを生成することができるようになってきましたよね。このような設計図を積極的に活用するリテラシーがあれば、われわれは数十年前に最新技術と言われていたレガシーテクノロジーを驚くほど簡単にそして安価に入手することができてしまいます。
特に農業だとか、自農によってちょっとした野菜を生産したりだとか、パーマカルチャーなんて言葉も流行っていて、そういった経験がある方はわかると思いますが、とにかく耕したり掘ったり運んだりってのが一番大変なんです。そこで道具を導入しようとすると高度な重機しかない。そうでもなければ極端に人力なクワとかシャベルとか一輪車みたいなレベルにまで後退してしまう。その中間の塩梅がないんですよね。以前、自力で空き地を農地化したことがあるんですが、まぁ人力って大変ですw とても社会のいびつさを感じたのを覚えています。自農や自作など小さなコミュニティーの軒先に先端の技術なんてほぼ不要です。ただ、わたしたちの技術に対する生身の実現レベルのリテラシーの向上と、こういったレガシーテクノロジーの組み合わせによって、身の回りの生活の様式が変容する可能性はあるように思うのです。
それこそ一昔前の枯れた技術による、丈夫で自分たちでメンテナンスができるレガシーテクノロジーを更に現在あるIT技術などと組み合わせて高度に使うというのも一つの在り方ではないかと思います。
化学から物理学へ
もう一つは、物理学的な技術のアプローチだと思います。これはわたしの好きなベルギー人の環境活動家のグンター・パウリという方が昔から主張しているのものですが、これも広義にはローテクの高度利用という枠に分類されるのではないかと、わたしは思うのです。
例えば、砂漠のアリクイの巣などを例にしたりするのですが、アリクイの巣の内部構造を真似て建築物を建てるんです。すると、自然に風通しがよく、砂漠地帯でもほとんどクーラーの必要のない建造物ができるそうです。あるいは、シマウマの白黒のラインに注目します。これは擬態の目的だと言われて来ましたが、最新の研究では実は白と黒の熱吸収率の違いによって、ここにわずかな気流が発生し、体表面の温度が涼しく快適になる、というんです。これを実際の都心のビルに利用したところ真夏のビルの表面温度が下がったなんて実験が紹介されていたりします。
こういった自然界に昔からあるシステムをより高度に解析し、現代のテクノロジーに応用することで実は高度な先端テクノロジーに頼らずともわれわれは快適な暮らしをより地球に優しい条件で実現できるのではないか?
グンター・パウリはこうも言います。
我々は物理学が「予測可能で例外がない」ことを忘れている
鉄球は手を離すと必ず地面の落ちます。この当たり前の事実に立ち返る必要があるのではないか?このあたりまえの物理法則からもっと多くのものを活用できる可能性が広がっていると思うのです。
化学反応の利用は部分最適に特化した技術なんです。ですから、より包括的で長期的な視点で見ると化学には多くの場合、例外があり予測不可能性にあふれています。原子力であったり、今話題のワクチンにしろ、害がないとされている電磁波ですら、実際にわれわれの体や自然にどんな結果をもたらすのか実ははっきりしたことはわかりません。もしかしたら、10年後とか、50年後くらいになってはじめてわかるものもあるかもしれません。
予測が可能であるという物理現象の良さというのはむしろここにあります。この非効率でも「確実な」ローテクを、ITや高度なテクノロジーを用いて上手に活用する道があるのではないか?そんな風に思ったりします。
りなる
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
