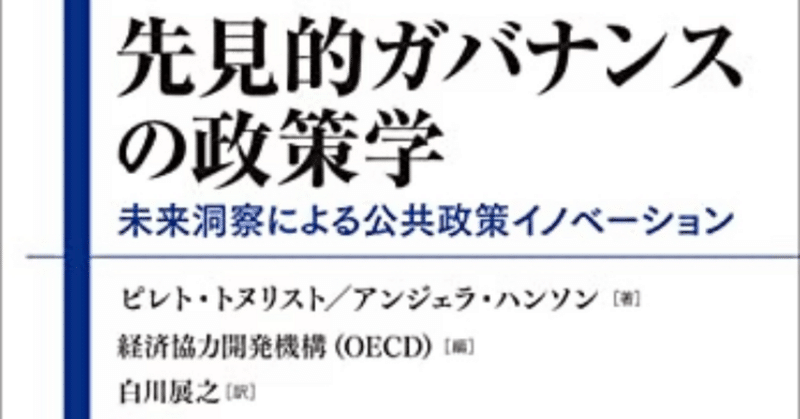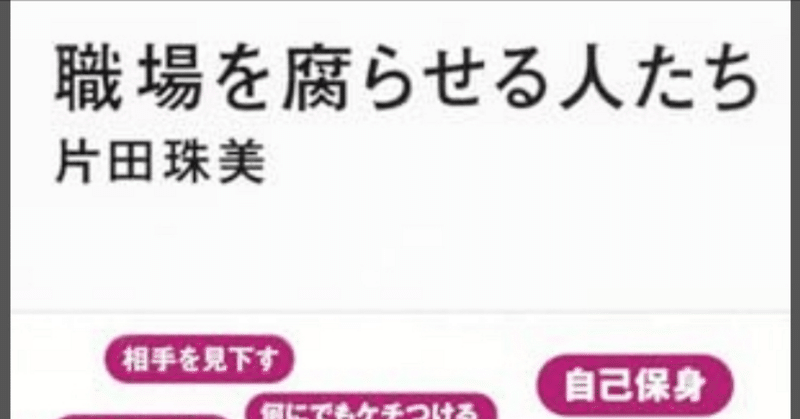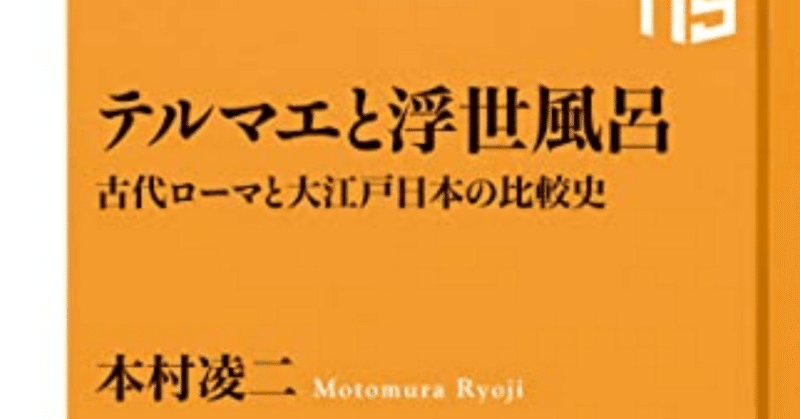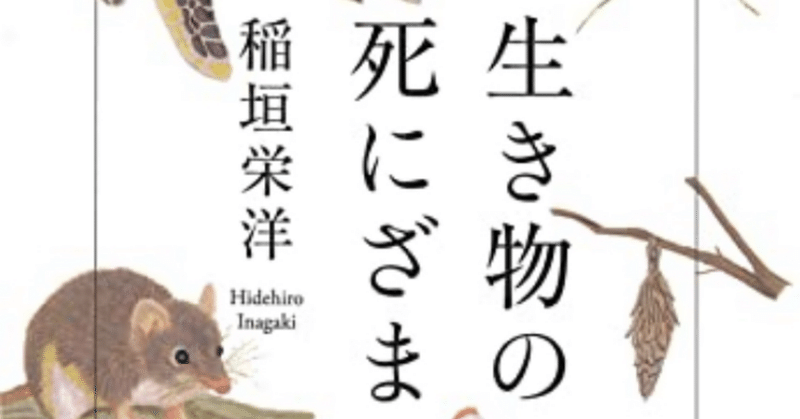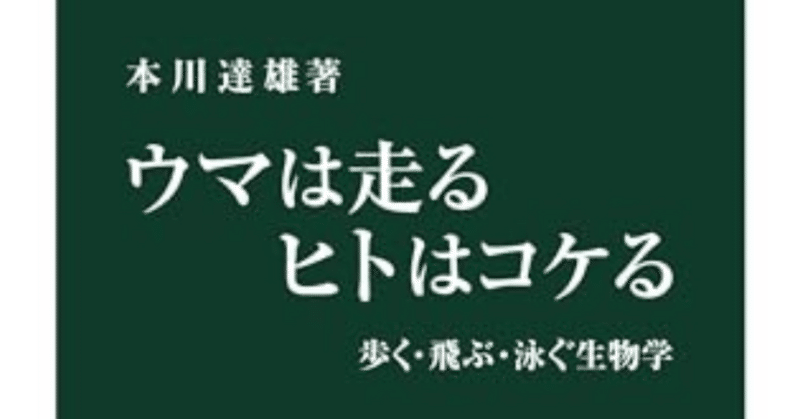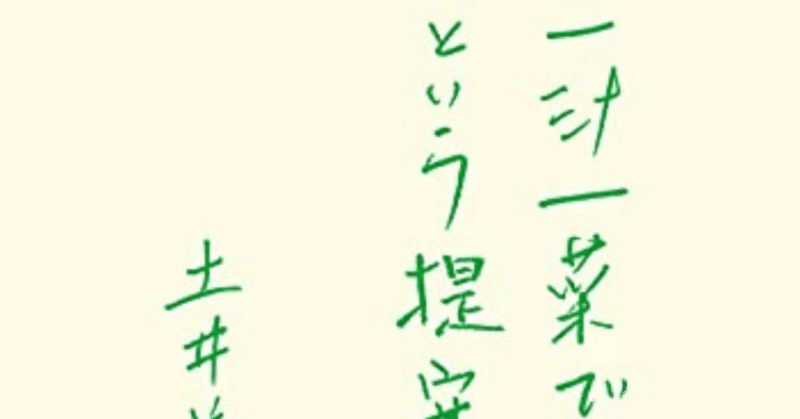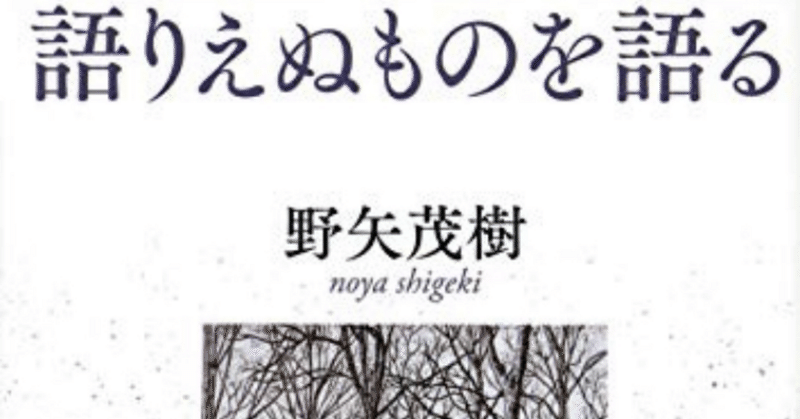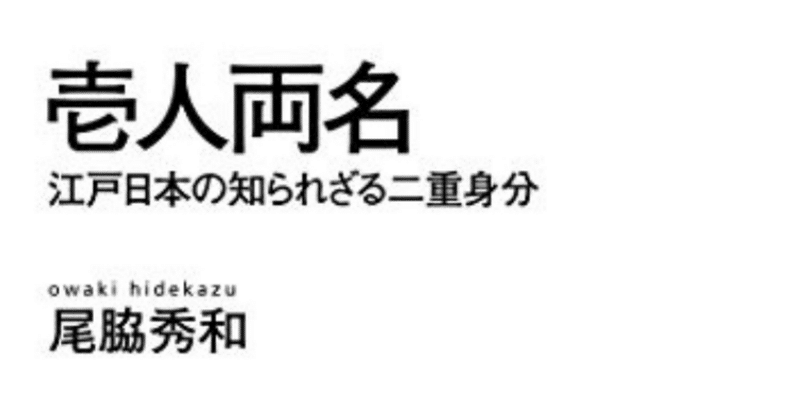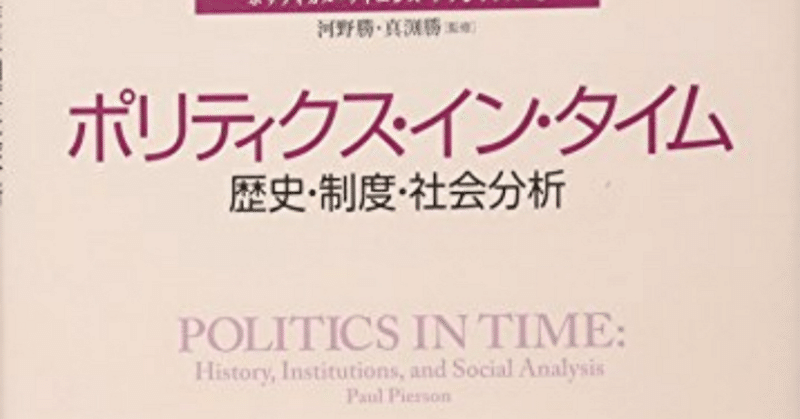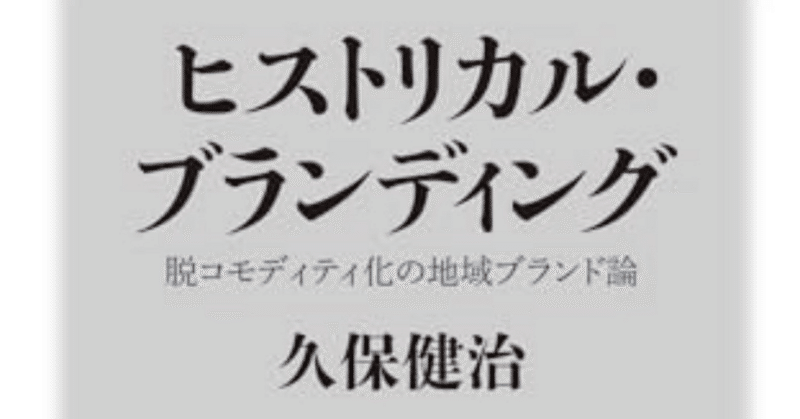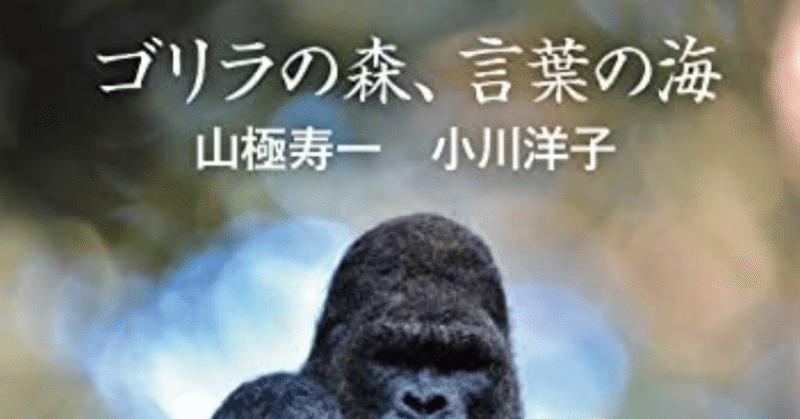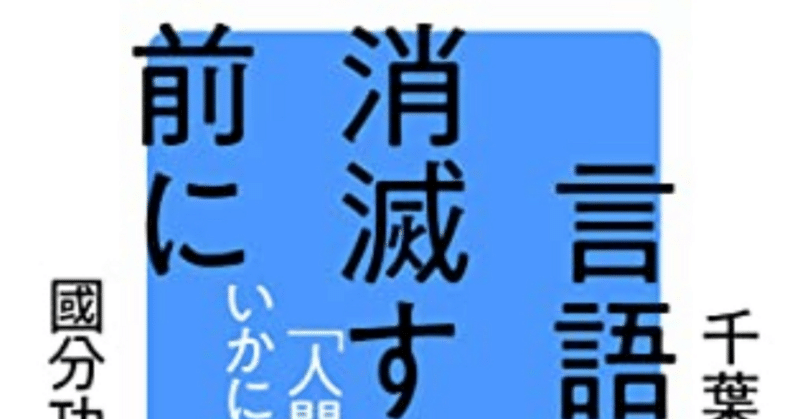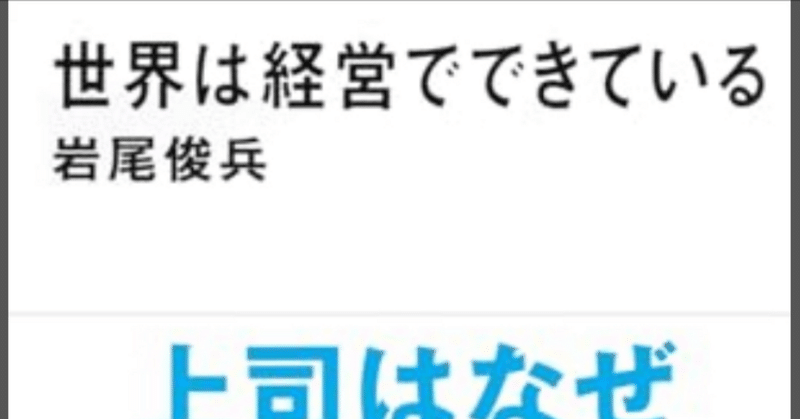記事一覧
『先見的ガバナンスの政策学 ――未来洞察による公共政策イノベーション』ピレト・トヌリスト,アンジェラ・ハンソン
OECDの公共セクターイノベーション観測所のメンバーによる未来洞察を通じた政策変革に関する報告書。関係者によるオンラインセミナーを視聴したため購読。
単線的未来予測を排し、未来像の振れ幅の範囲についてシナリオ作成する作業は、実験的で内省的なプロセスを要するが、これを確実性と安定性を徹底する行政システムにどう位置付けるかにジレンマがある。
欧州の中央・地方政府における先見的イノベーションモデル構
『孟子 ビギナーズ・クラシックス 中国の古典 (角川ソフィア文庫)』佐野 大介
孟子7編のうち51章を選んだ入門書。
人の善性は天が先天的に賦与したもので、その性質は惻隠、羞悪、辞譲、是非の四端の形を取るとし、悪は環境によって生じるとする。
革命(王朝交替)是認論、君主廃立可能論、民本主義的思想も表れ、孟子が君主より国家を重んじた事を表しているが、後世大いに物議を醸したという。
君子の三楽、すなわち身近な人への情愛、自己の道徳的完成、教育の喜びは、古今東西通じる人生論だ
『職場を腐らせる人たち (講談社現代新書)』片田 珠美
精神科医が、7000人以上の診察事例から、最も多い悩みである職場の人間関係を悪化させる原因である職場を腐らせる人の典型例と対応策をまとめた本。
15の典型例として、上司の中に、根性論や過大なノルマを課す例やその場にいない人の悪口を言う例もあれば、若手社員の中に、言われたことしかしない、特定の部署にこだわる、いつも人を見下すような例もある。
そういう人を変えるのが難しい理由として、自己保身、喪失
『テルマエと浮世風呂: 古代ローマと大江戸日本の比較史 (NHK出版新書 671)』本村 凌二
古代ローマ史の専門家がテンミニッツTV講義から加筆修正して出版。テルマエ展にて購入。
古代ローマと江戸を10のテーマで比較しているが、前近代の抜きん出た2つの大都市の存立要因に、永続した平和と道路、水道等の土木技術、海洋との近接性が含まれると感じる。
水道のおかげで発展したテルマエと湯屋は、文化、運動等のエンタメ機能も備えており、今のスパ銭も顔負け。
アッピア街道は2300年の使用に耐えてお
『文庫 生き物の死にざま (草思社文庫 い 5-2)』稲垣 栄洋
雑草生態学の専門家が描いた身近な生物の知られざる最期に係るベストセラー。
印象的なのは、多くの現代人のように自分自身の生き甲斐や幸せを求める姿ではなく、個体、つがい又は近縁集団が、子孫を残すことこそが生命の目的であるかのような行動を取り死にゆく姿だ。
子に身を捧ぐ母ハサミムシ、メスに食われながらも交尾をやめないオスカマキリ、メスに寄生し放精後はメスに吸収されるオスチョウチンアンコウ。
ニワト
『ウマは走る ヒトはコケる-歩く・飛ぶ・泳ぐ生物学 (中公新書 2790)』本川 達雄
ウニ等棘皮動物の研究者が、教科書編纂の経験を元に、移動に係る様々な生物のデザインを紹介した力作。
馬などの歩行・緩行・疾走時のモードの違いはエネルギー効率性の観点から説明。
熱気泡の上昇気流や高度別の速度勾配を活用して極めて効率的に滑翔するコンドルやアホウドリ。
息継ぎ頻度を気にするスイマーとしては羨ましい、口を開けて泳ぐことでエラに水を供給して呼吸できるマグロ。
ウニとヒトの移動は、倒立
『一汁一菜でよいという提案 (新潮文庫)』土井 善晴
料理研究家が、普段の和食はご飯と具沢山の味噌汁で良いとして、和食文化の過去から未来まで論じた書。
縄文時代が長く続いたのは多様な食材を採取し飢饉のリスクを減らしたからだが、採取した食物を汁や鍋のようにして食べたのだろうという。
ゴリラにはなく人間にはある子供・青年期に、親に料理を作ってもらった経験が揺るぎない安心感を生むとする。
一汁一菜の提案は、手を掛けることが料理との誤解を解き、素材を活
『語りえぬものを語る (講談社学術文庫)』野矢 茂樹
講談社PR誌への連載に詳しい註を付けて、反復重層的に議論が展開された哲学書。
ウィトゲンシュタインの「語りえぬものについては、沈黙せねばならない」に反駁し、論理空間にはあるが行為空間の外にあるもの(猫又は掃除機の「クリーニャー」等)は語りにくいだけだし、論理空間の外にあるが勉強すれば使えるかもしれないものは「今の」自分には語りえないだけだとする。
概念主義への反論の中で、動物・赤ん坊と違って大
『壱人両名: 江戸日本の知られざる二重身分 (NHK BOOKS) (NHKブックス 1256)』尾脇 秀和
江戸期の壱人両名(1人が2つの名前と身分を使い分ける形態)と明治期における消滅について、古文書から多くの実例を見出し解説した力作。
①両人別(二重戸籍状態)、②秘密裏の二重名義使用、③身分(町人等)と職分(医者等)による別名使用のうち、①②は非合法とされたが、いずれも縦割りの支配の管轄を保ちつつ、支配を跨ぐ活動を表向き問題なく実現するための方策だったと評価。
建前と実態のずれの黙認も知恵だった
『ポリティクス・イン・タイム―歴史・制度・社会分析 (ポリティカル・サイエンス・クラシックス 5)』ポール・ピアソン
合理的選択論による脱文脈化の最盛期に、政治分析における歴史の重要性について改めて真摯に論じた新しい古典。
英国留学以来、定性的分析に強いシンパシーを感じる者には違和感が少ないが、実務家の眼からも興味深い論点がいくつか。
自己強化過程が働く状況において、事象の起きるタイミングと配列の重要性が説かれ、前に起きた事象がより重要とする。
また、制度修正コストは、特定の環境や用途に限定される資源への投
『ヒストリカル・ブランディング 脱コモディティ化の地域ブランド論 (角川新書)』久保 健治
歴史研究者から観光系の経営学者兼コンサルタントに転身した筆者が、自ら関わった実例を中心に歴史を活用したブランディングの概念構築と実践のあり方を論じた本。
コモディティ化しないように、稀少性や模倣困難性を強調するとともに、史料調査の重要性も説く。
限界としては、挙げられた個別事例がどの程度定量的に他地域の事例より優れていて、その理由は何なのかといった点の分析が弱いのと、自らの事業紹介のようにも見
『ゴリラの森、言葉の海 (新潮文庫)』山極 寿一、小川 洋子
霊長類学者と小説家がゴリラと言葉の森を逍遥する対談集。
類人猿がいかに人に近くサルと違うかに目から鱗。
声を出して笑える、威嚇ではない形で顔を見つめ合える、勝者を作らない仲裁をする、対等性を大事にする。そんな違いは動物園では分からない。
類人猿も人も経験を積むことで親になるが、その経験が性的な関心を抑制し、そこから生じたインセスト・タブーが互酬性、更には複数の家族による地域共同体の形成の元と
『言語が消滅する前に (幻冬舎新書)』國分 功一郎、千葉雅也
2017〜2021年にかけて5度に亘る2人の第一線哲学者の対話を収録。
シリーズものではないが、言語の力の衰退が通底認識。
重要な問いとして受け止めた議論としては、崩壊しつつある「権威主義なき権威」をどう再生させるかと、エビデンス主義や法務的発想は民主主義的側面もあるが責任回避が過剰であり、重層的時間の中での正義を目指すべきというもの。
「中動態の世界」と「勉強の哲学」という各々の著書の紹介
『世界は経営でできている (講談社現代新書)』岩尾 俊兵
慶應の経営学准教授が、冗談とも本気とも取り難い比喩を駆使して、人間は「価値創造を通じて対立を解消しながら人間の共同体を作り上げる知恵と実践」と言う本来の意味の「経営」を行っていることの再認識を促した挑戦的作品。
例えば「就活時応募書類乱射型学生」など、鍵かっこで、誤った経営概念を持った人物像を揶揄。どこに著者の根本意図があるのか掴み辛かったが、最終章を読んで合点。
有限の価値を奪い合う発想では