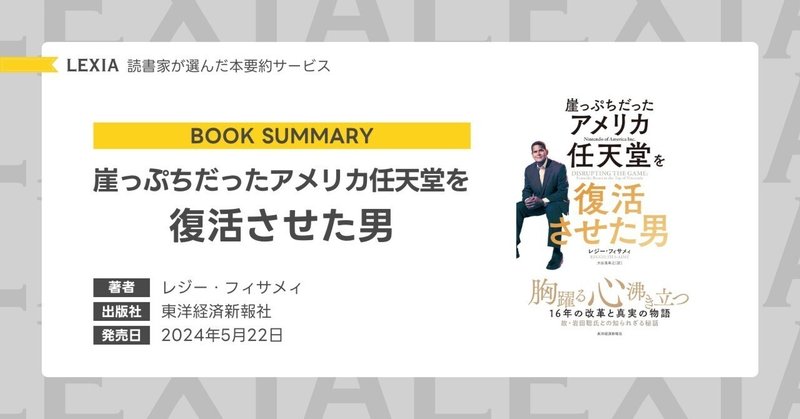
崖っぷちだったアメリカ任天堂を復活させた男
【書籍情報】
タイトル:崖っぷちだったアメリカ任天堂を復活させた男
著者:レジー・フィサメィ
翻訳:大田黒奉之
出版社:東洋経済新報社
定価:1,980円(税込)
出版日:2024年5月22日

【なぜこの本を読むべきか】
私たちが活動する現代は、絶えず変化しており、ビジネスや政治、社会正義においても状況は変わってきている。
ところが、それらに提示される解決策は変わらず以前と同じで、あまり機能していない事実が存在する。
本書は、アメリカ任天堂のトップに上り詰めた著者のキャリア人生と、その中で得た教訓を紹介した一冊だ。
本書は以下のような方にオススメしたい。
■リーダー、社長の立場にいる
■ビジネスを成功させたい
■人間として高みを目指したい
これまでの考え方に固執したり、方向転換を恐れていては、解決策は生まれない。
ルールで縛られたゲームを、叩き壊すしかないのだ。

【著者紹介】
レジー・フィサメィ
アメリカ任天堂元社長兼COO(執行最高責任者)。
ハイチ移民の子として生まれ、幼少期はブロンクスで育つ。
2003年、アメリカ任天堂に入社した後、社長兼COOに就任、任天堂本社の執行役員に任命される。
現在は、次世代のビジネスリーダーの育成に精力を注いでいる。

【本書のキーポイント】
📖ポイント1
迷ったとき、分析的思考が役に立つ。そして、前に進むと決断したら、全力を出して従うのだ。
📖ポイント2
信頼のおける外部の人は、現状をありのままに伝えてくれる。あなたの考えに意見を挟めるくらいの人を見つけよう。
📖ポイント3
リーダーは、厳しい決断をしなければならない。そんなときこそ前向きに検討し、決断した以上は結果を受け入れる必要がある。

【1】ピンチかチャンスか? ーー任天堂からの電話

任天堂の窮地
2003年の夏の終わり、自分のスキルと能力を発揮できる場所を探していた著者の元に、1本の電話がかかってきた。
相手は任天堂。
聞けば、セールスとマーケティングの代表を探していると言う。
このとき、任天堂は苦境に立たされていた。
当時から2年前の2001年、マイクロソフトはコンピューターゲームの「Xbox」を引っさげ、ビデオゲームのビジネスに参入。
任天堂も対抗するべく、家庭用のゲーム機「ニンテンドー ゲームキューブ」を発売。
しかし、どちらのシステムも、その前年に発売されたソニーの「Play Station 2」の前では霞んでいた。
ソニーには、プレステ2でいくつかの優位な点があったのだ。
➀初代プレステの成功
初代プレステを成功させており、この伝説的なプラットフォーム用に作られたゲームを、プレステ2でもプレイできるようにした
②コスト的なアドバンテージ
光ディスク中心のテクノロジーを使っており、安価で複製できる点がコスト的なアドバンテージとなった
③DVDプレーヤーとしての役割
プレステをDVDプレーヤーとして単独で使えるようにした
これまでの任天堂は、小型ゲーム機のビジネスをリードし、初代ゲームボーイのライフサイクルの末期には、「ポケモン」という現象を世に出していた。
実はソニーは、任天堂の小型ゲーム機独占をうらやんでいたのである。
そして2003年のE3(ビデオゲーム産業が集まる巨大なイベント)において、ソニーはPSP(プレイステーション・ポータブル)で小型ゲーム機マーケットへの参入の意志を表明。
名前を発表しただけで、任天堂の株価の下落は10%を超えることとなった。
著者は任天堂から電話を受けた後、この転職について、メンターや仕事のパートナーに相談した。
すると、彼らのほぼ全員が「やめたほうがいい」と言う。
元々ゲーム好きである著者は、任天堂の「マリオ」や「ゼルダ」などのゲームシリーズを知っていた。
任天堂がゲームシリーズに新たな命を吹き込んできたのを、消費者目線としても見てきた。
そんな任天堂が、ソニーやマイクロソフトにその地位を譲りつつあることも……。
著者は任天堂が直面する主な問題と、自分ならどう解決するかを、何ページもメモに記した。
そして出た結論は、「私なら任天堂を変えられる」。
周りはやめておけとアドバイスをくれたものの、著者はすべてを懸けることにしたのである。
ここでの教訓は、分析的思考が大事ということ。
分析的思考については、以下のようなものが挙げられる。
■公式に入手できる情報すべてに目を通し、会社を下調べする
■長期的に見て勝てる力があるか
■自分のスキルがその会社の需要に見合うものか
そして、自分の直感と、経験を使って考えることも必要である。
経験には、競合他社と関わったことを始め、消費者としての自分の経験も含まれる。
カルチャーについて考え、自分に合っているかを検討。
そして、ひとたび前に進むと決断したら、全力を出して従うのだ。
◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽
プロセスを明確にして、大きな成果を上げる
任天堂に入社した著者は、同僚全員と関係を築くように努め、製品開発のリーダーたち1人ひとりとも会って話をした。
製品開発を率いていたマナブ・マイク・フクダとも、何度もミーティングを開いている。
役職的には著者よりも下になるが、マイクは著者が知りたがっていた情報に精通しており、共に効率よく働くことは極めて重要なことだった。
その中で著者が行ったのは、宣伝制作を中心としたプロセスの透明化である。
宣伝制作の各ステップでは、
■実行責任者(R)
■説明責任者(A)
■相談先(C)
■報告先(I)
を明確にする必要がある。
通称、RACIモデル。
著者は宣伝制作で、マイクと彼のチームに重要な任務を任せた。
たとえば、製品企画書を承認する責任を与えるなど。
一方、著者自身はコンセプト提案の承認や、完成したCMの承認等を担うこととした。
当初、こうしたやり方はあまり受け入れられなかった。
マイクや彼の製品開発チームのメンバーを始め、著者のチーム内の宣伝担当のディレクターや同僚たちさえも、著者の決定権を持ちたいと考えていたからだ。
しかし、それを許すわけにはいかない。
真に最高の宣伝を作るには、透明性と協調によるプロセスが必要だ。
一方、重要な戦略・開発・ゴーサインを出す最終決断の決定権は、1人の人間だけが持つべきなのである。
このプロセスを用いた結果として、2004年のゲームボーイアドバンスSPから始まり、著者が退社する2019年のNintendo Switchまで、最高の宣伝を作り続けたのである。

【2】任天堂を再生させるための大勝負「E3」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
