しゅくだいやる気ペンにおける習慣化をUXデザイナーが分析してみた
くらくらしてしまうほどの暑い日々が続いている今日この頃、皆様はいかがお過ごしでしょうか。私は永遠に続くように感じていた夏休みも一瞬にして過ぎ去り、手元に残った多くの宿題を前に苦い顔をしていた幼少期の自分をたまに思い出したりしています。
本記事では、そんなあの頃の夏に怠惰だった自分に与えてあげたい、大ヒットのプロダクト「コクヨ しゅくだいやる気ペン」における体験について、主に習慣化という観点で考察してみたいと思います。
習慣化については、あらゆるサービスやプロダクト開発において往々に議論されるテーマだと思うので、プロダクト開発に関わる方に何かしらの示唆を与えられる記事になると幸いです。
コクヨ しゅくだいやる気ペンとは
「しゅくだいやる気ペン」とは、家庭学習の習慣化をサポートするまったく新しいコンセプトのIoT文具です。具体的には、普段使用している鉛筆に加速度センサーとLEDが搭載されたアタッチメントを取り付けることで、鉛筆を握っている時間や文字を書く動作を判別し、筆記量に応じてLEDの色が「やる気パワー量」として10段階に変化していきます。

また、スマートフォンの専用アプリケーションに鉛筆を傾けることで、やる気パワーを注ぐことができるといったリッチなインタラクションが施されています。さらに注がれたやる気パワーの量によって、キャラクターが進化し、リンゴを獲得。獲得したリンゴ1つにつき、1マスずつ進めるすごろく(やる気の庭)では、マス毎でアイテムを獲得できるだけでなく、ゴールした際のご褒美として「欲しいゲームを買ってあげる」などを親子間で事前に設定しておくこともできます。

ここまでは、直接ユーザである子供の宿題体験に関する紹介でしたが、「しゅくだいやる気ペン」では、間接ユーザである保護者における宿題体験をフォローする機能も提供されています。
具体的には、カレンダーで子供が宿題に取り組んだ日程と時間量を把握できる機能(やる気のキロク・やる気グラフ)と、宿題に取り組んだ時間量を前の週と比較できるレポート機能(週間やる気レポート)です。ちなみに「やる気のキロク」画面では、子供が頑張った日などに花丸をつけて記録でき、「週間やる気レポート」画面では、保護者に対して子供を褒めることの重要性を説くキャラクターのつぶやきが表示されます。

「しゅくだいやる気ペン」における習慣化をフックモデルで分析する
ここまで「しゅくだいやる気ペン」が提供する機能について、対子供と対保護者に分類して紹介してきましたが、ここからは製品のコンセプトとしても掲げられている習慣化について「フックモデル」というフレームワークを用いて分析したいと思います。
フックモデルとは、
Trigger(きっかけが与えられて)
Action(実際に行動をして)
Reward(行動に報酬が与えられて)
Investment(再度その行動を起こすために投資をする)
を繰り返すことで、習慣が形成されるという考え方です。

商品説明ページでも、「がんばる→褒める→がんばる→褒める...」といった「やる気習慣化サイクル」を親子でうまく回すことの重要性が述べられているように、「しゅくだいやる気ペン」によって、『子供が宿題を頑張る』という習慣と『保護者が宿題をした子供を褒める』という習慣が、フックモデル的に上手く形成・相互作用されているように見受けられたので、以下にまとめてみます。
『子供が宿題を頑張る』という習慣の形成
まずは『子供が宿題を頑張る』という習慣の形成についてです。

Triggerとしては「①学校から宿題が出される」がきっかけになります(当たり前ですが)。また、2回目以降からは「②アプリ上で可視化された情報をもとに行われる親とのコミュニケーション」や「③アプリ上でのキャラクターの進化やリンゴ・アイテムの獲得などといった成長的な要素」がきっかけとなり得るでしょう。
また、Actionとしては「①しゅくだいやる気ペンで宿題を頑張る」といった行動ですが、アタッチメントによる鉛筆の握りやすさなど、ユーザビリティ面で行動のしやすさに寄与していることが考えられます。
続いて、Rewardでは「①筆記量に応じてLEDの色が10段階に光る」「②やる気パワーを注ぐと、キャラクターが進化・リンゴを獲得できる」「③すごろく(やる気の庭)でアイテムを獲得できる」「④すごろく(やる気の庭)でゴールすると、親と設定したご褒美がもらえる」「⑤親から褒められる」など、良い行動に対して素早く享受できる小さな報酬と、良い行動を継続することで享受できる大きな報酬が設計されているようです。
良い行動に対して素早く享受できる小さな報酬が、サービス利用中におけるモチベーションの向上に寄与し、良い行動を継続することで享受できる大きな報酬が、次回利用に対するモチベーションの向上に寄与するとも考えられそうですね。
そして最後にInvestmentでは、「①親とすごろく(やる気の庭)のご褒美を設定する」が挙げられます。
『保護者が宿題をした子供を褒める』という習慣の形成
次に『保護者が宿題をした子供を褒める』という習慣の形成についてです。

Triggerとしては、「①子供がやる気パワーを注ぐ」「②『やる気のキロク』画面で、子供が頑張った日などに花丸をつけて記録する」「③『週間やる気レポート』画面で、子供を褒めることの重要性を説くキャラクターのつぶやきが表示される」がきっかけとなり得ると考えられます。
続いて、Actionは「①宿題をした子供を褒める」。この際、レポートで表示される前週比やキャラクターのつぶやきが参考となるため、褒めやすい環境が整えられているといえるでしょう。
そして、Rewardは「①子どもが驚くほど宿題をやってくれる」。Investmentは「①子供とすごろく(やる気の庭)のご褒美を設定する」といった具合です。
「しゅくだいやる気ペン」から見えてきた習慣化における示唆
このように見てみると、習慣化の形成をメインで促したいユーザ(「しゅくだいやる気ペン」における子供)に対してはフックモデルにおけるRewardを特に手厚く設計できるとよく、その上でサービス利用中におけるモチベーションの向上を意図するために、良い行動に対して素早く享受できる小さな報酬を設計する。
また、次回利用に対するモチベーションの向上を意図するために、良い行動を継続することで享受できる大きな報酬を設計するとよいという示唆が見えてきました。
さらに、Rewardに他者からの賞賛を加える際は、賞賛を行うユーザ(「しゅくだいやる気ペン」における保護者)に対して、フックモデルにおけるTriggerを特に手厚く設計できるとよいとも言えそうです。
また、本記事で深くは触れませんでしたが、「専用アプリケーションに鉛筆を傾けることで、やる気パワーを注ぐことができる」といった、作り手が“便利さ”を優先しすぎると実現されないようなリッチなインタラクションと演出が愛着を生み出し、その結果、習慣化へと繋がっているのでは?という妄想も膨らみました。
最後に
いかがだったでしょうか?人気のプロダクトの裏には、点ではなく線で紡がれるように体験設計された素晴らしい仕掛けがある。それをうまく伝えられていれば幸いです。
プロダクト開発の現場では、自社サービスや競合サービスの調査を行うことは往々にしてあると思いますが、たまには他のサービスにも視野を広げて観察してみると、意外なブレイクスルーに繋がるかもしれません。良質なアウトプットは良質なインプットから。皆さんも試してみてはいかがでしょうか。
実は以前、同僚と「人間性(Humanity)」というマニアックな観点でサービスを紹介する記事も公開しているのでよろしければそちらもご覧いただけると嬉しいです。
執筆者紹介
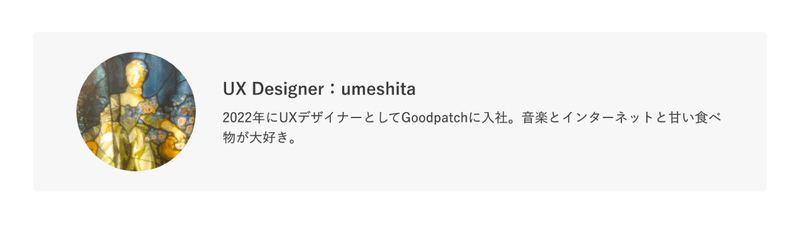
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
