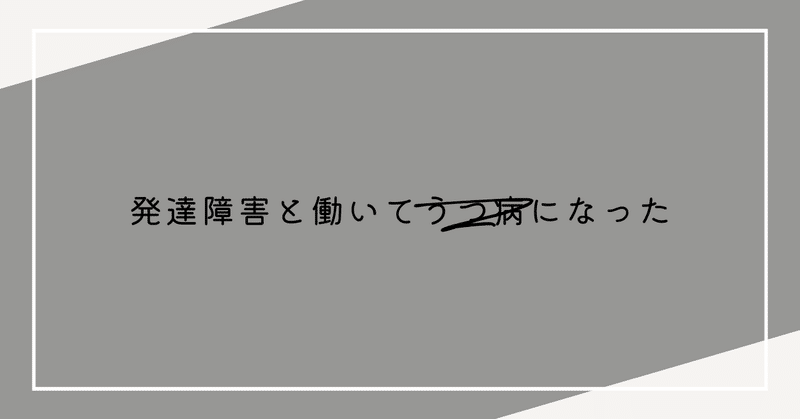
発達障害と働いてうつ病になった話
弊社の発達障がい社員のお話と、私のお話です。
引っ越しに伴って、事務職に転職した。
Aさん(発達障がい持ち)の入社は、私より少し前。
Aさんが障がい者であるということと、求めている配慮は、Aさん自身がチーム内に伝えていた。
Aさんと私の指導役は女性の先輩だった。転職で戸惑ってばかりの私にいろいろ教えてくれた上、引っ越したてであることも気遣ってくれて、かなり面倒見のいい方だった。
チームメンバーにはAさんと先輩の他に、サバサバしている有能な女性の上司もいた。
チームに違和感を覚えたのは、1週間くらい経った頃だったと思う。
先輩の機嫌が悪く、言い方がきついときがある。私とAさん以外のチームメンバーが、急に会議室に行ってしばらく帰ってこないこともたびたびあった。
そしてある日、その急な会議に、私も呼ばれた。
何かやらかしたのかとドキドキしていたら、Aさんへの今後の対応をどうするか、という話だった。
そして、私が来る前の、チームメンバーの戦いを教えられた。
電話対応を「できません」と断った。
デスク周りをうろうろ歩き回ったり、ビル内を徘徊してデスクに帰らなかったりした。
指示や指導をすると「無理です」とヒステリックになって泣いてしまった。
マニュアルを読まず、やり方を何度も聞いてくるうえ、メモも取らない。
などなど。
私は前職で発達障がいについて少しかじったことがあったので、「こういう言い方をした方がいいんじゃないですか」などと言ったことを覚えている。ドアホだった。もう戦って疲れている人に、専門家面してアドバイスめいたことを言ってしまったのだから。
状況が呑み込めたのは、1か月後くらいだった。
周りを見る余裕ができ始めて、ようやく、本当に大変であることを知った。
作成書類のどこかが必ず間違えている。
案件の内容の把握と分類にかなりの時間がかかり、精度が低い。
処理すべき期限が過ぎる(それを報告・相談もしない)。
頼んだ仕事の経過報告や終了報告がない。
電話対応や窓口対応ができない、気づかない。
これらは一部のことで、お世話役の社員が必要な感じだった。
先輩は、「いつか独り立ちできるようになる」と信じて、ひとつひとつ根気強く毎回指導してあげていた。
でも、Aさんはそのたびイライラして、大きな声で弁解していた。
何かひとつ改善されると新しい問題が出てくるか、前にできていたことができなくなる、といった調子だった。
どうにかしようと、チーム内で何回か話し合いの場を持った。
『合理的配慮とは』みたいな資料や本を読んだ。
障がい者雇用のセミナーみたいなのも受けた。
上司はAさん用に業務手順書を作ってあげていた(マニュアルは別途ある)。
やらなくてはならない業務を一緒にリストアップした。
でも、試したやり方では、期日通りにはできないこともあったし、正確性も上がらなかった。
毎日一緒に業務を確認した上、チェックもしなくてはならないので、負担が増えただけだった。
業務以外のコミュニケーション面でも問題はあった。
上司への質問や相談が上司の休憩前だったり忙しい時だったりする。
質問や相談内容は自分の休暇や給与の話、前に聞いたことがある内容。
回答に時間がかかることもあるのに、答えを聞くまで近くをウロウロする。
こんなことが重なって、上司は話しかけられる度にきつそうだった。
他にも、返事や態度が尊大だったし(Aさんのための業務が増えた先輩や私に「ありがとうございます」や「すみません」も言ったことがなかった)、
関係のない書類に的外れな指摘をしてきて、いちいち説明しなくてはならなかった。
課長に相談をしたら、「様子を見ましょう」と言われた。
医者に相談したら、「そもそもその特性の人に事務職は無理」と言われた。
専門家に相談したら、「客観的判断のもと辞めてもらうしかない」と言われた。
人事に聞いたら、「どこの部署でもそういう人がいて、だいたいどこでも飼い殺し状態」と言われた。
解決の糸口はなかった。
どこへ相談しても無理だといわれるので、先輩が指導を諦めた。
そして、Aさんの仕事を代わりに私たちでやり始めた。Aさんには簡単な業務だけが残ったが、それが業務のすべてだと思ったのか、ほっとした様子で、どっしり落ち着いてしまった。
Aさんの仕事をやっているから、私たちは逆にだんだん元気がなくなっていった。
そんなときに、先輩が家庭の事情で退職することになった。
この状態で辞められないと思ったのだろう、必死にいろいろ課長に働きかけてくれた。
結果、課長から言われたのは「新しい人を雇うから、Aさんには仕事をさせなくていい。新しい人が来るまで我慢して」。
それから、新しい人が来るまでの数か月間の繁忙期中、Aさんの仕事を先輩と私で分担してやることになった。
Aさんのポジションは年度末が一番忙しいのに、私たちは、自分の仕事と並行して、Aさんの仕事までやるはめになった。
しかも、Aさんは元気に出勤してくる。課長から「仕事をさせなくてもいい」と言われても、放置しておくわけにもいかない。
課内から、Aさん用の単純作業を募集することになった。
私と先輩には、その作業を発注者から聞いて、Aさんに指示を伝えて、正しく作業できているかしばらく見守って、作業が終わったら様子を見に行って、事後、やっぱり片付け忘れているテープとかハサミとかを片付けて、発注者に終了報告をして、……という業務が新たに発生した。
上司が見かねて、発注者から直接Aさんに依頼してもらうようにしてくれたが。
それでも、こっちがAさんが本来やるべき仕事をやっているのに、本人は「ありがとうございます、助かりました」などと言われているのは、納得がいかなかった。
なんとか繁忙期を乗り切って、先輩が退職してからも、状況は変わらなかった。
新しく入った社員は奇跡的に超絶に仕事ができる人だったので、業務上のストレスはなくなって平和な日々になった。
Aさんのお茶をすする音とか、あくびの声とか、でかい挨拶とか、雑用を頼まれている様子とか、そういう小さいことにいちいち耐えればいいだけの日々が続いた。
耐えればいいだけなのに、あまり楽にならない。
細かい事情を知らない他の人から、「平和になってよかったですねw」とか「一生懸命で誠実な方なんですけどね」とか「こんなことを頼んだら、丁寧にやってくれましたよ」とか「そっちの問題はまだマシですよね」とか言われるたびに、自分が心が狭いクソ野郎なのだと思い知らされた。
Aさんが直接の原因というよりは、Aさんにイライラしてしまう自分が嫌だった。
前職で発達障がい児を見ていて、私はその子たちが大好きで、敬意を持っていたのに、結局差別してしまう人間だったのかと自分に裏切られた気分になった。
先輩はAさんのことを「病気」と言った。でも、治すべきものではないから、特性であって、病気ではないんじゃないかな、と思ったりもした。
自分は発達障がいに理解があるつもりだったけど、結局、文句を言う側になっていた。
最初に現れた身体の不調は腹痛だった。自律神経の不調だと言われた。
次は不眠だった。心療内科に行ったら、適応障害の診断を受けた。
上司に事情を伝えたら、同情してくれた。「そんなことで不調になるなんて」と呆れられないだけでありがたかったが、すぐに課長に直訴してくれて、Aさんを課内の別チームのエリアに移動させることになった。
そのおかげで、たまにAさんの姿を見る以外、関与がなくなった。それでも、腹痛や頭痛があって、休みがちな日々が続いた。
有給がなくなった。無給休暇に切り替わったので、給料は下がった。
できる限り、有給扱いの休暇制度を使わせてもらったが、それでもダメだった。
半年経っても悪化する一方で、一睡もできないまま仕事にいくことが増えた。寝ていないのに夜は眠れないし、職場に行こうとすると吐いてしまう。
とうとう週に1回か2回しか出勤できなくなった。
で。鬱病ですね〜と、ついに医者に言われた。
先輩にも上司にも迷惑をたくさんかけたし、忙しい中、いろいろ対応をしてもらったのに、この体たらく。
情けなかった。
そういえば、Aさんは辞めるらしい。もう、正直、どうでもいいけど。
Aさんの意思なのか、何か理由をつけて辞めるよう促されたのかはわからない。
Aさんが辞めても、私の鬱病が治ることはないだろうなと思っている。
自分自身の感じ方の問題なのはわかっているので、Aさんに対しての恨みとか憎しみとかはもちろんない。
ただ、「発達障がいのある人との共存」を考えると、わからなくなる。
共存って、本当にできるのだろうか。
自分は弱者ですよという顔で、「できません」「あとはお願いします」「わかりません」と言って、ぼーっとしている。辞めさせることもできない。
そして、こちらは頭を、時間を、心を砕かなくてはならない。
働いていただくために。
それって、共存と言えるのだろうか。
もののけ姫みたいに、「君はあっちで、僕はこっちで暮らそう。共に生きよう」みたいな感じじゃだめなんだろうか。
「お前らのやり方が悪い」と思う人もいるだろう。
当初の私のように、物知り顔で説教をしてくる人もいるかもしれない。
私たちの戦いは、課内から「大変ですねw」と言われ続けた。
「発達障がい」というカードを持つ人と対峙するとき、きっと立場が弱いのはいわゆる健常者側なのだろう。
今回、私も「うつ病」というカードを手に入れたので、文章にしてみました。
いろいろ書きましたが、今回のことは、たぶん、受け入れ体制が悪かったんだろうなと、今では思っています。
Aさんが、次の職場では輝けますように。
※注釈
身バレ上等で書きましたが、一部改変しています
以前、この記事を読みました。
筆者の方、どうかもうその人のそばから離れて、平和で幸せになっていますように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
