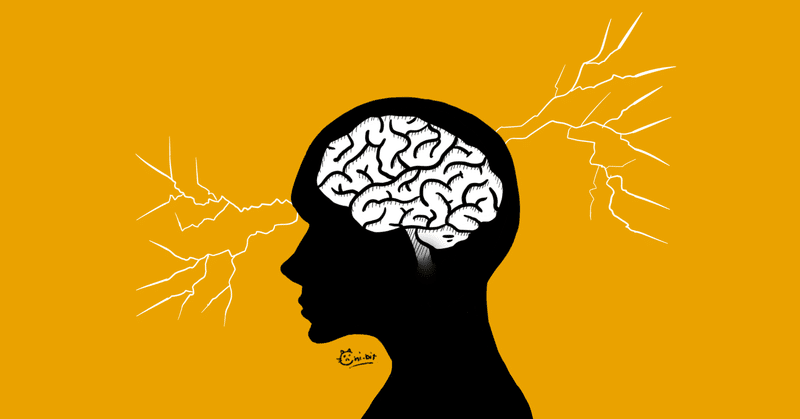
IT社会に潜む脳機能低下について危機を感じる本
はじめに
最近、認知科学の本にハマっている。前は心理学であったが、なんか自己啓発に寄っていたので、ここらで専門家の方の著書をひとつまみ。
どんな本
現代社会で現役ビジネスマンにも起こり得る「脳の機能低下」に関する話。
いくつかの事例を用いて、原因とその考察、改善法を述べている。
以下では三つの事例をピックアップ。
重要1「システムエンジニアは注意!脳機能の偏り」
10時間のプログラミング作業をしているエンジニアは一日中、PC画面の向き合うことになる。
プログラミングといえば論理的思考力や短気記憶力を要する。
脳に悪いわけではない。
しかしそれは脳機能の一部を酷使し、
それ以外の機能を使っていない脳機能の偏りが問題なのである。
休憩時間で、プログラミングでは養えない脳機能を使うことが重要である。
例えば、コミュニケーションや音読、散歩や筋トレなど。
重要2「人の話で上の空」
「人の話が頭に入ってこない。」
テレワークが推進される現代にありがちな相談らしい。
テレワークではZoom経由で会話するが、
直接会って話す時と比べて情報が入りにくい。
まず長い話が頭に入ってこない人は、単語を聞き取ろうとしすぎらしい。
話の全体像を理解するには、情景を思い浮かべる事が重要だ。
当事者意識を持って共感しようとすることがといいらしい。
重要3「インターネット依存で記憶力低下」
デジタルネイティブ世代の若者に多い。
まず記憶の保存について。
情報を分割し、
それぞれにタグ付けを行い、
タグ別の棚に収納する感覚。
ネット媒体からの記憶だと、単語と説明が瞬間的に表示されるので、こういった手順を踏まない事がインターネットの情報は記憶しづらい原因。
本やエピソードだとどこで知ったか、何で知ったか、知るまでに何をしたかなどのメタ情報も付随するので、より記憶として残りやすい。
次に思い出す作業について。
情報を棚から引き出す時に、
そのタグ情報などを元に情報に在り付く探索方法が理想的。
例えば、知らない情報を聞かれた時に、
何でもネット検索するのではなく、知っている情報をヒントととして推測するなどの訓練が必要らしい。
感想
わかっているけど実践が難しいんや!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
