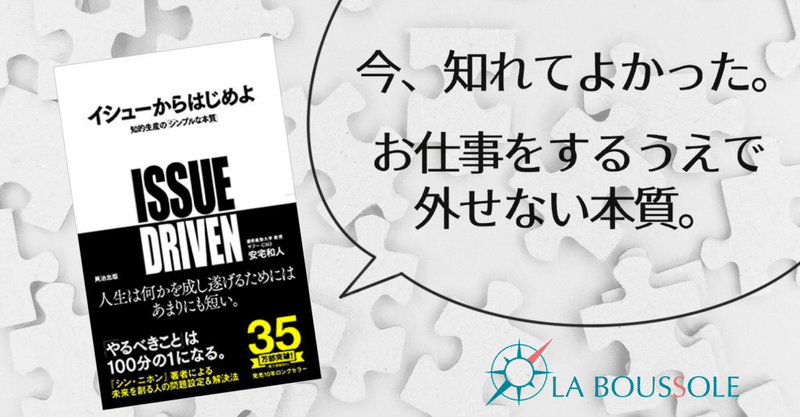
『イシューからはじめよ』行動する前に考えるべきこととは@meguuu_pinot
「私を変えた一冊」というテーマでお届けしてきたラブソルnote。
正直私にはまだ、自分を変えた一冊と言われてピンとくる本がありませんでした。
そこで、弊社ラブソルでおすすめしてもらった『イシューからはじめよ』を読んでみることにしました。
イシューってなんだっけ? と思いながら手に取りましたが、読み始めから、なるほどと腑に落ちることばかりだったんです。(Kindle版、Audible版もあります。)
改めまして、アライアンスメンバーの大学生、めぐみです。早いもので、ラブソルにインターン生としてジョインしてから丸半年が経ちました。
ラブソルでは、職業体験や就活の一環としてのインターンではなく、ありがたいことに実際の業務に携わり、さまざまな現場でお仕事をさせていただいています。
経験値があるわけでもなく、ズバ抜けて何かができるわけでもありません。私自身至らないところばかりで、情けなくなることも多々あります、、。
それでもお仕事ですから、当然、完成度などの結果を出すことが求められます。どうしたら一つひとつのお仕事に対して、質の高いアウトプットができるのか、たくさん学ばせていただき、模索しながら過ごしてきました。
そんな中、この本との出会いは、物事に取り組むときのそもそもの考え方を見直すきっかけになったんです。
というのも、これまでは目の前の状況に対してどう対処するかを考えていたのですが、まずすべきことは、本当の問題を見極めることだと知ったからでした。
イシューからはじめる、とは
タイトルにもなっている「イシュー」ですが、この本では、知的な生産活動の目的地となるものとして捉えられています。
つまり、意味のあるアウトプットを生み出すために、本当に考えなければならないカギのことです。時間や労力を無駄にしないためには、まず解くべき問題を絞ることが必須です。
たとえば、今目の前に複数個の課題があるとして、みなさんは何から手をつけますか?
本を読む前のいつもの私だったら、先に簡単に解決できそうなものや、楽そうなものから手をつけていました。
それも、ただそれだけの理由でです。
しかしこの本を読んで、物事に取り組む前の思考こそ重要なのだと気がつきました。取り組みやすそうといった感覚に惑わされて、すぐ解き始めるのではなく、最初に何に答えを出す必要があるのかを考え、仮説を含めて問題を明確にすることが大切なんですね。
バリューのある仕事への道
著者の安宅さんは、バリューのある仕事とは、丁寧な仕事や自分しかできないものではなく、図の右上の部分に入るもので、実際は極わずかだと言います。

参照 :『イシューからはじめよ』図6
この図における二つの軸は、
「イシュー度」 : 自分の置かれた局面でこの問題に答えを出す必要性の高さ
「解の質」 : そのイシューに対してどこまで明確に答えをだせているかの度合いを指しています。
安宅さんは、あれもこれもとがむしゃらに、たくさん量をこなすのでは、いつまでたってもバリューのある仕事の領域に行くことはできないから、まずイシュー度を上げ、その後解の質を上げるという正しいアプローチ(青矢印の進め方)を採ることが大切だと言います。
バリューのある仕事をできるようになるために、絶対にやってはいけないのは、一心不乱に大量の仕事をしてその領域に行こうとすることだそうです。×のついている進め方をしようとしても時間がかかり無駄が増えるばかりです。
はじめはとにかく量をこなすのがベストと思われがちですが、イシュー度を見極めたうえで、その度合いが高いものから取り組むことが必須なんですね。
イシュー度を上げることこそが、意味のあるアウトプットをして、バリューのある仕事ができるようになるための第一歩というわけです。
私は恥ずかしながらこの本を読むまで、何かに取り組む時に、課題の質について考えを巡らせたことがありませんでした。どう対処するかや、どのようなものを出せるかという解の質ばかり気にしてしまっていた気がします。
この重要な本質をスルーしたままだったら、この先なにも考えずに時間を使っていたかと思うとゾッとします。
イシューの言語化
なるほど、イシューの見極めが大切なのはわかったぞ、意識しよう! と読み進める中で、さらに刺さった言葉がこちらです。
何はともあれ「言葉」にする
(中略)
なぜ言葉にできないのかといえば、結局のところ、イシューの見極めと仮説の立て方が甘いからだ。
はい、おっしゃる通りです、、。
本当に価値のある仕事をしていくためには、物事に取り組むときにイシュー度の高い、核となる問題を絞り、質を上げていく、このサイクルをたくさん回すことが大切です。
そのためには、きちんと言葉に落とし込むことを意識的に繰り返していく必要があります。
この本を通して、私に足りないこと、意識していくべきことが見えてきた気がします。
実際私は、考えたことや浮かんだアイデアなど、自分の中に浮かんできたものたちを、言葉にして外に出すのは得意ではありませんでした。頭の中だけで考える方が楽だし早いしなんて言い訳をして、言ってしまえば逃げていたんです。
表層的な論理思考で、与えられた状況に対処して量をこなせばいいのではなく、まずその状況における核となる問題を見極め、仮説を立て、言葉に表してから動く。
間違いなく、物事への取り組み方を見直すきっかけとなりました。この本には、本質となる考え方や実際に行動するときの具体的なポイントを教えてくださっているのですから、あとは意識して普段から実践するのみです。
今、この本に出会えてよかったです。
***

〈ラブソルへのお仕事依頼はこちらから〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
