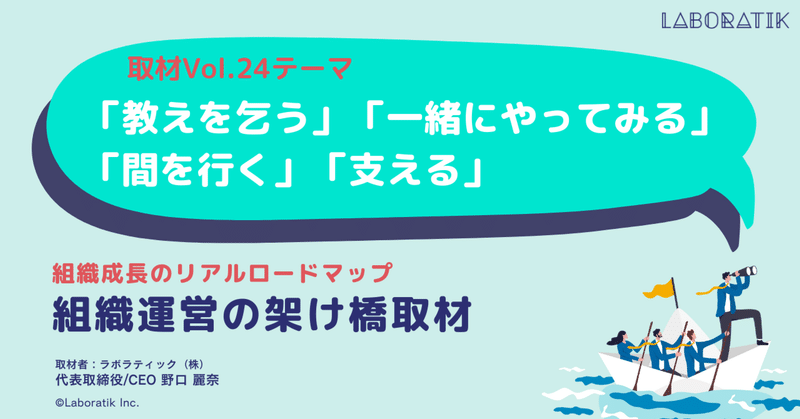
Vol.24「教えを乞う」「一緒にやってみる」「間を行く」「支える」
チェーンストア展開を行うスーパーを顧客に持つ和菓子メーカーで、業務プロセスや組織の様々な課題に取り組み、多くの実績を残されてきた鈴木さんにお話をお伺いしました。
入社当初は経営戦略室 室長として、現在は、西日本事業部全体の責任者として業務改革、組織改革を行い、会社の業績の向上や人材育成などに大きく貢献されています。
内在する問題は【教えを乞う】「身をもって確かめる」「全社に働きかける」
鈴木さんは12年前に、社長の呼びかけで経営戦略室 室長として入社されました。入社当時を「業種としての和菓子メーカーについては全くの門外漢だった」と振り返られたのが印象的です。和菓子メーカーの業界、スーパーマーケットのチェーンストアに関する知識、いずれも希薄な状態からのスタート。
「とはいえ・・社長直轄の経営戦略室 室長として、横断的な業務改善のミッションを託されたので、やるしかなかった」まさに、鈴木さんのキャリアにおいても、チャレンジの始まりでした。
鈴木さんは、業務改善等の遂行のためには、まず企業全体の現状を把握することに着手されました。どのような問題や課題があるかを理解し、製造部門、営業部門、品質管理部門など、全体にわたって働きかけるためにも、現状把握は必須の状況です。
しかし、これまで会社を背負ってきた職人気質の人やベテラン社員の人たちが組み立てた業務プロセスに対してのヒアリングにはデリケートな側面もあることでしょう。ご自身はどのように現場との対話を進められたのでしょうか。
「過去の経験やベテラン社員が築き上げた業務プロセスを批判するものではなく、『学ぶために教えを乞う』姿勢や、同時に『組織の一員として認めてもらうこと』を重要視しました。ただ、聞くという姿勢だけでは、表に見えている話だけで終わってしまい、本質に触れるような深さにはならないし、同僚としての関係性も構築できないですよね」
そこで、鈴木さんが、聞く以上に実践されたのは、「自ら、確かめる」ことでした。つまり、現場で得た情報を実際に再現し、現場と一緒にご自身も体験した上で、課題や問題を共有しながら改善に取り組む姿勢が、周囲への本気度を示す手段となったのです。
実際に確かめ、「全社に働きかける」までが鈴木さんのミッションです。次のような事例と共に全社に働きかけることの意義をお伝えくださいました。
自社工場からスーパーへの配送を委託している配送業者さまから「スーパーへの納品が間に合わないから、出荷を早めて欲しい」という依頼に応えるために、製造ラインでは生産を途中で切り上げて対応をしている、という状況を掴みます。現場では、確かに、納品に間に合わせるための措置として切り上げることで対応せざるを得ない状況だったと言います。しかし、「全社に働きかける」ことで、配送業者を管理する担当者からも「教えを乞う」ことで、事態を紐解いていくと、納品が間に合わない根本原因が、当社の製造・出荷時間や納品先の受入れ時間ではなく、配送業者さまが、途中に立ち寄りたい他社さまの都合だったことを突き止めます。
配送業者さまの売上獲得やコストダウンには、協力もするし工夫のジャマなどしないが、当初は発生していなかった一方的な都合で、当社がこの状況を受け入れ続けるわけにはいかない、と折衝。結果、当社製造ラインの生産を途中で切り上げる対応をやめて、改善に繋げたそうです。
丁寧なヒアリング、身をもって状況を確認し、さらに全社レベルで教えを乞いながら紐解くことを続け、現場と全社の循環で、様々な業務の最適化を実現させていかれました。
信頼感は、提案したことを【一緒にやってみる】、全体最適のために【間を行く】
全社に働きかけながら、丁寧に運営の改革を進められた鈴木さんですが、「課題、問題を洗い出す」その先についても、お話しくださいました。
「話を聞くのは重要ですが、聞くにとどまらず、聞いた内容に切り返し、改善を提案していくことこそが、私自身の存在価値を発揮すること」と、力強くおっしゃいます。
たとえば、生産のキャパシティ不足の問題があった場合、現状をベースに生産計画をシミュレーションをするだけでは、単なるキャパシティ不足という結論になります。その結論を持って、ライン担当者を増やしてラインを増設するというようなアイデアを出せば解決に向かうことができる。
増員にはグループ会社社員や派遣社員を利用する、グループ会社社員を連れてくる交渉や、派遣会社探しは私がやるからその後は頼むぞ、というところまで提案すれば、現場の方から見ても、机上論ではない、地に足のついた改善になるわけです。このようなサイクルは、本取材の読者の方であれば、当たり前のことのように受け取られる方もいるかもしれません。しかし、頭で理解しているのと、実際にできるのは全く別物。向き合い続けて、やり抜く姿を周りは見ているものです。
さらに、現場を巻き込むという意味で、鈴木さんが重視されているのが「一緒にやってみる」ことだそうです。つまり、鈴木さんが提案した解決策を実際に現場の社員と自分が「一緒にやってみる」ことで、問題の状況を確かめるという現場に根ざした実践を繰り返しているのだそうです。確かに、チームで一緒にやることで、互いの信頼感が生まれるだけではなく、みんなで取り組んだことで成果が出たという意識に繋がりそうです。鈴木さん自身も手応えを感じていると同時に、社員のモチベーションを高める役にも立っているとお話しくださいました。
組織においての課題と改革というと、誰かしら旗振り役がいるもの。鈴木さんもそのような役回りだったのだろうと推察します。推進の要諦を伺うと、次のような印象的な回答をいただきました。
「自分だけでやっていては、独りよがりで誰もついてこない。だからこそ、現場を熟知したメンバーも交えて、『やってみる』という対応を進め、やった際の課題を解決するというサイクルが好循環を生んでいること。私自身も、『事実ベース』の情報だけでなく、「気持ちベース」の情報も経験することで、問題の本質を見極め、より良い提案や解決策を導くことができているのだと思います」
まさに、組織の課題が、自分ごとになり仲間と解決していく醍醐味ですね。
ところで、このような改革の提案で、何か注意する点はあるでしょうか?
鈴木さんは、ご自身の組織で心がけたことを共有くださいました。
「問題の解決策は、社員のスキルのレベルのばらつきを考えて、中間レベルの経験値やスキルでこなせる提案をしています」
全体のメンバー・チームのバランスへの配慮がないと、組織としてマイナス効果が強く出ることを身をもって知った上でのご判断だそうです。
具体的にお話を伺いました。
「『間を行く』。つまり、組織としての現状の最適解を見出した上で、今のスキルでは50%しか対応できないメンバーに70%を、100%の対応ができるメンバーにも70%を目標にしてもらう。スキル差が大きいほど、ボトルネックが極端になり、生産性は上がりません。そればかりでなく、おかしな有能感や劣等感が生まれ、雰囲気まで悪化します。能力も意識も揃えない限り、チームの力は上がらないことを理解してもらい、お互いに協力してもらう必要があるのです」
組織におけるスキルレベルの最大値と最小値の中間、つまり最適はどこかを 常に探るという視点。皆さんはどのように見極めていますか?
ともすると、常にベストエフォートを弾き出したくなるけれど、それでは皆んながついてこないこともあります。今の組織の最適はどこか?という眼差しは、組織成長に必須ですね。
やりすぎたことを反省し、自ら考え動く社員を【支える】
鈴木さんは長年にわたり、同社内でさまざまなチームの運営に携わってきました。現在は、西日本事業部全体の責任者として、組織の安定を図るために様々な課題に取り組まれています。過去には組織の立て直しに成功し、全体最適をキーワードに組織を安定させる役割を果たしました。しかしながら、反省点から、ご自身のマネジメントでも新たな取り組みを始めているそうです。
「組織を立ち直らせる過程で、自分が現場に入り込んで指揮をとりすぎた副作用があり、『指示待ち』『考えない』傾向を助長したのではないかと疑問に思うようになりました。後進の育成のためにも、私自身には待つことを課し、メンバーが自ら動き、主体的に考えることを『支える』方針に転換したのです」
この方針転換は、現場主義と実践主義を大切にしてきた鈴木さんにとって、大きな転換点であったことでしょう。それでも、鈴木さんは「今では、自分の後を継いでくれる人材が育っている」と嬉しそうに話してくださいました。
鈴木さんは、一貫して、着実かつ地道な手法で業務改善と組織改革を進めていらっしゃいました。まさに、人と組織の成長や変化には時間がかかることを理解し、目をかけ、育み、思慮深く周りと着実に成長を進めていくアプローチは、一朝一夕にできることではありません。
私たちは、組織全体の成長を願いながらも、成果を勇み足で求めすぎてはいないでしょうか。周りが育つために、自分自身が待つ。周りと一緒にやってみるなど、持続的な組織運営のために必要な目線が詰まったお話を伺うことができました。
【取材協力】
明日香食品株式会社
取締役 西日本事業部 事業部長兼 スマート和菓子開拓室 室長
鈴木敬太様
http://www.asukafoods.co.jp/
《この記事に関するお問い合わせ》
ラボラティック株式会社 広報担当
info@laboratik.com
