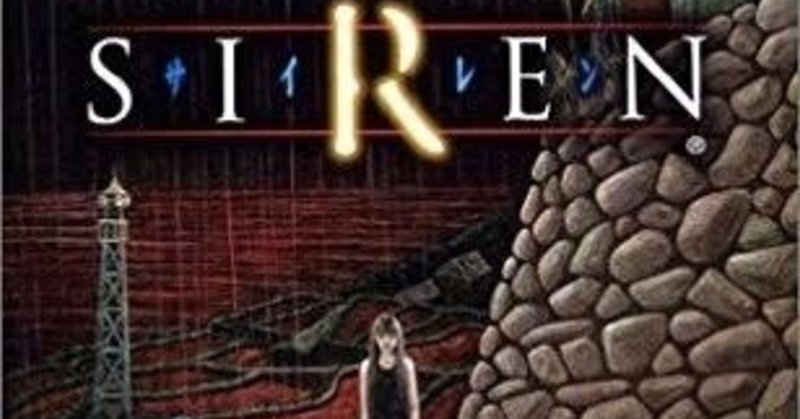
私の愛したSIREN
光を落とした寝室で、夫が泣いている。
私のせいだ。
夫は聞いていた。見てしまったのだ。妻である私が先刻、二歳の娘を寝かしつけた後に、スマホの画面を見ながら「愛してる…愛してる…」と繰り返しながら啜り上げているのを。
スマホの画面には、SIREN展が中野で開催され、盛況である様子が映されている。
「ごめん、ちがくて…SIREN展が開催されてるんだって」
スマホの画面を見せると、涙とその光で眩しそうに一瞥し、「じゃあ仕方がないな」と言って鼻をかみ、すぐにまた眠ってしまった。
しかし私の胸の震えは止まらず、今夜は眠れそうにない。
SIRENというゲームを知っているだろうか。
私は確かにSIRENを愛していた。そして発売から15年経った今も、SIRENがイベントを開いて愛を受け入れようとしていると聞いたなら、震えずにいられないのだ。
あの頃のゲームというものは、大手ハードで遊ぶものが主流であり、それは沢山の人が関わって作られ、沢山の人によって支えられる大規模なものだった。
ハード、制作スタッフ、デバッグ、ゲーム雑誌をはじめとするメディア。
今現在触れることが多いスマホゲームと異なる最も大きな点は、そのほとんどがオフラインゲームであり、アップデートができないことだろう。
初めから終わりまで、作って作って、気をつけてチェックして、出す。
やっぱりそれは、大切に大切に手をかけた制作者だけではなく、関わる全ての人の思いを載せた子供のようだったと、今は感じざるを得ない。
私がSIRENと出会ったのは、そんなゲームが生まれたり遊ばれたりする上で関わる者達の端くれとしてだった。
・高難易度と言われたゲーム
・SIRENは現実なんだ
・屍人と愛
・判明!屍人の愛らしさの秘密
・セクシーナースと仲間たち
・小学生からおじいさん
・和と洋、SIRENの世界
・2作目と3作目
・最後にSIREN15周年を祝って
高難易度と言われたゲーム
難易度が高いゲームが好きなわけではなかったので、仕事で出会わなければやらなかったかもしれない。
そう、当初このゲームは、難易度が高いということで敬遠されていた。
すぐに死ぬ。
そんなゲーム、面白いだろうか?
実際にやってみた。暗闇の中で、無防備な自分と拳銃を乱射する警官。すぐに死んだ。またやり直しても、ほかのホラーゲームのような地図もなく、すぐに死んだ。
高難易度、難しい?いや!違う。
「これが現実なんだ!」
SIRENは現実なんだ
ゲームじゃない。ほんとのことさ。
私は一気に楽しくなった。
今まで楽しいと思っていたホラーゲームは一体なんだったのだろう。
右上にいつも地図が表示されるばかりでなく、現在地がピコンと表示されている。
おまけに一度開いたドアまで表示され、地図の読めない私に優しい仕様だ。
**でもそれじゃまるでゲームじゃないか! **
実際にクリーチャーが暗闇で攻めてきたら、
…
すぐ死ぬだろーー!!
頭に地図表示されないだろー!
だからそれがないSIRENは現実なんだ。
という訳のわからないことを口走りながらハマってゆく私を、仲間たちは温かく見守った。
コンプリートのための条件機役もそうだ。
これが特に難しく、攻略本にも書かれておらず、悪名を知らしめた。
だが、どうだろう。
ネットで少しずつ、プレイヤーからの情報が集められていった。
灯油をまくタイミングから、電話をかけるタイミング。
ストーリーを深く進める契機は大変シビアだった。現代と違いネットというものはPCからしか使われないような状況の中、詳細が文字で情報交換されていった。
何度も死に、何度も失敗した。
小屋の上で武器を持ち替えてブンブン振るとか、そういうノーヒントで脈絡のない「まぐれ」がいくつもネット上で組み合わさり、プレイヤーみんなの力で物語の深淵に少しずつ近付いて行った。
…そうだ。これこそ現実の体験なのだ。
クリーチャーが跋扈する中に身を置いたら、普通逃げないか。
謎の深淵に辿り着こうと色々危険を冒すだろうか。
現実だったら、危険を冒しておかしな儀式を暴いて生きて謎の答えに辿り着く可能性は、何パーセントだろうか。
そんなことができるとしたら、それは奇跡的なことであり。
もしもヒントが散りばめられていて、誰にも相談せず自分の部屋だけで解決できることならば、それはゲームなのだ。
何度も死んで、ネット上という違う世界線の主人公と相談して生き返って試して、やっとおかしなホラー世界の中心へ辿り着く…
SIRENがくれたのは、ゲームではなく現実のホラー体験、冒険だったのだ。
屍人と愛
SIRENのもう一つの魅力は、なんといっても屍人たちだろう。
このゲームの特徴として、屍人ジャックと言うクリーチャーの視点をジャックしなければならない機能がある。
SIRENをやり始めた時は、この機能を使うだけで恐ろしい。何が恐ろしいかってクリーチャーの吐息が間近で聞こえるのだ。
主人公達を見つけて興奮した声を出したり、攻撃に走って行くのをクリーチャー視点で見なくてはならない。最低だ。
気持ち悪い。しかし、屍人をジャックし欺いていくうちに、屍人の笑い声や独り言を聞く余裕が出てくる。
彼らの多くが元人間の町民達なのだが、笑ったり独り言を言ったり、なんだか楽しそうだ。寂しそうに呟いている奴もいる。
あまり多くのことを考えず、純粋な奴らだとすら思えてくる。
何を言っているかよくわからないので耳を傾けているうちに、愛着が湧いてくる。それが屍人である。
その町民が住む羽生田村までもが、楽しい村に感じて来るのだ。
判明!屍人の愛らしさの秘密
屍人たちにどんどん愛着が湧いてしまう根本的要因が、最近判明した。
子供を産んでわかったのだが、1歳前後の乳幼児の言動に、それらは酷似しているのだ。
定まらない表情、何を言っているかわからない独り言、突然の笑い、ロックオンした対象に一目散…。
屍人ー!屍人の可愛さは赤ちゃんの可愛さ。
屍人のデザイナーがそれを意識したのかはわからないが、可愛くないわけがなかったのである。
一心不乱の怖さも似ている。
セクシーナースと仲間たち
また、町民の他には特別なキャラクターを持った屍人たちが存在する。中ボスであるが、サイレントヒルから存在する名物キャラである「セクシーナース」をはじめとして、小学生から老人まで、皆魅力的で、彼らはテレビCMでも活躍し、怖いと話題になった。
魅力的な屍人と闇人を描いたのは髙橋美貴さんというアーティスト。
小学生からおじいさん
人間であるプレイキャラも、皆さんキャラが立ち、実写とCGアニメの間のデザインが個性を引き立てている。
こちらも小学校低学年からお年寄りまで、操作感覚が全く違う。
お年寄りのキャラクターを操作する時には、息も切れやすく、現実でもお年寄りを大切にしなくてはと感じてしまう。
それでも強かったスナイパー(猟師)の志村さんは、忘れれないキャラクターだ。
和と洋、SIRENの世界
賞賛を省けないのが、世界観である。日本の田舎の村に、洋を感じさせる教会が融合している。
民家や食堂など、住民の息吹を感じさせる作り込みで、愛着を感じずにはいられない。
個人的には、終盤に屍人たちに村を改造されるのが悲しかった。屍人たちもその姿を変え、「普通のクリーチャー」になって行くのが、寂しかった–−。
終盤のほうでは、田舎的な雰囲気が変わっていくSIREN。
真相の方向性もかなり好きである。例えるなら、鈴木光司さんのリングからのループのような、ジャンルを超えた壮大さがある。
2作目と3作目
SIRENは素敵なゲームである。
入手当初は何度もプレイし、挙句にはSIRENの欧米版、三作目のNew Translationではなく1作目SIRENの欧米版ディスクを手に入れ、PS2をあーやらこーやらして英語版を楽しむという始末。
そんなSIREN好きの私にとって、二作目のSIREN2はどうだったか。
闇人という新クリーチャーは天井桟敷を思わせ(実際に意識したとのこと)、期待を膨らませた。
しかしながら、先述の「地図がないリアリティ」が外されてしまったこと、チュートリアルという「非現実」が介入したこと、更には冒頭の犬のジャックが画面酔いしてしまったことから早々にリタイア。
一作目が好きすぎて、以降を認められない面倒なファンを地でいくのであった。
今思うと、それでも一度通してプレイしておけば良かったと思う。
三作目SIREN:New Translationは主人公が日本人ではないということで、大丈夫なのか?と思ったが、雰囲気もストーリーもとても良いというのが感想だ。
しかし、自分の生活が忙しくなり、「積んプレ」のまま眠る。
最後にSIREN15周年を祝って
そんなわけでSIRENを愛して止まず、SIREN展にも行きたいが、幼児を連れて行くには我が家は少し遠いので、次の機会を待つことにする。
今でも、SIRENが皆に愛されている様子を見聞き出来るだけでも、幸せである。
課金ガチャのスマホゲーに並んで、一人きりで作ったスマホゲーを一人でリリースできる時代になったが、ゲームを愛することが出来ているであろうか。愛するゲームを見つけただろうか。
私達はまた、愛するゲームに出会うことが出来るだろうか。
私は自分の精神に不安を感じるとホラー映画やホラーゲームに没頭するのだが、一番最近にSIRENをやったのは、不妊という状況の最中にある3年前のことだ。
その時点でSIRENは10年以上を超える年季が入っていたが、相も変わらず、愛おしいゲームだった。
屍人は私を癒してくれた。
アーカイブの1つ1つに、制作者の愛情が感じられる。
娘が大きくなったら、一緒にSIRENをやろう。教育番組ではワルピットや黒玉軍が好きで、洋楽ではブラックサバスが好きな娘なので、きっと気に入ると思う。
では、いんふぇるのでまた会いましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
