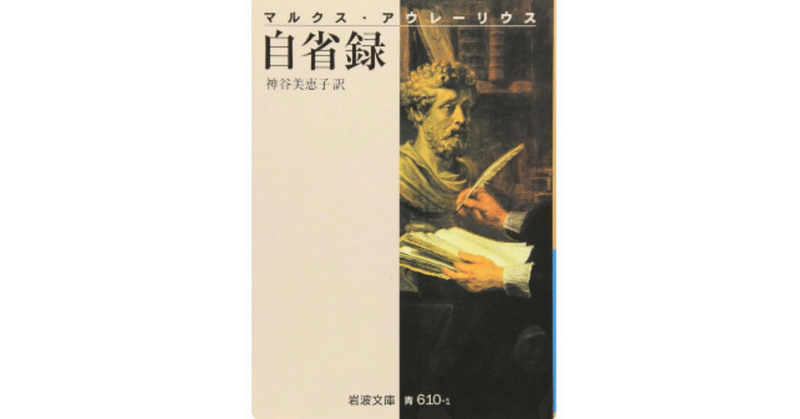
自省録 読書記録20
事物は魂に触れることなく外側に静かに立っており、わずらわしいのはただ内心の主観からくるものにすぎないということ。もう一つは、すべて君の見るところのものは瞬く間に変化して存在しなくなるであろうということ。
宇宙即変化。人生即主観。
「自分は損害を受けた」という意見を取り除くがよい。そうすればそういう感じも取り除かれてしまう。「自分は損害を受けた」という感じを取り除くがよい。そうすればその損害も取り除かれてしまう。
君に害を与える人間がいだいている意見や、その人間が君にいだかせたいと思っている意見をいだくな。あるがままの姿で物事を見よ。
あたかも一万年も生きるかのように行動するな。不可避のものが君の上にかかっている。生きているうちに、許されている間に、善き人たれ。
ここでいう「善き人」とはなにか。考える。
隣人がなにをいい、なにをおこない、なにを考えているかを覗き見ず、自分自身のなすことのみに注目し。それが正しく、敬虔であるように慮る者は、なんと多くの余暇を得ることであろう。[他人の腹黒さに眼を注ぐのは善き人きふさわしいことではない。]目標に向かってまっしぐらに走り、わき見をするな。
あれを見たか。しからばこれも見よ。いらいらするな。自分を単純にせよ。ひとが罪を犯すか。彼は自分自身にたいして罪を犯すのだ。君に何事か起ったか。よろしい。すべて起ってくることはそもそもの初めから「全体」の中で君に定められ君の運命の中に織り込まれたことなのだ。要するに人生は短い。正しい条理と正義をもって現在を利用しなくてはならない。くつろぎの時にもまじめであれ。
宇宙は一つの生きもので、一つの物質と一つの魂を備えたものである。ということに絶えず思いをひそめよ。またいかにすべてが宇宙のただ一つの感性に帰するか、いかに宇宙がすべてをただ一つの衝動からおこなうか、いかにすべてがすべて生起することの共通の原因となるか、またいかにすべてのものが共に組み合わされ、織り合わされているか、こういうことをつねに心に思い浮かべよ。
もしある神が君に「お前は明日か、またはいずれにしても明後日には死ぬ」といったとしたら、君がもっとも卑劣な人間でないかぎり、それが明日であろうと明後日であろうとたいして問題にはしないだろう。というのは、その間の期間などなんと取るに足らぬものではないか。これと同様に何年も後に死のうと明日死のうとたいした問題ではないと考えるがよい。
バディカの中野社長を思い出した。死ぬ前も今と同じように最高の仲間と最高の仕事をしているだろうからいつ死んでも後悔はないと言っていた。最高の最期だなと思った。
つねに近道を行け。近道とは自然に従う道だ。そうすればすべてをもっとも健全に言ったりおこなったりすることができるであろう。なぜならばこのような方針は、[労苦や争いや、ひかえ目にしておくとか虚飾を避けるとかいうすべての心づかいから]君を解放するのである。
明けがたに起きにくいときには、つぎの思いを念頭に用意しておくがよい。「人間のつとめを果たすために私は起きるのだ。」自分がそのために生まれ、そのためにこの世にきた役目をしに行くのを、まだぶつぶついっているのか。それとも自分という人間は夜具の中にもぐりこんで身を温めているために創られたのか。「だってこのほうが心地よいもの。」では君は心地よい思いをするために生まれたのか、いったい全体君は物事を受身に経験するために生まれたのか、それとも行動するために生まれたのか。小さな草木や小鳥や蟻や蜘蛛や蜜蜂までがおのがつとめにいそしみ、それぞれ自己の分を果して宇宙の秩序を形作っているのを見ないのか。
しかるに君は人間のつとめをするのがいやなのか。自然にかなった君の仕事を果たすために馳せ参じないのか。「しかし休息もしなくてはならない。」それは私もそう思う、しかし自然はこのことにも限度をおいた。同様に食べたり飲んだりすることにも限度をおいた。ところが君はその限度を越え、適度を過ごすのだ。しかも行動においてはそうではなく、できるだけのことをしていない。結局君は自分自身を愛していないのだ。もしそうでなかったらば君はきっと自己の(内なる)自然とその意志を愛したであろう。ほかの人は自分の技術を愛してこれに要する労力のために身をすりきらし、入浴も食事も忘れている。ところが君ときては、彫師が彫金を、舞踏家が舞踏を、守銭奴が金を、見栄坊がつまらぬ名声を貴ぶほどにも自己の自然を大切にしないのだ。右にいった人たちは熱中すると寝食を忘れて自分の仕事を捗らせようとする。しかるに君には社会公共に役立つ活動はこれよりも価値のないものに見え、これよりも熱心にやるに値しないもののように考えられるのか。
すべての自然にかなう言動は君にふさわしいものと考えるべし。その結果生ずる他人の批評や言葉のために横道にそれるな。もしいったりしたりするのが善いことなら、それが自分にとってふさわしくないなども思ってはならない。他人はそれぞれ自分自身の指導理性を持っていて、自分自身の衝動に従っているのだ。君はそんなことにはわき目もふらずにまっすぐ君の道を行き、自分自身の自然と宇宙の自然とに従うがよい。この二つのものの道は一つなのだから。
君の頭の鋭さは人が感心しうるほどのものではない。よろしい。しかし「私は生まれつきそんな才能を持ち合わせていない」と君がいうわけにはいかないものがほかに沢山ある。それを発揮せよ、なぜならそれはみな君次第なのだから、たとえば誠実、謹厳、忍苦、享楽的でないこと、運命にたいして呟かぬこと、寡欲、親切、自由、単純、真面目、高邁な精神。今すでに君がどれだけ沢山の徳を発揮しうるかを自覚しないのか。こういう徳に関しては生まれつきそういう能力を持っていないとか、適していないとかいい逃れするわけにはいかないのだ。それなのに君はなお自ら甘んじて低いところに留まっているのか。それとも君は生まれつき能力がないために、ぶつぶついったり、けちけちしたり、おべっかをいったり自分の身体にあたりちらしたり、人に取入ったり、ほらを吹いたり、そんなにも心をみださねばならないのか。否、神々に誓って否。とうの昔に君はこういう悪い癖から足を洗ってしまうことができたはずなのだ。そしてなにか責められるとすれば、ただのろまでわかりが鈍いということだけいわれるので済んだはずなのだ。しかもこの点についてもなお修養すできであって、この魯鈍さを無視したり楽しんだりしてはならない。
ある人は他人に善事を施した場合、ともすればその恩を返してもらうつもりになりやすい。第二の人はそういうふうになりがちではないが、それでもなお心ひそかに相手を負債者のように考え、自分のしたことを意識している。ところが第三の人は自分のしたことをいわば意識していない。彼は葡萄の房わをつけた葡萄の樹に似ている。葡萄の樹はひとたび自分の実を結んでしまえば、それ以上なんら求むるところはない。あたかも疾走を終えた馬のごとく、獲物を追い終せた犬のごとく、また蜜をつくり終えた蜜蜂のように。であるから人間も誰かによくしてやったら、[それから利益をえようとせず]別の行動に移るのである。あたかも葡萄の樹が、時が来れば新たに房をつけるように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
