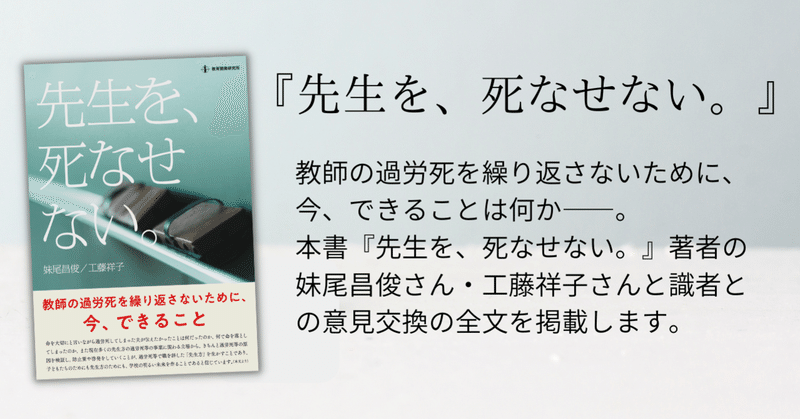
教師のメンタルヘルスを守る仕組みづくり ――大石智(北里大学医学部講師)
◆文部科学省「教職員のメンタルヘルス対策検討会議」委員などを務められた、北里大学医学部講師の大石智先生に、学校の先生方のメンタルヘルスケアのための仕組みをどうつくっていけばよいか等について、お話をうかがいました。
大石智(おおいし・さとる)学校法人北里研究所北里大学医学部精神科学講師医師、医学博士。1999 年、北里大学医学部卒業。2019 年1 月より現職。相模原市教育委員会非常勤特別職を務め、2011 ~ 2012 年度文部科学省教職員のメンタルヘルス対策検討会議委員。【著書】『認知症のある人と向き合う : 診察室の対話から思いをひきだすヒント』(新興医学出版社、2020 年)、『教員のメンタルヘルス──先生のこころが壊れないためのヒント(大修館書店、2021 年)教員の精神疾患による病気休職の背景
■教員の精神疾患による病気休職の背景
妹尾:学校の先生たちのメンタルヘルス不調、とりわけ精神疾患による病気休職はこの10年以上、5000人前後で高止まりしています。大石先生のご著書『教員のメンタルヘルス──先生のこころが壊れないためのヒント』(大修館書店、2021年)にも書かれていたように、世の中全体で増えているという部分もありますが、教員はそれ以上の割合で増えています。さまざまな背景があると思いますので、ひと言、ふた言で表せるようなものではないと思いますが、なぜ高止まりしているのでしょうか。学校のメンタルヘルス対策でがんばられている自治体もあると思いますが、正直うまくいっていない部分も大きいかもしれないという気がしています。
大石:背景要因を整理して申し上げるのは難しいですが、妹尾さんが言われたように、ひとつは世の中全体で増えているということもありますよね。1999年に新しい抗うつ薬が発売されて、多くの精神科医たちが製薬企業の広告宣伝の影響を受けやすくなり、「うつは心の風邪である」というキャンペーンがはられたりということがありました。そういう影響もあって、精神医療従事者以外の方たちも心の不調に関心が向くようになりました。
それまで理由のある悲しみは疾病化されず、人生の悩みであるとされていましたが、「心の風邪」キャンペーンを境に、理由のある悲しみも病気であるというラベリングが生まれやすくなりました。病気休職をする必要がある、あるいはしてもいいという状況が社会的に生まれていったというのはまずあると思います。
私が関わらせていただいている神奈川県相模原市では、学校の先生方自身や管理職の方への介入、あるいは保健師さんをハブにして早めに予防的な介入をしていこうという取り組みを行い、一時、精神疾患による休職者数は減っていったのですが、また増えてきています。
その要因を考えると、支援の取り組み自体に大きな変化はないけれども、やはり先生方の業務がどう考えてもあまりに忙しすぎるということがあると思います。相模原市でも勤務時間の管理が始まりましたが、タイムカードではなくデスクトップPCのログイン・ログアウトで管理しています。個別の先生方の支援のための相談でお話ししていると、提出された資料によれば時間外労働時間が長くはない人でも、よくよく聞いてみると、早めにログアウトしてますとか、実は仕事を持ち帰っているんですという話をよく聞きます。またコロナのこともあって、感染症対策のための新たな業務や、コロナ以前も学習指導要領の改訂、新たなICT関連の業務、小学校での英語の授業など、ますます仕事が増えています。
そして仕事ができる先生にはさらに仕事がまわされて、かなり疲れ切っています。異動とともに少し仕事量を減らせたら、と願望を抱きながら異動すると、また仕事が降ってくるということもあるようです。高学年をずっと担当していて、異動したら少し低学年をやりたいなとか負担を減らしたいと思っていても、なかなか言いづらい。また、校長先生からよくうかがうのですが、もともといたベテランの先生や勤続年数が長めの先生方は校長先生とも話をしやすくて、業務上の希望を伝えやすい状況にあり、そういう先生には仕事を振りづらいけれど、新しく来た先生はこれまでの学校の状況をあまり知らないから、なんとなく仕事を振りやすい、ということもあるようです。やはり、業務が過密な状況がかなりあるんだなと思います。
私自身は大学に長くいるのですが、大学の教員に比べて小・中・高校の先生方は子どもたちに教育を提供するということ以外の業務があまりにも多くて、文科省の事務次官通知「学校における働き方改革に関する取組の徹底について(通知)」で働き方改革の通知 が出て、自治体の中でそういう議論が生まれても、実際のところなかなか現場ではそういった変化が生まれていないという感覚を抱いています。精神疾患による病気休職者数が高止まりの状況というのは、労働環境が関連した不調がかなり多いのだとすれば、やはり労働の量が多すぎるということ、忙しいなかでは同僚間や上司から部下へのねぎらいの声掛けやポジティブなフィードバックによってストレス状況を緩和するということが生まれにくい状況もあるのだろうと感じています。
妹尾:保健師さんと一緒に支援されて、大石先生もスーパーバイズや診療をされたりしているのでしょうか。
大石:そうですね。最初は実態がよくわからなかったので、保健師さんと全校訪問することになりました。校長先生や副校長先生から状況を教えていただいて、これは大変な仕事を引き受けてしまったなという思いを抱きました。
全校訪問以降実施しているのは、校長を介して保健師さんにつながり、保健師さん単独での介入をしたけれどちょっと心配だなという先生に面談し、その後のフォローアップをしていったり、不調になりそうな先生、休職中の先生、復帰後の先生も、フォローアップをさせていただいています。復職後の事後措置、つまり業務負担の軽減措置や復職について審議する審査会でディスカッションしたりとか、そんなことで10年以上、いろいろと関わっています。
■セルフケアの意識を持ちにくい職場
妹尾:大石先生は民間企業に勤めている方や他の公務員の方とも接することもあるなかで、学校の先生たちについては、業務量としても性質としてもちょっと異常だぞと思われることがあったということでしょうか。
大石:そうですね。実際、一般企業の社内診療所の手伝いとか、公務員の方の健康管理など、公的機関や民間企業でも関わらせていただいています。「学校教員は感情労働の極北である」と言われています。確かに複数にまたがる対人関係をうまく調整しないと成り立たない仕事ですし、そこには無意識の中での感情調節が常に求められます。また、教育を子どもたちに提供していくなかで、子どもたちの成長はすぐに現れませんから、達成感の得にくさ、消耗しやすさがあると思います。
それに加えて社会が変化する中、多くの人々が問題の解決を専門家に期待するという風潮もあるでしょう。家庭の中で起きているさまざまなことを学校の先生に期待していく、解決を求めていくという変化もあると思います。退職した校長先生から話を聞いていると、昔は家庭でのしつけや育児の範疇だったことを、学校の先生に求める傾向が強まっているようです。たとえば、お風呂になかなか入らない、歯磨きを全然しないとか。また、登下校中の事故対応とか、学校にいる間のアレルギーの管理など子どもたちの安全管理もありますね。一昔前はあまりそういう話はなかったけれど、知らないうちに教員の仕事になってしまっていて、こんなに多くの仕事が増えて、「これを現場に任せて退職したんだけど、なんか心苦しいんだよね」という話を聞くこともありますね。
社会が教員に求める仕事が膨大になり、それが整理されないまま、先生方がやりがいや張り合いを得られる子どもたちとの時間が失われやすくなっている状況が、ここ何年もの間、高まってきているのではないかと感じることがあります。
妹尾:こんなことも学校に、という例はたくさんあると思います。教員の仕事はさまざまな人間と人間とのヒューマンサービスですから、くたびれやすいし、やりがいもあるけれどしんどい部分もあるということなんだと思います。感情労働とか仕事の性質によってメンタル不調の方が多いとか少ないとかはだいぶわかっていることなんでしょうか。
大石:いろいろ調べてみましたが、おそらくまだ質の高いエビデンスは不足していると思います。というのも、労働の種類によって精神疾患による病気休業や罹患率がどのぐらいなのかというのは、なかなか整理、公開されづらいと思うんです。一部比較しようとしても、調査年度が違っていたり、民間企業だとそういうデータはあまり公開したくないでしょう。公務員も休職者が増えているなど、ときどき報道はされますが、職種横断的にデータがちゃんと出ていないので、そこはけっこう難しいなと思いますね。
妹尾:仕事の性質によってストレスの度合いも当然違うし、メンタルヘルスへの影響もおそらくありますよね。ご著書にもあったように、先生方が自分たちは相当難易度の高いお仕事をされているということをまずは認識していただいて、また、これもご著書にあった職員室に休憩室がないというのも象徴的な話ですが、学校では子どもたちのことが最優先で、どんどん仕事をやってしまうけれど、自分や同僚のケアも大事にしないと難しい仕事なのだということを、まず職場の共通認識にしていただくというのも大事なんでしょうね。
大石:それはすごく大事ですよね。学校訪問をしていたときに、休憩室がないことや、子ども用なのではと思う職員用のトイレがあったりとか、洗面洗面台の高さも子どもに合わせてあったり、天井も低かったりすることに驚きました。ある校長先生に「学校ってほんとうに大人のためのつくりになっていないんですね」と話したら、普通に「だって学校は子どもたちのためですからね」と言われて。そのとき反論できなかったのですが、それはまあそうなのだけれど、働く人のことも考えないとちょっとまずいんじゃないかなと思ったのも事実で、そういう子どものための構造の中にずっと身を置いていると、セルフケアの意識が薄れてしまうのではないかなというのが心配ではありますね。
■コロナ禍による教職員のメンタルヘルスへの影響
妹尾:大石さんが関わられているなかで、コロナ禍での先生方のメンタルヘルスへの影響についてわかることがあれば、教えてください。
大石:相模原市は毎月リアルタイムでデータを見られます。2020年は、2月末頃から3月まで全国一斉休校がありましたよね。相模原市は6月くらいまで休校が続いて、その後分散登校、一斉登校となりました。
例年、4月から5月は一度不調者、傷病休暇者のピークが来て、期末試験とその評価のある7月に小さいピークがきて、夏休みで落ち着いて、9月にまたどんとくる、みたいな波があります。あの年は4・5・6月と全然不調者が出ませんでした。7・8月も出なくて、「いやあ、コロナって悪くないね」と保健師さんや関連している指導主事の先生と冗談半分で話していたのですが、「いや、これは分散登校、一斉登校で、夏休みが来て落ち着いて、でも9月にどんと山が来るでしょう。何かできることをやっておかないとね」という認識を共有し、相談などに対応していたところ、やはり9・10月と傷病休暇が急増しました。対応している保健師さんが参ってしまうんじゃないかというくらい増えて、年間の総数も結局前年度より増えましたし、その後、2021年度も増加傾向でした。
初任者の先生方の研修のお手伝いもするのですが、初任の先生方の研修も対面形式が減り、セルフケアのための研修が9月・10月にありましたが、そのときようやく対面で会えて、グループディスカッションができそうという状況でした。同期とのつながりというのがなかなか生まれにくい状況もあるだろうと思います。
また、感染症対策関連の仕事が増加し、相模原市は2019年度から小・中学校で統合型校務支援システムが導入されて、それに関連する業務も重なって多忙化が強まりました。そうすると若い先生方、異動後間もない人間関係がつくられていない先生方、もともと援助希求性が弱めな先生方は、忙しそうにしている同僚や上司になかなか相談しづらいというように、援助希求行動が取りにくくなってしまう。学校という小さな社会のなかで、そういった社会的な支援が生まれにくくなってしまっているという印象を抱きました。
■先生を守る仕組みが必要
妹尾:多くの現職教員の方から、産休・育休の際に補充されるはずの講師の先生がなかなか見つからないとか、病休の方がいらっしゃると、補充の常勤職がいないため非常勤の講師の方でなんとか授業の穴を埋める、みたいな話をよく聞きます。
もともと忙しいうえに、さらに人員も予算も少なくて、周りも忙しそうだったり、学級運営が不安な先生のケアもしないといけなかったりすると、なかなかサポートしてもらいにくいと思います。また、先ほど言われたように、ある程度経験年数のある方が異動してきて、これくらいの経験があったり、前任でたとえば教務主任をやっていたなら大丈夫だろうなどと思われてサポートを受けられず、その方もしんどくなってしまう、というようなこともあるかもしれません。いろんな難しさがあって、どこから手を付けていいのか、というのは悩ましいところではありますけれども。
大石:人的資源の厳しさというのはほんとうにそのとおりだなと思っていて、支援活動のお手伝いを始めた10年ほど前は、病気休職とか産休・育休で補充が回らないという話はほとんどありませんでした。でもここ数年、空いた穴を埋められないという状況はあちこちで聞くようになって。今おっしゃられたように背景要因が複雑すぎて、どこから手をつけたらいいんだろうみたいな、そういう悩ましさはありますね。
妹尾:前からおかしいなあと思っていたことなんですが、学校の先生は子どもたちのためならば、時間の制約がないかのごとく仕事をしてしまうようなところがあります。精神科医やカウンセラーの方は、面談や診察をするのは何時何分から何分までと決まっていますよね。たとえばいくら自殺したいという深刻な患者さんがいたとしても、1人あたり1時間も2時間も話を聞くというようなことをしていたら、聞いている側がつぶれてしまうので、ある意味バリアを張っている部分もあるのではないかと思います。
これが学校の先生だと、困難を抱える子どもとか、生徒指導上しんどい子がいると、ある程度の時間には切り上げるとしても、30分などと区切らずに、無限定にやってしまう傾向があって。学校の留守番電話の設定はひとつよいことだなと思っているのですが、まだまだその程度というか、始まったばかりです。
大石:精神分析療法と呼ばれるような、精神医学的な面接は、構造を重視しています。最初に来談者に、「じゃあ今日はいつもどおり40分程度のお話になりますが、あなたが今日話したいことは何ですか」と、何気なくその構造を示すんです。そういった面接の技術として、ある程度の防波堤というか構造を設けることで、来談した人がエスカレートするのにブレーキをかけてあげるという役割はあるんだろうなと思います。
一方で、俗に言うクレーマー的な保護者への対応とか、障害の非常に強い子どもへの対応などの場面では、そういった構造があまり生まれていないのかなと思うことはよくあります。対応がこんなに大変だったんですよという話をされて、どのくらいだったんですかと聞くと、もう3時間も怒鳴られっぱなしで、みたいな話を聞くこともあります。
病院には元警察OBの保安職員の方がいて、あまりにも厳しい面接を求めてくるような来談者の場合には、保安職員が面接の医者の後ろ側に立って、ある程度来談者のエスカレートする心情にブレーキをかける役割を果たそうとする構造があります。ただ、学校の中には、そういう来談者のエスカレートする心情にブレーキをかけるという構造がなくて、学校の先生が蜂の巣状態のようになってしまう、そういうつらさを感じるところはありますね。
妹尾:なるほど。たまたまその校長や教頭が保護者をなだめたり関係性をつくるのがうまいなどの運に期待するのではなくて、病院の保安職員さんみたいに、支援する人たちの体制が整っていること、また、困っているときはこうスイッチしようというふうに、能力とか意識じゃない部分で仕組みや制度としても考えていくことも必要なんでしょうね。
大石:先生方が守られている仕組みというのはすごく大事ではないかなと思います。どうしても専門職を攻撃してしまう気質のある方はいらっしゃいますが、彼らがエスカレートしないようにする。彼らもエスカレートしてしまう理由はいろいろあって、虐待のサバイバーだったり、親がアルコール依存だったり、児童期の逆境体験があったりする方が暴言を吐いてしまったり、クレーマー的になってしまったりすることが多いですが、彼ら自身も暴言を吐いて専門職を責めてしまうことでまた新たに後で傷ついたり、後悔したりというふうに再トラウマ化が生まれやすい。ですから、先生方、働いている人を守る、それから放っておくとクレーマーや暴言を吐く人になってしまう人たちを守る意味でも、保護的な構造というのはもっと考えていってもいいのではないかと、あらためて気づかされます。
■保健師の役割の重要性
妹尾:ご著書の中では保健師さんの役割について強調されていますね。おそらく先生方からすると、いきなりどこかの精神科医に行こうとするとハードルが高く感じるし、日頃忙しいからなかなか病院に行こうとしない人も多い。身近な保健師さんなど相談に乗ってもらえる方がいらっしゃるのは大事かなと思いました。うちは一番下の5人目の子が1歳なんですが、乳幼児のときは保健師さんがわざわざ来てくれたりとか、もちろん小児科の先生も頼りになるんですけれども、リファー(適切な機関を紹介)してくれる方、コーディネーター的な役割をしてくれる方がいらっしゃるのは確かに心強いなと思っていて、この相模原市の仕組みはいいなと思いました。おそらく他の自治体はそんなに仕組み化されていないのではないかと思うのですが。
大石:以前文科省の職員の方から、必ずしも全国の自治体に保健師さんが配置されているわけではないという話を聞きました。相模原市では最初は1名の配置だったのですが、健康管理という部分ではメンタルヘルスだけでなく、通常の健診後の対応も必要になります。学校の先生方はほんとうに自分を犠牲にして働いているなと思ったのですが、健診後の再検査の要請への再検査率がすごく低かったんですよね。そういう身体面もケアしなければということで、保健師さんを2名そろえていただきましたが、自治体によっては保健師さんが配置されていないという状況はまだまだあるんだろうなと思います。
自治体の保健師さんはメンタルヘルスだけでなく、子ども、子育て支援から高齢者支援まであらゆるところを異動しながら経験を積んできて、メンタルヘルスに関してとくに得意というわけではない保健師さんもいらっしゃると思いますが、そういう保健師さんでも我々がお手伝いして、保健師さんが困ったらメールや電話でバックアップしていますし、我々の面接に保健師さんが同席して経験を重ねていくうちにメンタルヘルス支援がすごく上手になっていく方も多いです。保健師さんが先生方の支援のハブになるような機能を果たしていただくととてもよいと思います。
というのも、まだまだ自分のやっている診療が優れているとは全然思わないんですけど、増えている精神科のクリニックの中で、受診したら初診の段階で待合室でアンケートに答えてその診察室のドアを開けて入るとアンケート結果をみてふんふんとうなずいて、「まあうつ病ですから休業の診断書を書きますよ」と言って、「抗うつ薬と抗不安薬と睡眠薬の3点セットを出しておきます、はい以上」みたいな、そういうクリニックがチェーン展開していると聞くことがあります。高額の報酬で精神科医を雇い入れて、給与は出来高制で短時間診療でたくさん見る医者は報酬が上がるシステムを設けている診療所があると聞いたことがあります。もちろん良心的な医療機関が多いのでしょうけれど、経済原理で動いてしまう医療機関があるということも事実なのでしょう。コロナの中で必要なリモートの診療がなかなか広がらない背景にも、リモートだと診療報酬が安いからやろうとしないというように医療が経済原理で動いてしまっているところも現実としてあって、心の不調を感じたときにぱっと精神科医療機関のドアをたたく前に、まず保健師さんに相談するということのほうがいいのかなと思っています。身内を背中から鉄砲で撃つみたいな感じなんですけど(笑)。
妹尾:そこの部分は僕も知らなかったです。普通の人はわからないですよね。大石先生が同業者の方とちょっと気まずくなるようなことも踏み込んで話してくださっているのはほんとうにありがたいなと思いましたが、教職員は、この診療所、クリニックは怪しいみたいなことはわからずに、しんどいなかで藁にもすがる気持ちで頼るわけです。たしかにワンクッション置いて、つないでくださる、信頼のおける保健師さんなどがいる、あるいはセカンドオピニオンをもらえる方がいるというのも大事な話ですね。そういうのを校長等が知っていたらアドバイスもできるかもしれないですね。
大石:そうですね。相模原市ではなるべく保健師さんに早めに相談をということで、初任者や異動後6年目の先生方の研修とか、新任の校長研修などで保健師さんに登壇していただいて、保健師さんの顔を売ってもらったり、校務支援システムの中に保健師さんの情報が折に触れポップアップで表示されるようにしたりと、大変なときは保健師さんがいますよ、と伝える工夫をしたので、精神科を受診する前に保健師さんにアクセスするというケースはだいぶ増えました。ただ、それでも休職者が増えているのでどうしよう、みたいな感じなんですが。
妹尾:厳密に検証するのは難しいですよね。保健師による支援がなかったら、休職者はもっと増えているかもしれないし、実験するわけにもいかないですしね。
■養護教諭との連携を深める
妹尾:関連しておうかがいしたいのは、養護教諭との関係です。養護教諭は労働安全衛生法上の衛生管理者、衛生推進者になっていることもよくあって、実際にこの先生は浮かない顔をしているな、というふうに気づきやすい一人だと思います。一方で養護教諭も忙しいので頼ってばかりでもいけないのですが。その養護教諭と保健師さんや精神科医の先生がうまくつながるなどの仕組みも大事なんでしょうか。
大石:すごく大事だと思っています。ただ、学校によって養護教諭が先生方のメンタルヘルスに関与する密度はだいぶ差があると感じています。また、相模原市ではメンタルヘルスに関する研究部会というのを年に数回やっていて、養護教諭の代表にもお越しいただいています。養護教諭って孤独なんですよとおっしゃっていて、一人職種で学校に存在することが多いので、子どもへの関わりが一義的に求められているという状況の中で、養護教諭はけっこう大変だし、先生方のメンタルヘルスへの関与というのを強く求めにくいということもあります。
ただ、養護教諭の中にもいろいろな経験を積まれて、子どもたちだけでなく、先生方へのケアという視点ももたれている方もいらっしゃって、実際に現場の先生方のお話をうかがっていると、けっこう早めに不調に気づいてくださっていたり、ちょっと心配な時期はこっそり養護の先生に相談していましたみたいな話もうかがいます。養護教諭の力にもっともっと信頼を置いて、先生方の支援の一員として連携を深めていくことができたらなと思っています。
妹尾:養護教諭の負担軽減は別途考えながら、そういうところも考えていくということですね。
■教職員のメンタルヘルスにおける産業医の関わり
妹尾:職員が50人以上いる学校は労働安全衛生法上で産業医を置くことが義務付けられていますが、小学校や中学校などは50人未満の職場も多く、学校医の先生もいらっしゃるし、みたいな感じで、産業医が選任されていなかったり、あるいはつながり先がなかったりするような学校も多いのではないでしょうか。
大石:産業医に関してはおっしゃるように自治体によってばらつきがありますよね。相模原市は産業医の設置義務を勘案して、学校を一つの事業所として考えて、その学校に何人の教員がいる、じゃあこの学校のブロックはこの産業医というように、産業医を複数名、年単位で少しずつ増やしてきています。ただ、産業医になるためには日本医師会等の研修を受けるという要件があるのですが、産業医育成のカリキュラムのなかでメンタルヘルスに関する資格取得のための研修のコマはほんとにわずかなんですよね。産業医の生涯教育の中でもメンタルヘルスに関して手厚く研修があるというわけではないですし、もともと大半の産業医は精神科以外の専門領域をお持ちなので、メンタルヘルスの視点での支援というのはけっこう厳しいものがあるんだろうなとは思います。
また、産業医は基本的には中立性を保たなければならないという原則がありますが、実際のところ事業所や会社から給料をもらっているので、どうしてもそこで利益相反関係が生まれてしまいます。医者も経済原理で動きやすい部分もあって、中立性を意識しているけれども、知らぬ間に事業所側に肩入れしてしまって中立性が失われてしまうというようなことはありますね。産業医の給料は普通の医師の非常勤の給料より、産業医手当のような形で上積みされているんです。私は産業医の資格がないので産業医手当はつきませんが(笑)。産業医が配置されても実質メンタルヘルス上の支援にものすごく有効になるかというと、どの企業も産業医はいるけれども別途非常勤の精神科医を雇っていたりという実態もありますし、産業医も限界があるなというふうに思います。
妹尾:今回、この対談は、わたしが主宰するオンライン学習会で実施しています。本日、参加されている方からも、ご質問やご意見があればお話しください。
■安全配慮へのプレッシャー
A校長(参加者):僕が今一番感じている学校教員のメンタル的なプレッシャーは、安全配慮義務ではないかと思っています。たとえば、高校の課外のクラブ活動のサッカーの試合中に落雷で生徒が負傷した事故の裁判では、最高裁で監督の教諭に事故を予見すべき注意義務違反があったとされました。そのように大きなこと以外でも、家庭が持たせたスマホのLINEで子ども同士でもめている、悪口を言われている、どうにかしてほしいというようなこともよくあります。そういうあらゆる側面に対してきちんと安全配慮をしなければならないということが、多忙につながっているという部分もあります。我々も精一杯がんばりますし、研修も受けようとするのですが、あまりにも要求されるスキルが多すぎるようにも感じています。
大石先生が見てこられた心を病まれたり、支援を求められたりした先生方は、このような安全配慮へのプレッシャーの感じ方や、スキルを学ぶ姿勢などはどうでしたでしょうか。
大石:休職されたり不調になられたりした先生方の背景要因の分析がまだまだ十分できていないので、印象論になってしまって申し訳ないのですが、安全配慮という部分が、心理的にも業務量的にもかなり負荷を高めるだろうなと思うので、その視点はすごく大事だと思います。医療も似たところがあって、医療安全という部門を中心にリスク管理をしていきますが、医療訴訟を意識しすぎると、提供する医療が萎縮していきやすくなることもあるので、今では一定規模以上の病院は医療安全管理を専門とする部署に医師・看護師・事務職を必置しています。そうやって分業していかないと厳しくなるのかなと、お話をうかがって大事な視点だと思いました。
また、がんばって積極的に学ばれている先生はたくさんいらっしゃるなと思います。むしろ、熱心でいろんなことに積極的に取り組んでいるけれども不調になってしまったという方に多く出会ってきました。学習姿勢という部分に関してはいろんな先生はいますが、熱心に学習され、校務分掌もいろいろ担って慣れないことも勉強しながらやっておられて、その中でバーンアウトしてしまうという方はすごく多いなと思いますね。
■事務負担の軽減
B教諭(参加者):私が勤めている地域の学校では、年休簿へのハンコ以外に、タイムカードと連動している勤怠システムと校務支援システムにも入力しなければならず、さらにその3つの整合性がとれていないと服務事故になってしまうため、その3つの整合性を確認するために会計年度任用職員の人が雇われている、というようなことになっています。でも、隣の地域の方に聞いたら、年休簿だけしかないと言っていて。こういった事務仕事について、先生はどのようにお考えになっているかお聞かせください。
大石:すごく大事なご指摘ですね。しかも自治体によって管理の仕方が違うというところも大きな課題だと思います。勤怠管理に関して二重三重の網目を敷いてどれだけ疑っているんだとさえ感じてしまいますが、ちょっと異様だなとも感じました。細かな制度設計をされている方には大変失礼かもしれませんが、ある意味それが無駄になってしまっていて、先生方の主たる業務に要する時間を奪っている可能性があるものはもっと整理していく必要があるなと思いました。そういう問題はやはり現場の人でないと気づかなかったりするので、現場の人たちから声が上がりやすくなる環境も必要だと思います。
それから、学校事務職員の方たちの存在はすごく大きいですが、人数は非常に少ないですよね。財源の限界というのもあるのでしょうが、事務職の方を各校に手厚く配置したり、あるいは一人職種で孤立しやすかったりもするので支援ももっと考えていかないといけないんじゃないかなと思います。そうすることで事務的な業務が見える化、整理されていったらいいなと、お話をうかがって気付かされました。
■心理的ダメージへの手当
妹尾:先生たちの時間を生み出すという意味では、事務負担や事務作業の軽減ももちろんとても大事なことですけれど、一方で事務作業が大変だからといって先生方の心が折れるということはあまりなくて、おそらく、子どもとの関係とか保護者との関係、あるいは同僚が助けてくれないとか、校長からのパワハラなどはよりダメージが大きいと思います。そういう、よりダメージが大きいところについては、やはりご著書にも書かれていたように、職場に支援の関係をつくるとか、職場がストレッサーになってしまっているところに対処する、あるいは悩みがある方に職場でどうケアをしていくかというところが、最重要ということでしょうね。
大石:そうですね。そこが一番大事ですよね。事務的な業務ももちろん大事ですが、感情に響く負荷にきちんと手当していく必要があると思います。不調になられた先生方、とくに若手の先生を対象にした調査でも、職場の中の支援関係、相談できる関係が薄いか厚いかがかなり大きく関連しているということが言われていますし、そこは変えていける要素だと思います。お互い支援する・支援される、相談する・相談される風土、文化をつくりあげていくことは、あまりお金もかからないですし、しかも非常に重要なことだと思います。
■不調に気づける、相談できるためのセルフケア
妹尾:セルフケアについてもおうかがいしたいです。このことを強調しすぎると、自分がちゃんとできなかったというような、自責の念にかられる方もいらっしゃると思うのでそこは注意して扱わなければいけないですが、とはいえ、セルフケアは非常に重要なことだと思っています。ちゃんと寝ましょうとか、けっこうシンプルなことが大事だったりするんじゃないでしょうか。
大石:精神疾患の一次予防というのは非常に難しい部分だと思うので、これというのはなかなか難しいのですが、睡眠衛生はやはり大事だと思います。業務が過密になって労働時間が長くなれば睡眠に影響も出てきますし、自分にとって心地よい睡眠習慣に着目するというのは大切です。睡眠を促進する因子は何だろうとか、逆に妨げる因子は何だろうとか、じゃあ自分の睡眠衛生ってどんなかな、ということを知り、意識していくということは、とても大事だと思います。
それから、疲労や不調のサインとして、自分の中で生まれやすい小さなサインに気づけると、そこから自分をケアする行動が生まれていくと思います。疲労のサインは人によりさまざまで、人によっては朝起きづらい、寝坊するようになったとか、食欲がちょっと落ちるとか、飲酒量が増えるとか、ギャンブルの回数が増えるとか、それぞれの不調のサインというのがあります。それはけっして悪いことでもないし、自分をケアしたほうがいいというお知らせだよ、という気づきのきっかけにしていただいて、自分にとってのセルフケア的な行動を知っておくことは大事なことだと思います。
最も基本的なケアスキルとしては、やはり相談できる人、早めに自分の気持ちを打ち明けられて、自分の思いをけっして否定せずに話を聞いてくれる人がいること。そういう関係性をつくっておくことが大切だと思います。
■部署を超えて包括的に対応をするための工夫
妹尾:大石先生からは何かご質問はありますか。
大石:ここ数年の悩みなんですが、毎月保健師さん、公認心理師と市内の状況をモニタリングしながらいろいろできることを検討し、年2回の研究部会で、小学校と中学校の校長と保健師と人事担当の課長さんと養護教諭と我々でディスカッションをする機会がありまして。メンタルヘルスの市内の状況を関連部署に伝えて、先生方を支援する体制を市内で包括的に整えていかないといけないですよね、という話をその研究部会でしているんですが、縦割文化なのか、伝えたけれどもあまり重く受け止められていなかったりすることがあります。
先生方の困難な状況、あるいは各校で努力してがんばっているグッド・プラクティスなどについて、関連している人事や教育・研修など、様々な部署ともっと包括的に同じ意識で連携していくためにはどうしたらいいのかなと思っています。何かいいアイデアがあったら教えていただけたらなと思います。
妹尾:僕もスパッと答えられるような簡単な問題ではないですが、メンタルヘルスの部署、研修の部署、学習指導の部署、とそれぞればらばらということがまずあります。また、学校の働き方改革は横断的なテーマなので、どこの部署が担当するのかというのはいろいろ難しいのですが、市教委とか県教委では教職員課が所管しているケースが多いのではないかと思います。教職員課は先生方の健康面なども関係しているので、比較的メンタルヘルスにも関心は高いと思いますが、横断的、包括的にやっていくのは必ずしも得意としていない部分もありますので、たとえば部門横断的なプロジェクトチームを立ち上げて、そこでメンタルヘルスも含めて対応していくということはあります。
それから、注目したいのは採用を担当している部署、これも教職員課の担当だったりもしますが、学校現場も教育委員会も、ほんとうに今、人手不足、教員不足を実感しているところは多いです。そんな中、教員が離職するというのはいちばんダメージですよね。企業でも、このままじゃ優秀な人が来てくれないぞとか、せっかく採用、育成した人が離職してしまうということで、採用部門が改革に本腰を入れて、当然経営者もそこに注目して、働き方改革が本格化する流れなんです。ですから、相模原市は政令市で採用もしているので、たとえば休職や離職されている人が毎年20人いたとしたら、20人を新たに採用するのはものすごくコスト・手間・大変さがあるというのは採用担当の方たちはよく実感されているので、そういう方たちと組んで、他の部署も誘いながらどういう体制をつくれるか、ということはできるのではないかと思います。教育長にもそのニーズなり危機感をちゃんと伝えていくというのも大事で、在校等時間の残業時間が減ればそれでいいという話ではないです。
C校長(参加者):最近私も取り組み始めているのですが、たとえばさきほどお話が出た一人職の方は、横のつながりがずいぶん助けになっているということを聞きます。養護教諭会とか、教頭会とか。それをハブのようにして、うまく支援の手を広げられないかなということを考えているのですが、大石先生はどのようにお考えでしょうか。
大石:それはすごく大事だと思っています。養護教諭の先生から横のつながりの場があってすごく救われたとか、コロナになってそういう機会が減ってけっこうしんどかったという話をうかがいます。校内の支援も大事ですが、学校を出て同じ職種とか、同じ採用年度などのつながりもすごく大事だろうと思いますね。つながりという部分では、ある校長先生から、学校の中で、たとえば特別支援学級と普通学級とか、あるいは一般の教諭と養護教諭と学校事務の方とか、分断が生まれやすいからこそ、それを防ぐためにいくつかの校務のコンセプトで小さい集団を作って、そのなかでつながり感を持てるようにしたことで雰囲気が変わっていったというお話をうかがったこともあります。
妹尾:お話をうかがって、保健師さんとの相談・支援の体制をつくること、そしてすごく重くなる前に早期に職場の中でも相談に乗れるし、職場の外にも頼れる人がいるという仕組みをつくる重要性などを感じました。ありがとうございました。
『先生を、死なせない。――教師の過労死を繰り返さないために、今、できること』は、教育開発研究所オンラインショップでご購入いただけます。↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
