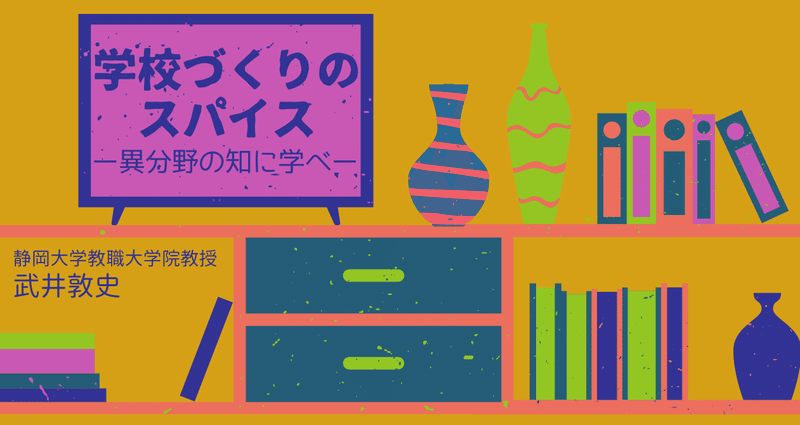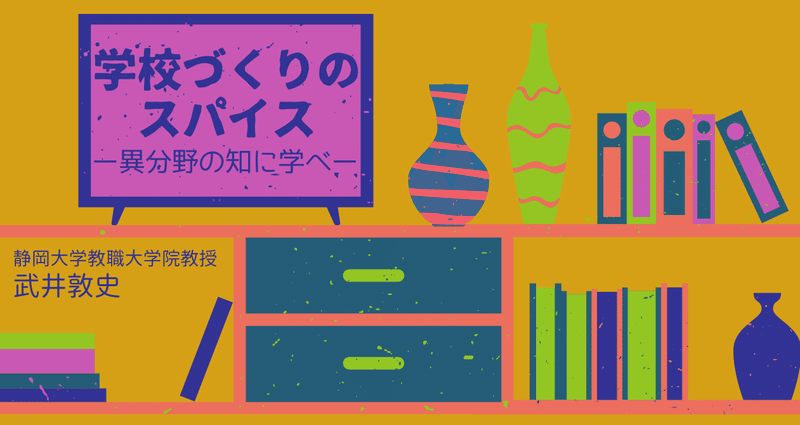#17 自然の知・人間の知・人工の知~ステファノ・マンクーゾほか『植物は〈知性〉をもっている』より~|学校づくりのスパイス
今回は、『植物は〈知性〉をもっている――20の感覚で思考する生命システム』(NHK出版、2015年)を手がかりに「知性をどう捉えるべきか」という教育の基本課題について考えてみたいと思います。著者は植物学者のステファノ・マンクーゾ氏と科学ジャーナリストのアレッサンドラ・ヴィオラ氏です。
彼らは知性を「問題解決能力」と定義したうえで植物の知性の性質を論じていますが、これは私たちが「頭がよい」と表現するように、知性というものを脳の属性・産物と捉える思い込みの再考を迫るものです