
第7回共創ワークショップ 公開プレゼンテーション 「このAI時代に、美大生達はどう生きるか?」
こんにちは、美大生×官僚 共創デザインラボです。この記事では、2023年9月30日に開催された、第7回共創ワークショップ 公開プレゼンテーションについてレポートしていきます。
2023年前期のデザインプレゼン報告会は、六本木ミッドタウン・タワーにある多摩美術大学TUBで開催。Aチーム・Bチームそれぞれが夏のワークショップで生み出したデザインアイディアを発表し、来場された方々ともテーマについて意見を交わしました。
開会のご挨拶

オンライン配信とのハイブリッド開催でスタートです!
本イベント、第7回共創ワークショップ 公開プレゼンテーション 「このAI時代に、美大生達はどう生きるか?」は官僚メンバーの曽和小百合さんの挨拶でスタート。リアル会場・ライブ配信ともに沢山の方がお集まりくださってメンバーも少し緊張していました。
美大生×官僚 共創デザインラボとは?これまでの活動を紹介

コロナ禍の中で立ち上がった共創デザインラボ(以下、デザラボ)。実は、今回が初めて対面での公開イベントです。まずは、官僚メンバーの二川慎之介さんによる「美大生×官僚 共創デザインラボとは?」について説明がありました。この活動も今年で4年目。紹介する活動内容や実績が多くなってきました。ご来場の方も興味深く聞いてくださっていました。
第7回共創ワークショップのプロセスについて説明

今回のワークショップのテーマ設定や設計をどのように進めたのかを田中さんからご説明しました。「このAI時代に美大生たちはどう生きるか」というテーマに決まるまでに、生成AIを美大生がどのように受け止めて、具体的にどこに興味を示したのかを紹介してもらいました。また、ワークショップDAY1にてメンバーが実際に生成AIを使って作ったプロモーションビデオもお披露目。これを踏まえていよいよ次はデザインアイディアの発表です。
デザインプレゼンテーション
Aチーム


私たちはどう生きるか?という問いの結論は「AIとお互いの苦手を補い合い、二人三脚で社会を共創していく。」でした。
Aチームの描いた未来の社会ではAIは人間と同じように教育され、個性ある人材として扱われます。その中で必要となるAI教育やAIカスタム産業についてのアイディアを発表しました。質疑応答ではAIに人権はあるか?など踏み込んだ話題にもそれぞれ意見を交わし、AIの創造性を社会でどのように定義して活用していけるのかといった視点での議論が深められました。
デザインプレゼンテーション
Bチーム


私たちはどう生きるか?という問いの結論は「AIを育てていくのが人間。美大生もAIを育てていく。」でした。
Bチームの描いた未来の社会ではAIが先生のサポートをして生徒の教育をより良いものにしていきます。AIライブラリーというデザインアイディアはそんな社会の中で専門人材の過去の経験やキャリアなどを蓄積して子供たちが参照できるものでした。質疑応答では、これから人がやらなくてはいけない部分はどこになるのか?という問いに対する意見交換を行うことができました。
最後に専門家の皆さんからコメントを頂きました。
日本画像生成AIコンソーシアム代表 望月逸平氏からのコメント

望月さんからは、人間がAIと関わっていく中でそれぞれ得意不得意を見極めるのが大切であるとのご指摘。AIの技術が「ものの識別」から「創造性をもった生成」まで拡張された今、人の創造性や本質を見極める力がますます問われる社会になっていくだろうというお話をいただきました。
文化庁 文化経済・国際課 専門官 工藤さやか氏からのコメント

工藤さんからは、デザラボのワークフロー自体も興味深く感じる、とコメントくださいました。それぞれが自分の仕事を理解して分担したものが、集約されて完成する様子が面白かったとのことでした。また、AIに対する向き合い方として、100点の答えを求め過ぎず、一緒に作り上げていく事が大切だというご見解でした。
多摩美術大学 統合デザイン学科 永井一史教授からのコメント
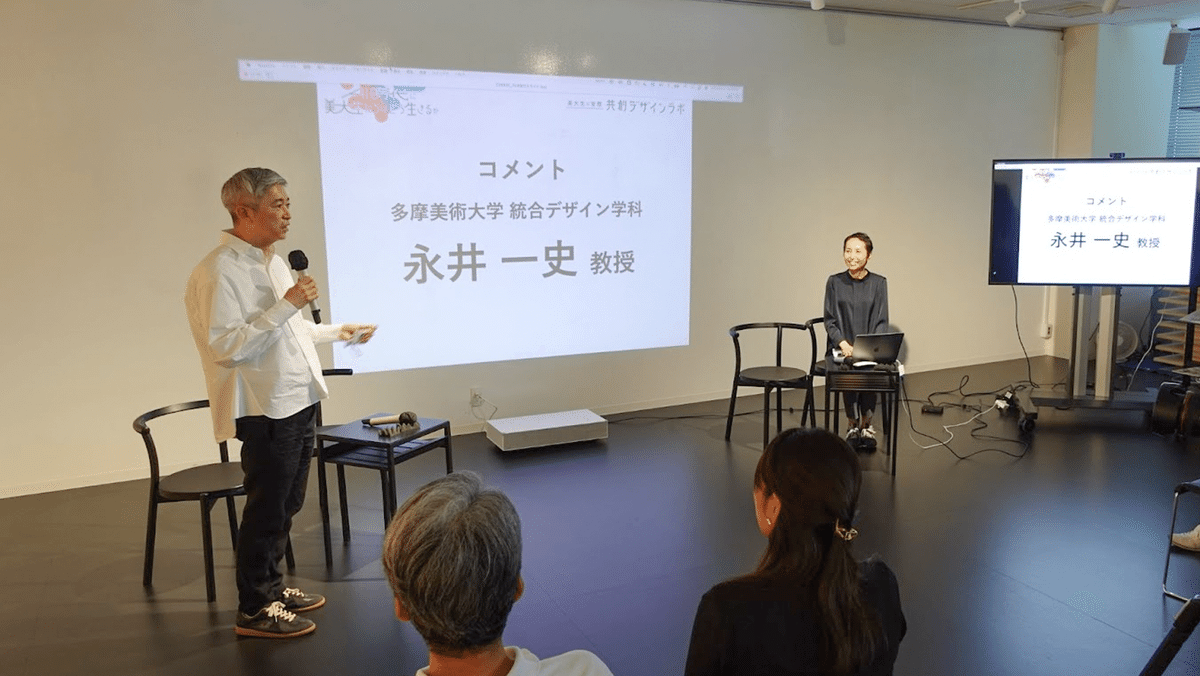
多摩美術大学の永井先生からは、それぞれのチームの発表に対してのコメントをいただきました。Aチームは、AIを人として捉えるというアイディアの核の部分が興味深く、単なるデバイスでなく人らしさが社会に根付くために「人としてなぞらえる」という事についてもっと踏み込んで考えてみてほしいとのご指摘。Bチームは、「教育」というジャンルにフォーカスされている事が深い気づきに繋がっているとしたうえで、絵の比較に関しては技術的にこれからAIにも人と同じことができるようになるのではないかとのご指摘でした。
今後、クリエーションが民主化したときに美大の役割はどうなるのかという踏み込んだテーマにも言及されていました。
2023年前期の活動を終えて
今年も様々な専門性をもったメンバーが集まり、両チームともに興味深いデザインアウトプットが生まれました。そしてテーマ決めからとても難しかった今回ですが、「生成AI」というトピックは世間一般にも広く注目されています。クリエイターである美大生、行政に携わる官僚が、そのことについてリアルタイムに議論できたことには大きな意味があるのではないでしょうか。
2024年3月23日(土)14:00 には、また多摩美術大学TUBでデザインプレゼンを行う予定です。今回の成果や反省を踏まえ、後期の活動も頑張っていきます。
多摩美術大学TUB開催|2023年9月30日
第7回共創ワークショップ 公開プレゼンテーション
「このAI時代に、美大生達はどう生きるか?」
ライブ配信映像はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
