
今、『文明の衝突』を読み直す・前篇〜割れるウクライナ🇺🇦
はじめに
こんばんナマステ 💙💛Kyoskéこと暑寒煮切(あっさむにるぎり)だよっ⭐️
火曜日に #Clubhouse 『 #インドの衝撃 ( #インド大学 )』で喋った『 #文明の衝突 』について今日明日でテキスト化していくぞ❣️
音声版はこちら(約33分)
本当は水曜、木曜で書くつもりでいたんだけど、
火曜日に八重洲の高速バスターミナルの第1期開業が発表されたのでそちらを取り上げ、
水曜夜には地震があり、木曜は急遽この記事を書いた。
昨日はお彼岸で元々決めていた内容があって動かせず、
今日にズレ込んでしまった。
この先を考えてみても、しばらくの間ネタに対して書くのが追いつかない状態というのが続く。
1日2投稿以上は負担が大きいので今は現実的じゃないかな。
1記事について数千円ずつ寄付が集まるなら、1日に数記事を投稿する専業にできるんだけど、それは自分程度の文章力ではほど遠い。
運用だけで食べていける資産もないしね。あったとしても、別のビジネスに投資したり、目一杯遊んだり、毎晩寿司かフレンチ食べるのでやっぱりそんな暇はない。やりたいことは無数にあるわけで。
ということで、日中の隙間時間と夜でどーにか1記事ずつ書き上げていくというリズムを続けざるを得ないかな。
こういう身の上話をしてるから記事が長くなるんだわ💦
それじゃあそろそろ始めていこうじゃないの‼️
『文明の衝突』とハンチントン教授の紹介
『The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order(邦題:文明の衝突)』はハーヴァード大学のサミュエル= #ハンチントン 教授が1996年に刊行した書で、
1993年に『 #フォーリンアフェアーズ 』誌に掲載された論文「文明の衝突か?」の反響を受けて加筆されたもの。
『フォーリン=アフェアーズ』はアメリカの外交問題評議会 が隔月で発行している政治経済の雑誌で影響力はめちゃめちゃデカい。日本の歴代首相も結構寄稿してたりする。
ハンチントンは1927年NY生まれの国際政治学者で、本来は政軍関係を中心にリアリズム(現実主義)に基づいた保守的思想を持ち、

1957年の『The Soldier and the State: the Theory and Politics of Civil-military Relations(邦題:軍人と国家)』などいくつか和訳もされていたけれど、学術書を扱う小さな出版社のものばかり。
研究業績のみならずカーター政権下でFEMA(連邦緊急事態管理庁)の創設、ブラジルの民主化🇧🇷、南アフリカ共和国のアパルトヘイト改革🇿🇦など現実の政治にも携わった。
急進的に民主化やアパルトヘイトの撤廃を推し進めるのではなく、秩序を重んじて緩やかかつ現実的に進めていくのがハンチントンのやり方。
アパルトヘイトについてはここでも語ってるので読んでね💚
政治学に興味のある人にとっては有名だったにせよ、圧倒的に世界的知名度を上げたのはやはり「文明の衝突か?」論文からで、著作は大手の #集英社 から和訳本が出版されるに至りその後日本にフォーカスした『 #文明の衝突と21世紀の日本 』という本も2000年に発売している。
詳しいことは後で書くけど、文明の衝突論が政治学以外の人にも注目されたってことが大きい。
『文明の衝突』の背景と概要
文明の衝突論が執筆された背景には1989年から1991年にかけてソ連が崩壊し東西冷戦が終結した後の世界秩序が大きな議論となり、
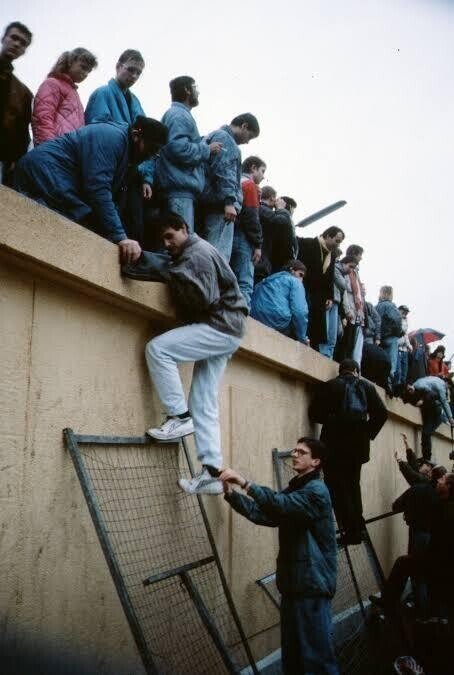
かつての教え子であるフランシス=フクヤマが

1989年に書いた『 #歴史の終わり 』において自由民主主義の勝利によりイデオロギー闘争が終焉するという理論に対して、反論を試みたというところ。
本書の内容を要約すると、冷戦後の世界では自由主義vs共産主義というイデオロギーに代わり世界に7つまたは8つ存在する宗教を軸にした「 #文明 」の対立が起きるというもの。
これらの境界線を断層線(フォルト=ライン)と呼び、そこで争いが起こると論じた。
フクヤマに対して言うなら「歴史は終わらない」ってことかな。
ここでいう「文明」は野蛮に対比する単数形(Civilization)ではなく、世界中に存在する複数形の文明(Civilizations)のこと。(日本人にとっては当たり前に思えるけど、欧米ではいちいち断らなきゃ意味が通じないらしい)
シュペングラー、バグビー、トインビーなどが歴史学者が論じてきた概念を国際政治学に取り入れたということになる。
それが故に人文学系の関心を持つ人からも注目され、そして大きな論争を生むことに。
昔は思わなかったけど、今回読み返して思ったのは人文学系の人の批判のなかには政治学的な秩序のバランスとかそーゆーの全然わかってないんだろうなってものが少なくないなって。
“The Clash of Civilizations” だけを見て“the Remaking of World Order”を無視したようなのが多い。
世界にひしめく文明圏の地図
それでは7、または8の文明とはなにか。前掲の集英社のハード=カヴァー版のP.59-62に書かれているものを見ていく。ここから先のページ数もそれに基づく。
★中華文明…中国を中心とし、海外の華僑社会を含めた中華圏、朝鮮半島、ヴェトナム。論文では「儒教文明」としていたが訂正された。中華圏の思想体系が儒教だけでなく道教をはじめ様々なもので成り立ってることは、多分アメリカ人のハンチントンより日本人の方がずっと詳しいはずだけど、ハンチントンも書籍化するにあたって色々調べてそのことを学んだみたい。

★日本文明…日本のみの文明。大半の歴史学者が論じている中華文明からの独立性を重視した。かつハンティントンはこの観点から日本の孤立を予見したことが日本で物凄く反響が大きかった理由。

★ヒンドゥー文明…インドを中心にネパール、ガイアナに広がるヒンドゥー教を軸にした文明。ハンチントンによる地図には載ってないけどガイアナが入るならモーリシャスも恐らく入る。明日の後篇はこのヒンドゥー文明についてもう少し深入りして見くよ🇮🇳🇳🇵🇬🇾🇲🇺

★イスラーム文明…東南アジアから北アフリカに広がる広大な文明だが、中核国がなく不安定。

★西欧文明…西方教会(カソリック、プロテスタント)に立脚する西欧、北米、オセアニアに広がる文明。諸文明の台頭に立ち向かうため欧州とアメリカは団結せよ、というのが著者の掲げるテーマ。

★ロシア正教会文明…今の世の中の主役⁉️ロシアを中心に東方正教会を軸にした文明。同じキリスト教、白人の文明として西欧文明と一体視する論もあるけども、ハンチントンは西欧文明との異質性を殊更強調する。もっとも東方正教会と東方諸教会の違いをわかってないんじゃないのかって思う箇所もあるけど。

★ラテンアメリカ文明…西方教会に立脚しつつも土着文化との融合が強く、ハンチントンは西欧文明とは別物と捉える。ブラジルの民主化に携わった経験則もあるんだろうね。

★アフリカ文明…ブラック=アフリカ。といってもその北部はイスラーム文明になっているので、ほぼバントゥー系の民族の国というか。執筆当時では文明として認められないが、今後目覚めてくる可能性があるかもね、とのこと。

アフリカ文明を含めず7つ、含めて8つの文明があるとするけれど、以下の留意点がある。
☆仏教…東南アジア、ブータン、スリランカ。主要な宗教としつつも、インドではほぼ滅びていること、中華文明や日本文明などに取り込まれていることから政治主体としての「文明」にはなりえないとしている(P.63-64)

☆孤立国…イスラエル🇮🇱(P.65)、エチオピア🇪🇹、ハイチ🇭🇹(P.203-204)はどの「文明」にも属さない孤立国としている。



著者は触れていないけれど、フィリピン北部🇵🇭についても西欧文明と中華文明が混ざった色分けをしていてよくわからないものになっている。
確かに華人はいるし、中華圏からの影響はあるけど、それをいえばインド圏の影響もあるし、フィリピンはフィリピンなのかなぁと。
西方教会+土着文化という意味でラテンアメリカ文明に近いかたちの孤立国なのでは❓文中、言及の多い国だけど不思議と文明論が語られない。

そんな感じで世界の諸文明は広がっている。いろいろ違和感はあると思うけど、ひとまずこういう組分けがされてるってことを理解してほしい。

そしてそれらはどう衝突していくのかというと、冷戦後の世界ではまず諸文明の断層線で争いが起こるという。
次に文明間の世界的な勢力バランスが崩れた時に諸文明の中核国(中国、ロシア、インドなど)同士による争いが起きるとしている。(P.314-315)
亀裂するウクライナ🇺🇦
著者が最も着目している断層線は東欧を貫く西欧文明とロシア正教会文明・イスラーム文明の間のもので、ローマ帝国の東西分裂に起源を持つものだという。(P.238-246)
佐藤優が好きないわゆるコルプス=クリスティアヌム、ユダヤ・キリスト教(ヘブライズム)・ギリシャ哲学(ヘレニズム)・ローマ法(ラティニズム)が基礎になっているキリスト教共同体というのがEUの基礎であり、ハンチントンのいう西欧文明ってことになるけれど、それは確かに東方正教会やイスラームとは相容れない。コルプス=クリスティアヌムの範囲っていうと確かにしっくりくる。
この観点からウクライナについては東西が完全に分裂している国としてハンチントンが注目しており、ページを割いて説明している。(P.249-253)
ウクライナの東部はロシア正教会文明に位置し、かつてキエフがこの文明の中心だった(キエフ大公国、キエフ=ルーシ)後はほぼ一貫してモスクワによって支配されてきた。

東部の住民の多くはロシア語を話し、なかにはクリミア半島のようにロシア人が住んでいる地域がソ連統治下でウクライナに組み入れられたところもある。

一方で西部は東方帰一教会(東方正教会の典礼を用いつつローマ教皇を受け入れてカソリック傘下にある教会)に属し、歴史的にはポーランドやオーストリアなど中欧の支配を受けてきたこともあり、ウクライナ語を話す住民の多くはEUやNATOに親近感を持つ。

ウクライナの政治は現在も親EU派と親ロシア派の間で揺れ動いている。
旧ソ連に特化した研究以外で、ウクライナに対する着目はかなり早かったといえるんじゃないのか。今、『文明の衝突』を読み直すべきだと思った理由はここにある。
文明間の戦争を防ぐために
著者のシナリオは西欧文明の相対的な地位の低下に際して諸文明の地域主義が高まり、儒教―イスラームコネクションやロシア正教会文明が西欧文明に対峙するようになる。
非西欧圏が連合して、西欧との戦争になるのを防ぐべく、ラテンアメリカ文明を早いうちに味方につけ、日本文明が中華文明と和解するのを遅らせ、ロシア正教会文明を尊重し、欧州と米国が団結を図るべきであるとする。(P.479)
この観点からの国連安保理改革を主張してるのがなかなか面白くて、現在はの常任理事国は西欧文明、中華文明、ロシア正教会文明しか選ばれていないけれど、各文明から常任理事国を出すべきで、どの国が文明を代表して出席するかはEUなどの地域連合が決まればいいと。(P.488)
P.367-368には西欧とロシアの間の融和について、NATOとロシアで相互不可侵の約束を取り、東方正教会の信徒が多い地域ではロシアが中心になって安全保障することを西欧が認めろとも言っている。
現実にはこうはならず、西欧との間に緩衝国家を欲しがるロシアに対し、喉元に刃を突き付けるかたちになっている。日本のメディアは一方的に侵略と言ってるけれど、ロシアからすれば今回の侵攻は自衛なんだよね。
ロシアを正当化する意図はまったくないけれど、西欧がロシアを尊重することなくEU、NATOの拡大を推し進めてハンチントンの恐れていた方向へ進もうとしている。
本書をよく読まずにハンチントンが文明の衝突を煽ったみたいなことを言う人もいるけども、リアリズムの観点から戦争を防ぐために色々提言をしていることはスルーしちゃダメだと思う。
「文明の衝突」は本当に起きているのか
2000年代初頭のアメリカ同時多発テロからアフガニスタン、イラクでの戦争の流れを見て、ハンティントンの予見は的中したという見方がされ本書は再度注目を浴びるが、個人的にはあまり同意しない。
なぜならアルカーイダ、タリバーン、フセイン政権といったアメリカに牙を剥く勢力にイスラーム諸国は積極的に味方はしなかったし、中国やロシアも反米攻勢に出ることはなかった。
むしろフランス・ドイツがイラク戦争に強硬に反対し、アメリカ・イギリスとの間に亀裂が入り西欧文明間での揺らぎが大きかったのではないのかと。
著者は2008年に帰らぬ人になるが、2010年代に入り、中国の台頭と日本やインドなどとの衝突、ロシアのクリミア侵攻からのウクライナそのものへの侵攻、ISの出現、タリバーンの復権、そしてそれらが結びついていく展開を見ているとその予見をやはり無視できないのではないかと思えてくる。
「文明」の恣意的な分け方やその内部での対立を軽視することなど、「文明」を国際政治の新たな主体に結びつけるという点において粗雑な議論であることは否めないんだけど、その大胆な分析は一度学んでおく必要があると思う。
日本では「日本文明の孤立」に大きく注目が集まったけど、そこは個人的にそんな興味ない。
そして今は中国で話題なんだってね。
おわりに
明日は先に書いたようにヒンドゥー文明について書いていくよ。
そして22:30からはClubhouse『 #日本とインドの架け橋 』で、インドの聖地について喋るよ❗️
色んなスピーカーの方が話す中の最後、つまり大トリKyoskéということで一番お気楽に聴いて、かつ後でコメントもいただければ幸い。

『インドの衝撃』と違って録音はされないけど、明後日テキスト化する予定なので聴けない人はそちらで‼️
Clubhouseに録音機能ができる前は『インドの衝撃』で喋って、その後もう一度広瀬さんとZoom繋いでそこで収録してたのね。
ちなみに仏跡までが再録で、ベンガルトラからが生収録。
だから結構疲れたんだけど、逆にClubhouseの方では収録されないので気楽に話せる部分もあって。
そういう気楽さを明日は出していければいいと思ってる。ホーリー=イヴェントだしね。
それじゃあバイバイナマステ❤️暑寒煮切でしたっ✨
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
