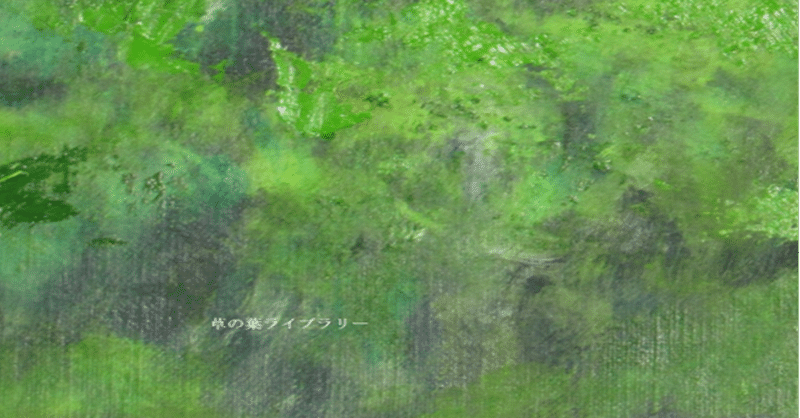
草の葉メソッド実践編 1 テキスト 英語を自分の言葉にするトレーニング
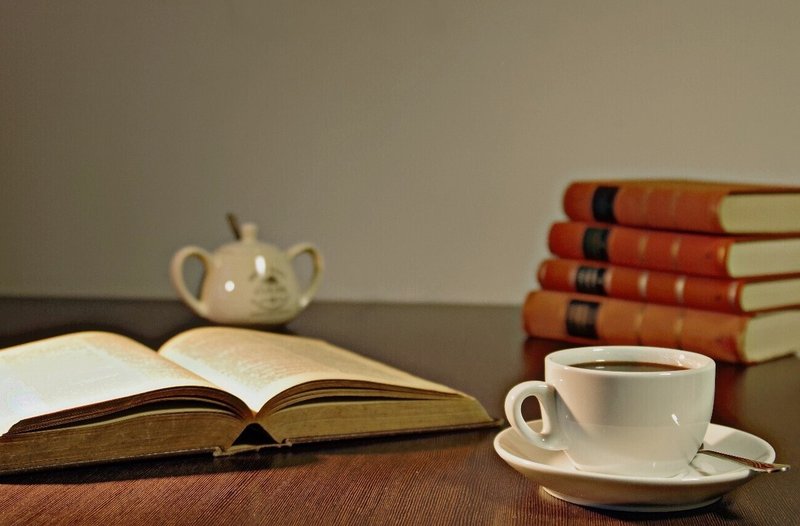
《草の葉メソッド》によるトレーニングで英語を学習してきた中学二年生の山口詩織さんと野田早苗さんは次のレッスンに取り組んだ。果たして彼女たちはどのような英語で会話したのだろうか。
![]()
いただきます──文化の発信
私の住む町品川とアメリカのポートランドは姉妹都市で、毎年交互に中高生の交換研修ツァーが行われている。私はそのツアーに参加することになった。私がホームスティしたのはピーターセン家だった。ピーターセン家は、私と同じ年齢のアンと、二歳下の弟ジョン、そして彼らの両親の四人家族だった。
食事のとき私はいつも胸の前に掌をあわせて、「いただきます」というのがとても不思議がられて、それはどういう意味なのだときかれた。私にもその言葉の本当の意味がわからなかったけれど、多分それはごはんが食べられることへの感謝の気持ちを伝える言葉ではないかと言った。「いただきます」という言葉は、ピーターセン家の人々の共感することとなり、食事のときは五人そろって、「いただきます」と言って食べるようになった! 私は日本語と日本の文化をポートランドに伝えたことになる。
対話編
A──あたしも二年生の夏休みに、ホームスティしたのよ。
B──あんたは、どこにいったの。
A──アメリカのシアトル。あたしがホームスティした家の人たちも日本のことにすごく関心もってて、いろいろ聞かれるんだけど、それがうまく説明できないんだ。
B──話したいんだけどそれが言えなくて、I don’t knowって言っちゃうんだよね。
A──そうそう。I don’t knowばっかりになって、それがすごくいやになってさ。だってさ、I don’t know っていったら、そこで会話が終っちゃうんだよ。
B──ピリオドが打たれちゃって、なんだかその場がしらけちゃんだよね。
A──あたしそれがいやで、ぜったいにI don’t know は言わないことにしようって思って、それからはとにかく単語だけでもいいから、話すようにしたのよ。
B──それって意外に通じるんだよね。
A──ちゃんとフォローしてくれるからね。
B──あなたの言ったことはこういうこととか。あなたの言いたいことはこういうことかね。
![]()
A──あたしもね、このテキストの子じゃないけど、日本の文化を広めてきたよ。
B──どんなこと?
A──豚骨ラーメンに、醤油ラーメンに、塩ラーメンに、味噌ラーメン。
B──うへっ、すげえ!
A──十回ぐらい作って上げたかな。あたしがホームスティした家族、完全にラーメンにはまっちゃってさ。
B──そんなに作ってあげたら、ラーメンにはまっちゃうよ。
A──ラーメンを作るのは簡単なのよ。簡単じゃないのは食べ方なの。まずさ、箸の持ち方からはじまるのよ、アメリカ人って、箸がぜんぜん使えないじゃない。
B──ラーメンはやっぱ箸だよね。フォークじゃないよね。
A──そうだよ、パスタ食べるんじゃないんだから。だけどさ、アメリカ人にとって、箸を使うのってものすごくむずかしいことなんだよ。
B──あたしも教えてあげたけど、全然だめだった。
A──ショックだったのは、アメリカ人ってラーメンすすれないのよ。あんた、知ってた? あたしはそれ知らなかったからさ、ちょっとしたカルチャーショックだった。
B──あの人たちは、ラーメンとか、おそばとか、うどんとかはすすれない民族なんだよ。
A──何度やってもだめなのよね、喉につまってむせちゃったりしてさ。そのうちジョンっていう男の子がハサミ持ち出してきてね、麺をさ、そのハサミで切って食べたりしてさ。
B──信じられない。
![]()
A──それで、あたし気づいたのは、やっぱ根底のあるのは、文化のちがいなんだってことに。アメリカ人の食事の食べ方って、ぜったいに音をたてちゃだめでしょう。小さい時からそんな風に教育されているわけだし。
B──そうそう、スープなんか飲むときだって、静かに、お上品に、音を立てないですするんだよね。それがあの人たちの食べ方であり、守るべき食事のマナーであり、文化なんだよ。
A──だから最初さ、あたしがずるずるって音たててラーメン食べたら、家族全員、ものすごい顔をして私をみるわけよ。
B──みんな目が点になるよね。どこからきた野蛮人なんだって目だよね。
A──それでさ、まずラーメンの食べ方のお勉強が必要だと思ってさ、レンタルショップにいって、英語バージョンの「たんほぽ」と「ラーメンガール」を借りてきて、そのビデオをみんなで見ることにしたのよ。
B──わあっ、それって最高のテキストだよ。
A──そのビデオ見て、彼らにもわかったのよ。ラーメンを食べるときは、ずるずるって派手な音をけたてて、すするもんだってことが。
B──それでみんなすすれるようになったの?
A──そうなのよ、家族全員が、アメリカ文化をぶち破って、派手な音をけたててずるずるってラーメンをすするようになったのよ。
![]()
《草の葉メソッド》に取り組むためのいくつかのポイント
1 ランナー(learner──学習者)は、まずテキストの本文と対話編の会話を、翻訳ソフトを駆使して英語に転換していく。翻訳ソフトの性能は格段に向上していて、とくに「Google」の翻訳精度は驚くほど高い。たとえばテキストの第一フレーズ、
「私の住む町品川とアメリカのポートランドは姉妹都市で、毎年交互に中高生の交換研修ツァーが行われている。私はそのツアーに参加することになった。私がホームスティしたのはピーターセン家だった。ピーターセン家は、私と同じ年齢のアンと、二歳下の弟ジョン、そして彼らの両親の四人家族だった」
を「Google」の翻訳ソフトで転換してみると、
Shinagawa, where I live, and Portland, USA, are sister cities, and exchange training tours for junior and senior high school students are held alternately every year. I decided to take the tour. It was the Petersen family that I homestayed. The Petersen family was a family of four, Anne, who was the same age as me, John, who was two years younger, and their parents.
ほぼ完ぺきに転換されてくる。しかし中学二年生のふたりはこの英語ではなく、もっと平易な英語にして表現されている。「交換研修ツアー」などわかりやすい英語で説明されている。これは彼女たちがすでに翻訳ソフトをもう一つの英語脳として駆使していることを語っている。
テキスト本文の第二フレーズの冒頭は、
「食事のとき私はいつも胸の前に掌をあわせて、いただきますというのがとても不思議がられて、それはどういう意味なのだときかれた」
を「Google」の翻訳ソフトで転換させてみると、
When I was eating, I always put my palm in front of my chest, and it was very strange to say "I'll have it", and I was wondering what that meant.
まったく意味不明の英語に転換されてくる。翻訳精度が上がったといえ、翻訳ソフトはいまだその限界を突き破っていないことを語っている。
英文には必ず主語が存在する。ところが日本語には主語が存在しない文章が存在する。それがあたりまえなのだ。いちいち主語など書き込まない。この第二フレーズの冒頭の息の長い文章には主語がない。主語がない日本語に翻訳ソフトは混乱するのだ。混乱した翻訳ソフトはかくも混乱した英文に転換してきたということだった(翻訳ソフトに混乱するなんてことはないのだろうが)。
ではどうしたらいいのか。それは翻訳ソフトが正確に転換されてくるような文章に書きかえるのである。この長文を解体して、
一 私は彼らと食事するとき、私はいつも胸の前に掌をあわせ、そして私はITADAKIMAS と言った。(三度も主語を入れることによって、翻訳ソフトは正確な英文に転換してくる)
二 彼らは私の行動を不思議に思った。
三 それで、彼らは私にITADAKIMASってどういう意味なのですかと聞いてきた。
山口さんも野田さんも、このようにテキストの日本語を解体分解して英訳したのだろう。わかりやすい英語で表現されている。
![]()
「草の葉メソッド読本──英語を自由に話せる民族にするためのテキスト」は《草の葉ライブラリー》より近刊。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
