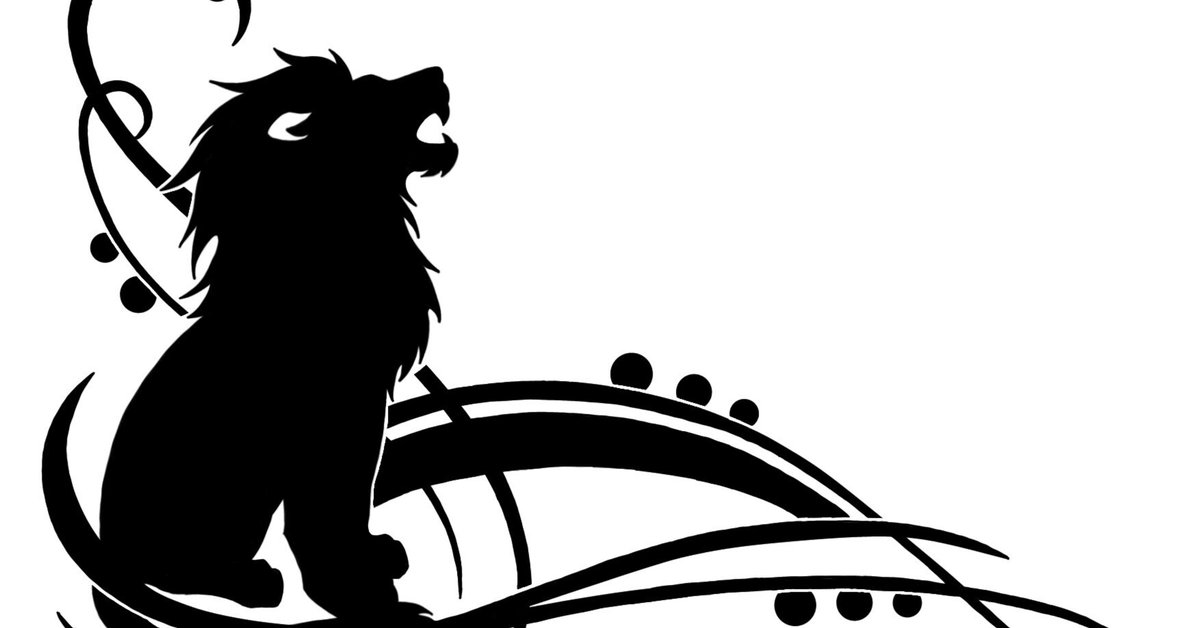
【小説】中二病の風間くん第10話 もしもこの手を引いてくれるなら
服装に困る季節がやってきた。空と人の攻防戦が繰り広げられる中、風間は浮き足立っていた。
「三組と合同というだけあって、なかなか豪華なシナリオだ。腕の見せ所だね。漆黒のマーメイド」
「なんでよりによってヒロイン役なの……」
「僕という主人公にふさわしいじゃないか」
「人前で演技できないの知ってるでしょ? 鬼かあんたは」
「いいや悪魔だ」
文化祭が迫っている。ポスターがあちこちに貼られ、各教室で実行委員が忙しなく動く。先ほどもらった出来立ての台本を手に、風間は口角を上げた。
「何度やれば気が済むんだ! お前にとってはたかが窓ガラス一枚だろうけどな、これは立派な器物破損だ」
飛んできた怒号に二人は足を止めた。出所は職員室。発信源は生徒指導の先生だ。そっと窓から様子を覗くと、宮下が深々と頭を下げていた。
「申し訳ございませんでした!」
「謝罪は前にも聞いた! 反省してないようなら親を呼ぶぞ」
「それだけは……!」
宮下は消え入りそうな声で必死に土下座した。
「どうかお願いいたします。どのような罰もお受けします。両親にだけはどうか……」
風間が止めに入ろうとした途端、反対側の扉が乱暴な音を立てて開く。
「はざーっす。先生久しぶり。元気してた?」
「加護!? 停学処分は!?」
「んなもんとっくに解けてますよ。いつの話してんすか」
「お前は扉の開け方も知らないのか? 相変わらず服装もなっとらん! それにその髪と耳! 直す気がないなら登校するな!」
「サーセン。なんせ久しぶりなもんで」
「大体お前はいつもーー」
完全に標的が変わった。グダグダ言い始める生徒指導に風間は既視感を覚えた。眼帯について担任と攻防戦を繰り広げたことは記憶に新しい。
眼帯はおしゃれではなくメガネのようなもの。よって必需品だと一ヶ月言い張り、担任が折れて申請書を渡したのだ。
十数分にわたって続く加護への説教に終止符を打ったのは、風間の担任・守谷先生だった。
「工藤先生、朝から熱心なご指導ありがとうございます。昨日も夜遅くまで勤務されてお疲れでしょう。彼らは私のクラスですので、後は私が」
身を引いた生活指導の代わりに二人の前に立つ。
「宮下くん、顔を上げなさい。加護くんは反省文を書いて、明日までにその服装を整えてきてくださいね。せっかく登校したのですから、授業には参加すること」
「うっす」
「宮下くん、上履きは?」
「……忘れました」
「ではこれは一体誰のものでしょう。焼却炉に捨てられていたのですが」
差し出されたのは、宮下の名前が刻まれたボロボロの上履きだった。
「あなたは他人の言いなりのまま、生きていくつもりですか?」
「……拾ってくださりありがとうございました」
受け取る宮下にいつも浮かべる笑顔はなかった。そのまま一礼して足早に立ち去っていく。廊下に出た加護はその小さな背中を見送った。
「よく学校来れるねあの子……ウチ無理だわ」内海が呟く。
「……宮下がああなったのは、オレのせいなんだ。なあ風間、アイツを地獄から引っ張り上げてくんねえか? オレ一人じゃどうも力不足でよ」
「いいとも! 今度は僕が君の夢を手伝う番だ」
教室に入った三人は、再び宮下の冷遇を目撃した。
「なんでまだボロ靴履いてんだよ! せっかく捨ててやったのに」
「ありがとうございます! 取り換え時ですよね」
「礼央くんの前でそんなボロっちい靴履いてんなよ? 今日帰ってくるんだから」
「よう。誰が帰ってくるって?」
高身長な上に強面の加護が睨めば、威勢の良かった二人は腰を抜かす。
「お前らも気をつけろよ? 礼央はマジで手段選ばねえから」
鬼気迫る忠告に、風間と内海は顔を見合わせる。
「礼央くんとはシーザー役の?」
台本を奪い取った加護は、苦虫を嚙みつぶしたような顔をした。そして、配役の中に自分の名も記されているのに気づく。
「……終わったな文化祭」
体育館でスキール音が鳴る。三組と四組の合同授業。風間と成上のテンションは必然的に上がっていく。
「キミの唯一の弱点は体力だと思っていたが……なるほど。面白くなってきたね」
「ようやく力を解放する時がきたんだよ」
対峙する二人を加護はコート外から眺めていた。器用にボールを回しながら己の出番を待つ。
「加護くん、おかえりなさい」
宮下が歩み寄ると、加護は回転を止めた。
「ただいま」
「卒業までもう会えないかと思ってました」
「んな大げさな……悪いな。守ってやれなくて。アイツが留学するっつーから、もう大丈夫だと思ったんだが」
「大丈夫ですよ! このスタイルが僕の天職というかーー」
宮下は飛んできたパスを受け止めた。
「お前はやっていいんだぞ、バスケ。部を立ち上げたのお前じゃん」
宮下は笑ってパスを返す。
「加護くんが戻るならそうします」
「オレはいろいろ事情がーー」
加護が再度ボールを放るも、宮下に届くことはなく、割り込まれた手におさめられていた。
「楽しそうだなァ。俺も混ぜてくれよ」
「お、おかえりなさい……礼央くん」
宮下はとっさに笑みを浮かべた。どこか気品のある佇まいに全身からあふれ出る自信。体は小柄だが、その眼光は加護に引けを取らないほど鋭い。
「昼休み、いつもんとこ顔出せよ」
「承知いたしました!」
試合終了の笛が鳴り、礼央と加護はコート内で対峙する。
座り込んで肩を上下させる風間は、背中をさすってくれる宮下に疑問を投げた。
「君は出ないのか?」
「僕、見学なんです。体調が優れないので」
「相変わらず、つかなくていい嘘ばかりつくね。キミは」
成上には宮下の考えなどお見通しである。歓声が上がりコートへ視線を向けると、礼央と加護の一騎打ちが繰り広げられていた。双方が体の一部とでもいうようにボールを操り、一歩も引くことなく睨み合う。
「あの加護くんと対等に渡り合うとは……彼、何者なんだ?」
「富沢礼央……加護くんの元チームメイトだよ。彼らは中学時代、同じコートで駆け回っていた。そこの宮下くんもね」
成上の指摘に、宮下は気まずそうに視線を下へ向けた。技術のぶつかり合いに、周囲は釘付けである。先生までもがその駆け引きに見入った。
礼央が舌打ちをこぼす。
「未練たらしくボールつついてんなよ。お前はもうとっくに終わってんだ。天地がひっくり返っても、オリンピックなんか出られっこねェ。まだ懲りてねェなら、いくらでもおかわりやるぜ。次は退学かァ? それとも刑務所かァ?」
「……百獣の王が聞いて呆れるな。お前は大勢の人を法的に葬ってきた。けど、一度も命に手をかけてねえ。ホントに邪魔だってんなら、オレを殺してみろよ」
凄む加護に一瞬礼央の動きが鈍くなった。ボールを奪い、通り抜けざまに加護が呟く。
「何でお前が一番ビビってんだよ」
きれいに三ポイントが決まると、礼央は殺気立ち瞳孔を開く。
「お望み通りむしり取ってやるよ。お前の友人も家族も地位も名誉も全部なァ……!」
「自分でエサも取りにいけねえお子ちゃまがよく言うぜ」
礼央は味方もついてこれないほど早い動きで、四人を抜き去る。立ちはだかるのは加護だけだ。
「幽霊部員の割には腕上げてんじゃん。未練あんのはそっちも同じだろ」
「未練だァ? 監視だよ。お前がヘタな真似しねェようになァ」
口角を上げる礼央を前に、一瞬憎悪が顔を出す。口をついて出てきたのは、氷のように突き刺す声。
「お前、バスケでオレに勝ったことなんてあったか?」
「あの頃のままだと思ってんなら、とんだ舐めプ野郎だぜェ」
礼央は加護を抜き去った。途端、礼央のチームメイトが、ヘルプに入ろうとしているのが見えた。
「ジャマだ退けェ!」
スピードを殺せず、二人は衝突した。背の高い加護が死角になっていたのだ。鈍い音と共に、礼央の膝が血で滲む。
「経験者でもねェやつが割り込んでくんなァ!」
「わ、悪かったって!」
「俺が加護を抜けねェとでも思ったんだろ。なァ? 舐めてっと地獄に落とすぞ」
立ち上がる礼央が纏う威圧感は、その名の通り獅子のようだった。すかさず宮下が駆け寄る。
「保健室行きましょう! 今日は先生が不在なので僕がーー」
「あァ? 手当もできねェお子ちゃまだってかァ?」
「いえ……お気をつけて!」
礼央は宮下を一瞥して立ち去った。その場に張り詰めた空気を残して。
校長室の机には、留学に関する報告書と学力テストが広げられている。校長は学年一位の文字を誇らしげに眺め、賛辞を口にした。
「さすが富沢くんだ。この先何を成し遂げるのか将来が楽しみだな」
「いえいえ、大したことはできませんよ」
礼央は慣れたように貼り付けた笑みを浮かべた。まるで社長同士の商談である。
「私としては、ぜひ君を生徒会長にと思ったのだが……」
「ありがたいお言葉ですが、半年も不在では務まらないでしょう」
「赤点常習犯で奇行ばかりの成上くんよりは、不在でも君の方がよっぽどふさわしいだろう。なぜ生徒たちは彼に票を入れたのか、全く見当もつかんよ。加えて転入生も問題児だ。このままでは学校の品位が下がる。君だけが頼りだよ」
上品な笑みを浮かべ、礼央は時計を見た。昼休憩は残すところ半分である。
「ところで、投資の件は考えてもらえたかな? その……ご両親はなんと?」
目の色を変えた校長に引き受ける旨を伝え、部屋を後にした。途端、礼央の笑みが崩れる。舌打ちをこぼしながら、足早に集合場所へ向かうその背中を、成上が目を鋭く光らせ見送った。
一方その頃、体育館裏では宮下がタコ殴りにされていた。
「何でもっと上手く隠せねえんだよ。危うく俺たち停学になるとこだったじゃねえか!」
「お前のせいで問題児扱いされるだろうが」
膝をつき、腹を押さえて宮下は咳き込む。
「面目次第もございません……」
缶の踏みつぶれる音が、彼の来訪を告げる。強気だった二人の動きが止まり、空気が凍る。三人の視線を受ける礼央は、怒気を放っていた。
「んだこの体たらくはよ……あァ? お前ら俺がいねェうちにずいぶん堕落してんなァ」
ハラハラと落ちていく書類の数々。礼央が放り投げたのは、三人の学力テストの総合結果だった。礼央は、地面に向かって舞っていく紙をぐしゃっと踏みつける。
「前にも言ったろ。先公がお前らの蛮行見逃してんのは、成績がよかったからだ。俺が臨時家庭教師までつけてやったんだから当然だよなァ?」
今にも殺しそうな冷徹な目に、言い返すこともできず二人は冷や汗をかく。
「次九十以上取らねえと、お前らの家族ごと潰す」
「たかがテストじゃ……」
開いた瞳孔に怯んだ一人が、苦し紛れに言い訳をこぼした。
「俺ァな、たかがテストもできねェやつらとつるんでる暇はねェ。そんな不甲斐ない紙切れ、燃やしてチリにした方がよっぽど役に立つ」
膝をついたままの宮下にも、その矛先が向かう。
「お前もだ宮下。こんなギリギリラインで安心してんなよ? 九十五点以下はゴミだ」
虚ろな瞳で礼央は続けた。
「聞いたぜ? お前ら窓ガラス割ったんだってなァ。つまんねェことしてんなよ。どうせなら学校ごとぶっ壊せや」
背筋を伸ばして返事する三人に、礼央は小箱を投げて寄越した。
「俺の下僕に役立たずはいらねェ。次はねェぞ」
立ち去る礼央の背中に安堵し、二人組は箱を開けた。飛び込んできたのは、一つ一つが宝石のように丁寧にしまわれたチョコだった。喜びや尊敬の声が上がるそばで、宮下だけが浮かない顔をしていた。
土産を手に駆け出し、小柄な背中を呼び止める。
「これ、僕にはもったいない代物です。いただけません!」
「あァ? やるっつってんだからありがたくもらっとけよ。それとも何かァ? 俺のセンスが気に食わねェとでも言いてェの」
「いえ滅相もーー」
「ヘコへコしてりゃ、俺のご機嫌取れるとでも?」
暗い瞳に睨まれ、宮下は何も言えなくなる。その様子を鼻で笑い、礼央は肩を組む。
「来い。昼飯奢る」
「いえ、僕には弁当がーー」
「つべこべ言わずに来いやノロマ」
「ではお言葉に甘えて」
食堂は人でごった返し、並んで空いた席が見当たらない。
「さすが金色の鷹匠! やはり加護くんの芸術センスは天才だよ」
「独創的だよね……」
「ピカソの再来か?」
「お前らそれ以上言ったら捻りつぶすぞ」
礼央は口角を上げ、盛り上がる一帯に目をつけた。彼らの視線の先は、美術で使うスケッチブックに向いていた。描かれているのは、歪な獣のようなもの。
「確かにこりゃ迷作だなァ。家に飾ってミルクティーぶちまけたくなるくらいに」
その声に加護の表情が歪む。
「何しに来た」
「昼飯に決まってんだろうが。おい宮下」
「はい! 本日の日替わり定食はハンバーグ、その他礼央くん不在の間、担々麺とカツ煮丼が追加されております」
「そうか。売り切れてねェやつ買ってこい。あとお前の分好きなだけな」
何十万も入った財布ごと渡され、宮下は苦笑を浮かべる。
「いやー悪いな礼央。じゃあオレ、ポテト追加」
加護の悪ノリに風間と成上も便乗する。
「僕もコーヒーをもらおうかな」
「私はBLTサンドを」
「お前らに奢るギリはねェ! 何しれっと注文してんだよ。宮下、こいつらのは無視していい」
返事をして去っていく宮下を見送り、風間は笑いかける。
「やあ久しいね。堕天使ルシファー。再会の宴といこうじゃないか」
「バリバリの初対面だわ! 誰だお前」
「僕は疾風の渡り鳥・ハヤブサ。もうじき世界を滅ぼす男!」
「類は友を呼ぶってかァ? 落伍者の周りにはロクなやつがいねェんだなァ。お前らこんな脳筋野郎とつるんでたら泣くことになんぞ」
「加護くんと過ごすひと時は最高に愉快だよ」
「……なるほどなァ。加護を引き戻したのはお前か。えらくチンケな相棒だなァ。せいぜい一緒に堕落してやれ」
「お待たせいたしました!」
戻ってきた宮下は礼央にコロッケパンとミルクティーを渡し、その後コーヒー、ポテト、BLTサンドを的確に配置し、さらにはシュークリームを内海の前に差し出した。
「お人好しにもほどがあんだろうがァ! つーかお前のはどした?」
「お構いなく! 好きなだけとおっしゃったので、僕からささやかながら……みなさんどうぞ召し上がってください」
礼央は興が冷めたと言わんばかりに舌打ちをこぼす。
「それがお前らの最後の晩餐だァ。よーく味わって食え。行くぞ宮下」
置き去りにしそうなほど足早に歩いても、宮下は駆け足でついてくる。礼央はその事実にどこか安堵していた。
太陽が役目を終える頃、礼央は一人帰路を辿っていた。遠く聞こえる幼い笑い声やボールをつく音に立ち止まることなく、大きな門の前に立つ。
「ただいま帰りました。礼央です」
重々しい金属の扉をくぐれば、すぐに無機質な音を立てて閉じた。中に入れば、列をなす使用人に頭を下げられる。
「遅かったな。何をしていた」
威圧感漂う父の声に、全身の毛が逆立つような感覚を覚える。
「文化祭の準備を……」
「わからんな。私の反対を押し切ってまであの学校に通う理由が」
気圧される礼央はまるで小動物だった。一言も発せずにいると、封筒を差し出された。
「パーティーの招待状だ。腹をくくれ礼央。お前は次期当主。全てを統べる王となる器だ。手を汚す覚悟はあるな?」
「……はい。お父様」
頭に乗る血塗られた手。何人も潰してきた大きな手が、礼央の心を重くした。
「それでこそ私の子だ」
生を受けた瞬間、運命は決まっていた。引き返す道などなく、この手はすでに、海水でも洗い流せない夥しい血がついている。
もしも誰かがこの手を引いて連れ出してくれるなら、何にだって牙を剥けるのに。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
