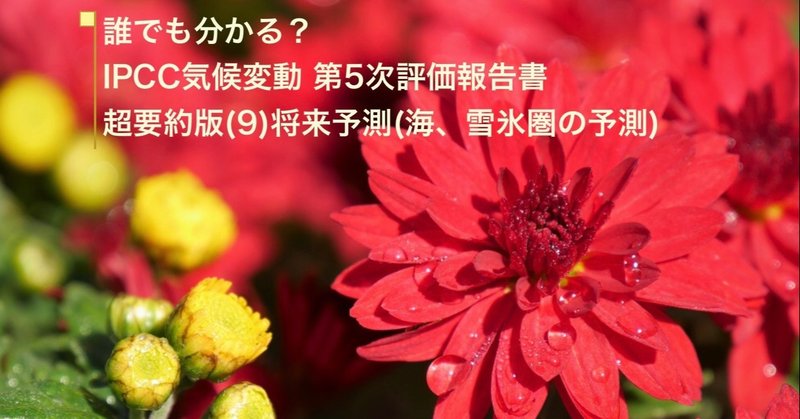
たぶん分かり易い!気候変動に関する政府間パネルIPCC第5次評価報告書の超要約版(9)将来予測(海、雪氷圏の予測)
【報告書の要点】は報告書記載内容から重要な文章をそのまま引用。【解説】は報告書に記載されている内容を用いて要点を解説。【補足】は報告書以外の情報も含めて私が必要と思う情報を記載。
【報告書の要点】
21世紀の間、世界平均海面水位は上昇を続けるだろう。
海洋による炭素貯留の増加が、将来において酸性化を進めるであろうことはほぼ確実(99%以上の確率)である。
21世紀の間、世界平均気温の上昇とともに北極海の海氷面積が縮小し、厚さが薄くなり続けること、また北半球の春季の積雪面積が減少することの可能性は非常に高い(90%以上の確率)。
【解説】
2081年〜2100年平均の1986年〜2005年平均基準に対する世界平均海面水位のシナリオ毎の予測上昇範囲は以下の通りです。RCPシナリオについては前回の「超要約版(8)将来予測(気温、降水)」を参照下さい。
RCP8.5=0.45〜0.82m(温暖化防止対策を実施しない場合)
RCP6.0=0.33〜0.63m(ある程度の対策を実施する場合)
RCP4.5=0.32〜0.63m(RCP6.0と2.6の中間の対策を実施する場合)
RCP2.6=0.26〜0.55m(IPCC目標の対策を実施する場合)
「炭素貯留の増加」とは、海洋が二酸化炭素を吸収し、海洋中の溶存二酸化炭素濃度が増加することです。その結果、海洋の酸性化が進みpHが低下します。現在の海洋のpHは約8.1ですが、2100年の予測は、RCP8.5シナリオでpH=7.75〜7.80程度、RCP2.6シナリオでpH=8.05程度となります。
RCP8.5シナリオにおいては、今世紀半ばまでに9月の北極海で海氷がほとんど存在しない状態となる可能性が高い(確率66%以上)と予測されています。
【補足】
海水温度の上昇(海水の膨張)と氷床の融解により海面水位が上昇します。
平均海面水位が59cm上昇した場合、日本の三大湾(東京湾、大阪湾、伊勢湾)のゼロメートル地帯の面積は5割増えると予測されています。また、海面水位の上昇は沿岸地域の防災上のリスク(高潮、高波等)を上昇させます。
海水の酸性化は、サンゴをはじめとする生態系に大きな影響を及ぼします(海水温の上昇と酸性化による生態系への影響は既に出ていると思われます)。
南極域においても21世紀末の海氷面積と体積の減少が予測されていますが、北極圏に比べると影響が少ないようです(超要約版(5)観測事実(降水・雪氷圏の状況)参照)。
次回は、極端現象の予測です。
ご意見、ご質問がありましたら気軽にコメントください。
