
MONJU 新しい翻訳マネタイズシステム みつける、やくす、まとめる(2020.09.18. 次世代リーダービジネスプランコンテストプレゼン)
2020.09.18.
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究、神戸大学V.School PRESENTS
次世代リーダービジネスプランコンテストにて、2位入賞させていただきました。
当日のプレゼンを元に私が何をしたいと思っているのかご紹介します(プレゼンがベースなので細かい説明してない箇所はたくさんあります)。

『MONJU 新しい翻訳マネタイズシステム みつける、やくす、まとめる』
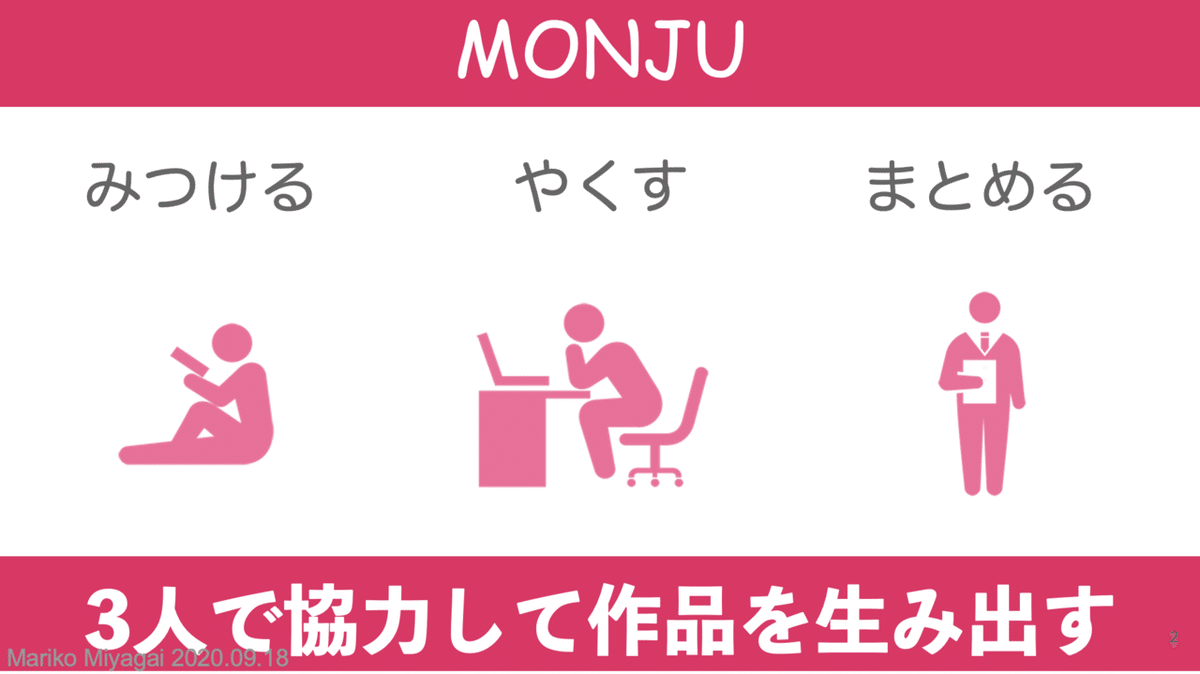
MONJUは「みつける人」「やくす人」「まとめる人」の3人で協力して作品を生み出すプラットフォームです。

全体概要です。わかりやすいように英語と日本語で紹介しますが、言語は特に限定しません。英語で書かれた文章をMONJUチームが日本語に翻訳して、オンラインプラットフォームで読者が日本語に翻訳された文章を読みます。

私の「翻訳者になりたい」は小説翻訳の出会いから始まりました。『赤毛のアン』『風とともに去りぬ』『ライ麦畑で捕まえて』『モモ』『エミールと探偵たち』…ここの話は過去のエントリーに詳しく書いてます。

しかし、2500億円の翻訳市場の99%はマニュアルや社内文章などの産業翻訳。書籍・映画の翻訳は1%程度です。「翻訳者」として生計を立てる、お金を稼いでいる人のほとんどは産業翻訳者です。
市場が小さいということはバリュー(価値)がないということでしょうか?私は小さい頃に大きな影響を受けた海外文学は市場価値が少ないのでしょうか?
市場が小さいから価値がない、のではなく、ここには産業構造上の問題があります。

一般的に、本は企画、執筆、編集、デザイン、構成、入稿、印刷、製本、宣伝、販売という工程を経て出版されます。他の要素が加わることもあります。この工程を回すのには、最低でも半年、長いと数年単位のプロジェクトになります。

翻訳出版となると、先の出版工程を、例えば、アメリカで回した後、日本で情報収集、企画、そしてアメリカの著者、出版社、またはエージェントとの契約、翻訳を経て再び出版工程を回すこととなります。

翻訳本ができるまで、それぞれの国での出版工程を半年としても最低でも1年以上かかることになります。

この工程の中で、翻訳者がやりたい工程はこれだけです。工程が多いという点と、マネタイズ(販売)まで時間がかかるという点で、翻訳で生計を立てている人にとっては参入しづらい分野です。
*契約にもよります。一般的には、翻訳したワード数でいくら、という契約と、売れた分の何%、という契約があり、後者の場合収入が書籍の販売後になるので、普通に生計を立てるのは難しいです

少し出版の話に戻ります。今私はnoteで文章を書いていますが、noteには有料で文章を販売する機能があります。ITの進歩により、個人が文章を書き、物理的な「本」に拘らず、オンライン上で公開して収入を得ることができるようになりました

左は過去の状態、右は今の状態です。過去、さまざまな工程が必要だった出版ですが、現在はいくつかの工程を完全に削除、またはオプションとして選択制(あってもなくてもいい)にすることができます。

シンプルに自分の書いたストーリーをマネタイズしようと思うと、書いて、売る、それだけでいいのです。
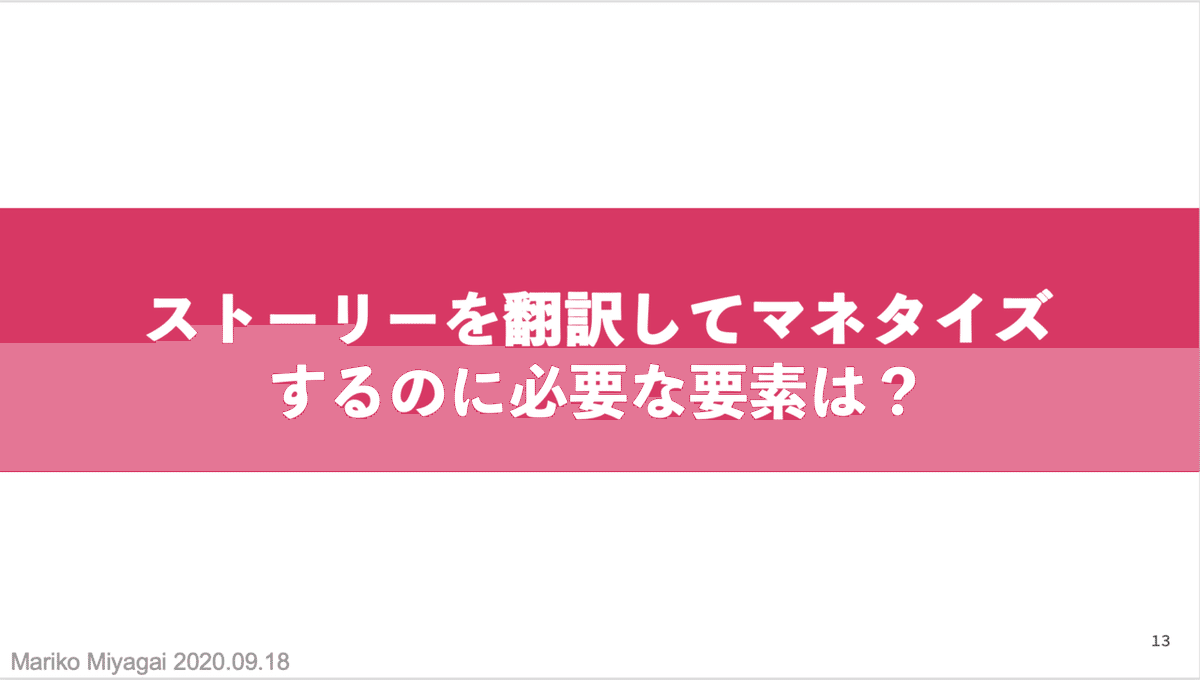
では、出版に翻訳機能を足すとどうなるでしょう。

現在多くの工程が必要ですが

だいぶ減らせます(濃赤が必須、ピンクがオプション、灰色は不要)

必須は6工程まで減らせました。

上の2工程は英語著者の話なので、MONJUでは下の4工程を扱います。

これが、「みつける」「やくす」「まとめる」となります。

マネタイズの方法としてはnoteの投げ銭やマガジンの販売と同じです。

翻訳者がストーリーの翻訳で生計を立てられるようなシステムをMONJUは提供します。
以上がプレゼンテーションの内容を少し編集したものです。みなさまのご意見等いただけると幸いです。
最後に、次世代リーダービジネスプランコンテストのスタッフの皆様、審査員の皆様、素敵な場を設けていただいてありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
