
入り口で深めるアクション
こんにちは、くらげ先生です。
最近行っている授業で、生徒の参加と自走性を高め、先生の負担をすこし下げることの出来る仕掛けを紹介します。
学校で使えるgoogleクラスルーム(共有ポータル)とJamboard(付箋ボード)などを使っています。同じ目的が達成できればほかのものでも大丈夫です。
大まかな流れ
生徒のショート発表
↓
Jamboard書き込み
↓
書き込みへの回答や深める活動
究極はこれだけですが、その中での仕掛けを解説していきます。
前提条件整備(トレーニング)
道具の使い方、踏み込み具合の体感をするため、トレーニングを兼ねて流れを理解するため、リハーサル的に同じフローの内容を実施します。
生徒のショート発表
発表する生徒には「テーマが何か」「なぜそのテーマを選んだか」「そのテーマで取り組んでいく課題は何か」「現時点のゴールイメージ」について発表してもらいます。

このとき、発表のフォーマットは統一して、話す人も、見る人も、構造を認識している状態で進めます。自由な形式で発表をさせたこともありますが、作り込みに凝り始め、中身を考える時間が減って内容が薄くなってしまいました。スライド形式もよいのですが、できることが広がる分アレンジをし始めてしまいます。
なので、上記例では、記述の構造だけを示して、手書きのマインドマップ形式にしています。※これ以前の段階で、少し、マインドマップ表現にも慣らす活動もしてあります。

※発表は、先生のカメラで手書きの資料を投影しています。昔だったらOHPでやったんだろうな・・・また、カメラで投影しているので、ついでに撮影もしてしまえば、後で提出させたり、返却したり、その間、生徒の手元に資料がなくなるということも解消できます。
※トレーニング段階では、探究テーマについて、キーワードをJamboardの真ん中に出してもらいます。
Jamboard書き込み
聞き役の生徒は、発表内容に対して思ったことを自由に書いてもらいます。とはいえ、自由ほど難しいことはないので、「疑問・質問」「話に出てこなかった観点」「提案・アドバイス」などを自由に!と伝えます。

書き込みは、考え込まず、素早く書いてもらい、次の生徒の順番に進めます。ここのフローをデジタルで行う理由がいくつかあり、手書きメモで収集すると自分の書き込みが手元に残らないし、他人が行っているフィードバックがどのようなものかわからないので、自分の書き込むレベルもつかめず不安がある。もし、オンライン対応にせざるを得なくなったときに、展開がスムーズになるなどの効果を狙っったりもしています。また、発言させるのも良いのですが、時間がかかる、発言したがらないというのもあるので、まとまりよく喋るためのトレーニングは先に伸ばしておきます。
同時に、先生が良い指摘などを拾って読み上げたり、面白がったり関心を寄せたりすることで、評価されている方向性なども掴んでいきます。
書き込みへの回答や深める活動
書き込みに対して、回答があるものはすぐに答え、回答がすぐにできないことの中から、自身のテーマに重要な内容は、知識を深めるための調査活動に展開してもらいます。
これによって、生徒の知識の幅と深さ・虫食いを減らしつつ、データソースの利用や検索技術も深めてもらう事を狙います。同時に先生側のアンテナも広がるので、次の授業までに出会った情報などを、話の素材にしたりできます。
個人面談
上記を1回行った後、調査活動を進めてもらいつつ、書き込みや後から生徒が書き足した内容などを見ながら個人別に面談を行い、進め方や観点についてサポートし、次に備えます。また、テーマによっては先生の得意不得意分野があるので、複数のタイプの先生が関われると進めやすくなるうえ、生徒も多角的に物事を捉える形になります。
これらの活動は至って単純ですが、数回繰り返すと、生徒のテーマの具体性が増しつつ、周囲の質問力も向上し、自走させる仕掛けになっていくはずです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます🎵
お読みいただいた貴重時間で少しでもお役に立てるよう今後も発信をしていきますので、応援よろしくお願いします💕
⭐個別対話ゼミをメンバーシップに用意しました
⭐探究関連のバックナンバーも是非ご覧ください
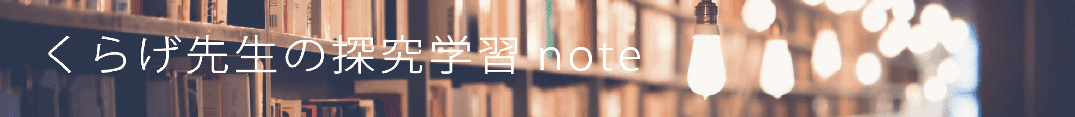
お問い合わせ
✅連絡フォームより、ご連絡ください。
内容が役に立った✨これからも読みたい📗と思っっていただけたら、投げ銭💰サポート🔯メンバーシップ👱をよろしくお願いします(_ _)
