
啓蒙時代における美学の誕生(2) ――井奥陽子『バウムガルテンの美学』をめぐって
2021年4月期に人文学講座「近代美学入門」を担当される井奥陽子さんは、昨年『バウムガルテンの美学』(慶應義塾大学出版、2020年)を上梓されました。本書の出版を記念して、昨年11月、市民講座「みんなで読む哲学入門」にて上野大樹さん(KUNILABO講師)とのオンライン対談が行われました。その中からヨーロッパ啓蒙と美学の誕生にかんするお話の一部を抜粋し、二回に分けてお届けいたします。前編はこちら。今回はその後編です。
百科全書的な体系と美学構想
上野: 修辞学はリベラル・アーツのひとつですが、リベラル・アーツを越えて、大学で教えられる学問として認められていなかったメカニック・アーツ=職人技芸――そのなかには絵画もあります――までカバーできるように、修辞学の枠組みを拡張していったと言い換えることもできそうですね。これはまさに、学問の円環的な体系をさらに広げて飲み込んでいくような動きの、その一端として解釈できるかなと思いました。その意味では、エンサイクロペディアという構想のなかに美学が不可欠な要素としてあることも、伝統的な大学で教えられてきたことを精緻化するだけでなく、その外にまで拡張し、しかも大学制度の枠組みに取り込んでいくひとつの運動のようなものの存在を示唆しているのではないでしょうか。この点、私自身とても関心のあるところです。エンサイクロペディアに注目された第2章が入ったことで、この著作に厚みが出たと思うのですが、第2章についてもう少し説明いただけますか。
井奥: はい。私も実は、第2章が一番のお気に入りです。
上野: 井奥さんとは18世紀学会で知り合ったと思うのですが、その時にこのお話をされていたような記憶があります。
井奥: そうです。日本18世紀学会で2017年に発表した内容が、第2章のもとになっています。第2章の内容を前提からお話しすると、伝統的に、アルスを2つにわける分類がありました。一つがリベラル・アーツ=自由学芸、直訳すると「自由な技術」ですが、エリートが学ぶ学問で、頭脳仕事です。もう一つがリベラル・アーツと対比的に、伝統的に貶められてきた、メカニカル・アーツ=機械的な技術、職人という身分的に下に見られていた人々が携わる、手の仕事です。拙著の第1章第3節で採りあげましたが、バウムガルテン以前のJ. P. ロイシュという哲学者が、メカニカル・アーツも厳密な理論にすることで哲学になるのではないか、と言いました。そのことが、私の推測では、バウムガルテンへヒントを与えたのではないかと思います。
バウムガルテンはリベラル・アーツのなかにあった修辞学を、論理学とセットであったという点も含めて利用したわけですが、他方でメカニカル・アーツも美学に含めようとしました。バウムガルテンは、哲学の各学科の総体を「哲学的百科事典」と呼びます。ここでの「百科事典=エンサイクロペディア」は、上野さんがおっしゃったように、書物としての事典ではなく、知の円環、百学連環という広い意味です。バウムガルテンは『美学』を公刊する10年ほど前に、「哲学的百科事典」という名前の講義を行うなかで、自身が提唱する美学の各部門についての構想を発展させました。つまり美学の具体的な構想は、大学の哲学講座のなかに知の円環的な体系を構築する、という目標のもとで練られていったのです。その点について論じたのが、拙著の第2章「哲学的百科事典のなかの美学――初期思想」です。
前回の隠岐先生との対談を聴講したときも、職人技術にまで目を向けるというフランスの百科全書派の立場は、ロイシュやバウムガルテンの立場に近いと感じました。相違点があるとすれば、バウムガルテンあるいはその先鞭をつけたであろうロイシュの特徴としては、あくまでも哲学という枠組みのなかで、哲学の一学科として理論を構築しようとした点にあるのかなと思います。その点、アダム・スミスに近いのかもしれません。バウムガルテンやロイシュは、絵画・彫刻なども含めて、職人のなかで培われてきた技術を理論的に整備することで、哲学のひとつになると考えました。それまでにない新しい学科を提唱することで、そうやって諸々の技術を哲学に組み込むときの受け皿になった、それが美学だったのではないかと思います。
リベラル・アーツ=自由学芸とエンサイクロペディア=知の円環という2つが重なったところに、バウムガルテンの美学が生まれたのだと思います。哲学における「知の円環」を確立しようとするなかで、メカニカル・アーツも取り込むための柱として、リベラル・アーツのなかの修辞学というすでにあった理論を、ちょうど当時あまり評価されなくなっていたところ、うまく作り変えることで新しい学科を創設しようとした。そういう発想でバウムガルテンの美学が生まれたものだと私は思います。
職人技芸の啓蒙思想と産業革命の時代
上野: ありがとうございます。残り時間も少なくなってきましたが、いまの話とも直結しそうなので、冒頭で述べた井奥さんの美学研究の潜在的な射程の広さという点について、アートとテクノロジーという観点から最後に触れておきたいと思います。
こちら、私が全然関係ない授業で使ってるスライドなんですけども、皆さんにイメージをしていただくためにいま見つけてきました〔図は省略〕。先ほど名前を出した『百科全書』というのは、フランス啓蒙の金字塔として名高いですけれども、こういった職人工房の様子を描いたものとか、本当に図版がたくさんあるんですよね。別冊で大量に付録として付いてます。その当時、これまでだったら知的階級にはあまり見向きもされなかったような、市民社会というか、インテレクチャルな世界からは少し隔たったところにまで眼を向けているというのがこれを見ると分かります。ちゃんと実地に赴いて観察するわけです。親方マイスターに限らず普通の人びとである職人が、どういう風にモノづくりをしているのかということに知的関心が向かうようになった。
当然、産業革命以前なので、道具を用いつつ手作業が中心なわけですが、プロト工業化(※1)という議論もありますし、また家内制手工業、いわゆる「内職」だけではなく、マニュファクチュアによる工場内分業も始まってきます。そういった実地情報を収集して、そのコツなどをできることならしっかりと観察・叙述して言語化し、そうしたコツが誰にでもいわば普遍的に共有可能な形へと変換していく試みとして、『百科全書』というプロジェクトを位置づけることができるかと思います。
※1 ここでの紹介は不正確ないし言葉足らずのため、詳細は斎藤修『プロト工業化の時代ーー西欧と日本の比較』(岩波現代文庫、2013年)などを参照のこと。プロト工業化論はむしろ、産業革命に先立って農村手工業の発展が広範にみられたということ、そのプロセスと後の工業化(産業革命)とのあいだには発生史的な連関がみられるといったテーゼを内実とする議論である(ただし同書によると、後者については本理論の提唱者であるF.メンデルスが唱えた命題はその後の経済史家の研究によって大幅な修正を受けた)。プロト工業化は主に農村地域における「問屋制手工業」の展開に関わるものとされ、工場制手工業(マニュファクチュア)の発展を産業革命の前提として重視したのはむしろ「大塚史学」(大塚久雄の経済史研究)である。両者の異同について同書第2章に有益な比較検討があるほか、戦後日本における大塚史学の継承と展開においてきわめて重要な役割を果たした小林昇について、野原慎司『戦後経済学史の群像ーー日本資本主義はいかに捉えられたか』(白水社、2020年)の第4章を参照。
井奥: 明文化されずに培われてきた技術を、共有・継承可能な知識にすることが目指されていた、ということですね。まさに、ロイシュたちと軌を一にしています。
上野: この当時まだ産業革命は本格化していません。産業革命というのは、単に発明が起きただけでは十分ではなくて、発明は確かに18世紀前半からいろいろと重要な発明がありますけれども、やはりそれが社会的な制度に組み込まれてはじめて、産業化・工業化というマクロなプロセスに繋がっていくわけですよね(※2)。
それにそもそも、発明自体も何も無いところから、それこそ天才の閃きによって生まれてくるというわけでもなくて、社会的・経済的・政治的な要求やニーズとかなりの程度セットになって、新しい機械や新製品が誕生してくるわけです。発明家が神のように無から創造する天才だというイメージは、多少とも修正される必要があります。需要があれば必ず供給が生じるわけではない一方、「必要は発明の母」という側面も確かにあるのでしょう。こういった複合的・綜合的な社会変容としての産業革命は、やはりイギリスが中心でして、18世紀後半にならないとまず現象としては明確になってきません。
例えばアダム・スミスの『国富論』初版が出版されるのは1776年ですね。これはアメリカ独立革命、独立宣言の年ですけれども、その時代でもどこまでいわゆる産業革命というものに直に接していたのかとなるとやや疑問があります。以上がいわゆる狭い意味での産業化です。
※2 生産工程への機械(固定資本)の導入に先立つ資本蓄積の重要性を唱える古典的議論、上述した農村工業化を重視するプロト工業化論にくわえて、近年では近代資本主義の発展史を直接に産業革命に結びつける生産力主義的な見方を相対化し、初期近代(特に17世紀)における市場・流通の変革や財政金融革命、企業家・プロジェクターの登場と企業組織といったマネジメント面での革新等に大きなウェイトを置く歴史観も影響力を強めている。日本人による近年の英語圏での成果として、山本浩司 Koji Yamamoto, Taming Capitalism Before Its Triumph: Public Service, Distrust, and 'Projecting' in Early Modern England (OUP, 2018) や伊藤誠一郎 Seiichiro Ito, English Economic Thought in the Seventeenth Century: Rejecting the Dutch Model (Routledge, 2020) が挙げられる。
井奥: 芸術における天才と同じく、行き過ぎた天才イメージというのは弊害になりえますね。思想でも科学技術でも、誰かひとりの人間が世界を変えたかのように語るのではなく、様々な要因とともに徐々に変化が生じた、と捉えることが大切だと思います。
上野: おっしゃる通りです。これに対して、狭義の産業革命を超えて、その背景にあった知的変動ということでいうと、私はその先駆けとなった思想史的基盤は啓蒙の発展のなかにかなり確認することができるのではないか、という感じがします(※3)。いま申し上げたような職人技芸に注目してじっくり観察し、そのプロセスをさらに分解・解析して客観的に叙述しようとする。ベーコンがスコラ哲学ともアリの方法とも区別したミツバチの方法です。そして目新しい機械の製作プロセスを再現しようとかもするわけですね。経験知・暗黙知というだけではなくて、そういった実践知を共有可能な知の形に変換しようという試みとしては、やはり『百科全書』は非常に重要な一大プロジェクトです。
※3 科学革命に端を発する知の体制の変容が、世界に先駆けてイギリスが産業化に成功し覇権を握った大きな理由だとするナレッジ・エコノミー論をめぐって、つぎの大著が翻訳された。ジョエル・モキイア、長尾伸一・伊藤庄一(訳)『知識経済の形成ーー産業革命から情報化社会まで』(名古屋大学出版会、2019年)。前掲の山本浩司の著作は、大英帝国の覇権を遡行的に説明するこうしたナラティブを批判し、経営者や学術組織に限定されない様々なアクターが各々のナレッジを駆使しながら相互的な干渉としてビジネスが展開される様を描き出している。
井奥: なるほど。それは重要な観点ですね。その点で、百科全書と多かれ少なかれ同じ志向をもった試みがヨーロッパ各地で確認できるというのは、注目すべきことですね。
上野: そう思います。そこに付け加えるならば、いわゆる市民的公共圏と公権力との中間的・媒介的な位置を占める学術機関であるアカデミーでの研究活動も大きな意味を持ちます。これは前回お招きした隠岐さや香さんの専門ですが、百科全書派のもう一方の雄であったダランベールは、晩年にパリ王立科学アカデミーの終身書記に就任しています。ディドロと距離を置くことになったとはいえ、こうしたダランベールの社会的・制度的なポジションは、いわゆる市民的公共圏の重層的な性格を示しています。そういうなかで、従来の自由学芸を主戦場とする文人たちの学芸共和国と、より民衆の側に帰属するような実践知との交流やコミュニケーションの場が生じてきた、と見ることもできそうです。そこには、国富と国力を増大させるのに産業テクノロジーの組織化が必要だという統治の思惑も絡んできて、都市政策・社会政策という面と産業政策という面とを無視することもできなくなってくるわけですが。
井奥: アカデミーというと民衆から遠い存在のように思いがちですが、ダランベールという人によって、知識人と民衆を媒介する場としても機能したのですね。
上野: ダランベール自身は、アカデミシャンとしての立場といわゆるグラブストリート三文文士も多数含まれる百科全書プロジェクトとは慎重に切り分けていて、中下層の意見をあまり好意的に取り入れたようには見えませんが(ジャンルイジ・ゴッジや王寺賢太さんが明らかにしたように後年は急進的な共和主義的言説を駆使するディドロにしても、ある出版社への手紙で自分たちの著作が民衆に何らかの形で読まれることを警戒しています)、いまいった産業政策を含むポリティカル・エコノミーの知が発展してくると、当時の意味での第三身分だけでなく、のちに言う第四階級のような民衆・群集が「統治」の対象としてですが、視野に入ってくる感じはあります。スミスも都市ポリスにかんして同様に民衆の習俗を論じています。あとは、コンドルセの時代になってくると、君主政統治に世論・公論のような民主主義的な要素を漸進的に導入する試みがより明確になってくると思います。
井奥: コンドルセも隠岐さんのご専門ですね。
上野: 詳しくは、コンドルセの科学アカデミーでの活躍と狭義の市民的公共圏での寄与を活写した、隠岐さや香『科学アカデミーと「有用な科学」』(名古屋大学出版会、2011年)をご覧いただくのがよいですね。
それとアカデミー関連で有名なところでは、ルソーのエピソードがありますね。パリに出てからはどちらかというと音楽家として活動していたルソーは、18世紀半ばに差し掛かって政治・社会思想の分野でマスターピースを相次いで執筆することになるのですが、最大の契機となるのは、ディジョンというマスタードで有名な地方都市のアカデミーが公募した懸賞論文でした。もちろんそれ以前から、マブリ家の家庭教師として教育カリキュラムを策定したり、実態としては寡頭制化していたヴェネツィア共和国でフランス大使秘書官の職務を経験したるするなかで、下地になるものは蓄積されていたわけですが。それでも、『メルキュール・ド・フランス』に掲載された地方アカデミーの懸賞課題というものが、啓蒙期ヨーロッパの言論空間の編成においてある重要なパートを占めていたということがわかります。
加えて、来年ゼミ形式の市民講座で読む予定なのですが、『人間不平等起源論』(1755年)を執筆したのは、アカデミーが「人間の不平等の源泉はどのようなものか?」という根源的問題を敢えて問うた、つまり勇気をもって問うたこと、言い換えれば、ふつうだったら臭い物として蓋をしてしまうようなことをアカデミーという公的機関が「敢えて知ろう」とした、「知る勇気を持とうとした」ことにルソー自身勇気づけられてのことだった、とのちに回想しています。以前に輪読したカントの「啓蒙とはなにか」では、「敢えて知れ」=「知る勇気を持て」が啓蒙の標語だという話が出てきましたが、これはあまり意識されていないようにも思いますが、急にカントが言い出したとか総括したことでもなくて、まさにルソーが『告白』で述べていたことなのです。いずれにせよ、地方のアカデミーがそういった問いを提出してくれたおかげで、パリの啓蒙思想家たちは、検閲のある当時の状況で正面から問うには相当なハードルがあった根源的=ラディカルな問いに向き合い、それについて学術的なコミュニケーションを繰り広げる機会を得ることができたとも言えるように思います。こうした文脈からは、『学問技芸論』(1750年)が、古代派的・共和主義的な論調のなかで、文明化、つまり学問とリベラル・アーツ発展の負の側面をレトリックと雄弁の限りを尽くして糾弾しつつも、手仕事や大地に働きかける労働に対して違った眼差しを向けているということの意味がいっそう浮き彫りになってくるかもしれないと考えています。
井奥: ドイツでも、とくにベルリンの科学アカデミーが公募した懸賞論文の課題が、その時々の重要なトピックを形成しました。たしかに啓蒙時代を語るうえで、アカデミーの存在は外せません。
上野: そういったわけで、啓蒙期のアートの概念と内実の地殻変動、自由学芸と職人技芸の再編とサイエンス(学問)観の変遷というテーマは、「啓蒙からフランス革命へ」という流れに加えて、「啓蒙から産業革命(19世紀)へ」というもう一つの流れを考えていくうえでも本質的なテーマじゃないかという気がします。都市の職人技・商工業技術や、農業技術の改良を学問的考察の対象とし、エンサイクロペディアやアカデミー、大学の講座のような社会制度の枠組みに取り込んでいくという知的運動が、国民国家と帝国主義の時代に突入していく19世紀ヨーロッパの下地を準備した部分があったのではないでしょうか。アートの地位向上は、「知は力なり」を地で行くようなこうした産業技術への眼差しの変容と、井奥さんがスコープを一挙に拡大する形で取り上げている美的アートの概念形成や実践という側面、この両面から見ていくことが大事かなと思えてきました。
井奥: なるほど。上野さんのお話で、私自身の研究がいっそう広い文脈ではどのような役割を果たしうるかクリアになり、視野が開けてきました。
上野: 最後に、今後井奥さんの研究を礎としながら考えていきたい、あるいは議論されるに値すると思う論点として、井奥さんがバウムガルテン研究を通じて同時代的な概念の外延を一挙に拡大した「美学」は、はたしてそう訳してしまってよい概念なのか? 「美的・感性的(aesthetic)」という語は「美(beauty)」を扱うにとどまらない広がりにおいて捉えられるべきなのではないか? という問いを投げかけさせていただきたいと思います。これはあくまで「発見的(heuristic)」な問いです。とりわけ、現在の制度化された美学という学問分野とそれ以外の人文社会科学の領域とを繋ぎ、交流を深めるのに資することを目指す問いかけです。
井奥: 美学研究での事情を言うと、20世紀末から、バウムガルテンが美学を「アエステティカ」と、つまり感性を意味する語から名付けた点を強調して、バウムガルテンの美学にも知覚論や感情論といった側面ばかりを期待する潮流が一部であります。拙著では、それではバウムガルテン自身の目指していた方向が分からなくなる、という立場をとりました。なので、バウムガルテンの美学はいわゆる〈感性の学〉ではない、という主張をしています(第3章)。ですが今日の対談を経て、18世紀の啓蒙の文脈から、バウムガルテンが美学という学科で何をやろうとしていたのか明確になりました。ここからは、再度「美学」を開いて捉えることが重要になると思います。
上野: ありがとうございます。今後も、学際的な研究組織である18世紀学会などを通じて、対話と議論を継続的に続けていければ幸いです。本日はどうもありがとうございました。
井奥: こちらこそ、ありがとうございました。
【了】
【登壇者プロフィール】

井奥 陽子(いおく・ようこ)
2018年、東京藝術大学美術研究科博士後期課程修了。博士(美術)。
現在、東京藝術大学教育研究助手。二松學舎大学、日本女子大学非常勤講師。
おもな業績に「A・G・バウムガルテンとG・F・マイアーにおける固有名とその詩的効果」『美学』70(1) 、2019年、"Rhetorik der Zeichen: A. G. Baumgartens Anwendung rhetorischer Figuren auf die bildende Kunst," Aesthetics 22, 2018など。
著書『バウムガルテンの美学』(慶應義塾大学出版、2020年)
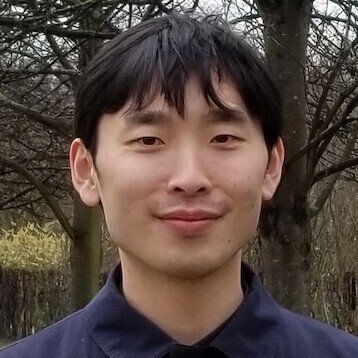
上野 大樹(うえの・ひろき)
一橋大学社会学研究科研究員。思想史家。京都大学大学院人間・ 環境学研究科博士後期課程修了。京都大学博士。 日本学術振興会特別研究員DC、同特別研究員PD等を経て現職。 一橋大学、立正大学、慶應義塾大学にて非常勤講師。 最近の論文に、"Does Adam Smith's moral theory truly stand against Humean utilitarianism?" (KIT Scientific Publishing, 2020), "The French and English models of sociability in the Scottish Enlightenment" (Editions Le Manuscrit, 2020).
【井奥先生ご担当のKUNILABO講座「近代美学入門」のご案内】
井奥先生は2021年4月期KUNILABO人文学講座で「近代美学入門」をご担当されます。
初回日時: 2021年4月22日(木) 19:30 - 21:00
日程:4月‐7月の第4木曜日(4/22、5/27、6/24、7/22)
場所: オンライン会議アプリ「Zoom」 を使用したオンライン講座
参加費: 全4回 一般8,000円/学生4,000円
詳細・お申し込みはこちらのリンクから。
【市民講座「みんなで読む哲学入門」次回イベントのお知らせ】
市民講座「みんなで読む哲学入門」では、西洋近代哲学の古典をとりあげ、上野大樹先生(政治思想史専門)と一緒に入手しやすい文庫を中心に読み進めています。現在、オンラインで実施中です。
・著者と語る 哲学オンライン対談(3): 野原慎司『戦後経済学史の群像』をめぐって【みんなで読む哲学入門・特別編】
◎日時:2021年3月16日(火)19〜21時
野原慎司先生の新刊の刊行記念です。野原先生をお招きし上野先生との対談イベントを行ないます。
・アダム・スミス『国富論』を読む
◎日時:4/13、4/27、5/11、5/25、6/8(全5回)19〜21時
2021年4月からはアダム・スミス『国富論』の一部分を先生と一緒に読みます。安価で手に入りやすい岩波文庫版(水田洋・杉山忠平訳)を用います。
KUNILABOの活動、人文学の面白さに興味や共感いただけましたら、サポートくださいますと幸いです。
