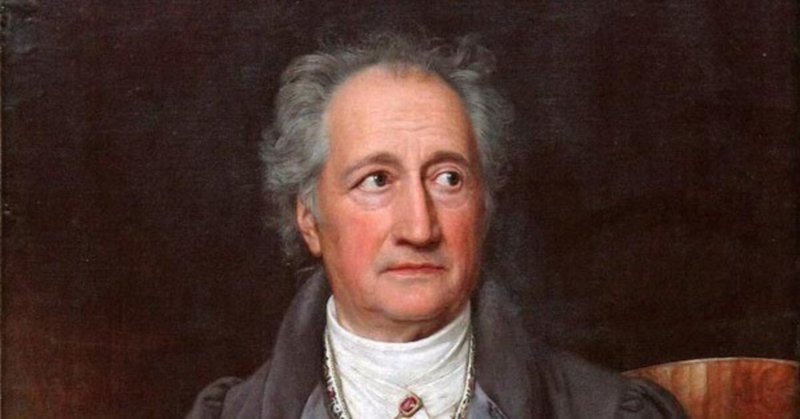2022年10月の記事一覧

再生
エッセー「幽霊城のドボチョン一家」
幽霊城のドボチョン一家、ドヒャドヒャバキ~ン。 " 幽霊場のドボチョン一家 "は、1970年11月30日 〜1971年3月29日の期間にNET(現在のテレビ朝日)系列で月曜 19:30 - 20:00に放映された。 このアニメ、日本語版の吹き替え陣が凄い。当時は現在のように"声優"というジャンルが確率されておらず、吹き替えには舞台俳優やコメディアン(今で言う"お笑い芸人”)が起用されるのが主流だった。 そうした時代背景もあり、この作品の吹き替え陣もなかなか豪華なキャスティングとなっている。 まず、ドラキュラは「オリエンタルスナックカレー」のCMで有名な南利明。子供の頃はドラキュラが名古屋弁をしゃべっていても全く違和感を感じなかった。 怪人フランケンは「あ~んやんなっちゃ~った、あ~んあん驚いた」のウクレレ漫談で一世を風靡した牧伸二。 ミイラ男は、あるマニアックな方々にはラジオ関東「男達のよるかな?」でお馴染みの名声優(当時は俳優業がメイン)・広川太一郎。「だっったりなんかしちゃったりなんかして~」の名調子が蘇る。 そして極めつけは狼男。なんと、かの由利徹。いきなり狼男が「おしゃ!まんべ!」 子供の頃に刷り込まれた記憶は鮮烈で、未だにドラキュラ伯爵は名古屋弁、そして狼男は東北弁と思っている。