
【活動録】第13回カムクワット読書会
【はじめに】
こんにちは。カムクワット読書会です。
昨日3月18日の読書会について、記録を残します。
感謝
まずはじめに、開催一週間前に参加者の方が複数人キャンセルが出たため、TwitterにてRTをお願いしたところ、多くの方々に応援していただき非常にうれしかったです。誠にありがとうございます。
おかげさまで満席とはなりませんでしたが、何とか読書会を継続できる見込みがつきました。
【自由紹介形式読書会】
3名の参加者が2冊ずつ紹介されました。それぞれ簡単に紹介いたします。
高山羽根子『うどん キツネつきの』
『首里の馬』で芥川賞を受賞した作家によるSF作品集。SFと銘打っていますが、未来的なガジェットが登場せず、不思議な出来事も「何だか不思議だな」と流してしまう。
まるでそれがふつうの出来事であるかのように。その読み心地がよい一冊。
百田直樹『夢を売る男』
変わり者の一般人に自費出版(ジョイントプレス)を持ちかける話し。出版社から一般流通する書籍はISBNコードがつきます。相手の自尊心をくすぐる謳い文句で高額の自費出版に誘導する。
作家になりたい、何者かになりたいという夢を食い物にするおかしさとおかしみ。
グレイディ・ヘンドリクス『吸血鬼ハンターたちの読書会』
猟期的な作品好きな主婦たちの集い。そこにイケメンの吸血鬼が現れる。それに気づく老婆、吸血鬼に取り入れられた旦那、吸血鬼退治を試みる主婦。
現代社会で「あの人は吸血鬼だ」と言うことは、頭がおかしくなったと思われてしまう。そんな中でどうやって戦うか。
バルガス・リョサ『都会と犬たち』
ラテンアメリカ文学に分類されるノーベル文学賞作家の長編デビュー作。軍人学校の不良グループによるテストの答案泥棒、実弾訓練による事故死の犯人探し。
物語としての面白さのみならず、三人称から一人称、過去から現在に語られる作り込まれた文章の巧みさも魅力。
今回は旧版を紹介本を持ってきていただきましたが、光文社古典文庫にもなり、『町と犬たち』というタイトルに変わっているものの、本文の面白さに差はないとのこと。
どちらもAmazonで購入できます。旧版は二段組、文庫は分厚い。わたしは文庫を探してみようと思います。
空木春宵『感応グラン=ギニョル』
Twitterにて見つけて気になっていた本書を図書館で借りました。まだ、全作品を読了していませんが、身体に欠損がある少女たちによる官能と復讐劇である表題作、性別の壁を越える「メタモルフォシスの龍」を紹介。
寡作ですが、今のところ全作品が傑作でした。
山田ルイ53世『ヒキコモリ漂流記』
「ルネッサンス」で有名なお笑い芸人のエッセイ。大人に認められるために子供らしくふるまう神童時代に書いた詩が印象的でした。
*小説限定ですが、エッセイもある種の創作であす。小説を広義の「創作物」ととらえれば今後もエッセイの紹介もありかもしれないと感じました。
赤江瀑『オイディプスの刃』
研ぎ師一家の物語。父親の割腹自殺の真相を探るというミステリ的側面、色や香りなどイメージをうまく利用している幻想的な作品。
今回は角川文庫の読み込まれた一冊をお持ちいただきました。気になったので調べたところ、ハルキ文庫、現在では河出文庫から復刊しているようです。
ピエール・ギュヨタ『エデン・エデン・エデン』
フランスの作家。中上健二が村上龍との対談で『限りなく透明に近いブルー』に近いという趣旨の発言があったらしく、紹介者はそれで興味を抱いたようです。
ストーリーがなく、話の筋を無視する地続きで改行すらない文章が特徴的。野営地を舞台に性と暴力の描写が続き、記憶には残らないがイメージが残る。絶版であるのが惜しいです。
【短歌ゲーム】
お昼時間に幻冬舎から販売されている『57577』で遊びました。5文字と7文字の手札を交換、並べ替えて短歌を作ります。


「ヤッホホゴリラ」のような独特な言葉もあり、組み合わせによって多面的な顔を見せる言葉遊び。正にこれという歌、意外にマッチしている歌が生まれました。
【課題作品読書会】
今回は島口大樹さんの『遠い指先が触れて』。参加者は1名。名作であるため、もっと多くの人に触れてほしい作品ですが、宣伝不足のためか参加者を集めることができませんでした。
しかし、参加してくださった方は「作品を面白い」くて、『トーマの心臓』の冒頭を想起したと話してくださいました。
冒頭にゴッホの耳の逸話が使われた理由は、一志の左手の指の欠損。そして、欠損しているからこそ幻の痛みは、ある種の身体拡張。肉体という牢獄から精神の解放でしょうか。
記憶と個人の関係性。既存の言葉によって定義されることの安心、苦痛。記憶を抜き取ることは救済か。
「私とは誰か」というテーマの中に、記憶と肉体、言葉、境界線などを使って、問いかける。特に物語の最後に、記憶が無くなってゆく老人を登場させることで、ある種の救いを提示しているように感じました。
【読書会後】
読書会後、ガストにてアフタートークを行いました。スイーツを食べながら、小説原作の映画の話題、読書のきっかけなどを話しました。

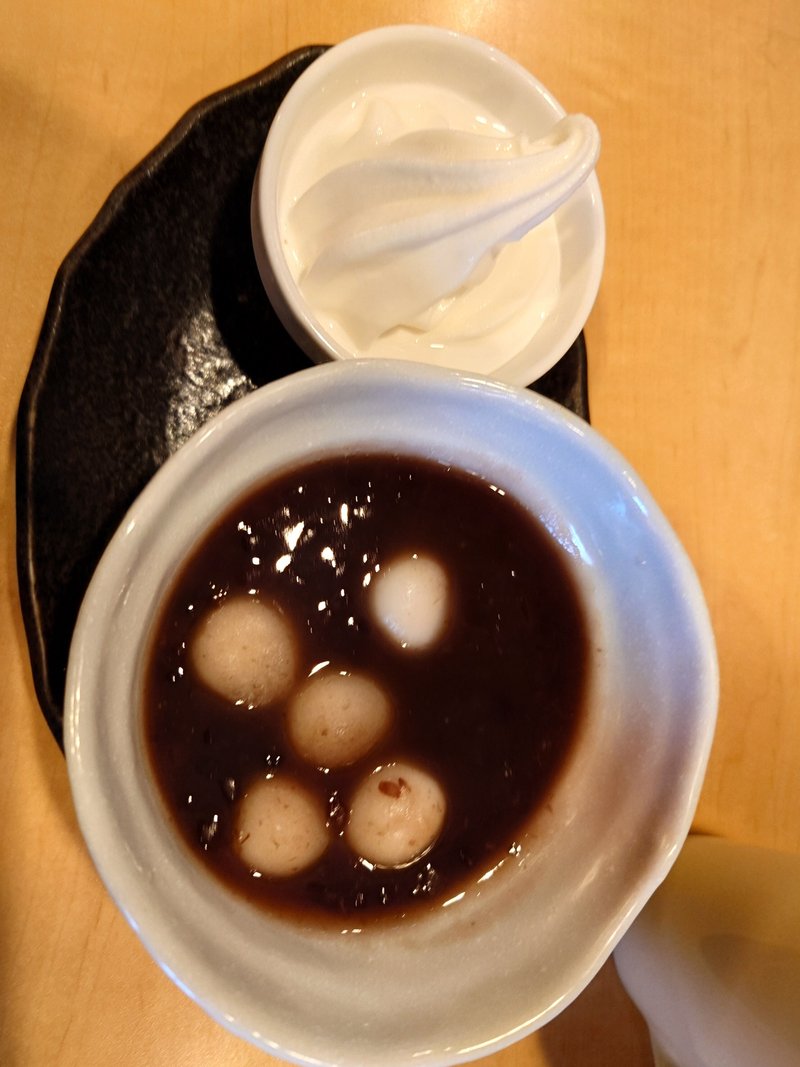
その後、ブックオフを2店舗まわりました。店内に入ると、各々が好きな棚に向かい、途中で並んでいる本についてあれこれと話しました。「芥川賞・直木賞を受賞したばかりの作品」や「なぜその本を書うか」など。

【おわりに】
冒頭にも書きましたが、今回は多くの方のご支援のおかげで、何とか読書会の開催にこぎ着けることができました。
また、読書会が終わったらさようならではなく、アフタートークや書店巡り、読書ではないゲームで遊ぶなどができて、非常に楽しかったです。
参加者の方は雨と寒さの中、お越しいただき誠にありがとうございました。
今後もさまざまな形式で読書会を続けようと思います。まずは、4月22日(土)に横浜にて読書会を実施します。
他の計画も発表予定です。引き続きお楽しみいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
