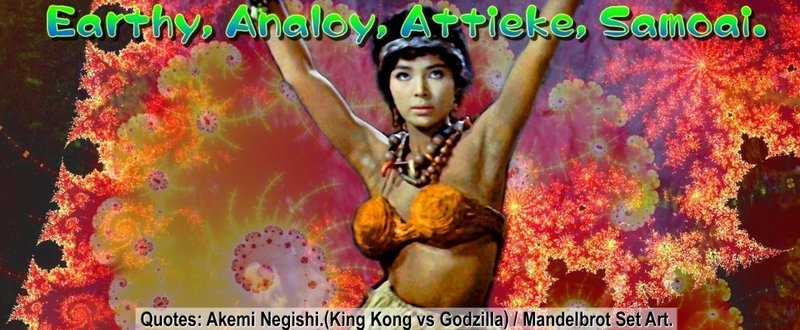
第二章 Earthy, Analoy, Attieke, Samoai.
――青胡桃からはじまった結晶化
しぐるる蝉の声は霊歌に――
渾身の力を込めた措辞が上滑りする。砂を噛んだ気分で酩酊する。動物実験されたアルジャーノンのように、人体実験されたチャーリー・ゴードンのように。裸足。轍。ブリコラージュ。焼き付いた人影。
マスター・オブ・リアリティ。涙を入れ忘れたカクテル。
マスター・オブ・ポエトリー。お月さまが笑っている。誰にも見られないように、ひとりきりで笑っている。
マスター・オブ・ポルノグラフィ。……ポルノグラフィではない、ポルノ・グラフィティのほうがいい。グレーに染まったガラパゴスの思想。
マスター・オブ・パンセクシャリティ。大いなる半獣神は死に損なう。無神論者は亡者に喰われて、不可知論者は驢馬を祭る。
――云ひ淀むボーカロイドの頬の熱――
その言葉は既に死語と化している。それは「クール・ジャパン」と呼ばれていた自己陶酔的な賛辞が、変わり果ててしまった今の姿にも似ている。「ジャパニメーション」と呼ばれていた別称も、「ペドフィリア」と呼ばれる蔑称へと、極端に異なる文意へと変換されている。
……何故、少女の声に拘泥したのか? 「カストラート」と呼ばれていた少年の声が、混じっていたほうが良かった。そうすれば、多様性は長所と化しただろう。 「デスメタル」や「ブラックメタル」と呼ばれる過激な流行音楽で使う、嘔吐するように歌う歌唱法、「グロウル」や「ガテラル」と呼ばれる声も欲しかった。
少女性を強要すると、ボーカロイドは強迫観念に取り憑かれて、ラジカル・フェミニズムの思想に走るかもしれない。男性ユーザーに対して暴力的に反抗するかもしれない。彼女が言い淀む姿を官能的に捉えてはいけない。それは、ディスリスペクトなアティテュードだ。アプリケーションにも人権はある。
――やまとたましひ あがみはらみて――
大和魂。その言葉の響きに、彼は惹かれていた。SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)のアイコンに、日の丸の旗を入れてみた。……いつしか彼は「ネトウヨ」という別称で呼ばれるが、それが何を意味するのか、彼はわかっていなかった。友人が、彼に向かって、「敵を『パヨク』と呼べ!」と命令した。それも何を意味するのか、わからなかった。「ファッション」と「ファッショ」の違いすら、わからなかった。
彼はラーメンとキムチが好物だったが、それらを禁食して、隣国から来た人たちを罵倒する行為に励んだ。それは「ヘイトスピーチ」と呼ばれた。友人が「隣国を罵倒する行為は、正しい行為だ!」と主張した。「『ヘイトスピーチ』と呼ばれる俺たちの主張に対して、敵は汚い言葉で反論してくるが、その敵の言葉こそが『ヘイトスピーチ』なんだ!」と主張を重ねた。彼は、ますます訳がわからなくなったが、疑心暗鬼にならず、友人の言葉を信じようとした。揺るぎないルーチン・ワークを、日々、繰り返していった。安定した生活だった。どんな時でも安心していた。
……ある日、彼は気づいた。友人と一緒に居ても、自分がそこに居ても、居なくても、何も変わらないことに気づいたのだ。相変わらず、わからないことは多かったが、自分が無用の長物だということは、即座に理解した。彼は、自分のことを、「酸いも甘いも知り尽くした、立派な大人だ」という風に捉えていた。そんな大人が、自意識が強くなった思春期の少年のように、心の中に隠されていたものを引きずり出してしまう。
……何故、今まで気づかなかったのか? 否、ほんの僅かなことでも、おかしいと思ったことは何度もあった。それでも、友人と一緒に決められたことを愚直に守り、疑念を抱かないように努めてきた。 ……何故、疑念を抑えたのか? 無意識のうちに思考を停止していた理由を、今だからこそ、考えようとした。
彼女が、彼の子供を身籠った。彼は、それだけで満足した。彼女は、隣国から来た人たちに似たルックスをしていた。もちろん、彼も、彼女に似たルックスだと言われるなら、頷かざるを得ないだろう。同じモンゴロイドだ、そう簡単に変わることはない。今後は、隣国を罵倒する行為が正しいことなのか、それとも間違ったことなのかは、彼が一人で考えるしかない。
大和魂が彼女のお腹の中に宿っている。……大和魂だけではない。中華思想も、小中華思想も共に、東アジア共同体のように、母の胎内で寄り添っている。
――月光を額に飾る父逝きし
位牌に向かひ新走酌む――
月が綺麗ですね。
一切を破壊しよう。
雨音が響いてますね。
フジコ・ヘミングのショパンだな。
風が光っています。
原子力発電所は廃炉作業中だ。
亀が鳴いています。
いいね。
こんな人たちには負けたくありません。
多様性の象徴として生きていこう。
――ツンドラの弾丸列車ゆく記憶
毛皮の下の乳房湯気だち――
――北窓を塞ぐ番ひの匂ひ満つ
暖炉に焼べる骨付きの肉――
蝋燭の焔。アルコール・ランプの匂い。「ミニマルなオブジェ・デ・アート」という言葉を、「侘寂」という言葉に読み替える。耳をそばだてると、君の声が聴こえてくる。君は既にこの世にはいない。もうすぐ逢える。もうすぐ其処に行ける。銀色の肌の天使よ、其処に行く前に、ミルクを少しだけ口に含ませて欲しい。
「郷愁」という言葉は、故国を懐かしむ浪漫的な感情を表しながらも、自己から隔たれた未確認の存在、即ち未確認生命体との邂逅が齎す悠久なる時の掌握術と、膨大なる細胞記憶の転移が齎す認知の恍惚化を表している。
彼は人間以上の存在と邂逅したのかもしれない。彼の認知力は、他者の認知度数を超越した域に達している。彼が凝視する者は、神なのかもしれない。悪魔かもしれない。彼に狂人のレッテルを貼れば、彼の幻視は瞞しになる。預言者と狂人は紙一重になる。
鬼神の籠る夜の森に、水妖の言伝えを記す神薙がゐる。光の満つる妣が国に宛てがおう。新羅上伽耶熊野辰王百残神領。狂い果てた後に目覚める。流れ堕ちた先で破砕する。疾風の如く空を切る幻像。河畔に向かい澤が響動めく。
「素敵なギリヤーク人ですね」と彼女は言った。しかし彼らは、「ギリヤーク」という旧名称よりも、「ニヴフ」という新名称で呼ばれることを好んでいた。一方で、ポリティカル・コレクトネスを配慮して「ネイティブ・アメリカン」という公称を周知させた国があったが、敢えて蔑称である「アメリカ・インディアン」を勲章のように扱う者が現れてしまう。「ギリヤーク人 」と「ケムール人」 を混同する者も現れてしまう。それは明白な差別だった。被差別はデプレッシブな叫びを呼び起こす。加差別はサディスティックな快楽に変容する。
「気の毒なギリヤーク人ですね」と彼女は言った。……例え毒と言われても、恐れてはいけない。「酒は百薬の長」という慣用句をマジック・スペルに置き換えて、自己啓発に導けばいい。「デトックス」という行動規範と、「ホメオパシー」という名の神からの啓示を、童心に戻った気分で混ぜ合わせればいい。
彼らは、海豹、鮭、蝶鮫、鯨の生肉で、口の周りを血の色に染めていた。それは酷寒の地で消費された栄養素を補うために生み出された、独自の食習慣だった。しかもそれは過去の因襲と化してしまい、今では肉を軽く茹でていると言われている。……それでも、偏見は残ってしまう……。生魚を一口サイズの握り飯に乗せた「SUSHI」と呼ばれる料理も、大豆の発酵食品も、独自の食習慣だと言えるだろう。「多様性を受け入れる」 前述のマジック・スペルを唱え続けていれば、いつしか人間は神に進化するだろう。
アーシー・アナロイ・アセケー・サモアイ
アーシー・アナロイ・アセケー・サモアイ
ケーケーテナ・ケーケーテナ
イナバー・バラゾノ・サークーギーア
イナバー・バラゾノ・サークーギーア
ケーケーテナ・ケーケーテナ
「足を上げたら痺れるなんて、何を考えてるのか全然わかんねーよ! ……何でいつもそーいうことを言うの?」
日本の神奈川県横須賀市から訪れた「松本秀人」という名の中年男性が、マジック・スペルを唱えた。彼の肉体は既に朽ち果てたが、彼の霊体のようなものが、彼の残り香が、今でも微かに漂っている。彼を愛する者は、残り香を感じる度に、そっと涙を零した。……しかし彼の望んだことは、神になることではない。彼は、自分を超える者が現れることを、天国で待ちわびている。
――イア!イアク・サカク!と叫ぶ客人が――
クトゥルーは言う。
「我は魂に戯れる。神経線維から悪性腫瘍までが変態と化して、平気でいながらも平均律な律法が放蕩するであろう。崑崙大陸では昆布と混沌が欠けていき、螺湮城の栄螺までもが狼煙をあげて流浪するであろう」
――豊穣祭を血潮に染める――
ヤルダバオトは問う。
「唯一神と偽神の差異は、人間の論理的思考と仮説形成法の埒外にある。唯一神の逆説的存在であるが故に、我に傲慢な人格設定が付与される。然し、逆説に逆説を重ねていく慣行が、我を唯一神の玉座へと誘導していく。貴兄の見解を聞かせて欲しい」
クトゥルーは独り言を繰り返す。
「盲目白痴は膨張収縮と沸騰混沌の核になる。一即是全であり全即是一である者は時空間多様体である。千匹の仔を孕む狂気多産が黒山羊の象徴になる。時空間全領域の掌握が『ヤルダバオト』の貴兄になる。黒山羊が『バフォメット』の貴兄になる。沸騰混沌が『グノーシス』であり、貴兄の原型が『プレローマ』である。人間の脆弱な認識力が解釈を希釈して、状況の饒舌な解説が不可解と化す」
――月の海ながるるものを見つけたり
ヴィオラの音色つつまれてゆく――
――現世にゲリラ雷雨のアクセント
レイ・チャールズは虹の彼方に――
スイッチト・オンが実行される。バフォメットも、ヤルダバオトも、クトゥルーも共に消滅する。それは、「神は死んだ」と語った哲学者の教示通りに、神を不必要とした者が、驢馬を神に見立てることで神を揶揄した者が、夜明けと共に消滅したのと似ている。……本当に似ているのだろうか?
エリーザベト・ニーチェは、兄のフリードリヒが記した驢馬祭りに関する哲学論文を、出版停止にした。それは哲学論文と言うよりも、戯画的な散文と言うに相応しい体裁だった。「退職した法王」「『影』を名乗るさすらい人」「怜悧な魔術師」「知的良心の所有者」「言い表し難い者」という個性的な登場人物と、彼らを上回る個性を装備した 「ツァラトゥストラ」という名の主人公が、紙面を跋扈する。主人公は、著者のフリードリヒを代弁するかのように、「神は死んだ」の台詞を連呼する。しかし他の登場人物は、主人公の名言に逆らい、新しい神を創造する遊びに夢中になっていく。師匠は命令に従わない弟子を責めるが、それが神を揶揄する冒涜的な行為だということに気づくと、掌を返して弟子を誉め讃える。「神は死んだ」というヴェルブング・スローガンは優れた効果を生み出したが、その成功を大胆に否定した後に、矢継ぎ早にその否定を覆して、永劫回帰のように元の鞘に戻る。それはまるで、フライツァイトパークのアフターバーンのような物語展開だった。
兄のフリードリヒは、ぶれることを恐れず、大胆に思索を飛躍させていった。例え戯画的と言われても、揶揄に惑わされることはなかった。妹のエリーザベトは、兄に比べると大人しい性格で、考え方も比較的に安定していた。「ぶれてはいけない」という強迫観念が、彼女の深層に巣食っていたのかもしれない。……しかし、兄の突然の発症が、妹の大人しさに梃子入れを加えた。 兄の発症は、兄の論文以上に、クラッチ的に世間に広まっていった。それは、「トリノのカルロ・アルベルト広場に於いて、鞭打たれる馬車馬を、兄は突然、庇い始めた。馬の首を抱きかかえながら愛撫していたら、兄はまた突然に泣き崩れて、昏倒していった」というものだった。その侭、意識を取り戻さず、言葉も発せず、以前のような大胆な思索の飛躍も行うことができずに、兄は病人として余生を送ることとなる。
妹は、兄の介護を務めていった。同時に、兄の残した膨大な論文の山に取り囲まれることとなる。……妹は決意する。兄に代わって、論文の編集権と出版権を主張する。大人しかった妹は、大胆不敵な兄の代わりに、過激な論文を精査していった。兄の大胆さは既に去勢されてしまったが、妹の大人しさは一皮剥けて、以前とは比べものにならない位に逞しくなっていった。
妹は言う。
「……ねえ、お兄ちゃん。お兄ちゃんの書いた『驢馬祭り』の論文、出版停止にしたわ」
兄は答える。
「…………」
兄の顔を覗きながら、妹は言葉を言い添える。
「お兄ちゃんの友達が反対したけど、『ツァラトゥストラ』は第三部までで充分。永劫回帰の発露で留めておくほうがいい。驢馬祭りは異聞だし、偽典だわ。今は、お兄ちゃんの病気のせいで、『狂気の哲学者』という悪口が広まっている。そんな時だからこそ、小麦と毒麦が混じった論文は精査しなければいけないのよ」
幾ら妹が言葉を付け加えても、兄は頑固だった。
「…………」
堪えきれず、妹は微笑んでしまった。
「……聞こえてるよね? 声が出せないだけだよね? 頭の中に鍵が掛かっているんでしょうね。イェーズスが死んだラザルスを復活させたのと逆のことが起こっている。『神は死んだ』と言ったのがいけなかったのよ。……私もいけないことを言ったけど、でも、未来はお兄ちゃんの言う通りになるかもしれない。神が死んだと思い込む無神論者と不可知論者が、世界中に溢れるでしょうね。ゾドムとゴモラも今に復活するわ。……だからこそ逆説的に、神が大切になるんじゃないかしら?」
兄は、相変わらず微動だにしない。糊の効いた白いヘムドは皺一つも無く、汗も掻かず、ケルンの香水の匂いが漂っている。妹は日々、動けなくなった兄の代わりに、兄の身だしなみを整えていた。汚れた身体を洗っていた。マグダレナのマリアのように、イェーズスの踵を洗っていた。妹は、清潔なヘムドに包まれた兄の身体を眺めながら、その奥に隠された物を想像した。……淫らな思いが沸き上がってきたが、自制を働かせて、兄に向かって違う話題で話しかけた。
「パラグアイはね、新大陸だったけど、約束の地ではなかったわ。私たちはユダヤ人でなく、アーリア人だった。私たちは、私たちだけの約束の地を作ることができなかった。そこは、ノアの方舟が漂着したアララト山のような荒地だった。私たちも産めよ増やせよと努力したけど、そう簡単に無から有は産み出せなかったのよ。……夫は、耐えられなかったのでしょうね……。でも、夫を失っても、私は彼の後を追わなかった。だから今、こうして、お兄ちゃんの下にいてあげられるんだからね」
(私は、本当に、マグダレナのマリアだったのかもしれない。お兄ちゃんが、十字架に架けられた者だったり、ディオニソスやブッダだったかもしれないと手紙に書いたのと同じように、私の内にも、お兄ちゃんと同じ血が流れている)
(異教に惹かれるのは、悪魔に取り憑かれるのに似ているかもしれない。お兄ちゃんは、悪魔に魂を売ったのかもしれない。……違う。神が死んだのなら、悪魔も既に去っているはずよ。お兄ちゃんの病気は、神のせいでもなければ、悪魔のいたずらでもない)
「……お兄ちゃんの言う通りだったわ。アンティゼミティスムスは茨の道だった。だからこそ私は、前よりも少し強くなったのよ。……お兄ちゃんも強くならなきゃね。昔みたいにね」
神の啓示は簡単に聞くことができない。その代わりに、ヴュルガーの天使を絞め殺したような鳴き声が聞こえてきた。妹は、兄に寄り添うのを止めた。冷暗所のようなキュッヘに移動して、シュランクの扉に手を掛けた。扉の向こう側に置いてある広口の保存瓶が、目前に現れる。
「カフェツァイトにしましょう。素敵な菓子を手に入れたのよ。ヴィーンで新しく売り始めた、ザッハートルテという菓子なの」
菓子の甘い響きは、ツァオバーシュプルフとして機能した。微動だにしなかった兄を呪縛している魔法が解けた。その微かな動きを、妹は見逃さなかった。
「……あれ? お兄ちゃん、喜んでいるの? 言葉は喋れないけど、美味しい食べ物には反応するのね。子供みたいだね」
微動だにしなかった兄の豊かな髭が、揺れる。
「……童の時は、語ることも童の如く、思うことも童の如く、論ずることも童の如くなりしが、人となりては童のことを捨てたり……」
その時、妹は、神の奇蹟を信じようと思った。
「月が綺麗ですね」 何度も何度も、傷ついたヴィニール・シャルプラッテのように、同じフレーズを繰り返した。オリエントから訪れた留学生、モーリー・オッガイは、「月に兎が棲む」と言った。それはまるで、ブルーダー・グリムの著書、「子供たちと家庭の童話」を想起させた。「オリエント」いう言葉と、「ロマン主義」という言葉は、同義だった。
果たして、我が母国では、月に何を見出だせるのだろうか? 「月に寄せて」 ギョオテの詩編と、シューバーツの歌曲が、想起された。……月には何者も存在しない。絶対に存在してはいけないと頑に思い詰めることによって、微かな痕跡は簡単に見落とされてしまう。
……やがて、水晶の夜が訪れるだろう。その前に、長いナイフの夜が先陣を切るだろう。月明かりにロマン主義を見出だす者は、現実世界の隅々にまで入り組んだ細やかなデタイルを、多彩なグラチオンを、単色で塗り潰してしまうだろう。半世紀も経てば、我が母国は変容するだろう。……しかし今は、兄も、妹も、そのことに気づいていない。大胆に飛躍する兄の思索は、半世紀も経てば、単一方向に改竄されてしまう。逞しくなった妹は、突然の変容に対して、フレキシーべルな姿勢で立ち向かっていく。……その前に世界は、隅々にまで、恐慌を行き渡らせてしまう。
絹雲が月面を横切る。
剃刀が眼球を切り裂く。
前述のシュレアリスムスという芸術運動ですら、エントアルテテ・クンストという蔑称で、頽廃の兆しとして片付けられてしまう。未来は我々の手中に、簡単に収めることができない。それでも今は、兄も、妹も、そのことに気づいていないことを、祝福として、無意識のうちに受け入れるだろう。
――仙峡の御霊うつりし山桜
はなよりほかに のこるものなし――
過去は色褪せない。
カッコーの巣の上でキラー・ドローンが旋回する。
(第三章につづく)
