
【ブックバー・月に開く】 読書会
【読書会にて ~数学は人生の役に立つのか~】
不定期で開催される店主・肥沼和之さん主宰の読書会。
課題図書があるときもあれば、“愛”や“人工知能”などテーマが決まっていて、各々がオススメの本を持ち寄るといったスタイルのときもある。
あつかわれる本は、ルポルタージュ、文学、小説、漫画などさまざま。
今まで、上原隆の“こころが傷んでたえがたき日に”、太宰治の“斜陽”、エーリッヒ・フロムの“愛するということ”、小西明日翔の“春の呪い”などがあった。
著者本人をゲストに招いて行われることもしばしば。
近所から参加する常連さんもいれば、作品やゲストのファンでわざわざ遠方から足を運ぶ方もいる。
『議論をバチバチかわす』といったことはなく、思い思いに語り合うゆるい雰囲気が特徴的だ。
今回は課題図書形式の読書会。
《論理ガール》
数学オタクですべてを論理的に思考するあまり、『低レベルな会話しかしない同世代と友達になっても、私にとって何のメリットもない』と切って捨ててしまい孤独な女子高生・詩織と、コミュ力は高いが『将来役に立たない学問はしない方が賢い』と公言する、数学が苦手なド文系アラサーホテルマンの翔太。
ひょんなことから、このふたりが『人間関係・お金・仕事・遊び・恋愛・未来』といった人生の課題に対して数学的対話をかさね、人間的に成長していく、という物語。

著者は、ビジネス数学が専門の教育コンサルタント・深沢真太郎氏だ。
彼は理学修士でありながらアパレル業界に就職し、数学を使ったロジカルな仕事で販売員として実績を上げたという経歴をもつ。
今回はゲストに、論理ガール担当編集の小谷俊介さんを招いて行われた。
参加者は3人。高校の男性教諭Kさん、経理の仕事をしている女性Tさん、そして私。
店の広さからすると参加者10人が限界なので、個人的にはちょうど良い、ゆったりとした雰囲気に感じられた。
各自、簡単な自己紹介をしてから、感想を述べる。
『友達はたくさんいた方がいい。俺は昔から友達が多い。SNSの友人も2000人近くいる』と言う翔太に対し、
『これからの時代は、ますますSNSなどのインターネットツールで人が関係性を築く時代になるはず。でも、友人が多い方が幸福だという主張は、私には正しいとは思えません。人数を自慢するだけの薄っぺらい関係を構築し、必死でそれを維持しようとしている。いまの大人は、自分を自分で疲れさせているようにしか思えません』
と、機械のように淡々と翔太を論破していく詩織に、爽快感を感じたというKさん。
さらに、あることがキッカケで、年下の男の子とデートをすることになった詩織が、翌日のデートに着ていく服装が決まっていないことに対し、「ばかばかしい。服装なんてどうでもいい」と言いつつも、一睡もできなかったという人間くさい一面にグッときた、ともKさんは話す。

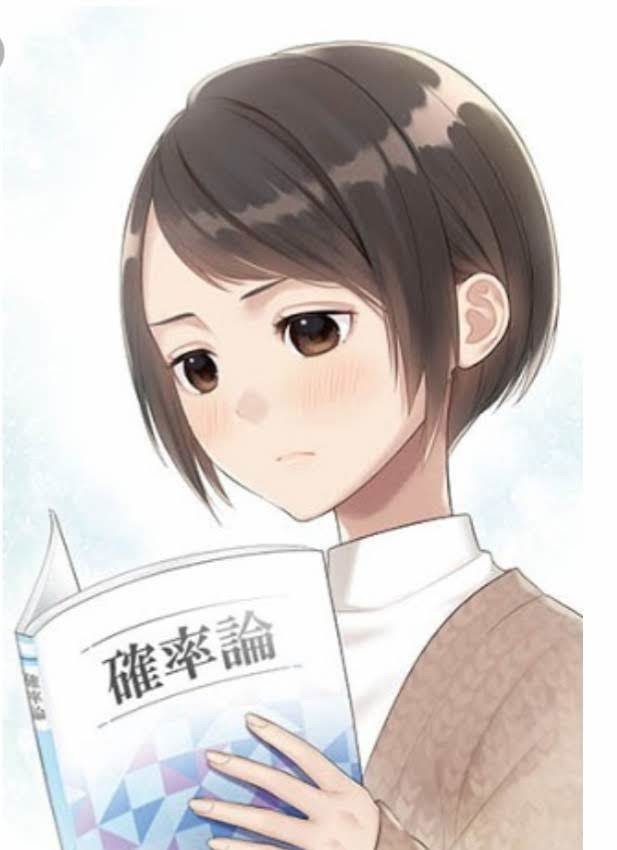
数学は苦手で、授業中かくれて本ばかり読んでいたというTさんは、「数学は苦手だったけれど、今経理の仕事をしていて、わりと楽しいんですよね。この本を読んでみて、数学の本質をちゃんと知っていたら、本当は数学苦手じゃなかったのかもって感じました」、と遠い目をして語った。
ゆったりと、思い思いの感想を語り合う参加者。
いろいろな感想が飛び交うなか、店主が銀座の有名ナンパスポットで、論理的思考を駆使してナンパを成功させようとした逸話には、思わず会場が笑いに包まれた。
さらにゲストの小谷さんは、作中の数式はあえて中学高校レベルのものを使ったということ、制作委員会方式でファンと一緒に作り上げたこと、実は著者は数学の偉人や歴史にはそれほど興味がなく、それよりも数学が苦手な人を0(ゼロ)にすることに使命感をもっているなど、編集者ならではの制作秘話や裏話を披露してくれた。
そのなかでも、とくに印象に残ったのが、制作へのかかわり方の話だ。
小谷さんは言う。
「論理ガールは、『数学って人生の役に立つの?』という疑問の答えがこの本にある、というテーマがあります。じつは私自身、この疑問を感じていたひとりでした。なのであえて自分の苦手にフォーカスした企画を、深沢さんに投げてみたんです。そうすることで編集者としてだけではなく、数学が苦手ないち読者としても、制作にかかわることができました」
編集者というものは、自分に得意分野のみで企画をするものだと思っていたが、あえて苦手分野も取り入れることで、作品を自分事にし、より良いものにしていくのだという。
さらに、著者と自身が共通して読者に伝えたいこととして、こう述べた。
「作中にもあった、『自分が中心となって、好きなことで“円”を作る』ということは、ぜひ実践してもらいたいです」
円とは、平面上のある一点から等距離にある点の集合。
自分が中心の一点となり、『好き』が共通する人たちを等距離の点とみたてて、“円”を作る。
人間関係において、その“円”の中に『疲れる』という概念はないと、作品のなかで説かれている。
その言葉を聞いて、日常生活のなかに、はたしてどれだけ円があるのだろうかと考えてみた。
学校や会社は、円よりもヒエラルキーの三角形が多い。
そして、この三角形には緊張感がまとわりついている気がする。
頂点から底辺まで、自分がどこにいようとも。
だが、この場所は“円”だと感じることができる。
店主という中心の一点から、参加者という等距離にある点の集合。
この円は心地よさに包まれている。
今までなんとなく感じていたことも、数学的な円をイメージすることで、明確になった。
数学は一部の人のための高尚な学問というイメージもあったが、本当は多くの人が豊かな人生をおくるためのツールなのではなかと、教えてもらった気がする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
