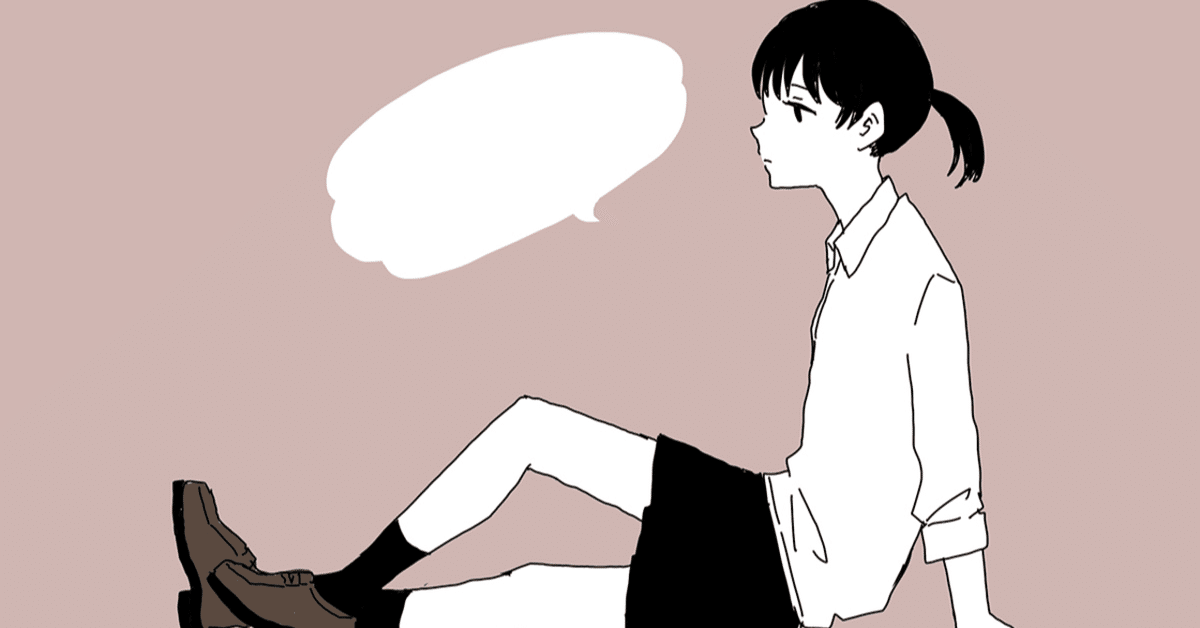
平手打ちの蹉跌
高校時代、美人で勝ち気な友だちがいた。もうずいぶん昔のことだから、どういう経緯があったのか、細かくは思い出せないけれど、ある日の放課後、階段を上がった踊り場で、彼女と彼が言い争いをしていた。交際中の2人がこじれている、とは聞いていた。見ちゃいけないとは思いつつ、気になって、少し離れた教室から、ちらちらと様子をうかがっていた。
突然、パーンと乾いた音がした。彼が彼女を平手打ちしたのだ。もちろん、手加減はしたのだろうけど、人気(ひとけ)の少ない廊下に、その音はよく響いた。私は息を飲み、こんなドラマみたいなシチュエーションが本当にあるんだと、驚いていた。
そこからがすごかった。彼女はたたかれたほうの頰を手のひらで一瞬押さえ、キッと彼をにらみつけると、こう言った。
「これで満足!?」
その場に泣き崩れるのでも、ムキになって反撃するのでもなく、たった一言、冷たく鋭利な台詞を放ち、彼女は一撃で彼を打ちのめした。虚を突かれたように彼はたたずむ。振り返りもせず、彼女は短髪を揺らしながら、悠然とその場を立ち去った。格好良かった。美人はこんな修羅場でも、とことん絵になる。
平手打ちなんてまったく最低だけれども、いまから数十年前の漫画やドラマでは、男子が女子に、女子が男子に、平手打ちする場面がときどき描かれていた。たいていそれが契機になって、頭に血が上ったどちらかが、ハッと我に返る、という展開だ。もしかしたら、彼もそういう流れを思い描いていたのかもしれない。もちろん、現実はそんなに甘くない。彼女と彼は破局した。
それからずっとあとになり、ひょんなことから高校時代の友人で、夜に食事をすることになった。彼女も、彼も、参加する。あの頃、互いに10代だった2人も、いまや立派なおばさんとおじさんだ。私の知る限り、彼女と彼の交流は、その後ほとんどなかった。たぶん、高校を出て以来の再会だ。強烈な場面の記憶があったから、長い時が過ぎたとはいえ、はらはらしながら会食に出た。ところが、拍子抜けするほど、2人は普通に談笑していた。
年を重ねても、彼女はやっぱり美しく、年下の恋人とつき合っていると話していた。既婚の彼も、年齢の割には若々しく、高校時代の雰囲気を残していた。2人はもともと穏やかで、そんなに怒りをあらわにするようなタイプではない。恋を覚えた思春期だからこそ、もつれた感情を上手にさばききれず、あんな激しい応酬になったのだろう。
「あれ、私、あなたとつきあっていたんだっけ?」。お酒が進むと、彼女は思わぬことを口にした。彼は「そうだよ。忘れたの? ひどいなあ」と苦笑した。まわりのみんなは仲睦まじく寄り添う制服姿の2人を覚えていたから、このやりとりは意外だった。平手打ちしといて「ひどいなあ」はないだろう、と内心もやもや感じつつ、あんな見事に切り返したのに、交際そのものの記憶が彼女から欠落していることに、ちょっと驚いた。
「そうだっけ? つきあってたんだっけ?」。彼女は薄く笑みを浮かべると、ワイングラスを口にして、「私、最後の一年、ほとんど登校しなくなっちゃったんだ。だから、高校時代のこと、あんまりよく思い出せないのよ」と言った。そして、彼に向かって「ごめんね」と詫びた。
彼女と同じクラスになったことはなく、不登校だったのは初めて聞いた。確か、彼女と彼は、互いに「はじめての恋人同士」だったはずだ。つきあってたのを覚えてないのは、彼女にとっての「黒歴史」だからかと思ってたけど(もちろん、それもあながち外れじゃないと感じるけれど)、それ以上に、彼女にとっては、高校生活全般が、あまり思い出したくない過去だということなのだろう。快活な美人だったから、当時はもっと、「女子高生」を謳歌しているように感じられた。本当のことは、時間が経たないと、なかなか分からないものなのだなあ。
結局、終電近くまで飲み食いし、「またね」と言って私たちは別れた。高校時代の「またね」は翌日か、せいぜい、週明けだ。でも、この年齢になると、「またね」が本当にあるか、わからない。仕事や家族、恋人と、みんなそれぞれ抱えているものがある。寂しいけれど、これはきっと、仕方がない。
「相変わらず、きれいだったね、彼女」
帰路、誰かがそう言った。
「きれいだったな」
彼が応える。
今さらだけど、彼は謝りたかったのかもしれない。謝る過去すら彼女の中にはすでになく、きっと彼の気持ちは宙ぶらりんだ。
男の子は成長しても、男の子なんだと、しみじみ思う。
いつまでも、センチメンタルに、初恋を引きずっている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
