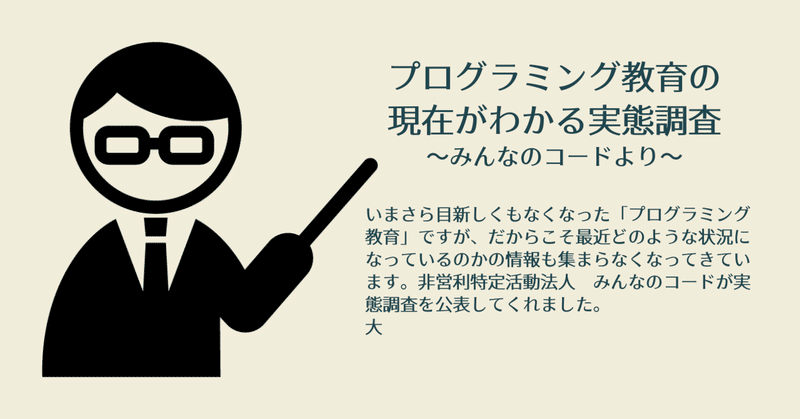
プログラミング教育の現在がわかる実態調査〜みんなのコードより〜
「プログラミング教育」という言葉を聞いてからそれなりの時間が経っています。子どもの習い事としても定番化してきており、学校教育にも以下のように取り組みが広がっています。
▼小学校:2020(令和2)年度から学習指導要領が全面施行
「プログラミング的思考」の育成を目的に、プログラミングを体験する授業の実施
▼中学校:2021(令和3)年度から学習指導要領が全面施行
技術・家庭科技術分野(以下、技術分野)のプログラミングを扱う内容が拡充
▼2025年度入試:大学入学共通テストの科目にプログラミングを含む「情報」が追加される方針
先日、「特定非営利活動法人 みんなのコード」が、プログラミング教育に関する現状を調査した報告書を公表しました。現在、どのように学校内外でプログラミング教育が受け止められているのかを詳しくみることができる調査結果となっており、大変参考になりました。
今回は、小学校・中学校教員に関する結果の一部を抜粋してご紹介したいと思います。どなたでも閲覧できる調査報告書なので、興味のある方はご覧いただくと興味深くみることができると思います。
1.調査対象者

この調査では、2021年7月に小学校と中学校技術分野の教員それぞれ約1,000名を対象としてプログラミング教育の現状についてアンケート調査を実施しました。アンケートに加えて教員12名へ個別インタビューを行っており、アンケート結果の裏付けとなるようなヒアリング内容が詳細にまとめられています。
▼小学校教員のアンケート内容
プログラミング教育に関する研修の受講状況や授業の実施状況など
▼中学校教員のアンケート内容
「D.情報の技術」の実施状況、使用した教材・プログラミング言語、課題など
▼小学校・中学校教員12名へのインタビュー内容
プログラミング教育への印象/プログラミングに関する研修の有無、学校や教育委員会の方針、学校の状況/GIGAスクールの状況/プログラミングを扱った授業、児童•生徒の反応/プログラミング教育への期待・思い/外部連携のニーズなど
また、教員だけでなく、小学生・中学生・高校生の子どもとその保護者3,000組を対象に、プログラミング教育に対する意識調査が実施されました。こちらについても、保護者16名ヘグループインタビューを行っているようです。
▼小学生・中学生・高校生の子どもとその保護者のヒアリング内容
プログラミング教育のイメージ、今後の学習意欲など
▼保護者のグループインタビュー内容
プログラミング教育への印象/(実際のねらいや授業に関する説明を聞て)印象の変化/家庭の教育方針、子供の特徴/ITの利用方針、懸念事項など
2.小学校教員の調査結果
▼研修実施時間:各教育委員会の積極度合いによる違い
調査結果によると、小学校教員の8割はプログラミング教育の研修を受講済みでした。
しかし、その研修時間には幅があり、参加した時間が長いほど、参加者の満足度は高く、プログラミング教育の実施に積極的だったそうです。実際にプログラミング教育を実施したときに手ごたえを感じる教員も多かったとのことでした。
研修時間にばらつきがある原因の一つは、校務の多忙さよりも各地区の教育委員会の積極性が影響しているようでした。
筆者もプログラミング教育実証事業などに携わった経験もありますが、確かに教育委員会の担当者によってその温度感はかなり違っていたように感じます。
▼プログラミング教育の実施:8割ほどの教員が実施済か実施予定
調査の段階では、小学校の学習指導要領施行から1年半が経過していましたが、プログラミングの授業を実施したことある教員は半数弱という結果だったようです。今後は3割程度の教員が実施予定とのことで8割程度が何らかの形で授業で扱っていくことが見てとれます。低学年担当の先生もいますので、全く実施しないという教員はほとんどいないのではないかと推測できます。
算数と総合的な学習の時間でプログラミング的思考について学ぶ機会が多いようです。
▼授業前日の準備時間:校務などで十分に準備できず
しかし、授業前日の準備に目を向けると、授業の準備時間を「十分に確保できている」と回答した教員は17.7%に留まったようです。
「必要最低限しか確保できていない」または「不十分である」と回答した理由として、ほとんどの教員が「校務」を挙げています。
二番目に大きな理由として「生活指導」が挙げられているが、2倍以上の開きがあり、校務による多忙となっている状況が明確になったようです。
特にコロナ禍への対応や、GIGAスクール構想の本格的な推進が始まったタイミングとも重なったことで、より校務の負担も大きくなったと言えるでしょう。
3.中学校教員の調査結果
▼前提として「技術」分野担当の教員の領域は広い
中学校教員のアンケート対象者は、主に技術分野担当の教員でした。
一口に「技術」といっても「A 材料と加工の技術」「B 生物育成の技術」「C エネルギー変換の技術」「D 情報の技術」その領域は多岐にわたります。世の中だと全く別の業種といっても過言ではありません。ですから、教員のよって得意不得意や専門性は大きく分かれます。
もちろん、全てにおいて指導できるようにするのが教員に求められている資質であることは確かですが、プログラミングに関する領域に関して、専門外であったり、苦手意識を持つ教員がいることも前提としてこのアンケートを見るべきだと筆者は考えています。
▼「D 情報の技術」が特に重要と考える教員は2割にとどまる
今回の指導要領で大きく変わったのは「D 情報の技術」の箇所です。この分野がプログラミング教育にあたるわけですが、他内容(A〜Cの技術)以上の重要性を感じている教員の割合は2割に留まっていました。
一方で、7割以上の回答を占めていたのが「 プログラミングも他の内容と重要度は同じ」という回答だったようです。
調査報告のまとめに
「しかし、Society5.0の社会を生きる子供たちの将来を考えると、プログラミング教育を含む『D 情報の技術』の重要性は増してきている」
との記載を見たときに、この資料を作った担当者の方のもどかしい想いを感じ取ることができました。
▼プログラミング教育に関する研修に参加している教員は半数以上
コロナ禍の状況の中、それでも技術分野における学会などの研修に参加している教員は5〜6割の間程度だったようです。指導要領の内容が大きく変わるという状況において、この割合を多いと見るのか、少ないと見るのか、は筆者にもわかりません。プログラミングに専門性を持っている教員にとってはあまり必要のない研修だったかもしれません。
ですが、プログラミング教育に関する分野における課題感のアンケートをみると「指導・授業展開の難しさ」「教員の専門性の不足」といった悩みが上位を占めていることを考えると、必ずしも十分な研修量ではなかったのではないかと筆者は考えています。
とはいえ、研修に参加しないことを一方的に責めることもできません。参加できない理由の9割は部活動にあるとしています。平日だけでなく、休日も部活動の顧問としての業務を行なっているため、研修の日程が合わないなどの原因もあるようです。
▼実は少ない授業時数
あまり一般的な話になっていないようですが、筆者もプログラミング教育のが浸透しない理由の一つとして授業時数の少なさがあると感じています。4割の先生がこの課題感を感じています。
前述した「7割以上の先生が『 プログラミングも他の内容と重要度は同じ』という回答した」理由もここに原因があるのではないかと感じています。

プログラミング的思考を養う過程として、技術を理解し、試し、試行錯誤を行い、考察をすることが重要となりますが、試行錯誤の時間や考察をする時間を十分に取れない授業時数になっています。
ですから、基本的な触りの部分だけを扱わざるを得ない状況になり、結果的に他の分野と同程度の重要度とせざるを得ないのではないかと想像してしまうのです。
調査報告には、「3時間以内でも学びを深められる情報共有をする必要があるだろう」との記載があり、その工夫としてGIGA端末を活用した反転授業が例示されていました。それでも子どもたちが学びを深める時間としてはなかなか厳しい授業時数だなと個人的には感じています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
