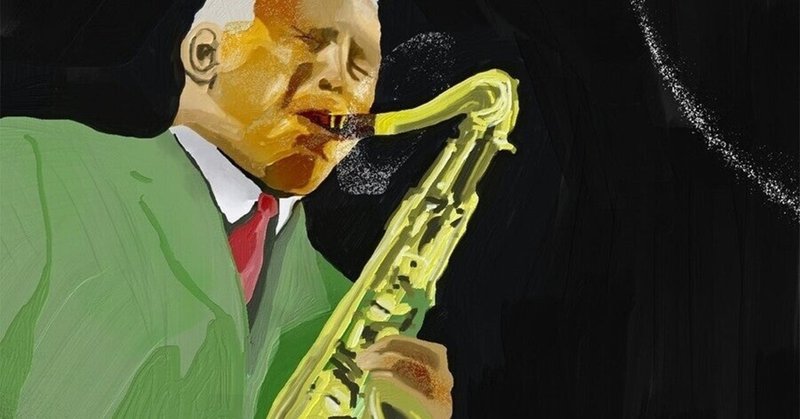
北米における20世紀から現代までのブラックミュージックの歴史3・ジャズ編
北米における20世紀から現代までのブラックミュージックの歴史1・ブルース編はこちら
北米における20世紀から現代までのブラックミュージックの歴史2・ゴスペル編はこちら
北米における20世紀から現代までのブラックミュージックの歴史4・R&B(ソウルミュージック)編はこちら
北米における20世紀から現代までのブラックミュージックの歴史5・ヒップホップ編+総括はこちら
※以下の文章は大学時代の卒論に一部動画等を加えたものです。2013年に書いたものなので一部稚拙且つ古い部分も有るかもしれませんがご容赦ください。
・ ジャズについて
・発祥1
一般的にジャズのスタートとも言える場所はニューオリンズと言われている。19世紀のニューオリンズには特定の主人を持たない自由奴隷、そして雇い主のいる農場から逃亡してきた奴隷が集まり、コンゴ・スクエアなどの街の広場で手製の楽器で歌い踊る光景が見られた。南北戦争以降には、北軍に負けた南軍の必要とされなくなった楽器(主にコルネット、トロンボーン、テューバ、クラリネット等)が質屋に大量に並び、それらを手にした黒人達は街中を演奏しながらパレードするようになり、ブラス(管楽器)バンドのスタイルが形成されていく。
・発祥2(ラグタイムとジャズ)
18,19世紀のニューオリンズはアメリカ南部一の貿易港で、貿易船の船員、乗客、そして元奴隷や失業者等で溢れかえっていた。その結果、歓楽街が発展、売春宿そしてその周辺の酒場、ボールルーム(ダンスホール)が栄え、多くのミュージシャンはそういった場所で仕事をするようになる。この時登場したのがラグタイムピアニストでもあり、ジャズピアニスト(=ジャズの創生期にあたる)のジェリー・ロール・モートンだった。彼は自ら「ジャズは自分が創った」という言葉も残しており、一部では顰蹙を買ったがこれは必ずしも間違えではない。
・ジェリー・ロール・モートンの代表曲の一つである「King Porter Stomp」
・発展1(ルイ・アームストロング)
ニューオリンズでは、終始大きな音で高らかにメロディーを奏でるコルネット(トランペット)が楽器の花形だった。ルイ・アームストロングは1910年代にコルネット奏者のキング・オリヴァーに認められ登場することになる。「サッチモ」の愛称で親しまれたルイは、並外れたテクニックと即興によるメロディー作りに非常に長け、それまで演奏で主流だった楽器同士が競い合った「集団即興演奏」に変わるメンバー個々の即興能力をソロ・パートとしてクローズ・アップする方向へ向かうきっかけを作った。またインストゥルメンタル(歌無しの演奏)がメインのジャズにヴォーカルを持ち込み、ジャズヴォーカルの礎を築いたのだ。
・ルイ・アームストロングが歌唱・演奏を披露するスタンダード・ナンバー「Dinah」
・発展2(デューク・エリントン)
第一次世界大戦後に勝利したアメリカは、1910年代の終わりから政治外交経済面で他を一歩リードする存在になった。そのような状況の中でニューヨークには既に1910年代から多くの黒人が移住し、その多くが中流階級化(=白人社会と同化)していった。そして1920年代にニューヨークに登場するのがデューク・エリントンで、
「彼の登場とその後の活躍で、ジャズ不在の金融都市ニューヨークは、新しいジャズのメッカとして注目される街へと変貌をとげました。」(相倉久人 (2007) 『ジャズの歴史』新潮社)。
エリントンはバンドを結成し、ハーレムのナイトクラブと契約を結ぶ。それはコットンクラブという名のナイトクラブで、1940年に閉鎖されるまでにエリントンの他にも前述のルイ・アームストロング、キャブ・キャロウェイといったミュージシャンが出演した。このクラブの様子を描いたのがフランシス・フォード・コッポラ監督の映画『コットンクラブ』(The Cotton Club, 1984)で、前述のデューク・エリントンにキャブ・キャロウェイ、そしてチャールズ・チャップリンといった実在した人物が登場する。
禁酒法時代(1920年~1933年)のアメリカにおいては、人々の娯楽は踊ることだった。これがスコット・フィッツジェラルドの『偉大なギャツビー』でも描かれている「ジャズ・エイジ」の幕開けである。マンハッタンにはそんな踊るためのボールルーム(ダンスフロアー)があちこちに存在し、巨大なフロアーで人々を踊らせるために音楽を提供する側のバンドの編成は次第に大きくなっていった。これがビッグバンドで、前述のデューク・エリントンやその彼のライバルだったフレッチャー・ヘンダースンは10人を超える編成のビッグバンドを率いていた。ビッグバンドの全盛はその後1930年代の終わりまで続く事になる。
・デューク・エリントンの代表曲「Take the A Train(A列車で行こう)」
・独特のスキャット唱法やダンスで知られるエンタテイナー、キャブ・キャロウェイの「Minnie the Moocher」
・発展3(ビ・バップ)
1930年代の終わり頃、ニューヨークのハーレムに「ミントンズ・プレイハウス」というクラブがオープンする。そこの売りは専属バンドに飛び入り自由というジャム・セッション方式だった。ビッグバンドに次第に飽きてきたミュージシャン達はこれを好み、セロニアス・モンク、チャーリー・クリスチャン、ディジー・ガレスピーといったその後のジャズシーンを牽引する人々が続々と集まった。
1940年代に入ると、真珠湾攻撃の影響で戦闘態勢に入ったアメリカでは多くの有望なジャズミュージシャンが兵隊に取られ、残ったミュージシャン達はますますミントンのクラブへと群がるようになる。そこで演奏されるのは入り組んだ難解なリズム等を取り込んだジャズで、新しいジャズの実験とも言える様な事が行われていた。それから戦時中の「レコード・ストライキ突入」を挟み、第二次世界大戦終了の1945年、マンハッタンにはあらゆるタイプのジャズクラブがオープンし、それらは通称「ザ・ストリート」呼ばれるようになる。そこではミントンで培われた新世代のジャズが産声を上げ、前述のディジー・ガレスピー、そして1940年代のジャズを代表するチャーリー・パーカー等が鎬を削っていた。彼らの奏でるサウンドがビ・バップ(あるいはバップ)と呼ばれるようになった。
ビ・バップを代表するチャーリー・パーカー自身が作曲・演奏し、スタンダード・ナンバーにもなった「Now's the time」
・発展4(クールの誕生)
シーンの先端を行くディジー・ガレスピーに憧れていた人物の一人にトランペット奏者のマイルス・デイビスがいた。しかし彼の様に吹けないマイルスはしだいに
「抑制のきいた独特の音色でソロをコンパクトにまとめる、密度の高い奏法を追究するようになりました」(同上)
とされている。そしてその完成ともいえるのが、木管楽器やホルンを加えた9人編成で収録されたアルバム、「クールの誕生」(Birth Of The Cool,1949・1950)だ。文字通りこれがクールの誕生ではあるが、しかしこれに前後して他の所からもクール・ジャズへの動きが見えていたとされている。
・マイルス・デイビスのアルバム「クールの誕生」収録曲「Boplicity」
・発展5(ハード・バップ)
1950年代に入り、バップに続くジャズの表現方法はクールだったが、ミュージシャン達全てがその方向へ向かったわけではなく、様々な方向性を模索している状態が続いた。そこから一歩抜きん出た存在となったのがピアニストのホレス・シルヴァーだった。彼はラテン・ビートや南部黒人教会のゴスペルの要素を取り入れた躍動感のあるサウンドで人気を博し、彼に続けとばかりにアート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ、クリフォード・ブラウン、マックス・ローチ、ジョン・ルイスがミルト・ジャクソンと組んだモダン・ジャズ・カルテット(MJQ)と50年代のジャズを代表するミュージシャンが続々と勢いを増して登場することになった。彼らはハード・バップという呼び名で通るようになった。その勢いの背景には人種差別に関わる事件の頻発、人種意識の高まり等が存在し、それらが自然とミュージシャン達の音楽に対する情熱として昇華されるようになったからともいえる。
50年代を下るにつれて、ハード・バップはゴスペルやワーク・ソング等の黒人音楽のルーツであるものを更に本格的に取り入れていき、前述のホレス・シルヴァーやアート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズに代表されるそのスタイルはファンキー・ジャズと呼ばれるようになったのだ。
「ファンキーというのはスラングで、泥まみれの労働で疲れた黒人の汗のにおいに関係した表現です。それを自分たちの音楽の看板にかかげたことは、「われわれは黒人である」という一種の確認作業 =アイデンティティ宣言とみていいでしょう。」(同上)
ファンキーという表現は後述のソウルミュージックでも登場する言葉だが、黒人「らしさ」を強調する為のキーワードとして存在するものといってよいだろう。
・ホレス・シルヴァーが作曲・演奏した代表曲の一つ「Song For My Father」
・親日家でも知られてたドラマー、アート・ブレイキーの代表曲「Moanin’」
・発展6(フリージャズ)
1950年代後半には、新たな動きが見えるようになる。アルト・サックス奏者のオーネット・コールマンは、その型破りな演奏スタイル(約束ごとを無視したコード進行、崩れた音)で正統派の人々からは嫌われていたが、その肉声をそのまま楽器に移したような吹き方等は本来のジャズが持っていた要素、つまり先祖返りに近い要素を持っていたことで、一部から注目されるようになった。そして1959年にマイルス・デイビスは、彼自身が導入した<モード奏法>の成果であるアルバム、「カインド・オブ・ブルー」(Kind Of Blue,1959)を発表した。モード奏法により、
「従来のジャズのソロは、それがニューオリンズ・ジャズであれスウィングであれビバップであれ、基本的には機能和声的なコード進行の束縛を受けていた。(一部省略)マイルスはこうした限界を打破するために楽曲のコード進行を最小限に抑え、和音ではなくスケール(音階)を中心にソロを組み立てようと試みた。これはジャズの即興演奏が(左手)の和音の束縛から解放されることを意味し、プレイヤーはより自由度の高いソロをとることが可能になったのだ。」(大和田俊之 (2011) 『アメリカ音楽史 ミンストレル・ショウ、ブルースからヒップホップまで』講談社)
とされている。
・マイルス・デイビス「Kind Of Blue」収録の「So What」
1960年代に突入すると、50年代後半から高い演奏家として高い評価を得て、その後のジャズの推移に大きな影響を与えたジョン・コルトレーンがジャズシーンの中心となる。そして彼こそが、フリージャズという形式にとらわれない自由な発想から生まれるジャンルを特に発展させた人物の一人である。50年代までは比較的オーソドックスな演奏していたコルトレーンは、60年代初頭に発表したアルバム「マイ・フェイバリット・シングス」(My Favorite Things, 1961)で彼は聴き手、そして演奏する本人達をある種のトランス状態に導くような長時間の演奏で、
「宇宙哲学を内包した霊性の世界へと昇華をつづける」(相倉久人 (2007) 『ジャズの歴史』新潮社)
ことを試みたのだ。彼は更にその後、「至上の愛」(A Love Supreme, 1964)、翌年には「アセンション」(Ascension, 1965)と更に宗教色の強い音楽を追究していく。しかし、前衛に走り過ぎたコルトレーンの音楽は聴き手とミュージシャンとの乖離を加速させ、限界に達する。1967年にコルトレーンが肝臓ガンで亡くなるとそれと共にフリージャズは急速に衰えることになった。コルトレーンの死はフリージャズの限界(あるいは死)を意味していた。
・ジョン・コルトレーン「My Favorite Things」
・その後(60年代後半以降)
1960年代の後半にマイルス・デイビスは「マイルス・イン・ザ・スカイ」(Miles In The Sky, 1968)、「イン・ア・サイレント・ウェイ」(In A Silent Way,1969)、そして「ビッチズ・ブリュー」(Bitches Brew,1969)でエレキギター、キーボードといったエレクトリック楽器を導入したサウンドを展開した。このような音楽的展開は70年代以降隆盛するフュージョンにも繋がる。しかし彼の音楽がフュージョンかと言われば疑問が残る。進化を続けた結果、融合された音楽(フュージョン)のイメージの更に上を行く彼なりのフュージョンを彼は死ぬまで続けたのである。
・最晩年はヒップホップの要素も取り入れていたマイルス・デイビスの「The Doo-Bop Song」
フュージョン(時としてクロスオーバー、ジャズロック、ジャズソウル、ジャズファンク)はジャズの要素をベースにロックやR&B(ソウルミュージック・ファンク)といったメインストリームの音楽を融合させた、難解になりがちだったジャズにポピュラーな要素を取り入れた音楽で、代表的なミュージシャンにクインシー・ジョーンズ、ザ・クルセイダーズ、ジョージ・ベンソン、グローヴァー・ワシントン・ジュニア、アール・クルー等が挙げられる。このジャンルは洗練された音の中にジャズに元々存在していたポップ(親しみ易い)な要素を取り戻し、時にボーカルをゲストに招いた楽曲は普段ジャズに馴染みのない聴衆にも親しまれ、商業的な成功を収めたミュージシャンは数多い(フュージョンは90年代以降もスムース・ジャズという名前として通用することになる)。
・マイケル・ジャクソンのプロデューサーでも知られるクインシー・ジョーンズのCMでもお馴染み「Ai No Corrida」
・ボーカリスト、ランディ・クロフォードをゲストに招きヒット曲にもなったザ・クルセイダーズの「Street Life」
これに並行し、70年代にはジョン・コルトレーンの晩年の表現を更に発展させたような前衛的思想+ファンクやR&Bの要素が強いサウンドが主にベースのスピリチュアル・ジャズというジャンルも一部で人気を博し、フュージョンと共に(時にこれもフュージョンの一部と捉えられることもある)後に既存の曲を使い新たな楽曲を作り上げる事が多いヒップホップ、クラブミュージックの音源・ルーツとして非常に若者達に価値を置かれた。現在ではサックス奏者カマシ・ワシントンがこのジャンルの後継者として名を馳せている。
突飛なビジュアルでも知られるスピリチュアル・ジャズ系ピアニスト、サン・ラとその楽団による「Take The A Train」
80年代にはウィントン・マルサリスとその兄のブランフォード・マルサリスが伝統的なアコースティックジャズに回帰するスタイルで評価され、90年代以降はスティーブ・コールマンやロイ・ハーグローブ、ロバート・グラスパー、サンダーキャットといったミュージシャンがファンクは勿論、ヒップホップを導入したサウンドでジャズの新境地を開拓している。
・ジャズ以外の様々なミュージシャンとのコラボでも知られるロイ・ハーグローブの「Crazy Race」
・近年のジャズシーンを代表する一人でもある、ロバート・グラスパーの「So Beautiful」
ジャズファンには伝統的なものを求める保守派も多く、後者のような他ジャンルや新しい要素を取り入れたミュージシャンを正当に評価していない聴き手も多い印象を受けるが、ジャズのテーマとして常に掲げられていたのは「自由」であり、他のジャンルから影響を受ける事で幾多の時代に渡って大きく進化してきた音楽の代表的なジャンルの一つなのである。
R&B(ソウルミュージック)編に続きます
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
