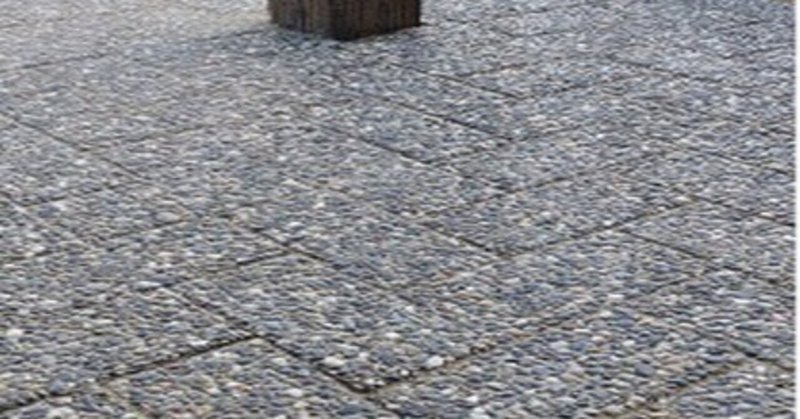
人はゆっくりと治る。
ノートで文章を発信していこうと思います。これが初めての記事です。
どうぞよろしくお願いします。
私は愛媛県西条市で公認心理師・臨床心理士として心に問題を感じる人の援助をしています。仕事の喜びは、やはり、心理面接を続けるうちに、状態が良くなる患者さんを目の前にすることです。どうして心理面接、心理カウンセリングというものはしんどい心をらくにするのでしょうか。さまざまな説明がされますが、私が実践している実感からすると、それは、「人間が本来持っている、人にうけいれられると伸びる力」が発動するからだ、と感じています。
いちばんぴったりくる説明は、「人は、自分の中に回復する力をもっている」ということばでしょうか。たとえば、風邪をひいてしまうある日のことを想像してみましょう。おおむねお母さんは「いろいろやらないで寝なさい。あったかくして横になりなさい。」と言うでしょう。食欲も落ちますし、寒気もするので愉快ではないのですが、二三日も寝てますと、おおむね薬も飲まなくても,風邪はなおります。風邪には特効薬はないのだと言います。風邪薬、といって飲むものは、ただ症状を小さくするためのもので、風邪という病気そのものを治すものではないのです。治すのは、自分の身体の中にある「治ろうとする力」だと言ってよいのだと思います。
じゃ、心の問題はどうでしょう。「うつは心の風邪」という言い方をよく聞きますが、実際にうつになった患者さんの身になれば、風邪ていどの軽いしんどさではない。そのいい方は、「風邪なら必ず治る、と思うでしょ。うつも同じ。必ず治るんだよ」とよびかけるために発明された言い方だと思うのです。しかし、しんどさのたとえには全くならない。「心の病気」というから、なにか「しんどさは気の持ちよう」と近しい関係の人からも思われるかもしれませんが、あのしんどさのことを、患者さんのご家族には、私は「ほぼ身体の病気なんですよ」とお伝えするようにしています。
ですが、いちばんしんどい状態にある患者さんでも、やはり自分のからだの中に、治ろうとする力は存在しています。そして、その力を最大限引き出して、治る力をどんどん発揮させるのが、心理カウンセリングのプロセスです。
治る力はどうしたらひきだせるのか。それは逆に言うと人はどうして心を病んでしまうのか、ということを考えると理解できるのかもしれません。現代社会は数多くの心傷つきかねない事件、出来事、そして環境にとりまかれています。現代人は子供から大人まで、たいへんです。素直に遊びたいだけ遊びたいように遊び、働くのも楽しく働いて自分のペースで生きていく、自分の気の合う人とだけつきあって、気の合わない人とは会わないようにしていれば毎日がまわっていく……そんなこと、もはや小学生の生活にもないんじゃないでしょうか。いやだけど勉強する。しんどいけど仕事する。眠いけど時間に間に合うように起きあがる。そんな毎日の中、「人はせねばならないのだ」という項目をたくさんもちます。強くしばられます。そして「せねばならないのにへこたれそうになっている」自分のことを「へこたれそうになっているダメな人間」と評価してしまうことが多いでしょう。「だめな人間」になりたくないから、たいていの人はがんばって苦しい中を、苦しいことをやり続けていく。そんな中で「ありのままの自分」はなにをつぶやくでしょう。「休みたい」。「遊びたい」。「今日はねていたい」「しばらくねていたい」「やりたいことをしたい」…けれどそのつぶやきは、もはや認められないことが多い。愚痴を言うことは、「愚痴ばかり言うな」と励まされてしまうし、悲しんでいると「いつまでも悲しみの中にいないで歩き出しなさい」と力づけられる。思いのままに悪口雑言吐いたり、おちついて泣きたいだけ泣き続けるようなことはなかなかしにくいのが現代社会。喜怒哀楽は、すべて人間の自然な感情なんですが、そのうち「怒り」「哀しみ」はもはや長々と表出しちゃいけないかのような扱いになっていないでしょうか。私は現代社会のことをそう観察しています。人に見せていいのは「喜怒哀楽」のうち最初と最後のふたつだけ。「喜」「楽」だけしか人に見せられない、ってことに追いつめられている現代人、多くないですか?
患者さんをとりまくすべての人が、間違いなく現代社会の風潮の中に生きていますから、悪気もなく、「さあ前をむこう」「そんなこと言っててもしかたないよ」とこたえてしまいます。それが現代では「ふつうの」考え方だし、「自然に」そういう考えがわいてくるのが、現代人なのです。
けれど、人は、だれでもへこたれる心も持っています。「喜怒哀楽」のまんなかにあるふたつ「怒」「哀」ももっています。だけどそれが認めてもらえない。認めてもらえないことが続き、それが通常運行状態になると、自分自身がその自分を認めないということを学習し、身につけます。「ありのままの自分」が好きだ、ということにはなりにくくなります。「ありのままの自分」がいやだ、という状態は、つまり、自己肯定感が低い状態です。自己を愛するきもちが小さい状態。それでは元気が出ません。そういう長い「通常運行」状態が続いた結果、心がしんどくてたまらない、という症状を発するのでしょう。
心理カウンセリングでやることはおおざっぱに言いますと、基本的なことです。「ありのまま」を受け容れる会話、です。患者さんのありのままの心、きもちをお聞きします。ありのままを受け容れます。そうしているうちに、少し時間はかかりますが、患者さんは楽になっていきます。治っていきます。きっと、受け入れてもらえる体験自体がとても珍しい体験になるのじゃないかと思います。そして受け入れてもらえる時間がしばらく続くと、自分の中にある「自分のことを受け容れる」臓器が動き始めます。そんなイメージです。今まで動いてなかった臓器が動き始めて、すると自分への肯定感がじわじわとあったまります。自分を愛するきもちがあったまってきます。すると自分をとりまく周囲のこと、条件のことが怖く見えすぎていたのが、おちついてニュートラルにながめられるようになったり、すると実際に合理的な行動が少しずつできるようになったり、すると自信も少しずつ持てるようになったり…
どこからどう見ても出口など見えない、というように感じていた心が、ありのままの観察力をとりもどす、ということが実現します。
基本的ですから簡単そうに聞こえるかもしれません。が、なかなかこれが現代人には意外とむつかしいのです。心がけひとつで、その患者さんのきもちをすべて受け容れることくらいできるのか、というと、それほどこれは容易ではないものです。なにしろ実際のところ世の中はきびしくて、だれにも頼っちゃいけなくて、自分一人でなんとかしないと生き残っていけない……ように見える。そんな甘いこと言ってたら、世界の進行から取り残されるに決まってる……ように見える。そんな世界の中で、ありのままの心はどうやったら受け容れつづけられるのか?
これが、専門職としての心理カウンセラーのうでのみせどころです。専門職の技能はそこにむけて訓練されていますし、しかしそれだけでは不十分で、私たち心理カウンセラーは年々の心理面接の経験の中で鍛えられていくのも実際のところです。
ただ、「いっしょにどうしたらいいか考えていきましょう」と寄り添う立場に徹底することが、患者さんを孤独の状態から少しは希望の持てる状態に連れ出せるのだとは信じます。私は「よりそっていきますよ」という約束を患者さんに受け容れてもらうこと自体が、治る道のスタートになるということを確信しています。
心のことでしんどい状態におられるあなたに、希望をもって治るみちへのスタートを切ってもらいたい。そう思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
