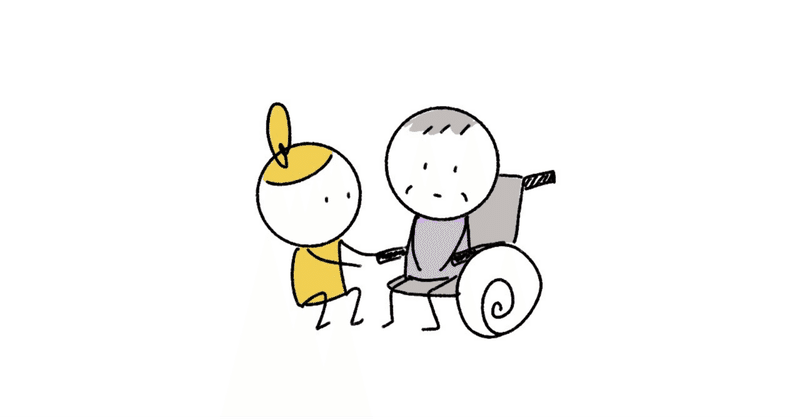
なぜ全く理解できないのか
父が老健施設(介護老人保健施設の略。在宅への復帰を目標とする介護サービス施設)から特別養護老人ホームへ移ってしばらくした頃のことです。母と一緒に、父のいる特別養護老人ホームに行って、「ケアプラン会議」に参加しました。ケアプラン会議とは、ケアプランの情報共有や意見交換をする会議です。参加するのは、ケアマネジャーや利用者とその家族のほか、医師、看護師、理学療法士が加わる場合もあります。「サービス担当者会議」と呼ぶこともあるようです。介護対象である父も同席しました。
私は初めて参加したのですが、全く、本当に全く内容が理解できないまま、会議が終わってしまい、呆然としていました。私は行政の職員をしているにもかかわらず、それはもう、笑ってしまうくらい分かりませんでした。会議は15分程度で、関係者の方々が父の状態について、順番に説明していましたが、全く頭に入らないまま終了しました。
ただし、ここで書きたいのは会議の批判ではありません。会議の終了後に、呆然としていた私たちに、スタッフの方が、個別にとても丁寧に説明してくださり、感謝しています。
私が書きたいのは、普段ファシリテーターをしている人間としての教訓です。どうして分かりにくかったのかを振り返ってみます。
1 会議の名称、テーマ、目的やゴール、終了予定時間が共有されていなかった。
2 配布資料の説明がなく、何の資料なのかが分からず、また資料に掲載されていることを説明しているのかそうでないのか分からなかった。
3 私たち家族は、普段の父の様子が分かっていないのに、補足的な説明がされていた。
4 拘縮(こうしゅく)といった専門用語が多かった。
5 父は父で「ちゃんと歩けるよ」といった誤情報を発信していた(本当は歩けないのに。そしてスタッフも本人の前でそれを否定できなかった。)。
会議の進行方法については、そのときどきに参加者としてきちんと質問して確認すれば良かったという反省があります。主催者だけでなく参加者も会議をつくることができます。
そして何より感じたのは、圧倒的な情報格差です。普段、日常的に父と接して介護やケアをしている人たちと、コロナ禍で月に一度10分間しか面会できていなかった家族との情報量が雲泥の差だったのだと思います。
「基本的な情報の共有なくして、議論は始まらない」という良い教訓となりました。私自身も会議を運営するときに気を付けたいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
