
大枝亮さんに聞く「漂着鯨類の研究とは?」
今回はプラスチックが鯨類に与える研究をしている大枝亮さん(筑波大学)にお話しをお聞きました。
鯨類研究において、漂着した鯨類を扱うことの重要性について語っていただいたインタビューです。
大枝さんはなぜクジラの研究を?
佐々木:大枝さん、本日はよろしくお願いします。
大枝:よろしくお願いします。
佐:今回は事前に「海獣学者、クジラを解剖する。」を読んで来て色々と質問したいこともあるのですが、まずは簡単に大枝さんの取り組んでいる研究についてお伺いしたいです。
www.yamakei.co.jp/products/2820062950.html
大:私の専門はクジラのおなかの中にあるプラスチックになります。プラスチックがクジラにどういう影響を与えているのかを知りたいのが大きなモチベーションです。最近だと、色々なところでプラスチックがやばいよと言うけど、本当にやばいのは何で、生物に対してどの程度影響を与えているのか知るために研究をしています。

実際に首にプラスチックが絡みついちゃって成長が止まっちゃったりとか、動きが阻害されて死んでしまったりみたいなことが起こっているわけで、目の見える形で分かっているものもあります。
あるいは実際に打ちあがったクジラのおなかを開けてみて、明らかにこんな量のプラスチックを食べたら死んじゃうよね、みたいな量のプラスチックが発見されたりしています。
ただ、このような形で大量の生物が死んでいるかというとそういうわけでもなくて、きっとレアケースではあると思うんです。
佐:言われてみると、そうかもしれませんね。
プラスチックから考えるクジラたちのこと
大:はい。プラスチックだけで死んだという表現には違和感がありますし、じゃあ、プラスチックがどの程度生物に影響を与えているのか。まだよくわかっていないだけで多くの生物に何か悪い影響を与えているのではないか。あるいはプラスチックの存在が生態系全体ではどのような影響を与えているのか。
例えば、プラスチックが首に絡まって死ぬウミガメがいたとしても、そのカメがいわゆる生物が増えていく中で、自然淘汰的に消えていく範疇であれば問題ないと言えば問題ないとも考えられるわけじゃないですか。そういった意味でも、プラスチックが個体に与える影響と生態系に与える影響についても考えています。
佐:確かにプラスチックの影響をよく知らないままに、イメージだけが独り歩きしている印象はありますね。
大:基本的に我々が環境に与えている影響の中でも既知の危険と、今我々が知り得ていない未知の危険があると思います。
今私がやっているのは、プラスチックが持っている既知の危険、あるいは想定されうる危険とでもいうんでしょうか。こういうことが起こっているだろうなという仮説を確かめる研究をしているわけです。そのような仮説がクジラで実際に起こっているのを確かめた上で、未知の危険についても調べていくことに意味があると思うんです。
そういう意味で環境分野において、クジラを研究対象としてプラスチックの影響を研究するのは大事だと思っています。
あと、クジラを研究対象とする意味としては、クジラが非常にアイコニックだというのもあります。魚の中からプラスチックが出たというよりもクジラやイルカからプラスチックが出てきたという方が、市民の皆さんは結構身近に感じてくれることが多いと思うんですね。
何というか、私の印象ではあるのですが、クジラも哺乳類なので、人間でも同じことが起こり得るというのを魚以上に言える生き物だと感じています。
佐:確かに今でこそ鯨類が哺乳類であるというのは周知の事実として世間的にも認識されていますが、そうじゃない時代もあったわけですよね。よく考えてみると、あんな風に海で優雅に泳いでいる大きな魚のような生物が同じ哺乳類というのはとんでもないことですよね。
海に棲む哺乳類たち
大:海に棲む哺乳類って書いて海棲哺乳類(かいせいほにゅうるい)と読むのですが、この海棲哺乳類を研究する意味の1つに、我々人間と同じ哺乳類が海に戻っていったというのがあると思います。鯨類や鰭脚類、海牛類など、そういった海に帰った哺乳類のグループを研究することで、陸の哺乳類を改めて認識することができると感じています。
海棲哺乳類データベース:海棲哺乳類図鑑 (kahaku.go.jp)
ひいては我々人間についても理解が深まるという風に、どんどん繋がっていくというところもこの研究の面白さだと思います。
佐:なるほど、木を見て森を知るじゃないですけど、クジラを見てヒトを知るという観点は非常に興味深いですね。
ストランディングとは?
大:私の研究テーマはプラスチックがクジラに与える影響なんですが、1)ストランディングというキーワードをもっと取り上げていく必要があると考えています。

最近、ストランディングについてどのくらい知られているのかアンケートをとってみたのですが、現状としてあまり知られていないことを改めて認識させられました。
佐:ストランディングですね。それこそ、私の場合は海洋大学でそういう話題に触れる機会があるので知っていますが、世間一般にはあまり知られていないというのは同意です。淀ちゃんで少しこの言葉を知った人は増えたのかなという気はしますが。
1)ストランディングとは、鯨類が生きたまま海岸に乗り上げて身動きがとれない状態(座礁)を意味する。厳密には死体の漂着と区別する場合があるが、一般的には生死を問わずに海岸に到達したものすべてをストランディングと称し、複数の個体が同時に座礁することをマスストランディングと呼ぶ。またストランディングを救護の対象として扱う観点からは、水棲哺乳類(鰭脚類、海牛類およびラッコを含む)が「自力で対処できない」すなわち人為的な救護を必要とする状態をすべてストランディングと呼び、この意味でイルカやアザラシなどが本来の生活水域から離れて港や河川の奥に迷入する現象もストランディングに含まれる。
大:日本だけで考えると年間に300件以上のストランディングが報告されていて、つまり毎日日本の海岸のどこかにクジラの仲間が漂着している計算なんです。
このストランディングした個体を用いて、我々は研究をしているので、漂着鯨類という言葉についてもっと大々的に知ってもらう必要があると感じています。
というのも、国際的に見たとき野生の大型哺乳類を捕獲して解剖して研究するという流れは現在ないんですよね。倫理的にも、それから保全の観点からその傾向は今後も変わらないと思います。日本も現在は商業捕鯨をやっていますが、あくまでも商業目的なので純粋に研究としての捕鯨は行っていないわけです。
そう考えると、鯨類の研究をやる上で、ストランディングした個体を用いることは不可欠なんです。
漂着鯨類を研究対象とする理由
佐:なるほど。私なんかはずっとイソギンチャクの研究をやっていて、周囲も無脊椎動物をやっている人が多いので、どこかで生体を採って標本にするというのが当たり前のように感じていますが、大型の生物、そして何よりも哺乳類であることを考えるとそもそもの研究のハードルは高いわけですもんね。
大:そうなんです。例えばイワシが何を食べているのか知りたいというのと、イルカが何を食べているのか知りたいというのでは、そもそも解剖する個体を手に入れるという点でも難易度が違います。
それから、私がメインで研究対象にしているのがアカボウクジラ科というクジラなんですが、そもそも生態情報があんまり分かってないんです。
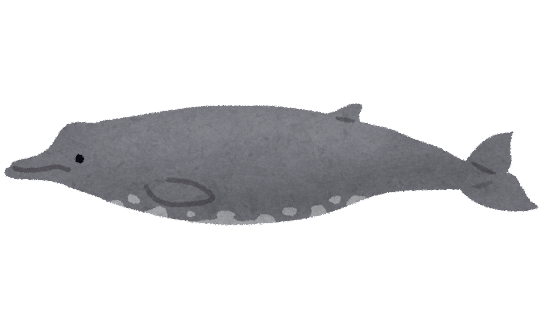
佐:なるほど、アカボウクジラ科っていうんですね。このクジラはどういう特徴があるんでしょうか?
大:アカボウクジラ科はとても不思議なクジラなんです。
まず、漂着だけでも片手で数えるほどの報告で、世界中で見ても漂着事例が数えるほどしかない種もいるんです。アカボウクジラ科の仲間は、基本的に大きな群れを作るわけでもないですし、結構深くまで潜ってしまうので、呼吸するために海面に上がってくるわずかなタイミングを狙って観察しなくてはなりません。目視観察(船の上から野生の鯨を観察すること)を研究者も行うのですが、実際に船を出して必ずそれが目撃できるかというと、そういうわけでもありません。

非常に目撃するのを難しい種類で、個体数が多いのか少ないのかも分かっていません。それこそ情報不足過ぎて研究もなかなか進んでいません。そのせいもあって、2)絶滅危惧種のリストでは情報不足という扱いになっています。こういった種類の生物は偶々漂着した貴重な個体を使って研究をするのが非常に有効になります。
2)アカボウクジラ科21種のうちIUCNレッドリストカテゴリーで、低懸念LCが2種、データ不足DDが19種となっている。低懸念種はアカボウクジラとミナミトックリクジラの2種に限られ、アカボウクジラ科全体ではデータ不足が大半を占め、分布状況や個体群状況がまだまだ明らかになっていない。
佐:捕鯨という文化が根付いている日本では特に漂着鯨類への認識は低いかもしれませんね。クジラの研究も捕鯨した個体を使ってやっていると思っている人は多いと思います。
大:実は、捕鯨対象種っていうのは数種に限られるんです。
クジラやイルカの仲間は世界で約90種類なんですけど、そのうちいわゆる捕鯨の対象となる種類はだいたい10種類ぐらいだと思います。地域によっては小型のイルカを獲っていますので、 そういう種類を全部合わせて、多めに見積もっても20種強くらいだと思うんですよね。
捕鯨ではおよそ20/90種しかその対象とならないので、その中で研究をしようとすると、相当狭い範囲になってしまうわけです。日本人がお刺身とかで好んで食べているのはヒゲクジラのナガスクジラ科という種類になるのですが、このグループは口の中にクジラヒゲと呼ばれる器官が生えていて、オキアミなどを濾しとって食べるんです。
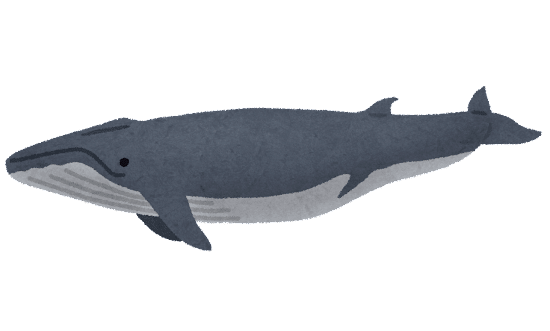
つまり、捕鯨に限定するとこのような種類のクジラしか研究できなくなってしまいます。イルカ類を獲っている地域も限定的ですし、一昔前ならマッコウクジラも獲られていましたが、現在はほとんど獲ってないですよね。ヒゲクジラの研究に偏らないためにも、漂着したクジラを使った研究を進めていくことは、広くクジラを知る上で重要になると考えています。

佐:なるほど、では漂着鯨類という分野が捕鯨の代わりとして発展してきたわけではなく、捕鯨で扱われないものも含めて様々種類の鯨類を研究するために発展してきたというような感じですね。より純粋科学としての側面が強いというのも印象的です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
