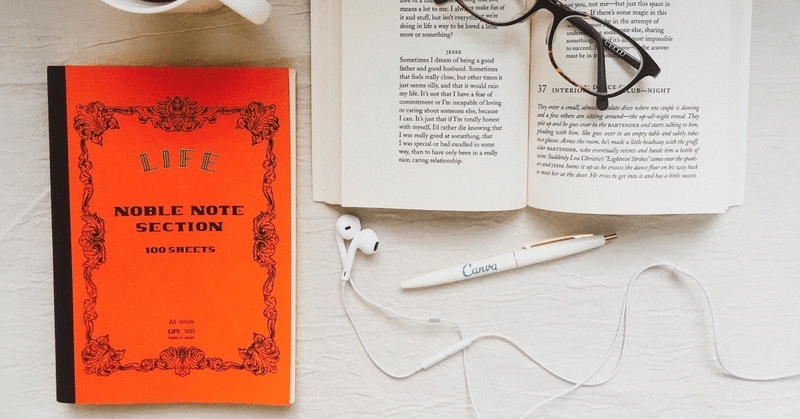
小理屈野郎の読書ノート最前線 改良の続く読書ノートについて思索する
デジタル読書と著書の読了時につける読書ノートは小理屈野郎にとっては常に改善を指向する大事なもの になっています。
以前にもいろいろな変更をして、それに対してnote記事をアップしていました。
読書ノートも記事をアップした以外に小変更 は数回行っており、それについて今回は思索してみます。
まずはじめにやったのは、出口氏のアドバイスにヒントを得た ことです。
出口氏のアドバイス
そのアドバイスとは、再読をするときどんなときにしたいか、ということでした。
具体的には読書ノートの質問の中に
どんなときにこの本を再読したいか?
というのを入れてみました。個人的には元々再読の習慣があまりない こと、そして気分、といってもうまくいくかなあ と思いながら、しばらく(約100冊分の読書ノート)質問に回答してみました。
実際にこの質問を使って再読することもなく、これはあまり意味がないなあ 、と思いながらも情報なのでなんとなく入力は続けていました。
そんな中に出てきたのがZettelKasten法に関する著書 でした。
、ZettelKasten法に準拠し、自分の環境に順応させるように読書ノートやそれを保管しているEvernoteのフォルダ構成を変えてみました。
そのときに同時に読書ノートの質問構成をいじってみました。
ZettelKasten法に準拠したノート構成に変えてからの変更点
まずは前述の再読したいシーンを記録することについては、えいやっとやめてしまう ことにしました。
その代わりといっては何ですが、検索ワードを入れる ことにしました。
ZettelKastenのフォルダであるPermanent notes用(note記事など自分のアウトプットや完成した思索のノートを収納しています) と、別のフォルダのLiterature notes用(読書ノートなどを主に収納しています) の2つに対する検索ワード記入する欄を設けることにしました。
検索ワードについてはZettelKastenでは1~2語とすること、一般の検索で引っかかりにくい言葉、将来もう一度見つけてみたいと考えられる言葉を検索ワードとするように 、としています。ですので、2つの検索ワードの質問があるので多くても4つまで、ということになります。
あえて、検索ワードを分けたのは、Literature notesフォルダだけを検索する場合と、Permanent notesフォルダの思索を拡張しようと思って検索するときのキーワードが微妙に変わってくるかもしれない 、と考えたからです。
さらに検索ワードの前にハッシュタグ(#)をつけ、マークダウンで使うハッシュタグと区別するためにハッシュタグの後に半角スペースを入れない ようにしました。(マークダウンでハッシュタグを使うときは、ハッシュタグの後に半角スペースを入れる必要があるため)こうすれば、ハッシュタグの後すぐに検索ワードを入れれば検索ワードで検索できることになります。
さらに、Indexフォルダ(検索ワードをまとめたノートを格納するフォルダ) があるのですが、そこに検索ワードを50音順に並べていく ことにしました。検索ワードには紐付く読書ノートを内部リンクで張り、すぐに見にいるようにしています。
実際のワークフロー
なんだか言葉で書いてもなかなか分かりにくいですね。
リストでワークフローを整理してみます。
ある著書を読みだすときに読書ノートを用意する。具体的には、新しいテキストファイルを用意し、そこに読書ノートのひな形を貼り付ける(後でひな形についてはお見せします)。
同時に質問の中にある、その著書を購入に至った背景についての質問があるので簡単に記載しておく。そして読書中に得たいものなどもあればその質問のところに書いておく。
デジタル読書で読了したら、可及的速やかに読書ノートののこりを記述する。(できるならば読了直後、無理でも数日以内に作るようにしています)
質問を見ながら自分で思索をしながら文章をまとめていくのと同時に、特に大事だと思うところは実際にポメラで書き写しながら自分の意見を書くこともあります。
結構面倒くさそうに思われますが、早いものだと30分、時間がかかるものでも1時間から1時間半あれば完了します。
できあがった読書ノートをポメラのアップロード機能を使って自分のGmailのアドレスに送ります。
Kindleハイライトのページに入り当該著書のページを開きます。そしてその内容をすべてEvernoteウェブクリッパーでEvernoteに送ります。
Evernoteで先ほど作ったノートを確認。編集できるようにウェブクリップから編集できる形式(簡略化して編集可能にするを実行する)にします。
先ほどGmailに送った読書ノートの内容をコピーし、Evernoteに貼り付けます。
Evernote上にキーワードの欄を設け、上記のように最大4つあるキーワードを貼り付けます。
キーワードをコピーしIndexフォルダに入っている索引のノートに貼り付けます
作成中のEvernoteの読書ノートに戻り内部リンクをコピーのところからアプリリンクをコピーします。
索引のノートに戻り、コピーしたキーワードの後にリンクをそれぞれ貼り付けます。
それぞれのキーワードを50音順に並べられているその他の索引の中に挿入します。
これで完了です。
ワークフローは文章で説明すると結構不便ですが、ファイル操作部分は実際にやると数分で終わる感じです。
ZettelKasten準拠の読書ノートを作成しだしたときは、このあたりのワークフローの細かいイメージがうまくできていなくて、少し混乱しましたが、ちょうど時期としては隔離自宅療養を行っていた時期と重なったので、時間に余裕を持って肌間隔に持って行くことができました。
※ちなみに私が現在使っている読書ノートのフォーマットを以下に示しておきます。
もし利用したい、とおっしゃる方がいらしたら遠慮なくご利用下さい。改変も自由です。
参考にさせていただきたいので、もし可能であれば、改変した場合はその部位と理由を教えていただければ幸甚です。
読書ノートフォーマット
書名
読書開始日
読了日
読了後の考察
キーワードは?(Permanent notes用)
(なるべく少なく、一般の検索で引っかかりにくい言葉、将来もう一度見つけてみたいと考えられる言葉)
質問1 概略・購入の経緯は?
質問2 本の対象読者は?
質問3 著者の考えはどのようなものか?
質問4 その考えにどのような印象を持ったか?
質問5 印象にのこりったフレーズやセンテンスは何か?
質問6 類書との違いはどこか
質問7 関連する情報は何かあるか
質問8 キーワードは?(読書ノート用)
(1~2個と少なめで。もう一度見つけたい、検索して引っかかりにくい言葉を考える)
まとめ
使用感
ZettelKasten法準拠で運用し始めてから新しくできたのは索引のノート ですが、これ、結構良いかもしれません。毎回新しいキーワードを挿入していきますので、その他のキーワードも一覧で見る ことになります。あ、こんな本読んだな、とかあ、こんな話があったな、などがあり、そこでなんとなくひらめいている こともあります。
ZettelKasten法再考
読書ノートをZettelKasten法に準拠して運用しだしたのですが、私のZettelKasten法ではひょっとしたら大きな問題として認識されるかもしれないこと があります。
それは、一つのノートが一つのテーマを扱っているわけではない ところです。原法では大原則として一つのノートには1つのテーマしか書かない、と言うものがあるのです。
オムニバス系の著書を読んだ後に作る読書ノートなどは、いろいろな内容が満載になっていることもしばしばあります。
今までの読書ノートの記録が結構あり(850冊分ぐらいあります。細かく読書ノートを取り出してからのカウントでも250冊前後はあります)それらをすべて準拠するために半ば作り直しに近いことをしなければならないとするとものすごく時間を食ってしまう ことが一つ大きな理由としてあります。
もう一つの理由としてZettelKasten法では1ノート1テーマで検索性をあげる、というのが目的の一つであったようで、アナログで検索性をあげる 、というところもポイントのようです。ですので原法ではさらにノートの一つ一つにはある一定のルールで番号を振っていったりする ようですが、すべてアナログでの検索性をあげるため、ということです。
幸い今の時代はデジタルデータとして保存している場合は非常にたくさんの文献や文章などでも一瞬で検索結果が出てくる わけです。
さらにEvernoteの場合はテキストデータだけではなく写真の中に入っている活字もOCRで認識した上検索の対象 になります。ここまで検索機能がしっかりしているのであれば、検索に任せても良いだろうと思ったのです。
ZettelKasten法ではアイデアの飛躍を求めるため、検索ワードとして「一般の検索で引っかかりにくい言葉、将来もう一度見つけてみたいと考えられる言葉」を検索ワードとしてあげる ようにしています。
こちらは今まで検索ワードをあげるとしても考えつかなかった発想 であり、これについてはアイデアの筋もよいと考え今回採用しようとすぐに思いました。
このような経緯を経て下位互換を保ちつつ読書ノートは少しずつ進化 しています。
まとめ
読書ノートは継続的に改良を加えているが、今般大きな改良があったので前回note記事にしてから変更のあったものに具体的に言及し、なぜ導入したのか、なぜ廃止にしたのかについて少し深く思索しました。
ZettelKasten法が根本に根ざしている読書ノート記載法や情報収集法というのは小理屈野郎独自のものも含めいろいろとありますが、やはり原法の考え方やその目指すところをしっかりと踏まえた上で改良する必要があると考えられました。
読書ノートの記事になると本当にややこしくなってすみません。
実際やっていることは流れ作業に近いことなんですが、文章で説明すると結構面倒なことになっています。
読書ノートは最初に完全なフォーマットを組むことが理想 なのですが、やってみると分かることですが、それは本当に理想です(苦笑)。
いかに今まで蓄積してきた情報(読書ノート内容)をうまく使えるようにしながら、今後さらによくなるか、ということを考えながらフォーマットを考えていく、ということが大事ではないかと思います。
よろしければサポートお願いいたします。 頂いたサポートは、書籍購入や電子書籍端末、タブレットやポメラなどの購入に充当させていただきます。
