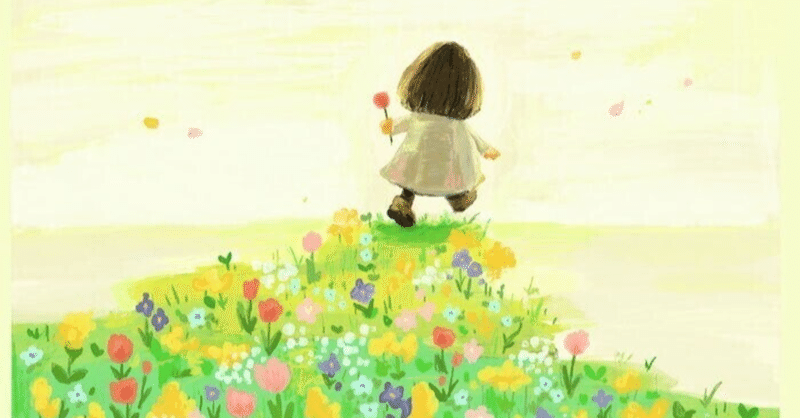
[読書ログ]森絵都とモーリスセンダック
『チイの花たば』
2021年10月第1刷発行の絵本。
森絵都さんの文とたかおゆうこさんの絵。
小学4年生以上かな、という内容。
花屋のおばあちゃんをもつチイ。おばあちゃんが花屋のテストに合格したという話を聞き、チイにもテストの試練がやってくる。そんなおはなし。
チイが3つほど受けるテストの内容に独創性とかわいらしさ、面白さがある。
個人的には、1つ目のテスト、おじいさんからの依頼で、ようちえんがきらいなユキオにあげる花束を作ったときのこと。海が好きなユキオのために、青い花で花束をつくったチイだが、最後におじいさんに以下のような言葉を添える。
おじいさん、どうか、ユキオくんがようちえんへ行くとき、この花をひとつ、おまもりのかわりに、ポケットにさしてあげてくださいな。そしたら、海のかけらをもってるみたいで、ちょっとだけ、心が元気になるかもしれないから。
「海のかけらをもってるみたい」の表現が秀逸。
こういうちょっとした表現に作者の書きたかった意図を感じる。
全体的にみると、冒頭でチイはおばあちゃんの様子を常日頃から眺めていて、自分もおばあちゃんみたいなお花屋さんになりたいという。
チイが花屋にふさわしい人間かどうか、花に試されるテストがある、大切なのはチイの心に花屋の心があるかどうかだとおばあちゃんから言われる。
すると、夢の中で3つのテストで試されて、ラストでおばあちゃんからガーベラを渡され、(ガーベラの花言葉はつねに前進)合格おめでとう、となる流れ。
何かになりたい主人公がそれを達成する話なら、ふつう、花屋になるためにあれこれ努力したり、水をあげたり、枯らさないように育てたりする苦労が描かれるように思うが、そうではなくて、花をあげる相手のことを思ってあれこれ悩んで花束をカスタマイズしていく流れ。ここでチイの内面の豊かさややさしさ、そういった心の重要性を描いている。
個人的には冒頭がじゃっかん冗長な感じがするが、このくらい丁寧でリズミカルに刻むことで、花屋になりたい理由付けがより印象的になるのかもしれない。
ちょっと冒頭を書いてみる。
チイのおばあちゃんは、お花屋さんです。チイの家の近くで、ずっとむかしから、お花を売っています。
チイは、ちょこちょこ、おばあちゃんに会いに行きます。
お店のすみっこから、おばあちゃんとお客さんのやりとりを、ながめているのがすきなのです。
「けっこんいわいの花束をつくってください」
~中略~
おばあちゃんのお店には、家にかざる花ではなく、プレゼント用の花を求める人たちもたくさんおとずれます。きれいな花たばは、「おめでとう」の言葉を、色あざやかにてらしてくれるのです。
プレゼントのりゆうは、人それぞれ。
だから、おばあちゃんがつくる花束も、それぞれ。
ここが少しボリューム多いように感じたが、書いてみると、花屋の詳細や状況を説明する部分がこの冒頭しかないので、場面描写や背景を細かく書く必ようがあったように感じる。
また、『花束が「おめでとう」の言葉を色あざやかにてらす』というのが、ラストの一文の「合格おめでとう、チイちゃん」に対して、伏線的役割を担っているようにも感じる。
プレゼントの理由が人それぞれで、花束もそれにあわせてそれぞれ作るのだという前提を書いておいて、その後のチイの花たばの選び方に説得力(おばあちゃんと同じやり方をしている点で)を与えている。
読んでいてはわからないが、写してみると理解できることがある。
花って素敵、今日花を買ってみようかな、そういう気持ちにさせる読後の心地よさがいい。
「ロージーちゃんのひみつ」
「かいじゅうたちのいるところ」で有名なモーリスセンダックの作品。
モーリスセンダックは画家として名を成す前に一時失職して家にひきこもっていたところ、下の通りで遊んでいる子どもたちをスケッチしており、それが「ロージーちゃんのショー」という構想でまとめられ、本書に発展したという。
センダックがコルデコット賞の演説の中で、以下のように述べているとあとがきに記載がある。
しばしば見逃されているのは、子どもたちがごく小さい時から、心をかきみだされるような感情をうちにひめて暮らしているということです。子供たちは、ファンタジーによってこの挫折感を解消します。
子どもたちは、ファンタジーと現実と、二つの世界を自由に出入りしているのです。
さて、物語のほうの感想を。
ロージーちゃんの自由奔放な感じと、それにのっかる子供たち。
ただ、空想のなかをあちこち飛び回ったりするようなコテコテファンタジーでもなく、歌手になりきったロージーちゃんのショーをみんなで見たり、みんなを花火にすると言うと、みんなで花火のまねっこをしてみたり。
それぞれの子どもが空想のなかで表現をしたり、遊んだりする。
実際に花火にならないところがかわいらしさであり、子どもの頃は確かに自分でありながら、全く違う自分になるのではなく、ベールをかぶるみたいに別の何かになってみたくなったり、(それはすぐに本当の自分に戻れる安心感の上での変身願望である)したもので、そういった小さい頃の記憶を思い出させるような表現が大人にも刺さる。
この絵本の良さは、もうひとつある。
お母さんの登場と描き方だ。
途中で「ママ、あたし ママのこ?」と訊くと、「もちろんよ」と答えて三回キスをする。戻る場所と愛されている安心感の上に、空想や冒険が成り立っている。これは読み手の子どもにとっても安心感があるだろう。
逆に、ラストのページで、ネコのように床に寝ているロージーちゃんと母親のシーンは、お母さんがわの読み手も、この奔放さを許容しているところを微笑ましくも教訓的にも受け取るのではないだろうか。
とをあけると、ベッドにねむっているのはバタミルクでした。もうふをあごのところまでかけています。
ロージーは、じゅうたんのうえにまるくなっていました。
「ロージーったら!」
「しーっ。バタミルクがおきちゃうじゃないの」
「なぜあなた、ゆかのうえにねているの?」
おかあさんは、そっとききました。
「あたし、ねむたがっているこねこなの」
「ああ、そうだったの」
おかあさんは、あしおとをたてないようにして、そっとへやをでました。
「おやすみ!」
とをしめながら、おかあさんはいいました。
「ニャオン!」と、ロージーはこたえたのです。
子どもの行動には理由がある。そんなところで寝たらだめじゃない!と言わず、ああそうなのと納得して、ロージーのやりたいようにやらせる。
まあ風邪ひくかもしれないが、それよりもロージーに任せて口出ししない。お母さんの立ち振る舞いも見事、と思う。
他、個人的には、しょうぼうふの帽子をかぶったレニーの登場シーンも好きだ。
しょうぼうふのぼうしをかぶったレニーがたっていました。
「ぼくもいれてよ」
「これ、ほんもののショーなのよ」とアリンダのロージーがいいました。
「あなたはショーにはでられないわ」
「なぜさ?」
「なぜでも」
「なら、いいや。どうせぼく、かじをけしにいくところなんだから。いっしょにいきたいやつ、いるかい?」
みんな、あたまをよこにふりました。
レニーはいってしまいました。
「では、うたいます」ロージーはめをつぶって、うたいはじめました。
「ひのあたる――」
「いいことおしえてやろうか?」
レニーがまたもどってきたのです。
レニーがてじなをやろうと言って、みんなでてじなをやりはじめる。
そうしてロージーがショーを再開しようとすると、みんなおなかがすいたとか、レニーの火を消すのを手伝うとかでいなくなってしまい、ずっと最後まで歌いきれなかった歌を、ロージーは一人になってはじめて歌いきる。
日常のやり取りの滑稽さがいい。
レニーがきて、火を消すのを手伝ってといっても、みんなで頭を振る動作もかわいらしい。作者がそれぞれの子どもに平等に愛らしい視線を送っているように思われて、ほっこりするのだ。
ロージーの場合は、普段子どもがやりたくてもやれないことを思いっきりやっているところに心の解放があり、楽しく思うのだろう。
絵と文のマッチングが秀逸。絵も文も両方書くからこそ生まれる融合性もまたいい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
