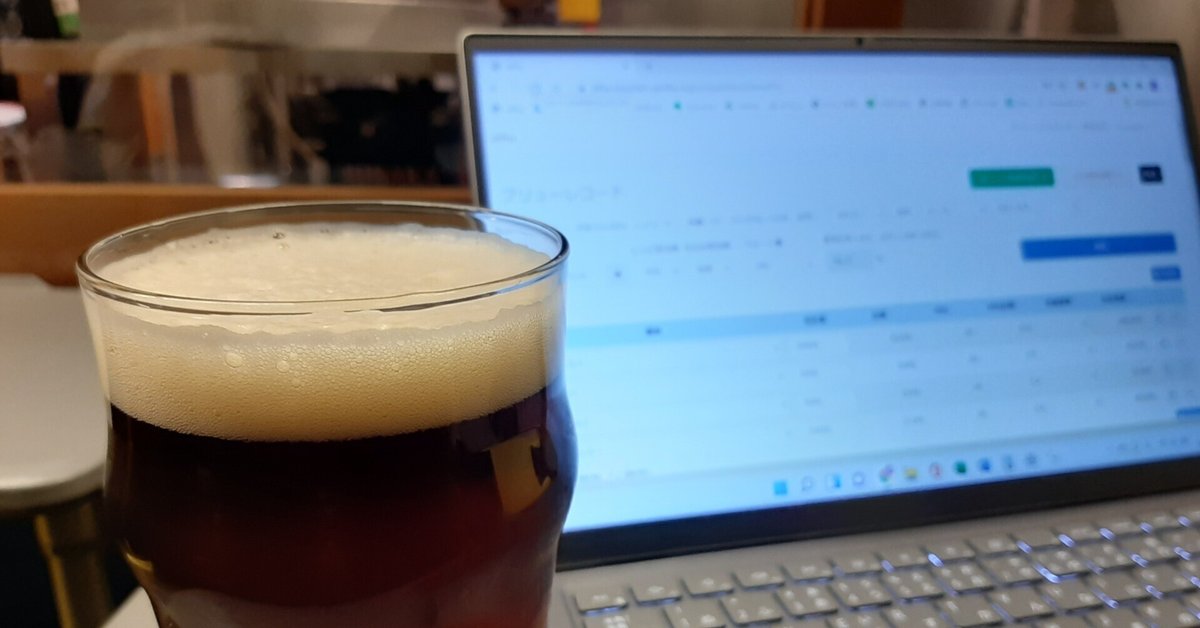
シン・ニホンを読んで電脳戦を妄想する
絶賛コロナ中。積読を消化しようと思っております。
そんな中で、今更?感のあるこの本。
メモ多めなので、目次で読み飛ばしてもらってもOKです。
シン・ニホンを読んで納得メモ
あまりにも売れてる、話題になったところで手を付けてなかったんですが、個人的には今読んでよかったかなと。
内容は読んでる人も多いと思うので、納得メモしたとこだけ。
未来(商品・サービス)=課題(夢)×技術(Tech)×デザイン(Art)
これからの価値創造の図式。技術だけではだめ。
日本人は働きすぎ、労働生産性が低い。イタリアの2倍働いてる。
日本の新卒層の課題。
基本的な問題解決能力の欠如。数字のハンドリングの基本が欠落。分析の基本ができない。統計的素養がない。平均を鵜吞みにする。情報処理、プログラミングの基本的な理解がない。
AI vs 人間 という議論はほとんど意味がない。
一度その分野にキカイが入り始めると、手作りの良さやキカイの生み出せない味わいをベースにしたプライシングを行えない限り新しい技術を取り込まないという選択肢はなくなる。
課題解決の各段階で求められるスキル
ビジネス力・データサイエンス力・データエンジニアリング力
この3つのスキルのうちどれか1つでも欠けるとダメ。
人間の知的生産は、そう安易にAIに置き換わるようなものではない。人間を極めて強力にアシストするキカイ。
学校教育が思考能力を鍛える場になっていない。社会に出てから独学で学ぶ。体系的かつ徹底的に論理的な思考や表現をする訓練を受けたことがない。大学が、本来的にはこれらの能力があることを前提とした上での教育・研究機関であることを考えれば、これらの能力開発は初等中等教育で行われるべき。国語教育のコマ数は多いはず。
仕事とは何か?
仕事=力×距離 force × displacement
生み出す変化がなければ意味がない。
あらゆる文化は「手」によってつくられる。真の創造は最終的には「手」によってなされる。「手」を忘れることは文化の原点を忘れ、人間性を見失うことである。
プロフェッショナルというのは単なるスペシャリスト、エキスパートと異なりクライアントに対してきっちりとバリューを提供することにコミットする人材。
時間を売る時代は終わり、アウトプットが仕事の成果になる時代になる。時間に縛られることはなくなり、自由になる。アウトプットドリブンな社会を創る。細切れで複数の仕事をすることも可能。
未来は目指すものであり、創るもの。
不確実性の4つのレベル。
①確実に見通せる未来 ②他の可能性もある未来 ③可能性の範囲が見えている未来 ④全く読めない未来
変化の激しい世の中では、従来型の比較的変化の少ない静的な市場構造を前提とした戦略立案はあまり役に立たなくなっている。完全な予測は不可能という前提の下に、何を仕掛けるかを考える。刈り取りの時間軸と事業側の馴染みやすさによってバランスよくポートフォリオを組む。
思ったより長くなりそうなのでこれくらいで、、、日本がこれからどうやって再生するか、その人材教育論がメインの話なので興味ある方は読んでみてください。
そして攻殻機動隊を観まくる
まぁもともと好きな作品ですが、時代を追うごとに味が出てくるスルメアニメです。
ノラブリュワリーのもととなったスタンドアローンブリュワリーももちろんこの作品から。
AIのこととかはよくわかりませんが、クラフトビールがこれからますます情報戦になるんちゃうかと。電脳戦を妄想するわけです。
クラフトビールの液体としての価値がだんだんと曖昧模糊としてきて、ビールを飲んでるというより情報を飲んでるような感覚になるときがあります。
液体としてのビールの製法や原料に大差がなく、出来上がった製品にも際立った個性がない。(個性的すぎるエクストリームなビールも間々あるが。)
そもそもビールとはそういうもんだった気がするんですが、ここまで世界中でクラフトビールがある意味で標準化されつつあり(少し前であれば、国や地域に固有のビールの特性があったが、今では世界中で世界中のスタイルのビールが存在しつつある)、世界中の色んなビールが気軽に手に入るようになってくると、なぜそのビールを飲んでいるのかという動機付けにブランドやストーリー、デザインやキャラクターなどの情報がもっともっと重要になっていく、と考えてしまうのです。
ネットしない、は可能か?
攻殻機動隊の作品中で、ほとんどの人間は電脳化していて、張り巡らされたネットワークにいつでもアクセスしている。作品中では、それによって重大な犯罪や問題が頻発するんだが、ネットしない(ネットワークにアクセスしない)という選択肢がそもそも難しい社会になっている、という設定。
シン・ニホンを読んで思うのが、ネットしない、がもはや選択できなくなっていくやろうなと。もちろんビールに限らず、世の中のありとあらゆる物事がネットしないと生産性が追い付かなくなる。という意味で。
で、今現状で日本に乱立しつつあるノラブリュワリーがいつまでネットせずにいられるのだろうかと妄想します。アナログローテクの手仕事がもちろん我々のウリではあるのですが、ネットしない、という選択肢で生存できるほど甘くない気がするのです。
世界中の情報を整理し、世界中の人びとがアクセスできて使えるようにすること
Googleの使命で割と初期からずっと言われてるこのメッセージ。
現在、あのGoogleでも世界のクラフトビールの情報を整理できているとは言い難い。ネットしてないクラフトビールの情報があまりに多すぎるからです。
これが実にもったいないことなんじゃないかと感じています。ビールがますます情報を飲む物になっていってしまう(情緒的には否定したいが)のであれば、ネットせずに刹那的に消費されてしまうクラフトビールのほとんど全てが忘れ去られてしまうんじゃないかと。
前述のこれからの価値創造の図示に当てはめると
・課題=夢はもっと日本でクラフトビールが日常的に飲まれること
・技術は醸造技術はもちろん、DXやAIを使ったビール自体の進化
・デザインはそこにネットする包括的な情報、世界観
この3つが掛け合わさって未来のクラフトビールができるんじゃないかという妄想。
そのためにもクラフトビールの情報を整理して、多くの人がアクセスできるようにしたいなぁ。
記醸くんやビアレコの取り組みもまだまだ始まったばかりで開発途上なんですが、妄想ばかりが膨らんでおります。笑。
定期的にこんな話してる気がしますし、じゃあ自社がそもそもネットできているかというとこれもまた問題で、自戒も込めて。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
