4つのカテゴリーと、城郭史との関係について
「お城へ To Go」番外編の再録です。
このコーナーは、統合医療ブログとは一線を画して連載していますが、じつは医療とは全く無関係とは考えていません。ウィルバーの4象限の「ITS」(客観・複数)の実例でもあるのは、これまで書きましたが、多元主義理解のための実例でもあるのです。それを今回は示してみましょう
教条、折衷、多元、統合という、複数のカテゴリーの括り方の差異について考えてきましたが、本来「統合医療」という概念は極めてあいまいであり、それゆえに現在でもその概念の混乱がある、というのがこれまでの(これからも)私の主張です。この説明の具体例として、結構、城の分類が役に立つ、ということを見ていきましょう。
いわゆるお城を時代的に大きく分類すると、古代山城、中世山城、近世城郭に大別できます。
少なくても100名城などの城巡りでは、これらのどこに分類されるのかを意識しながらめぐることで、見どころポイントを外さずに済みます。(類型化には多くの問題もありますがやはり分かり易いというのが最大のメリットではあります)
古代山城に関しては、大和朝廷の対外政策の関連(大野城・鬼の城・金田城)なので、少し例外的で、東アジアにおける世界情勢に大きく影響されます。それゆえに大規模ではありますが、築城の意図などは明確で、統合医療のモデルにしては極めて単純なものになります。(「正しい統合医療」といった言説に近いでしょうか)
それに対して、中世山城となると、まさに「折衷」から「多元」への移行、そしてその発展としての近世城郭は「多元」から「統合」への移行、を象徴していると考えられます。
応仁の乱以降の混乱期から、戦国時代へと突入、「くに」が次第に吸収合併が進んでいくさまは、まさに折衷状態が、力の強さによって統合へと向かう様子そのものとも見れます。この過程がまさに中世山城的です。
それから織田信長による安土城築城から、統合への意図がちらほらと透けて見えるようになります。
それでも、各地の大名が群雄割拠した政局が続くため「多元的」状況が続き、或る意味そのまま近世江戸期に入ります。そしてこの幕藩体制そのものが、「多元的」政体とも言えます。幕府自体は中央集権化しておらず、天領など直轄地からの税収で運営されいると考えられるので、多元の要素を多くもつわけです。つまり、近世城郭は「多元」の象徴とみなすことが出来そうです。
そして明治政府の樹立により近代国家が形成され、廃藩置県が断行されることで、「統合」(そしてある種の「教条」)が完成されたと見ることもできるわけです。中央集権という言葉にそれが象徴されているわけです。
これまで、多元と折衷の違いなどでは歴史的視点で解説してきたのですが、城との関連で今回は解説してみました。
いずれにせよ、こうしたモノサシ📏の導入により城も統合医療も、混乱を少しはのぞけるのではないか、という試みです。
少し「恣意的」な感じもしますが、結構良いモデルなのではないかと自負しています。
ちなみに統合医療の臨床連携のモデルとしては「離島」をモデルとして昨年の統合医療学会で発表しました。抽象的な概念や仕組みついては、やはりモデルによる「比喩」が分かり易いように感じています。
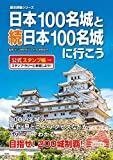
公式スタンプ帳つき (歴史群像シリーズ)
公益財団法人日本城郭協会
ワン・パブリッシング 2020-12-17
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
