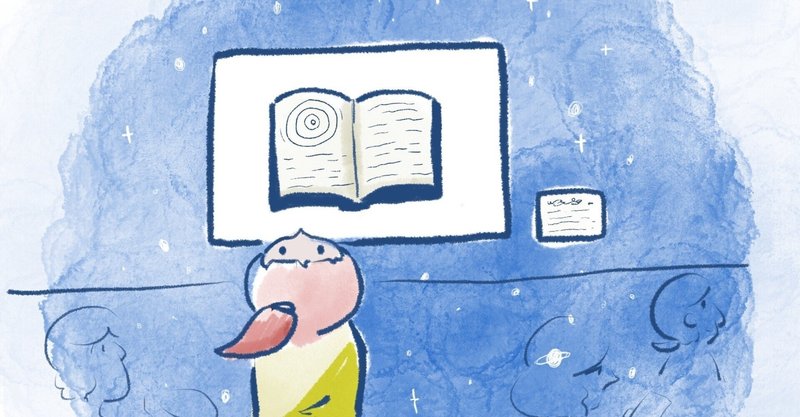
タオ自然学
今月はStay Homeでした(2020年06月01日)ので、統合医療の「そもそも」を考える時間にしていました。統合、インテグラルの在り方や、スピリチュアリティの位置づけなど、ちょっと忙しい時には考えにくいものに時間をかけてみました。(この成果?としてオンライン統合医療講義を開講しますので、ご興味ある方は是非ご参加下さい)
特に歴史的には、統合医療の前段階ともいえるホリスティック医療の在り方や、その母体とも言えるニューエイジムーヴメントについては、医学生の頃に盛んに読んでいましたが、ずいぶんご無沙汰していました。
そうした中で原点回帰のような形で『タオ自然学』読んでみました。この本はたしか、まだ大学教養部だった頃、友人に借りて読んだ以来です(この愛煙家の友人の下宿でワイルの著作とも出会いました)。当時はざっと、こんな感じか、といったくらいでしたが、現在読むと少し感想が異なります。
ケン・ウィルバーはカプラのこの著作を独白(モノローグ)であるので、大きな変化につながらなかったように述べており、確かに読んでみるとその通りではあります。ただ当時の雰囲気として何人もの人達が、ここに物理学をはじめとした科学が東洋の深淵な思想と統合されていく様子を夢想し、輝かしい未来を思い描いたのではないでしょうか。そうした歴史的な意義は大きかったのではないかと思います。しかしそれでも、この内容はウィルバーの言う「左上象限(1人称)」であることに変わりはありません。
そうしたことの影響なのでしょうか、続くニューエイジの旗手、デヴィッド・ボームは、ダイアローグの重要性を説きます。隠れた変数説により量子力学を説明しようとした物理学者ですが、ダイアローグへの可能性を見出している姿勢は、この1人称性を超えるべく、2人称(左下象限)とウィルバーの表現する「間主観性」の重要性を理解したうえでのことなのかもしれません。
いずれにせよ。この『タオ自然学』のベストセラー化によりニューエイジムーヴメントが展開していくことになるのです。そうした当時の「力」を感じ、ややもするとEBMの申し子に自ら進んでならんとしている統合医療の昨今の風潮を、再考させてくれる良い機会になりました。(ちなみにEBM的な方向性自体は良いと思います、他の視点とあわせて複眼的にインテグラルにいくべきではないか、というのが私の主張です)

タオ自然学―現代物理学の先端から「東洋の世紀」がはじまる
F・カプラ 工作舎 1979-11-15
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
