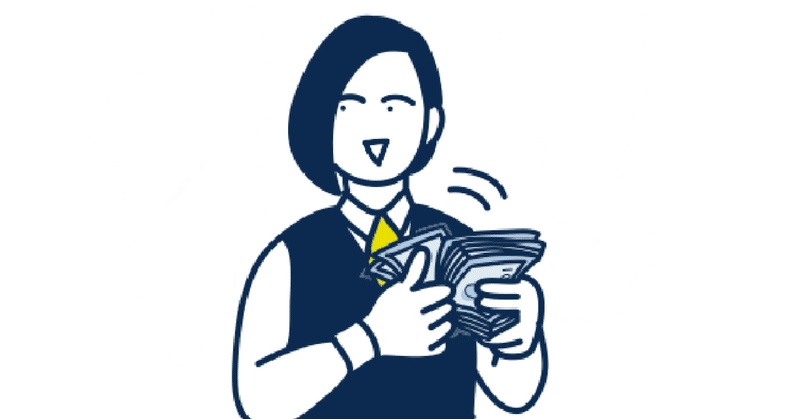
動画制作は売り切り商売
どうもです。動画制作とWebマーケを生業としている、しかたこうきです。
最近は、社会経験が浅い中、動画制作ビジネスにフリーランスとして飛び込む人が多いですね。
それを良いとか悪いとか言うつもりはないんですが、ビジネスの基本を知っていないと、フリーランスはなかなか辛いものがあると思います。
この記事では、フリーランス若年層向けに、動画制作ビジネスの特性について説明したいと思います。
サービス業には、3つの案件特性がある
これは、私がWeb制作会社にいた頃に学んだことです。
まず、ビジネスの原則として、以下の2種類があるということを認識してほしいです。
実際に存在するモノを売って対価を得るビジネス
自分や社員がサービスを提供して対価を得るビジネス
一般的には、1は製造業だったり、卸業だったり、小売業だったりしますね。物販ビジネスと呼ばれたりします。原材料だったり、売る商品だったりを仕入れる必要があります。
一方で、2はサービス業と呼ばれます。モノを仕入れるのではなく、自分や自社のスタッフが顧客に技術や情報を提供して報酬を得ます。toCだと、美容師やエステティシャン、toBだと、税理士や司法書士などの士業、コンサルタントなどが思いつくと思います。
では、動画制作はどちらなのか。これは、誰も間違うことなく、2のサービス業だということがわかると思います。
クライアントから動画制作の依頼を受けて、動画を企画し、撮影し、編集し納品する。機材を購入する経費はかかりますが、仕入れではないので、この辺りは美容師やエステティシャンに近いものがあるでしょう。
で、このサービス業では、3つの案件特性があると、私がかつていたWeb制作会社では学びました。以下では、Web制作会社の例をあげて、3つの特性について紹介します。
①単発の発注
Web制作会社では、いわゆるWebサイト(ホームページ)を作るのがメインの仕事になります。
ただ、ホームページを作るというタイミングは、
会社を新たに立ち上げたのでコーポレートサイトを作りたい
新製品やサービスを紹介するためにミニサイトを作りたい
リスティング広告をするので、ランディングページ(LP)を作りたい
などの機会か、新規に作成してから何年か経ったのでリニューアルしたい、というタイミングに限られます。
たくさんの顧客を抱えていたら、毎月そういう案件がポツポツ入ってくるかもしれませんが、そうでなければ、単発の受注だけで毎月稼いでいくのはしんどいです。
とはいえ、私が勤めていた会社では、この単発の発注がメインの仕事で、営業チームは新規案件の獲得に頑張ってくれていました。(私も営業現場へ出向くこともありました)
2~300万円クラスの更新機能付きWebサイトを3~4ヶ月で納品するので、それぐらいの案件を3~4件ぐらい並行して回していました。
営業が頑張ってくれていたのももちろん、私も得意としていたCMSが高付加価値商品になってたのもあって、結構調子良く新規の案件がコンスタントに取れていたと思います。
ただ、これはラッキーが色々重なってたのもあり、高付加価値商品がなければ、新規の案件を定期的に受注していくのは困難です。
②継続の発注
Web制作の業界には「保守」というサービスがあります。保守の言葉の定義は制作会社や人によってまちまちなのですが、新規やリニューアルで作ったWebサイトを、毎月最新の情報に更新していくサービスです。
つまり、新製品が登場したら、その月は製品情報に新製品のページを追加する。お知らせ記事を更新するなら、トップページと新着情報のページに追加する、といった内容です。
もっとも、今はWordPressなどのCMS(コンテンツマネジメントシステム。HTMLやCSSなどの知識がなくても、簡単に更新できる仕組み)が普及したのでクライアント企業側でも更新できるようになりました。
従って、こういう単純なコンテンツ更新の保守サービスは縮小傾向にありますが、一方でクライアント企業側で出来ないCMSの機能拡張や、複雑なコンテンツ改修などを毎月行なっていきたいという保守サービスの企業ニーズは増えています。
いずれにしても、保守は単発の発注と違い、毎月どれぐらいの作業を行い、何ヶ月間実行するか、という契約になります。
よくあるのは、スタッフ1名月40時間分の作業を半年契約みたいな感じで、それを超える分は超過料金が発生したり、単発の発注を追加する、みたいな契約です。
Web制作業の保守サービスのように、毎月一定量の発注が決まっている案件を継続の発注と呼びます。
③手数料
別名、チャリンチャリンビジネスとも呼ばれますが… リスティング広告などの広告手数料、サーバー月額費用にマージンを乗せる、自社開発したソフトウェアを使ってもらい、ライセンス手数料を取るなどの手法があります。
手数料と継続発注の違いは、作業が発生するかどうかの違いです。継続発注はある程度の長期間、仕事が確約されていますが、どちらにせよ手を動かして制作(生産)する必要があります。
手数料は、定められた契約期間の間、何もしなくても収益が発生する仕組みです。(リスティング広告の場合は、多少配信設定の調整などは発生するかもですが)
Web制作会社では、この3つの特性をうまく調整して経営している
とある統計では、日本には個人事業主も含めると1万7000社ものWeb制作会社があるとのこと。しかし、長く続いている企業は当然一握りですが、どの会社も概ね、上記3つのタイプの案件で収益を上げています。
重要なのは、この①〜③のバランスです。
先述の通り、私が勤めていたWeb制作会社では、①の案件比重が大きかったです。一発受注が決まれば売上も大きいのですが、逆に受注が続かなければ、途端にキャッシュフローが崩れ、経営危機に立たされます。
その制作会社では、なんとか②の案件や③の手数料を増やそうと画策していましたが、結局有効な打ち手もなく、営業や制作にもそこまでのマインドもなく、①を受注し続ける自転車操業が続いていました。(今はどうなのか知る由もないですが…)
逆にとある有名制作会社ではどうしてるか、という話も聞いたことがあります。
その会社は、大企業(少なくとも上場している)としか取引しない大原則があるそうです。
次に、チームが大きくAチームとBチームに分かれている。
Bチームは、創業から付き合いのある大手通販会社の巨大ECサイトのみ担当するチーム。
Aチームは、新規案件を中心としたBチームが担当する通販会社以外の企業を担当するチーム。
要は、Bチームが保守サービスで、Aチームが新規の単発発注を受け持つチームとなります。
興味深いのが、未経験者や新卒採用者はBチームに配属され、中途採用でスキルのある人はAチームに配属されるとのこと。
Webサイトの保守は、新規にデザインを起こしたり、自分でアイデアを形にするような案件ではないので面白みに欠けると思う制作者も多いのですが、既存の出来上がっているサイトに改修をかけたり、バナーを作って追加したり、比較的少ない行数のコードを書き換えたりと、業界未経験者には、まず実務を覚えてもらうためには最適のポジションなのです。
このように、未経験者には保守の仕事から任せる制作会社は他の会社でもよくあるパターンなのですが、この会社の面白いところは他にあります。
それは、Bチームだけで、その会社の全員分の給料を出せるだけの売上と利益を稼いでいる、とのこと。
当たり前ですが、会社員は毎月給与が出ます。会社から見ると、雇っている社員には毎月給与を払わなければなりません。しかし、①主体の売上を上げていると、受注が途切れてしまったら、社員に給与が払えなくなり、倒産します。帳簿上は儲かっているけど、支払い期日に間に合わなくて黒字倒産、ってやつです。
しかし、この会社のように、毎月の売上が予測できる保守案件で全体の人件費を確保できていると、①の案件受注がストップしても①を担当する社員にも給与は払えますし(まあ、その社員はタダ飯を食うことになりますが…)、毎月案件受注にがむしゃらにならなくてもよいわけです。
また、心にも余裕が生まれるので、ちょっと斬新な提案をしてみるとか、すぐ売上には繋がらないけど、新しい技術を習得して、商品化してみるといった、R&D的な活動もできるわけです。
どのWeb制作会社も、最初は①の単発受注から始まると思います。そして、しばらくはそれを追いかけ続けるしかないでしょう。
しかし、時間が経つにつれ、①だけを受注するのではなく、②や③のサービスを手がけていかないと、キャッシュフロー的な意味ではキツくなります。特に社員を雇うのであれば、こういう営業戦略は必須でしょう。
以上が、Web制作会社の案件特性による営業戦略の話でした。
では、動画制作業界はどうか
一口に動画制作業界とか動画制作会社といっても、昨今はビジネスモデルが多様化しているので、なんとも言いづらいところがありますが、とはいえやはり、この業界の基本は「動画を作って納める」というのが基本だと思います。
動画を作りたい企業があって、それを制作する制作会社がある、という関係性なので、それが一番自然です。だから動画制作は売り切り商売なんですね。
ただ、Web制作会社と違うのは、保守や手数料という概念が無い、というかまだ薄いのが実情です。
例えば、サーバー費用にマージンを乗せる手法は、動画制作では使えません。現代では、大抵MP4データを納品しておしまいです。クライアントは、自社のホームページサーバーにアップしたり、自社のYouTubeアカウントにアップして利用します。
また、保守という概念もありません。動画を納めたら基本的にはそれでおしまいです。たまにあるのが、人材採用動画で、インタビューに出てくれた社員が退社したので差し替えてほしい、という要望。
ところが、そうなるとインタビュー撮り直しになるので、そこそこ金額がかかる。だったら新規に動画を発注し直そうか、という話になるんですね。この場合だと、毎月定額で保守費用をもらうというわけには行かないです。
最近のトレンドでいえば、企業のYouTubeチャンネル動画の制作支援サービスなどがあります。ちなみに私の個人事業でも請け負っておりますが、制作費月60万円~で、6ヶ月間以上の契約をお願いしています。
これが受注できると、Web制作業の保守に近い受注モデルを作ることができます。
ただ、Web制作の保守は、簡単な更新しか無い月でも満額の制作費を払ってもらえる契約にしてる場合が多いです。YouTubeチャンネル動画の制作支援の場合になると、月◯本制作確約とか、制作本数の縛りが出てきます。顧客都合で制作本数が減った場合、減額交渉される可能性もあるので、そこは契約書でしっかりリスクヘッジする必要があるでしょう。
さらに、Web制作の保守は先述の通り、簡単な更新だけで済む場合があるのですが、YouTubeの制作の場合は、動画を新規に作ることになるので、結構工数がかかります。ここがしんどいところでもあるな、というのが実際に経営してみての感想です。
Web制作の保守の場合、簡単な更新だけで済めばその月はラッキー、その代わり、修正が立て込んでも柔軟に対応するよ、というシステムです。実際にはクライアント次第ではほぼ1年間手のかかる更新が全く無い、ということもあります。そういう意味では、③の手数料案件に近い案件も存在します。
しかし、YouTubeチャンネル制作支援は、先述の通り、新規動画制作を作り続けていかなければなりません。ある程度動画のパターンやフォーマットは固定できますが、毎月撮影が発生し、ディレクターとカメラマンを拘束し、編集作業に時間を取られる。これが結構キツいですね。
ですから、YouTubeチャンネル制作支援は、①と②の案件特性の間にある感じです。半年先まで、新規制作案件の予約が入っているイメージ。
最後に:動画制作は自転車操業化しやすい
結論はこれです。動画制作は売り切りビジネス。リピートされる可能性はゼロではないが、Web制作の保守案件よりは旨みが少ない。
フリーランスであれ、制作会社であれ、クライアントがいて、動画を作りたいというニーズを受託しているのが動画制作業界なわけですが、作って売る、作って売るの繰り返しを、どう上手くやっていくか、っていうのが各社各個人の課題なのかな、と思います。
その辺、うちではどうやっているのか。また機会があったら書いてみようと思います。
今日はこの辺で。
頂いたサポートはクリエイター活動の主に機材費・出張費に充てます! より良い作品アウトプットのためにご協力よろしくお願いします!
