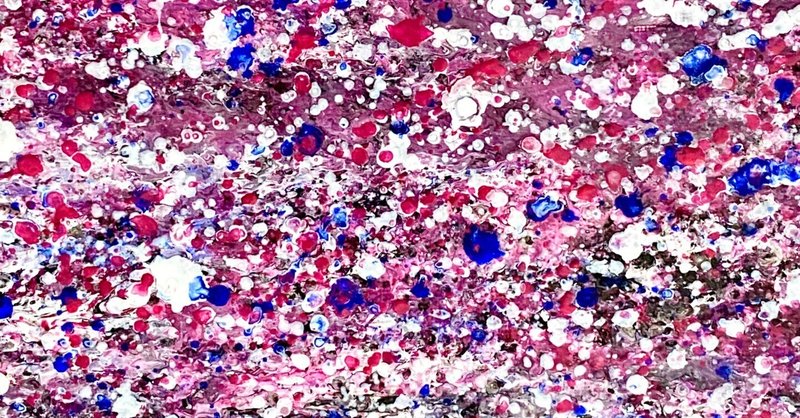
『演技と身体』Vol.45 世阿弥『至花道』を読み解く①
世阿弥『至花道』を読み解く①
今回は世阿弥の中期の伝書『至花道(しかどう)』を読み解いていく。
前回紹介した『音曲声出口伝』と比べると概念的なところも多いが、それだけに汎用性が高い。世阿弥が57歳の時の作で、世阿弥の中でのテーマが“花”から“幽玄”へと移ってゆく時期である。
花から幽玄へ
“花”から“幽玄”へ。というのはどのような変化なのだろうか。
それが最もよく表れているのが『至花道』の中の「体・用事」の項目だ。
体は花、用は匂ひのごとし。
体とは役者の在り方で、用とは観客が受け取る印象だと言えるだろう。用語が少しややこしくなってしまうのだが、ここで述べられている“匂ひ”というのが前期の『風姿花伝』で述べられていた“花”という言葉に相当するのではないだろうか。
すると、「花」という言葉の持つ意味が世阿弥の中で変化しているように思われる。(『至花道』が“花”から“幽玄”への過渡期にあたる書なのだと考えるとこうした用語の意味の変遷も肯ける)
ともかく、世阿弥の着眼が「観客からどのように見えるか」という外側の視点から「役者はどうあるべきか」という内側の視点へと変化しているように思う。
「体・用事」については次回詳しく扱うことにして、『至花道』の頭から順番に見ていこう。
「二曲三体事」
習道の入門は二曲三体を過ぐべからず。二曲と申すは舞歌(ぶが)なり。三体と申すは物まねの人体なり。
演技の基礎について述べた項である。
「初歩の学習としては二曲および三体のほか手を出してはならない」と言っている。
二曲とは舞と歌という能の基本を指すのだが、敷衍して言えば基本的な身体能力のことだと考えて良さそうだ。能では幼少から稽古を始めるわけだが、いきなり役になりきろうとするような演技をすると却って演技を固定化してしまうことになり変な癖ばかりが身についてしまう。だから、まず単純に大きな声を出すとか思い切り動くとかそういった身体のダイナミズムを養うことが重要なのである。
これは大人になってから芝居を始めた人にも重要なことだ。人は成長するにつれて身体が固定化してくる。だから役者は演技の練習ばかりでなく、体の開発をすることが大事だ。しかもそれは筋トレのように何かを身につけるような開発の仕方ばかりではなく、凝り固まった身体性を解体していくような開発が必要なのだ。
そして世阿弥はこの二曲こそが「後々までの芸態に幽玄を残す」のだと言う。というのも、世阿弥の芸論によれば演技者はその究極においてはもはや演技をしないのだ。そのような「演じない境地」に至った時、身体的なダイナミズムが非常にものを言うようになるのだ。
次に三体の方であるが、世阿弥は役の基本を〈老体〉〈女体〉〈軍体〉の三体と定めている。(『風姿花伝』では役ごとの演じ分けについて細かく述べていたが中期以降はこの三体に集約しているという点は最も大きな変化の一つだ。)
〈老体〉とは老人の芝居である。現代の映像・舞台役者のほとんどは老人の役をやることはないだろう。しかし思い出して欲しいのは、世阿弥の演技論が外見ではなく、役者の内側へと主眼を移していた点である。
つまり、老人の芝居というのは外見的に老人に似せよということではなく、老人の心持ちや身体の状態に成り入るということなのだ。そして、「閑心遠目」と表現される心身の状態は、侘しさ、寂しさ、心細さといった演技表現の基礎となるものだ。
同様に、優美さ、優しさ、しなやかさの表現の基礎となるのが〈女体〉であり、強かさ、怒り、不器用さの基礎となるのが〈軍体〉である。
無主風事
習い似するまでは、いまだ無主風なり。これは一旦似るやうなれども、わが物に未だならで、風力不足似て、能の上がらぬは、これ、無主風の為手なるべし。
師によく似せ習ひ、見取りて、わが物になりて、心身に覚え入りて、安き位の達人に至るは、これ主なり。
無主風(むしゅふう)とは、主体性のない演技のことである。逆に主体性を得た演技を有主風(うしゅふう)と言う。
師匠に習ってうまく似せることができるようになったとしてもそれはまだ無主風の芝居である。我がものになっていなければ、一時的に良い芝居ができたとしても、演技は上達していかないのだという。
これは演出家による指導を含むあらゆる外発性の演技に言えることだろう。例えば演出家の要求に応えた結果として良い演技ができたとしても、それは外発的に創造されたものであり、すぐに我がものになるわけではない。そこで掴んだものを内発性のものに落とし込んでいき、心身でその感覚を覚え込むことによって自分の演技というものが出来上がってゆくのだろう。
先に述べた二曲三体のうちは当然ながら無主風である。必要なプロセスではあるが、二曲三体ができるというだけなら他の誰が演じても大差はないのだ。二曲三体を修めた後、有主風の演技を体得できるかどうかが役者にとっての大きな分かれ道になる。
僕の考えでは、この段階においてその役者の人間性というものが非常に重要になってくるのだと思う。それまで経験してきたことだったり、考えてきたことや見聞きしてきたこと、周囲にどのような人たちがいるのか、そうした意識・無意識によって内側から役を想像してゆくのだ。
他方、こうした内発的な役の創造は二曲三体のプロセスを経ている場合にのみ表現としての力を持つものなのだと思う。二曲三体というのは表現の基本的なダイナミズムであり、伝わる力の根源だ。伝わる力なしに主体性を確立しようとしても、それは自己満足に終わってしまうだろう。
闌位事
・闌(た)けたる位の態とは、[中略]是を集め、非を除けて、已上して、時々上手の見する手立ての心力なり。これは、年来の稽古のほどに嫌い除けつる非風の手を、是風に少し交ふることあり。
・非風かへって是風になる遠見あり。
闌位(らんい)とは、世阿弥が最高位のひとつに位置付ける芸の境地である。
長年稽古を積んで、是風の演技を集め、非風の演技を退けた役者が時々「心」による演出によって非風の演技を是風の演技の中に混ぜるのが、名手の奥儀なのだという。
是風の演技とは正当な演技のことであり、非風の演技とは通常はやってはいけない邪道な演技のことである。
本来なら悪手に思われるような演技を、名手がふと演じるとそれがとてつもなく面白く感じられる。
だが、注意しなくてはいけないことがある。非風の演技が面白く感じられたからといって未熟な役者がそれを真似すると、元々欠点のあるところにさらに悪手を打つことになるわけだから、最悪の事態に陥るわけである。
良い役者はそれが非風であることを心得たうえで演じるが、未熟な者はそれが分からずに非風を是風を取り違えて真似しようとするのだから「黒白の違ひ」である。
返すがえす重要なのは二曲三体である。
さて、この後「皮・肉・骨事」、「体・用事」と進んでいくのだが、それらは次回に回そう。今回はここまで。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
