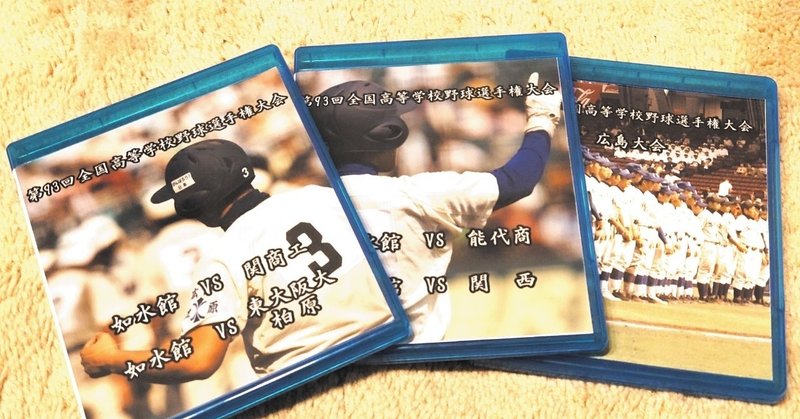
如水館高校野球部OBが2011年甲子園ベスト8に輝いた世代がいかに凄いか語る。
1993年に創部された如水館高校野球部は、その歴史の中で夏の甲子園7回、春のセンバツ1回の出場を誇る県内では有数の強豪校である。
夏将軍とも言われた如水館は、1997年の初出場から夏3期連続出場や2009年の2日連続雨天中止再試合など、歴史の浅い高校ではあるが、高校野球ファンに少なからずのインパクトを与えてきた。そんな如水館が夏の甲子園でその名を全国に轟かせた年がある。それが2011年の第93回大会である。その大会で如水館は初めて夏の甲子園ベスト8まで上り詰めたのだ。
この記事では、その全国ベスト8に輝いた2011年の世代がいかに凄かったかをたっぷりと掘り下げていこうと思う。
ちなみにサムネイルは筆者がリスペクトという意味で作成したBDです(笑)
"内弁慶"と呼ばれ続けた広島県の強豪如水館。
まずは簡単に如水館が今まで残した戦績を下記の資料を参考に確認していこう。

この戦績表は筆者が2012年からコツコツと作り上げたものだ。※夏のみ
甲子園出場七回、地方大会は歴史の半分くらいは準優勝以上という輝かしい結果を残している。だが、甲子園大会の戦績だけフォーカスすると、厳しい現実が垣間見えるだろう。そう、如水館は2011年までは夏の甲子園で一勝しか出来なかったのだ(センバツも二回戦負け)。 出るたび初戦負けや二回戦負けを繰り返す如水館に人々はこう呼んだ…”内弁慶”と。
元々広陵や広島商業、崇徳や県工など、広島県の強豪は全て広島市に位置しており、昔ながらの高校野球ファンからは三原市(広島県の東側)のど田舎から急に台頭してきた如水館に対してあまりいい印象を持たれてなかったと思われる。これは筆者も身を持って体験したが、旧広島市民球場で試合をする時はいつも完全アウェイである。広島商業なんかと対戦したらそれはモロにでる。おいおい高校野球やぞ(汗)と。カープを相手にする巨人かな?というくらい凄い。そんなヒール役とも言える高校が甲子園にちょくちょく出てはすぐ負けるので、それはもう広島の高校野球ファンにとっては相当嫌な存在だったはずだ。
ただそんな内弁慶如水館というレッテルを跳ね返した世代が誕生した。それが16期生が率いる2011年世代だ。事項からは、彼らがいかに凄い事をやってのけたのか項目ごとに解説する。
…ちなみに、筆者は内弁慶等のヘイトに対しては、まあ言われて当然であり、非常に申し訳ないと思ってました。中には高校の部活動にそこまで批判するなという声もあると思いますが、甲子園は負けた高校の思いも背負って、広島県唯一の代表として出場しているわけであり、応援して頂ける全ての方々に納得して頂けるような内容をお届けすべき場所だと考えます。
甲子園は思い出を残す場所ではなく、結果を残さなければならない場所です。決しておまけ感覚という様な気持ちで出場するべきではないと個人的には思ってます。
応援しているチームに一喜一憂する。この力が高校野球を日本が誇るビッグイベントへと成長させた原動力であり、その既に出来上がったステージの上で野球をプレーさせて貰ってるのです。なので批判はありがたい事であり、なんとかならないかなと当時から思っていました。
如水館高校史上初の甲子園ベスト8。
まずはなんといってもコレ。如水館高校野球部始まって以来の甲子園ベスト8。如水館を知ってるという方はだいたいこの世代の戦いを思い浮かべるだろう。甲子園に行ってから4回試合を行うという衝撃。前項で申し上げたとおり、如水館は創設以来二回戦の壁にぶち当たってきたが、それをこの世代は飛び超えた。彼らが我々の悲願であった高い壁を突破してくれたのだ。
歴史を塗り替える三週間ほど前、広島大会の決勝戦を筆者は観に行ったが、これ勝ったけど甲子園で大丈夫か?というのが当時の正直な印象だった。その決勝を戦った相手が広島新庄高校で、今となっては甲子園常連校の仲間入りを果たしているが、当時はまだそのレガシィを構築していく最中であり、格で言えば如水館がかなり上回っていた。下馬評も如水館が有利の中始まった試合は、お互いが大味な試合を展開し、浜田君の出来も本来とは程遠く、正に経験の差で甲子園の切符を掴み取ったという印象は拭えなかった。
しかし、筆者の予想は尽く裏切られ、彼らは甲子園で120%の力を発揮し、試合を重ねる毎に逞しく成長し、如水館の名を全国に轟かせ、世間から”内弁慶”というワードを打ち消したのである。
人々の印象に残る中身の濃い試合内容。
まずは彼らが戦った全試合のスコアをご覧いただこう。

そう、彼らは敗戦した関西戦以外は全て延長戦を戦い抜いた。負けたら高校野球人生即終了という甲子園の試合で、それだけでもプレッシャーがかかる中、彼らは終盤1投球・1スイング・1守備機会という、何か一つミスをすれば勝敗に直結してしまう極限の状況下で死闘を繰り広げ続けたのだ。
準々決勝の関西戦も、前日午後から始まった能代商業との死闘を制した翌日午前から始まる鬼畜日程。一日も経っていない状況でグランドに立った彼らは、正に力尽きたという言葉が相応しい試合であった。つまり楽な試合など一つもなかったのである。筆者は最後の関西戦は苦しくて観てられなかった…
このような厳しい試合展開を炎天下の中、何試合も戦い抜いた如水館ナインは、結果を加味せずとも賞賛に値する活躍を見せたと言えるだろう。
強豪校ひしめく大阪代表校に土をつけたという事実。
よくこの年のベストゲームを上げるとしたら、サヨナラ勝ちを収めた能代商業戦や関商工戦を上げる人が多いだろう。筆者もそのうちの一人だ。ただ、よく考えてみてほしい。彼らはあの大阪代表を撃破してるのだ。しかも如水館が長年越えられなかった二回戦という壁で…
大阪代表といえば、大阪桐蔭や履正社、PL学園等の強豪が集い、毎年大阪大会の参加校数は多い時で190を超え、それでも与えられた枠はたったの一つというとんでもない激戦区である(広島は90チーム前後)。
この激戦区大阪府内にとどまらず、大阪出身の球児たちは各都道府県に散らばって活躍している現状を考えると、激戦大阪大会を勝ち抜いた高校は間違いなく強敵であり、優勝候補といえる立ち位置に君臨していると言っても過言ではないだろう。
大阪代表に運悪くクジで当ってしまったなら、たまらず地元の仲間に連絡を取り、楽しい楽しい引退後の予定を早め、夏休みを出来るだけ長く満喫しようと段取りを企む対戦校の球児もいるだろう。
そんな大阪代表に勝つ大金星を上げた如水館。二回戦の相手としては歴代屈指の一番高い壁であったが、その壁を見事に突破した。この事実が若干埋もれ気味なのが、ある意味彼らの素晴らしい所だと言えるだろう。
技巧派の大投手、保坂祐樹君を擁する能代商業を撃破。
如水館のベスト8入りを語る上で外せない好敵手。能代商業の保坂祐樹君だ。彼のピッチングスタイルは素晴らしいもので、小柄で球速は120キロ台で決して速いとは言えないが、コースを付くコントロールや緩急が抜群であり、打者との駆け引きも上手く、相手を打たせて取るお手本のような好投手で、その技巧派スタイルでここまで勝ち上がってきた大会屈指の好投手だった。結果は如水館が延長12回で逆転サヨナラ勝ちを収めたが、サヨナラを二度も阻止され、一時は勝ち越されるなど、一歩間違えば負けても不思議ではなかった。目まぐるしく、手に汗握る展開で人々を釘付けにした2時間17分の激闘はこの大会における名場面の一つとなり、この試合を通じて如水館と能代商業の名は全国に響き渡ったであろう。

リスペクトを込めて他校では保坂君のみディスクレーベル化しました。
マスコミやネットが取り上げやすいネタも備える如水館
これは余談的な話ではあるが、ネットが広く普及した今、少なからず影響があったのではないかと考え、項目の一つとして取り上げることにした。
まず、迫田穆成監督が強烈だ。迫田監督はマスコミ受けが良い。甲子園のレジェンドではあるが、常に記者と談笑しては笑いを獲っている気さくな人物だ。たまに行う解説もなかなか、というかかなり面白い。だが、選手達に激を飛ばす時は「カメラさん一旦止めて下さい」と言って、場にピリッとした空気を呼び込む。このメリハリが記者達の興味関心を引き寄せているのかなと個人的には思う。
そして何故か長島三奈さんと仲がよかった(笑)。そのおかげかどうか分からないが如水館の事も結構気にかけてくださってて筆者の世代が敗戦した次の日、大阪駅までわざわざ見送りに来てくださった。筆者も意外と会話する機会があって今思えばいろいろ失礼な事も言ったような気がする(汗)が、如水館としても個人的にも長島三奈さんには大変お世話になった。
話が少し逸れたが、何が言いたいかというと、如水館はマスコミに取り上げられる下地が既に整っていたのだ。特に熱闘甲子園。割と如水館は取り上げて頂いた。我々の世代は純恋歌を唄ってた(三奈さんに捧げた笑)が、そのような作り上げたネタより強烈なネタがこの世代にはあった。
”せんとくん”と”1年生の四番”である。
前者は如水館のエース浜田君(奈良県のマスコットキャラクターと顔が似ている)、後者は1年生で四番を打った島崎君の事である。この話題性抜群の二人に全国ネットで放映される熱闘甲子園とが見事ハマり試合結果と相乗効果で如水館の名前が広く知れ渡ったと筆者は考えている。
最後に
彼らの達成した偉業を長々と書き連ねたが、2011年の如水館は、その活躍によって野球部が常に念頭に置いていた「甲子園で勝つ野球」を見事に体現した。そして、如水館の名を全国に轟かせ、広島県における強豪校としてその地位を確固たるものにした。
筆者を含めた関係者にとっても喜ばしい出来事で、本当にこの世代には感謝している。この築き上げたレガシィを後世が受け継いで、如水館という高校が末永く強豪校であり続けれるように切に願い、今後も応援していきたい。
という様にきれいな終わり方をしたかったのだが、如水館野球部の状態を考えると、楽観的に〆る事が出来ないのが現状であり…まあその話は長くなるのでいずれ踏み込むつもりである。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
もしよろしければ今後のモチベーション向上に繋がるのでいいねやフォローなどして頂ければと思います。Twitterのいいねもよろしくお願い致します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
